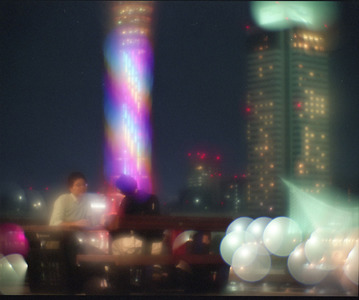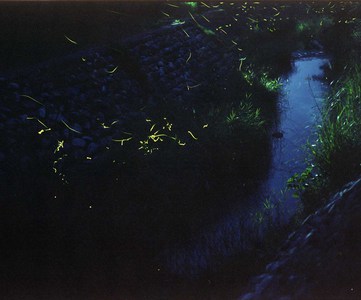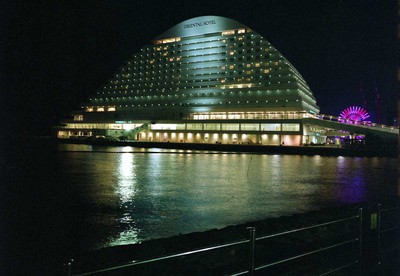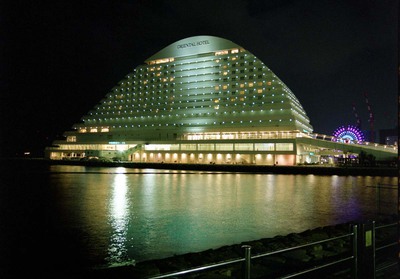�@�u���j�J��S�n�͋@�B����̃t�H�[�J���v���[���V���b�^�[�@�ŁA�ȉ���4�@�킪���\����Ă��܂��B
�[���U�u���j�JS�iSupreme�j�F
�@�u���j�JD���������@�\�̎�̑I�������A��{�I���\�̈��艻��}�������f���ł��B
�@�s���g�����@�\�̓��b�N�s�j�I���^�C�v�̃m�u��]�ɂ�钼�i���o�������B�����Y���o�ʂ͌����S2�����͂��ɑ傫����16.5�����B
������S�͌o�N�ω����L��A�ő呀�o���ɂ̓����Y�̋��������������Ȃ�̂ŁA
�����Y�͍ő呀�o��Ԃł̉��͂��Ȃ������ǂ������m��܂���B
�@�����Y�}�E���g�͏��^�o���l�b�g�Ƒ�^�o���l�b�g�iS2�Ƃ͈قȂ�܂��B�j�A��57 P=1.0�̃X�N�����[�}�E���g������Ă��܂��B
���̋@��܂ŏ����̃j�b�R�[��250���������g���܂��B
�@�V���b�^�[��B�E1�`1/1000�B�@���ԑ��x���g���܂��B�V���N���X�s�[�h��1/50�ŋ@�B���u���j�J�ő��̖������ւ�܂��B�@
�{�f�B���ʂɃ����[�Y�\�P�b�g���L��܂��B�~���[�̐旎�Ƃ����\�ł��B
�@�V���b�^�[�_�C�A���ɂ͓�����D�^����p�����ꂽ�A�N�Z�T���[�V���[���L��܂��B
�A�N�Z�T���[�V���[�͈�ʓI�Ȍ`��ł͗L��܂���B���̕����Ɉ�ʓI�ȃX�g���{��t����ɂ͐�p�̃A�N�Z�T���[���K�v�ł��B
�Ǘ��l�l��HP�{���̕��ɂ��̋M�d�ȃA�N�Z�T���[���f�ڂ���Ă��܂��B
�@S2�ŗǂ��b��ɏ��O���O���K�L�b�Ƃ��������グ�ɑ��āAS�͌㔼�������X�ɏd���Ȃ�O���O���O�V���Ƃ��������ɂȂ�܂��B
���슴��S�̕����ǂ���������܂���B
�@S�̃t�C�����o�b�N�͌����S2�܂ŋ��L�\�ł����AS�I���W�i���̃t�C�����o�b�N�ɂ͕z���S���R�[�e�B���O�̃}�K�W���V���b�^�[����������Ă��āA
�_�[�N�X���C�h���������ނƘA������M�~�b�N����������Ă��܂��B�܂��A�u���j�J�p�e���g�̃t�C�����ْ��@�\����������Ă��܂��B
�@�ǂ����������u���j�J�̕]�����㐢�ɂƂǂ߂��@��ł����A�����ɂ܂��ߓn�I�v�f�������A�@�\�I�Ȉ��萫��S2�ɂ͂���т܂���B
�����Ɠ����@�킪�����Ă��܂����B�Ƃ��������@�̂����Ȃ��Ȃ�܂����B
�[���U�u���j�JC ��C2:
�@S�̕��y�@�̈ʒu�t���ŁA�}�K�W���Œ�A�V���b�^�[�ō����x1/500�A�V���N��1/40�Ƀf�O���[�h���܂����B
�i�ł����A��55�����̃V���b�^�[�J��������14�`16msec�ő��s���܂��̂ŁA���o�I�ɂ͒x�������͎Ȃ��Ǝv���܂��B
����͎S�����x���Ȃ��Ă��܂��B�j
�@�ȗ����Ə�����鎖�������̂ł����A��q����S2�Ƌ@�\�I�ȑ傫�ȈႢ�����������m���Ă��܂��B
�@�����Y�͌���t�H�[�J���v���[���u���j�J�̊�b�ƂȂ�w���R�C�h�����O��]���̒��i�w���R�C�h�ŃX�g���[�N��14�����ł��B
���̂���75mm�g�p���̍ŒZ�B�e������S��500mm�ɑ���C��600�����i�ȉ�S2�܂œ��l�j�ɂȂ�܂����B
�w���R�C�h���j�b�g�ɂ͋������x������������Ă��܂�������ɂ���Đ��킠��܂��B
�w���R�C�h���j�b�g���O���Ƒ�^�̃o���l�b�g�}�E���g������A��ɖ]���p�̏d�������Y�������\�ł��B
�@��p�@�Ƃ���220�t�C�����Ή���C2�����\����܂����B�V���v���Ȉ��͎��v���b�V���[�v���[�g�Ȃ̂ŁA120��220�̐�ւ��̓J�E���^�[�݂̂ŗe�Ղł��B
�[���U�u���j�JS2:
�@�@�B���u���j�J�̍ō���i������ƍT���ڂȕW���ł����B�c�j�ŁA�u���j�J�̉��䍜���x�����@��ł��B
�V���b�^�[��B�E1�`1/1000�B�@1/4�`1/8�@1/30�`1/60�̊Ԃ��������ԑ��x���g���܂��B�V���N���X�s�[�h��1/40�B
�@�{�f�B�[�̐M�����͂��̋@��ł���Ƃقڈ��肵�A���݂ł��I�[�o�[�z�[�����\�Ől�C�̗L��@��ł��B
���̕��A���슴�A�~���[�旎�Ƃ��A���d�I���@�\�͏ȗ�����A���p�{�ʂ̋@��ɂȂ�܂����B
�@�u���j�J�ŗL���ȁh�O���O���K�L�b�h�͂��̋@��̑㖼���ɂȂ�܂����B
�V���b�^�[���̓��[���CSL66�̗l�ȗ}���̂��������l�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����ȍ쓮�������Ă܂��B
�@�~���[�͏]������C���X�^���g���^�[���ł����A���˖ʂ𔖂����ʼn������A�~���[�����A�E���^���ʼn�������\���ł��B
�E���^���̗ɂ��A�������鑽���̋@�̂̃s���g�ʒu�s�ǂ������Ă��܂��̂Ńt�@�C���_�[�X�N���[����������O�ɂ��������ȂƎv������`�F�b�N���Ă݂ĉ������B
�@S2�̌���ɂ͈ꕔ�̃M�A��^�J����|�ɕύX�����}�C�i�[�`�F���W���L��܂����B
�t�C�����m�u�̌`�قȂ�܂��̂ł����ɔ���܂��B�A���A�}�`���A���g�p�����Ŏ����I�ȃA�h�o���e�[�W�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B
�@���̋@��܂ł͌X�̕��i�ɂ����镉�׃o�����X�͂��܂�ǂ��Ƃ͌������A
�l�W���ɂݎn�߂�ƕs��̔����ɂȂ��鎖�������A�i���g���ɂ̓I�[�o�[�z�[������x�s���Ă��������I�X�X�����܂��B
�@S2�͎g���郌���Y�������A���̈Ӗ��ł��u���j�J�̒��S�I�ȋ@��ł��B�����Y�V���b�^�[�̃j�b�R�[��105LS F3.5�����Ȃ��g�p�\�ł��B
�@���Ɨǂ��Y�����̂ł����A�ʓ|�ł������Y�����̓w���R�C�h���ő呀�o�̏�Ԃōs���ĉ������A
75mm���ł͌�[���~���[�܂ŒB���Ă��܂��ꍇ���L��܂��B�i�����EC�n�ɑ������̂ł��B�j
�@�����Y�F
�@�u���j�J�̃����Y�͍��Y�̒������t�ł͌Q���Ď�ނ������A��ʓI�ȃ����W���烌�A�A�C�e���A���{���w�����瓌�ƃc�A�C�X���܂ő����Ă��܂����B
�܂��Ă�ߔN�܂Ŗw�njڂ݂��Ȃ������R�����[�����Y�ɂ܂ł������ȃR���N�^�[�Y�A�C�e���ɂȂ��Ă��܂��B
�@���\�I�ɂ͈ꕔ�̃����Y�������Č��݂̕]���ړx�⓯�����̃n�b�Z���p�ɕC�G����Ƃ͐����]���Ȃ��Ǝv���܂��B
�j�b�R�[���ƕ����ĉߑ�Ȋ��҂͂����܂���B����ǂ��납�`�ʂ��\��郌���Y�������A�ӊO�ɋZ�ʂ�v������郌���Y�Q�ł�
�i���b�I�����܂ł������ł��B�j����ȂƂ�������͂̈�ł��B
�܂��A�J�����̍\���I�Ȗ��ŁA200mm�ȏ�̃����Y�͏����ŒZ�B�e�����������Ȃ�܂��̂Ŏg���h����������܂���B
�@��r�I���肵�Ղ������Y�͎���5�킾�Ǝv���܂��B
�E�j�b�R�[�� O 50mmF2.8 �F
�@�g���Ղ��X�y�b�N�̍L�p�����Y�ł��B���˓������Ȃ�O�ɗL�郌���Y�ł��ˁB�t�B���^�[�a�̓�77mm
�E�j�b�R�[�� H 50mmF3.5�F
�@���N�̖������Y�@Nikkor 28mm F3.5�@�̃u���[�A�b�v�łł��B�]���̍��������Y�Ȃ̂ł����A�t�B���^�[�a����82�������L��܂��B
�@����ȃt�[�h���L���ł��B
�E�j�b�R�[�� P 75mmF2.8 �F
�@�u���j�J�̕]�����߂��W�������Y�B�Ō���ɑO�ʂ̏���`�ς��܂����B�ŏ����̃����Y�ƍŌ���̃����Y�ł͍\���������Ȃ̂ɕ`�ʂ����Ȃ�Ⴂ�܂��B�t�B���^�[�a�̓�67mm
�E �j�b�R�[��Q 135mmF3.5�@�F
�@���]���̒�ԃ����Y�ł��B�ɏ�������p�ӂ���Ă��܂����B�i��̘A���@�\�����̃����Y�Ə�������Ă��܂��B�t�B���^�[�a�̓�67mm
�E�[���U�m�� 150mmF3.5 �F
�@���]���̒�ԃ����Y�ł��B�����O�i�O���j/�V���[�g�o�����i����j�@���L��܂��B�t�B���^�[�a�̓�67mm
�E�j�b�R�[�� P 200mmF4�F
�@�ŒZ�B�e�������J�o�[�����p�̃A�^�b�`�����g�����Y���L��܂��B�t�B���^�[�a�̓�67mm
�@���傤�ǁA�R�[�e�B���O�����m�R�[�e�B���O����}���`�R�[�g�ɂȂ��������ɏd�Ȃ�܂��̂ŁA�}���`�R�[�g��搂��������Y������܂��B�A�������̃}���`�R�[�g�����Y�͂܂������x���キ�A
�����e�i���X�ɂ���ăR�[�e�B���O�̃������������������Y�������̂ł����Ӊ������B����Ƃ܂������Y�G�������g�̋Ɉꕔ�����}���`�R�[�g�ɂȂ��Ă��܂���̂ŁA
�]�������������Ă��Ȃ��ƕ`�ʂɑ傫�ȍ�������鎖�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B��������t�[�h���d�v���Ǝv���܂��B
�A�N�Z�T���[�F
�@�u���j�J�̓A�N�Z�T���[����r�I�L�x�ł��B
S�n�̓t�@�C���_�[�X�N���[���̌����o���܂��A
�E�`���j�[�t�@�C���_�[
�E�A�C���x���v���Y���t�@�C���_�[
�E30���v���Y���t�@�C���_�[
�ETTL�t�@�C���_�[
�E�t���[���t�@�C���_�[
�@���p�ӂ���Ă��܂����B�v���Y���t�@�C���_�[�̑��{���͂��قǍ����͖����̂Ŏg�p���͗ǍD�Ƃ͌����܂��A���[�y�t���̃`���j�[�t�@�C���_�[�͗����������t�@�C���_�[�ł��B
�@�����Ӓ��������̂͌`���Ă���EC�n�Ƃ̓C���^�[�t�F�[�X���قȂ��Ă���_�ł��B
�@����S2A����̍��̃t�@�C���_�[��EC�n�Ɠ����d�グ�ɂȂ��Ă���A���X�ł��ԈႦ�鎖���L��܂��B
�@���㊴��������̂�TTL�t�@�C���_�[�ŁA��N�̃}�~��M645���̃t�@�C���_�[���v�������ׂ�Ƃ��Ȃ������C���[�W������Ǝv���܂��B
�@�t���[���t�@�C���_�[�͐܂��݃t�@�C���_�[���ł͂Ȃ��A�V���b�^�[�_�C�A���ɓ����̃A�N�Z�T���[�V���[�ɑ������܂��B
�@�O���b�v�ɂ�
�EL���O���b�v
�E�s�X�g���O���b�v
�@���p�ӂ���Ă��܂����B�s�X�g���O���b�v�̓v���r���[�{�^��������\�ł����B
�@S�n�̃u���j�J�ɂ̓}�N�������Y���p�ӂ���Ă��܂��A�N���[�Y�t�H�[�J�X�W�ł͌�N��EC�n�ɑ����x���[�Y���j�b�g��G�N�X�e���V�����`���[�u���p�ӂ���Ă��܂����B
�@����ƁA��57�̃X�N�����[�}�E���g�ɂ̓~�m���^SR�}�E���g�̃G�N�X�e���V�����`���[�u�U�^�������\�ł��B
�i������SR�}�E���g�G�N�X�e���V�����`���[�u�͌a���قȂ�܂��̂ł����Ӊ������B�j
�@S2�͐F�X�Ɠ`���̗L��J�����ł����A�����ƃ����e�i���X���s���Ă���Ή]���Ă���l�Ȍ̏�����Ȃ��Ǝv���܂��B���̒������t�Ɣ�ׂĂ����^�ł��B
�@S2�ɂ̓N���[���t�B�j�b�V���̑��Ƀu���b�N�{�f�B�[���L��܂��B�����m�̕��������̂ł����AS2�̃{�f�B�[�J�o�[��18-8�X�e�����X�ł��B�X�e�����X�͓h��������f�ނł��B
���̃{�f�B�̍����Z�p�͓������C�c�ЂɋZ�p���^���ꂽ�Ȃ�Ă̂��L��܂����B
�@�ǂ��]����쓮���ł����A���O�ł͂��܂�C�ɂȂ��������L��܂���B�����݊������炩���m��܂���i�݊������炱�����HP�ŃX���b�h�����Ă���̂����ł��B�j�B�@
�V���b�^�[���Ŗ{���ɔ�����т����������͎����������L��܂���B
�@�摜�̓u���j�JS+�����R����-200�����@����ƃu���j�JS�ARB67�AGX680��1cm���݂̃{�f�B�T�C�Y��r�ł��B
�@�u���j�JS�n���Ă������Ⴂ�ł���B!
�@�ܘ_�������ɂ̓s���g�����܂���B
 efunon
efunon  2015/11/14(Sat) 11:12 No.50
2015/11/14(Sat) 11:12 No.50
�u���j�J�r�Q�Ńu���j�J�������̈�ɒB�����Ƃ����̂͂��������Ƃ��肩�Ǝv���܂��D�m���ɋ@�\��J�͎���ɃV���v��������Ă��܂����C����ł��n�b�Z���u���b�h���ɔ�ׂ�Ɨy���ɕ��G�ł����C���[�U�[�̃~�X��h���ł������S�@�\�͍���Ă��܂���D�Ō�Ƀo�L�b�Ɨ��銪���グ���o�����J�I�Ȉ��萫�����߂���̂��ƕ����܂������C����ɂ����قƂ�ǂȂ��C�Ȃɂ��ƈ��S���Ďg���鎿�������ȃJ�����ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��D�n�b�Z���u���b�h�i500�n�j�͑�σV���v���ȃJ�����ʼn��ɂ������Ɏv���܂����C�@�B�I���x�ō��킹����ł��镔���������������C�����т�Ă���ƃ����Y�ƃ{�f�B�̑g�ݍ��킹�ɂ���ăV���b�^�[�`���[�W���������Ȃ�������C�o�b�N�h�A�����܂��Ȃ������肷��̂����\����܂��D����ɔ�ׂ�ƃu���j�J�r�Q�̓s���œ������`�F�b�N�����蓮���ɗ]�T�����������������������߂��C�i���w�E�́C�����g�ɂ��s���g�̋����������j���ł��������Ȃ��̂͂��܂�Ȃ��̂͂������Ǝv���܂��D
�ł͂r��c���s���肩�Ƃ����ƁC�����ł��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��D�r�Q�i���Ɍ���^�j�̓��[�U�[����̃t�B�[�h�o�b�N��^���ɔ��f���Ĕ��ɐM�����������Ȃ��Ă���C����ɔ�ׂ�Ɨ�邩������܂��C�����̗l�X�ȃJ�����̒��ł͂ƂĂ��ǂ��o�������ނɑ�����Ǝv���܂��D�C���ł���l�����Ȃ��C���R�X�g���������߂ɗǍD�Ȍ̂������Ă���͎̂c�O�Ȃ��Ƃł����C�D���ȋ@�ނ͎�r���g��Ȃ�������s���͂���܂���D
���āC�u���j�J�̒��ł̔�r�ƂȂ�ƌ��\�Y��ł��܂��܂��D�j�R���e�̂悤�ȁi�Ƃ����ƌ���������������܂��j�M���������߂�Ƃ���r�Q�ł����C�r�Q�͒��]�����g���ɂ��ǂ��ł����C�����g�͂c�Ƃr�̃{�f�B�T�C�h�̃m�u�J��o�����ƂĂ��C�ɓ����Ă��܂��D�b�E�r�Q�ȍ~�̃w���R�C�h�͉�]�p���傫���C���x�̍����s���g���킹�ɂ͌����Ă��܂����C�ċߐڂ܂Ŏ����čs���̂ɂ͏������Ԃ�v���܂��D���̓_�C���[���C�R�[�h�̂悤�ɉE��Ńs���g�����킹����c�Ƃr�́C����ɂ��{�f�B�̃z�[���h�����肵�܂����C�Ȃɂ��s���g���킹���C���������Ǝv���܂��D�����d�������Y��t���č��g����ɂ͂�����ƕs���̂���\���Ȃ̂ŁC�ǂ����Ă��C�������Ȃ���g��Ȃ��ƂȂ�Ȃ��Ƃ���͂���܂��ˁD���́u�������v�Ƃ����_�ł́C�c�͔������C�y�����^�őf���炵���J�����ł͂�����̂́C��͂肢����C���g���J�����ł�����C���̏ꍇ�C�����o���@���r�I�����{�f�B�͂r�ł��D�J��o���ʂɂ��Ă��C�r�Q�� 600mm �ɑ��Ăc�E�r�� 500mm �� 35mm �J�����̕W�������Y���ł����ւ�g���₷���ł��i�L�p�����Y���ƁC�ǂ̃{�f�B�ł����Ȃ����炢�ߐڂɋ����Ȃ�܂����D�j
�c�̓T�C�h�̃m�u�������グ�ƃs���g���킹�ŋ��p����Ă���C�����o������߂����肷����Ԃ�����܂��D���̓_�C�r�̓N�����N�őf���������グ�����C���������Ƀs���g���킹�̃m�u�������đ�ϑ��쐫���ǂ��ł��D�J���t���b�N�X�����l�̑���n�Ŏg���₷���C����ɔ�ׂă��[���C�t���b�N�X�Q��t��SL66�n�̓t�H�[�J�V���O�����葤���ʂł�����z�[���h�ƃs���g���킹�̗�����������������܂��Defunon ���܂͂悭�����m���Ǝv���܂����C���[�U�[�ȊO�ɂ͈ӊO�ƒm���Ă��Ȃ���������Ȃ��u���j�J�r�̐▭�Ȉʒu�ɂ���~���[�旎�Ƃ��{�^���i�V���b�^�[�{�^���̂������C�{�f�B��ʁj����ϑ��삵�₷���C�V���[�Y���ł͂r�̍ő�̒�����������܂���D�r�ł̓m�u�̍��{�̋����w�W����]�����āC135/50mm�p��75mm�p�̋����w�W���ւ�����̂��ӊO�ƒm���Ă��Ȃ������D�D�D
�ׂ������Ƃł����C�r�̂ق����r�Q�������엦�������Ȃ��Ă��܂��D�t�@�C���_�X�N���[���̏�ɂ���g�̕��𑪂�ƁC�r�Q�� 50mm �ł����r�� 51.5mm ����܂��i���Ȃ݂ɂc�́C�\�����Ⴄ���߃X�N���[���̏�ɘg������܂��C�X�N���[���̗L�������̕���53mm������܂��j�D�������������������Ƃǂ����Ă����������z�����ނ��Ă��銴������̂ł����C�����Ɏg���Ă����v����n�C�A�}�`���A�̎��_�͂��������Ƃ���ɂ͂Ȃ������Ƃ������Ƃ�������Ȃ��ȂƎv���܂��D�Ȃ��C�����̌́i�c�Ƃr�ō��킹�ĂR��j�ł͋ߐڎ��������Y�Ƃ̘A���Ɉُ�̂���{�f�B�͂���܂���D
�b�Ƃb�Q�͂ǂ�������ʂ� MODEL C �Ə�����Ă���C���������Ƃ��莯�ʓ_�� 120/220 ��ւ��̗L���ł����C�b�Q������Ăb�Ƃ��Ĕ̔����Ă���悤�ȃP�[�X���悭�������܂��D�������b�͋ɂ߂Đ��Y�䐔�����Ȃ��C���ӂ��K�v�ł��D
�R�[�e�B���O�ɂ��Ă̓����Y�ɂ���ĈႤ��������܂���D�����̓}���`�R�[�e�B���O�̏o�n�߂ŁC�e�Ђ����Ȃ�͂����C�܂�����ɂ��Ă�������̂悤�ł����C���������Ƃ���}���`�R�[�e�B���O��搂��Ă�����̂̎{����Ă���̂͂P�ʂ��Q�ʂ����Ƃ��������Y������܂��D���̓_�ł̓j�R���͌��\�����������̂��C�u���j�J�p�j�b�R�[���ł͂��Ȃ�ӂ�Ƀ}���`�R�[�e�B���O����Ă���Ǝv���܂��D����̓j�R���e�}�E���g�̃I�[�g�j�b�R�[���̂b�t���C�j���[�j�b�R�[���Ȃǂ����l�ŁC�ނ����̎���ɔ�ׂ�ƈʼn_�Ƀ}���`�R�[�g���̗p���Ă���Ǝv����悤�Ȃ��̂�����܂��D���ʁC�[���U�m���͂l�b�Ƒ傫��������Ă��܂����}���`�R�[�e�B���O�ʂ����Ȃ��C�����ڂɂ����邢�A���o�[�F�̔��˂��ڗ����܂����C���ʂł��t���Ɏア���̂������悤�ł��D�����ETR�o�������炭�������悤�ŁC��� PE/PS/PG �ɔ�ׂ�ƃR���g���X�g�������銴�������܂��D�����Ƃ��ŋ߁C���̓��m�N������Ȃ̂Ń[���U�m�����D��Ŏg���Ă��܂����C�̂̓J���[���o�[�T������g���Ă���C�d�b�Ƒg�ݍ��킹�Đ[���t�[�h���g���C���F�̗ǂ��͑傢�ɋC�ɓ����Ă���܂����D
�����Y�̕`�ʂ͍D�݂�����C�܂����ꂼ���������܂����C�W���ɂ��Ắi�u���j�J�p�̊e�����Y���D�ꂽ�����Y���Ǝv���܂����j�n�b�Z���̕W������������ɂ߂ėǂ������Y�ł��̂Ŏ���������Ƃ��낪���邩������܂���D�������W�������Y�͂��Ƃ��C�L�p�����Y�����ꂼ�ꂿ���Ƃ悭�ʂ�܂����C�n�b�Z���p�ɔ�ׂ�Ə��^�y�ʂȂ��̂������̂�����菕����܂��D���������킯��SL66�p�̃����Y�͑��₳���ɁC��p�I�ȓW�J���K�v�ȏꍇ�̓u���j�J�̏o�ԂƂȂ��Ă��܂��D
�@S�͑��슴���D�����ł����A�`���j�[�t�@�C���_�[���̂����Ȃ���̃s���g���킹�͔��Ɋy�ł��B
�����Ƃ���R�B��ꍇ��EC-TL�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�u���j�J�̃t�H�[�J���v���[���V���b�^�[��������@��ł͌����EC�������߂������ł��ˁBEPR��EC�̑g�ݍ��킹�͂ƂĂ��D���ł����B
�@�j�b�R�[���ƃ[���U�m���ł����A���炭�O�Ƀj�b�R�[����40mm�ƃ[���U�m����40mm���ׂČ������Ƃ��L��܂��B
�@�F�X�ȏ��Ђ���B�e���ʂ͖��炩���낤�Ǝv���Ă����̂ł����A�ŋ߂̍ʓx�̍����|�W�Ƃ̑g�ݍ��킹�ł̓[���U�m���̕����ǍD�Ȍ��ʂł����B
�@�j�b�R�[���͎��ɂ̓R���g���X�g���������A�����ɋC��t���Ďg��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂����BC��DC���g���܂����������l�Ȃ��̂ł����B�ŋ߂͂Ȃ�ׂ���̃l�K���g�����������ł��B
�@���ł�SL66��40mm�͌���̃t���[�e�B���O�t�����g���Ă��܂����A�Ȃ�Ƃ������Ȃ����₩�ȕ`�ʂł�����C�ɓ����Ďg���Ă��܂��B
 efunon
efunon  2015/11/15(Sun) 01:31 No.54
2015/11/15(Sun) 01:31 No.54
�d�b�n��ɂ��Ă͂܂��ʍ��ŁC�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂����C�d�b�n��ł͂d�b�������߂Ƃ����_�����ӂł��D�茳�Ɏc���Ă���͍̂��@�\�� EC-TL �����ɂȂ��Ă���̂ł����C�v���d�b�͂����@��ł����D�~���[���n�[�t�~���[�łȂ��̂Ńt�@�C���_�����邭�C�V���b�^�[���x�\���ʼnB��镔�����Ȃ��C�^�C�����O���������ł��̂ŁC�V���v���Ŏg���₷���J�������Ǝv���܂��D��ԓ��ʔ��˂����Ȃ��R���g���X�g�������{�f�B���ȂƂ��v���܂��D
���������������Ƃ���C�d�b�ƃj�b�R�[���i���Ƀ}���`�R�[�g�j�̑g�ݍ��킹�ł͔��ɍd���ƂȂ�̂��m���ł��D���̓t�W�ł����ƃx���r�A�ł͂Ȃ��v���r�A��A�X�e�B�A���g���Ă��܂������C�ŏI���ł̓R�_�b�N��E100S�Ȃǂ��C�ɓ����Ă��܂������C��ʑ̂��X�Ȃǂ̎��R�̕��i�Ƃ������Ƃ������č��ʓx�C�d�߂̕`�ʂ�Nj����Ă����Ƃ��낪����܂��D�v�����̕`�ʂł͐l�����n�߂Ƃ��č���Ȃ���ʑ̂������������낤�Ǝv���܂��D�[���U�m��40mm, 50mm �͋����̏������ŁC����ł����Ɖf��̂��Ƃ����s���𐁂�����f���炵�������Y�ł��ˁD�c��r�̌J��o���@�\�ɂ́C�ォ��o���j�b�R�[��40mm�����[���U�m���̂ق������S���y���̂ŁC�����̃{�f�B�ɂ̓[���U�m���i40mm�܂���50mm�j��g�ݍ��킹�邱�Ƃ������ł��D
���͊��̂��D���Ȃ̂ŁA�ŒZ10cm�̍����傫���AS���D�ޏ��Ȃł��B
�W��75mm�ł́A�w���R�C�h���j�b�g�Œ����̂܂܂ł͗������B��Ȃ��̂ɑ��AS�͖����Ȃ����̏オ�ʂ��܂��B
�]��150mm�ł́A�o�X�g�A�b�v�����ɁB
200mm�́A6��̒[����[�ŏœ_������Ȃ��̂��A�����̒��ł��B�e�\�Ƃ����傫�ȍ��ɂȂ�܂��B
S2�Ɗr�ׂč쓮�����ɃW�F���g���Ȃ̂��悢�ł��ˁB�����ă~���[�A�b�v�{�^������ώg���₷���ʒu�ɂ���AEC�����֗��Ȃقǂł��B
����2���S�̂����Е��́A�~���[�Ռ��̓����������A����B�e�ŃX�^�b�N���Ă��܂��܂����B�������������Y���O���ĎՌ�����Ŗ߂��B�e���s�����̂��悢�v���o�ł��B���̌��]���ɒ����ŕ��������̂ł����A�܂����I�����ɎՌ����߂肫�ꂸ�ɉ�ʂ��R��g���u�����N����A�x�܂��Ă��܂��B
�������͑�ό��C�B���̖��@���I�[�o�[�z�[�����o���邤���ɒ����Ă�����ق����ǂ��̂ł��傤�ˁB
�u���j�J�͊��S�����i��A���̐ڎʃA�N�Z�T���[�������A�����i��̂܂܂Ŋ���̂͏d�v�Ȃ̂ł��B�O�r�Œ�Ȃ畁�ʍi��ŏ[���Ȃ̂ł����B
�g������ł͎��_�F�R���p�N�g�x���[�Y�̃Z�~�����A���̎������o�[�X�A�_�v�^�ōi�背�o�[���w�ő��삷��̂������ł��B�x���[�Y�Q�^�͑��ʐ��̓_�ŗ��܂��B
efunon�l�̂��Љ�̂悤�Ƀ~�m���^MC�p���ԃ����O�̃X���b�h���u���j�J�Ɠ���ŁA�I�[�g�x���[�Y���b�R�[�����������ő����o����̂͑傫���ł��ˁB�܂�MC/MD�}�E���g��L39��M42�A�_�v�^���L�x�ŁA�l�X�ȋ@�ނ̋��n�����ɂȂ��Ă���܂��B�����A100mm�ł������͏o�܂���B
�c�O�ł����R�j�JAR���ԃ����O�͌a���قȂ�AAR���N�_�ɂ����A�_�v�^�͎g���܂���B�i�z�b�g�O���[�Œ����Ďg���Ă��܂����j
�j�b�R�[��75�͂��̂܂ܐڎʃ����O�ʼn�������ƁA�傫�ȍi��ł̉掿�͊��҂ł��܂���B
���o�[�X���ƁAf8���炢������܂��ۂł��B
�x���[�Y���b�R�[��100�́A�J������ڎʉ掿�͐M���ł��d�܂��B
���ɂ�12.5mmf1.9����I����������̂Ő���͍L��ł��B
�����Ń~���[�A�b�v���З͂����܂��B
�l�b�g�ł̓u���j�J�͂Ԃ��Ǝv���Ă��������锭���������A���ێB�e���ʂ��ڍ������Ĕ�������Ă��邩�^��Ȃ̂ł����A�o���u����Ă݂�ƁA��ɓ`���V���b�N�̂قƂ�ǂ̓~���[���߂�ۂ̂��̂ŁA�V���b�^�[���s�܂ł̃V���b�N�͂悭�ɏՂ���Ă���̂������ł���͂��ł��B
����̓y���^�b�N�X�U�V�ɂ������邱�Ƃł��B
�������A���ڎʂł͋͂��ȐU������G�ł�����A�~���[�A�b�v�͗L�p�ł��B
����S2�Œ��ڎʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�����Y�V���b�^�[���g�����A�Í����o���u�J�����I�[�v���t���b�V�����܂��B
�Ō�ɁADX�CS�̊O�܃}�E���g��p�����Y�̖��͂��傫���ł��ˁB
180/2.5�̓��A�����Č������Ƃ�����܂��i�L��Ƃ���ɂ͑�ʂɂ���悤�ł����D�D�D�j�A250/4�͌��\����ł����A360�͏��Ȃ��Ă��~�����l�����Ȃ��̂œ���\�ł��傤�B
�O�܃����Y�p�ڎʋ@�ނ����݂��Ȃ��͎̂c�O�ł����ǁA250��350�̐��\�ɂ͂ق�ڂꂵ�܂��B
�w�������X�܂̂��Z����́A350�͐����K���X���g���Ă���ɈႢ�Ȃ��A����������ƃV���b�g�̃X�g�b�N���g�����̂��A�ȂǂƋ��܂��B
�{�����Ȃ��D�D�D
Nikkor-T350/5�@�J���A�x���r�AF
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2015/11/15(Sun) 21:51 No.58
2015/11/15(Sun) 21:51 No.58
�������ނƂ����ƃ��b�N���O���̂��m�F�D�����ԃv���[�g�����܂�܂����D
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2015/11/21(Sat) 23:43 No.67
2015/11/21(Sat) 23:43 No.67
�@���b�I�@�����������͂����Ɖ]�����ɖ��ɗ����܂��B
�@�[���U�m��MC 50�oF2.8 �ł����A�t���Ńt�[�h�������Ƃ��̗l�ȑ�_�ȃS�[�X�g���������܂��B
�@����ł����ʂ̕`�ʂȂǏ\���Ȑ��\���Ǝv���܂��B
 efunon
efunon  2015/11/22(Sun) 13:58 No.68
2015/11/22(Sun) 13:58 No.68
���̃S�[�X�g�́A��ʉ��̐��ʔ��˂���ł��傤���A����Ƃ���p�O�̑��z���ɂ��̂ł��傤���B
��������͉�ʂ̃n�C���C�g���炩�Ȃ��B����ƃt�[�h�ŃJ�b�g�ł��Ȃ��B
�ŋ�Rhinocam�Ƃ�������SLR�����Y���f�W�J�����X���C�h������645���B�e����A�_�v�^�������Ă��܂��B
www.fotodioxpro.com/vizelex-rhinocam-for-sony-nex-e-mount-cameras.html
14M��NEX-5�ł���9000����f�i��
SL66��HFT�����Y�ł����t���̉e����[���Ă��܂��̂��悭�킩��܂��B���ʓI�ȃn���肪�K�v�ł����A�Œ�t�b�h�����ł͂Ȃ��A�唻�p�̃n������L����������܂���B
��芸������Ńn���肵���̂ł����A���������摜�̔Z�x�ɍ����o�ĕs���R�ȍ������ɂȂ��Ă��܂�����B
Rhinocam�͑S�����ʐ����Ȃ��@�ނȂ̂ŁA�莝���͍l������K�v������܂��A��ʎB�e�ł������ȃn���肪�]�܂����̂ł��傤�ˁB
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2015/11/22(Sun) 19:39 No.69
2015/11/22(Sun) 19:39 No.69
>�唻�p�̃n������L����������܂���B
�@���������ʂ�ŁA���z�������ŎՂ邾���ŗlj����܂��B����̓t�[�h�����n���肪�K�v���Ǝv���܂����B
�@Rhinocam ��fotodioxpro �������Ă���V�X�e���ł��ˁB
https://www.flickr.com/photos/fotodiox/22091593984/in/dateposted/
�@���̉�Ђ̃A�N�Z�T���[�ނ͉����q�l���������Ă��āA�t���b�J�[�ł��Z���A�N�Z�T���[���Љ��܂��B
�@��ND����}�E���g�A�_�v�^�[�Ȃ�ĉ]�����̂��L��܂��ˁB
 efunon
efunon  2015/11/23(Mon) 06:58 No.70
2015/11/23(Mon) 06:58 No.70
�@���x�̓X�[�p�[�R�����[45mm��t����S2��CM�ɓo��ł��B
�X�[�p�[�R�����[�Ȃ�āA������荡�̕��������t���O���O���摜�p�Ƃ��ĕ]������Ă���l�ł��B
 efunon
efunon  2016/10/08(Sat) 21:42 No.520
2016/10/08(Sat) 21:42 No.520
�@���̃����Y�A���茳�ɖ����̂ł����AEC��p�iEC-TL�͕s�j�ƕ����Ă����̂ł����AC��S2�ł��g����̂ł��傤���B
�@S2�Ŏg�p���Ă݂悤�Ǝv��ꂽ�����g���Ȃ������ƂƂ����c�C�[�g��q�����܂����B
�@���̃����Y�́A�i�背�o�[���쓮�̃g���K�[�ƂȂ����ē��삷��̂ł����A���̌�̃{�f�B�[���Ƃ̋@�B�I�ȐM���̂����͗L��܂���B����̑��������Y�ł��B
 efunon
efunon  2017/02/05(Sun) 01:30 No.690
2017/02/05(Sun) 01:30 No.690
���Ȃ��Ƃ����Ƃ�2��ł�OK�ł����A�i���݃��o�[���R������斋�����肫��
�^�C�~���O���x���ƃt�H�[�J���v���[�����S�J����O�Ƀ��[�t�V���b�^�[��
�J���Ă��܂��댯���͂���܂��B
�e�X�g�B�e�͕K�v�ł��ˁB
�Z���t�^�C�}�[������̂ŁA�u���j�J�V�X�e���Ŏ��B��ł���M�d�ȑ��݂ł́B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/02/05(Sun) 11:35 No.692
2017/02/05(Sun) 11:35 No.692
�@���肪�Ƃ��������܂��B
S2���������̕����ALS105mm�����܂��쓮���Ȃ������B�Ƃ������b���Ă��܂����B
�@�����Ă������́AEC�����L��܂���ł����̂ŕs��͖��������̂ł����A�悭�X�l����Ƌ@�B�I�ȃg���K�[�ŁA�{�f�B�[�̃~���[�_�E���Ƃ�����蔲���Ȃ���쓮������̂͑�ς��Ǝv���܂����B
�@������ǂ����ɗL��Ηǂ��ł��B
 efunon
efunon  2017/02/05(Sun) 12:57 No.694
2017/02/05(Sun) 12:57 No.694
�Ⴆ��S2��C2���ڂ��Ă���J�^���O�ɂ́C���̃����Y�͍ڂ��Ă��܂���i�����炭�C�܂��o�Ă��Ȃ������j�D
����������̂��̂Ǝv����C�C�O��S2A�̎����CS2�EEC���p�̃A�N�Z�T���J�^���O�ɂ͂��̃����Y���ڂ��Ă��āC
�����ɂ͓��ɒ��L�͂���܂���D
����CEC-TL��EC-TLII�̃J�^���O�ɂ͑Ή������Y�̂Ƃ���Ɂu�������j�b�R�[��105mm�͏����܂��v�Ȃǂƒ��L������܂��D
�����̂��Ƃ���C��͂�S2�ɐ����Ή����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��D
���̃����Y�ɂ͍i��쓮���o�[������Ă���V���b�^�[������܂ł̎��ԉ҂�������E�G�C�g�i�������S�ɉ��
�d�������O�j�������āC����Ń^�C�~���O������Ă��܂����C�{�f�B���̓������x���ƃ^�C�~���O�������Ǝv���܂��D
�����Y���̒x���@�\�̓K�o�i�[�ł͂Ȃ��̂ŁC���ԓI�ɐ��m�ł͂Ȃ���������܂��C������̓{�f�B���̓�����
���������ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��D�������Ń~���[�̓����Ȃǂ��x���{�f�B������C���ꂾ�ƃ^�C�~���O��
����Ȃ����낤�Ǝv���܂��D
������� EC-TL �� EC-TLII�͏u�ԍi�荞�ݑ����̂��߃^�C�~���O���قȂ�C�g�p�ł��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��D
 ���Y
���Y  2017/02/05(Sun) 18:11 No.695
2017/02/05(Sun) 18:11 No.695
�唻�p�j�b�R�[���̂��̂ɂ��悭�������̂�����悤�ł��D�ǂꂪ�ŏ��̂��̂�������܂��C������ɂ��Ă�
�e�b�T�[�^�̐v�ŁC���[�t�V���b�^�[�Ɏg���C�U�X�����J�o�[����C�v���X�J�����p�Ƃ��ēT�^�I�� 105mm F3.5 �����Y�C
�Ƃ������Ƃɂ͂����Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁC��͂�U�U�����́i�����Y�{���́j�C���[�W�T�[�N���͑傫���̂��낤�Ǝv���܂��D
 ���Y
���Y  2017/02/05(Sun) 18:18 No.696
2017/02/05(Sun) 18:18 No.696
����EC-TL�ł��I���ł���Ə����Ă���T�C�g������A���͉��^�I�ł������������̑g�ݍ��킹�̑��݂͔ے�ł��܂���B
�������EC-TL�ŘI�����邱�Ƃ͉\�ł��B
105LS��1�b�A�t�H�[�J����1/8��荂���ŁALS���J���Ă���ԂɃt�H�[�J���ŘI������킯�ł��B
LS�̈Ӗ�����܂��ǂˁB
����ƁA�u�ԍi�荞�ݑ�����LS�͕��Ă��܂��Ă���̂�ET-CL������AE�͎g���܂��A����Ƃ�TTL�����̂��ߍi�荞�݃{�^����������105LS�̃V���b�^�[���쓮�J�n���Ă��܂��܂��B
EC-TL�Ƃ̑����͍ň��ł��ˁi��
EC�ł�105LS�����������Ń{�f�B���V���b�^�[��1/60��荂���ɃZ�b�g�ł��Ȃ��Ȃ�A�둀���h���ł��܂��B
�i������ƍ��茳�ɂȂ��ċL���ŏ����Ă��܂��B�Ԉ���Ă����炷�݂܂���j
1/60�̓V���N�����x�܂�t�H�[�J���̃X���b�g���S�J�ɂȂ鑬�x�ŁA���̌̂ł�LS1/500�`1/125�Ŏg�p�\�ł��B�iEC�͖�����S2��S��葬���V���N�����x��35mm�J�������݂ł��j
�t�H�[�J��1/8�ɂ��Ă����LS1/30��荂���œ�������̂ŊȒP�ł��B�i�̍�������̂Ńe�X�g�K�{�ł��j
��͂�EC�Ŏg���̂������Ƃ����ɓK���������Y�ł���܂��傤�B
���FECTL, 105/3.5�J���i�{�f�B1/60,�����Y1sec�jReala Ace, Pentax closeup S82
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/02/05(Sun) 20:57 No.697
2017/02/05(Sun) 20:57 No.697
�@�u���j�J�Ɖ]���Ƃ�����̃T�C�g���Q�Ƃ������������̂ł����ALS105mm�͖ӓ_�ł����B
�@�e�b�T�[�^�C�v��3G4E�̍\���ŁA����Ȃ������̂��A���܂�ꐶ���������Ă������������܂���B
�@�����Ă��Ă��ϋɓI�Ɏg�����L�����L��܂���B���������̃C���X�^���g���^�[���~���[���X�|�C�����Ă��܂����A��������v���r���[�{�^���������ƍ쓮���Ă��܂�����ŁA�g���h�����������o���Ă��܂��B
�@
 efunon
efunon  2017/02/05(Sun) 22:00 No.698
2017/02/05(Sun) 22:00 No.698
���̓����ł��w�nj����Ȃ��W����p�̃e�b�T�[�ŁA�J���t�߂͂���قǐ��\�͍����Ȃ��B
�|�[�g���[�g�p�Ȃ̂ł��傤���A�{�P���͂����قǗǂ��������Ȃ��B�i�D�������ł��傤���j
�V���b�^�[�`���[�W���Ȃ��ƃt�@�C���_�[���������Ȃ��B�i����͌��_����ł͂Ȃ�LS�`���[�W�Y���h���ł���܂����j
���̓t���b�V���ڎʖړI�ōw�����܂������A�P�̂ł̍ŒZ�͉����A�Ɠ��̍\�������璆�ԃ����O��x���[�Y���g���܂���̂ŁA�N���[�Y�A�b�v�����Y�����I�������Ȃ��B
���ۏ������Ă��Ă��A�����ӎu�Ńt���b�V�������ړI�ɒǂ����܂Ȃ��Ǝ����o���@��Ȃ������Y�ł��ˁB
LS�Ȃ̂ő���a���͓��������������܂��A�����ꖡ�������Ă���Ȃ��Ǝv���܂��B�g������ł݂�ΈĊO�X�����̂悤�ɖ����o�Ă��邩������܂��D�D�D
�]�k�ł������̌��ETR��SQ�AGS�V���[�Y�̃����Y���S�R���Ȃ���ł��B�ӏ��͊��S���ꂳ��Ă��Đ������Ȃ��Əœ_�������ʂł��Ȃ����炢�����B�ǂ��ʂ邵�A�Â��Ă����������ڂ��邩����Ȃ���ł����A���]���̉��D�D�DGX680�͖��邢���C����p�ӂ��Ă��āA���������łĂ��܂��ˁB
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/02/06(Mon) 21:48 No.700
2017/02/06(Mon) 21:48 No.700
�@�u���j�J�R�����[�̓j�b�R�[����[���U�m���ɔ�r���āA�����Ȑݒ�ɂȂ��Ă��܂����B
���̂��߁A���\�I�ɒႭ�����Ă������炢���L��܂����A���ꂪ�ǂ̒��x�Ȃ̂�������
�C�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�R�����[��300mm�ȏ�̃����Y���C���i�b�v��
�E300mm�@F5.0�@4���\���@�t�B���^�[�T�C�Y67mm�@�iNo30425�j
�E400mm�@F6.3�@4���\���@�t�B���^�[�T�C�Y67mm�@�iNo30426�j
�E500mm�@F7.0�@4���\���@�t�B���^�[�T�C�Y77mm�@�iNo30427�j
�@�����̃����Y�̓w���J���t�H�[�J�b�V���O�}�E���gNo2�iNo30430�j�Ƃ����}�E���g���j�b�g
�ɑ����i�l�W�}�E���g�j���Ďg�p���܂��B���Ȃ݂Ƀw���J���t�H�[�J�b�V���O�}�E���gNo1
�iNo30435�j�Ƃ������̂��L���āA135mm�@F2.3�A200mm�@F3.5�p�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�����̃J�^���O�ׂĂ݂�ƁA�ǂ̃����Y���v���Z�b�g�i��Ə�����Ă��܂��B�������A��
�ʓI�ȃv���Z�b�g�Ȃ̂�300mm�����ŁA400mm��500mm�͕��ʍi��ł��B
�@�{�f�B�[�ɂ̓{�f�B�[���̃w���R�C�h���j�b�g�ƃ}�E���g���j�b�g���������Ďg�p���܂��B
�����i��ł͗L��܂���̂ŁA�A���@�\�͗L��܂���B�A�b�T���Ƃ������̂ł��B
�@����300mm��500mm�������Ă���̂ł����A2�{�Ƃ����ЂƔ�ׂ�ƂƂĂ��y�ʂł��B
����ȂƂ���ɃR�����[�̃����b�g���L��̂ł͂Ǝv���܂��B�@�A���A�w���J���t�H�[�J�b�V���O
�}�E���gNo2�ɕt���Ă���O�r���̓o�����X�������J�߂�ꂽ���m�ł͗L��܂���B
�iEC-TL�ɑ�������300mm��500mm�̉摜��Y�t�v���܂��B�j
 efunon
efunon  2017/02/11(Sat) 21:41 No.711
2017/02/11(Sat) 21:41 No.711
�@���ӕ��̓_��������l�ȉ摜�ł��B�t�B������RDP�V�@�i���F22
�ӊO�ɋt���ɋ����āA�������܂����B�_�ސ쌧�̍]�̓��W�]�䂩��B�e���܂����B
�@�t�B������RDP�V�ł��B�@�{�f�B�[��EC-TL�@�A���b�H
 efunon
efunon  2017/02/11(Sat) 21:47 No.712
2017/02/11(Sat) 21:47 No.712
�@���̃����Y�̏ꍇ�n������������肵�Ȃ��ƁA�����x�C�����O�O���A�[���������鎖���L��܂��B
���̎���̃����Y�ł͕��ϓI�Ȑ��\��������܂��A�g�p�ɂ͂����Ӊ������B
�@���̓_�ɔz������ΐ��\�I�ɂ͏\�����Ǝv���܂��B���ɋߔN�̍ʓx�̍����t�B�����ł́A�����̍��Ƃ͈Ⴄ���ʂɂȂ�Ǝv���܂��B
�@��Ƀj�b�R�[����[���U�m���Ɣ�r����Ă��܂��u���j�J�R�����[�ł����A�����x�g���Ă݂ė~�����Ǝv���܂��B
 efunon
efunon  2017/02/11(Sat) 22:08 No.714
2017/02/11(Sat) 22:08 No.714
�@50,150,300,500mm ���o�b�N�ɋl�߂āA�]�̓��̗�����o���Ă����܂����B����ł��y�ʂȃR�����[�����Y�ɂ͏������܂����B
�@����͈ꏏ�Ɏ����Ă������Ō����50mm F3.5 �ł��B
���Љ�����œ_�Ƃ͈قȂ�A�����i��ł��B
�@�f�W�^���@�͖�i�ɋ����Ɖ]���Ă��܂����A�t�B�����J�����ł����Ȃ�̈Â��ł��Ή��\�ł��B
�@�������A�I���͂����Ղ�ڂ��ǂ��Ǝv���܂��B
 efunon
efunon  2017/02/11(Sat) 22:19 No.715
2017/02/11(Sat) 22:19 No.715
�E�w���J���t�H�[�J�b�V���O�}�E���gNo1���g���^�C�v�B
�@�v���Z�b�g�i��ł��B
�E�i�胊���O�����F�A���}�C�g�̃^�C�v�B
�@�����Y�����[�L���b�v���˂����݃^�C�v�ŁA�������v����ł��B
�E�S�g�u���b�N�^�C�v�B
�@�����Y�����[�L���b�v�̃l�W���ȗ�����āA�j�b�R�[�����Ɠ����^�C�v�̃L���b�v���������ł��܂���B
�@�ȑO�A�v���Z�b�g��200mm�������Ə������̂ł����A�Ă̒�g��������Ă��܂����B
�@��Q2�����t�ɑg�����Ă��܂����B���������B
 efunon
efunon  2017/02/17(Fri) 20:56 No.732
2017/02/17(Fri) 20:56 No.732
���ЃT���A�\���S�[���A�V�O�}�A�^�������Ȃǂ�35mm���t�p�ɍi���ă��C���A�b�v���\�z���Ă����̂ɑ��A
�i�^�������͑唻�p���ꕔ�������j
�R�����[������35mm�����W�t�@�C���_�[�p����A�������t�p�A�唻�p�܂ōL��ȃV�X�e�����ێ����Ă��܂����B
�����̒����J�����ɑ��ẮA�y���^�b�N�X67�A�[���U�u���j�JS�AS2�A���[���CSL66�ɑΉ����������}�E���g���p�ӂ���Ă��܂����B
�������S�Ăɋ��ʂ���킯�ł͂Ȃ��X�ɑΉ��o���郌���Y��}�E���g������A�Ή��}�͕��G�ł��B
�u���j�J�p�ɂ́A�����̎����i���A�������}�E���g�i���ł͒��i�j�ƁA����̎����i��Ή���p�}�E���g������܂����B
�����300,400,500�̌����}�E���g���]������������܂����B
�����i�ɑ��Ĉ����ł����Aefunon�l���w�E�̒ʂ肩�Ȃ菬�^�y�ʂł���̂����[�U�[���_�ł̓|�C���g�����ł��B
�J�������������Y�����ł́A�Ȃ��Ȃ������_�������Y������܂��B
�ّ�ɂ̓u���j�JS2�p��100/2.8�����i��ƁASL66�p400mmf6.3���ʍi�肪����܂��B
100�͏����Ɋr�ׂ�Ƃ�����ƃk�P�������R���g���X�g���Ⴂ�C�����܂����A�𑜗͂͂�������������I���R���p�N�g�ł��B
400�͑�Ϗ��^�Łi�œ_���߂̓{�f�B�ɔC���ċ�������������j�����^�т��y�ł��B
�����̃e���e�b�T�[500/5.6�������o���̂��S�O���Ă��A�R�����[400�Ȃ犓�ɓ���₷���ł��傤�B
�����Y�����ł͍��]���ł���������ƃR���g���X�g����߂��ȂƁB
�u���j�J�p300��500�͑��������������������L�����O�ł��B
500�̍��͑f���炵���ł��ˁB���b�g�̃V���G�b�g�̃G�b�W�������B�_�����͂��Ȃ�ψ�Ɍ����܂����B
300��50���Ȃ��Ȃ��ł��B�������ׂ����\�ł͂Ȃ��ł��傤���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/02/23(Thu) 22:24 No.745
2017/02/23(Thu) 22:24 No.745
�@�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�R�����[�����Y�͍ĔF������Ă��ǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B�ʼn_�Ɏ��������邱�Ƃ͂ł��܂��B500mm�͗ǂ��Ӗ��ŗ����܂����B�����ƃK���K�������̂��Ǝv���܂������A���S�t���ł��t���A�������Ȃ��Ďg���Ղ��Ǝv���܂��B
�@�������R�����g�̒��ɋL�ڂ���Ă���l�ɁA���Ɍy�ʂł��B
���ꂪ���̃����Y�̗ǂ��_�ł����B
�@500mm�ɔ�r�����300mm�͎g��������������Y�ł����B
�i��H���̕\�ʏ������`�[�v�ŁA�i��ƃS�[�X�g����������Â��^�C�v�̃����Y�̗l�ł��B
�@���t�̃t�@�C���_�[�ŏ\���ɒ��ӂ���K�v���L��܂��B
�@�ǂ���̃����Y�������R���g���X�g���Ⴂ�Ǝv���܂��B���A�ŐV�̃|�W�ɂ͑������ǂ������ŁA�Õ����ӊO�Ƀl�o���܂��B
400mm�͂ƂĂ��]�����ǂ��l�ł��ˁBSL�p���ƃ}�E���g�͌Œ�Ȃ̂ł��傤���BSL�p���ƌy�ʂ͕K�{�ȗv�f���Ǝv���܂��B
�@
 efunon
efunon  2017/02/24(Fri) 22:23 No.746
2017/02/24(Fri) 22:23 No.746
������ SANKYO KOHKI�̕\�L�������Ȃ鍠����
�R�X�g�_�E�����̉e���Ȃǂŋ}���ɕi�����ቺ���Ă���Ƃ̎��ł����B
�u���j�J�p�͑��v�ł��ˁB
 �䂤�ꂢ
�䂤�ꂢ  2017/03/06(Mon) 19:34 No.747
2017/03/06(Mon) 19:34 No.747
>�R�X�g�_�E�����̉e���Ȃǂŋ}���ɕi�����ቺ�c
�@�u���j�J�R�����[��300mm��500mm�͂�͂�j�b�R�[����[���U�m���Ɣ�r����ƍ��̓`�[�v�ł��ˁB
�@����ł����������ꂽ��g�������H�v����Ƃ��Ȃ�ǂ��Ȃ�܂��B
���[�J�[���R�X�g�I�ɏo���Ȃ������o�b�t���̒lj��┽�˖h�~�h�����s���ƌ��ʓI�ł��B
 efunon
efunon  2017/03/06(Mon) 21:21 No.748
2017/03/06(Mon) 21:21 No.748
���o�[�X�}�E���g��A�i�荞�ނ��Ƃł�����x�͋ߐڎ��̐��\�͊m�ۏo���܂����A�ߐڐ�p�v�̃����Y�̂ق����i����J������Ԃł̐��\�͂��D�G�Ȃ��Ƃ͊ԈႢ����܂���B
���efunon�l�����Љ��Ă����悤�ɁA�u���j�J��3�̃}�E���g�̂�����ԓ����̃X�N�����[�́A�~�m���^MC�p���ԃ����O�Ƃ҂������v���Ă��āA�����H�Ń~�m���^SR�}�E���g�����Y�������o���܂��B
�����ă~�m���^�ɂ͗D�G�ȃx���[�Y�p�Z�����}�N�������Y�������Ă��āA�������͂łȂ����̂́A�u���j�J�ɗ��p����Ƒ�ώ��p�I�ł��B
���́A�����Y�ʑ���180�x��]���A�\�����^���ɗ��Ă��܂����ߎ��F������邱�ƁB����͎�ԉɂ��l����Ɨe�F���Ă��悢���ƁB
�ł��悭�p����̂�MD�����100mmf4�ŁA�K�E�X�^�C�v�BMC�����100/4�̓g���v���b�g�ł��B�{�����グ�������ɂ̓x���[�Y�}�N��50/3.5�A�����RMS�}�E���g��25mmf2.5�A12.5mmf1.9���g���܂����A��v�ȃX�^���h�ɌŒ肷�郌�x���̊g��ɂȂ�ł��傤�B�]�k�Ȃ���25mmf2.5�͑f���炵�����\�ł��B�����ɂ̓��C�c����t�H�^�[���̒��Ă��܂������A�Ȃ��Ȃ��s��ɏo�ė��܂���B
���̓I�I�f�}�����u���j�JECTL, �R���p�N�g�x���[�Y�Ƀx���[�Y�I�[�g���b�R�[��100mmf4���A�J���莝���B�e�ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/05/22(Mon) 00:13 No.814
2017/05/22(Mon) 00:13 No.814
�t�H�[�J���v���[���@�̂��肪�����ł��ˁB
����ς�u���j�J�t�H�[�J���ɂ̓j�b�R�[������ˁA�Ƃ������͐���F�}�E���g�A�_�v�^������肭�������B
����20������������Y�L���b�v�ƒ��ԃ����O���G�|�L�V�ł��������̂��g���Ă܂��B
���ɂ́A��X�n�b�Z��1000F�p�T�[�h�p�[�e�B���ԃ����O�̃X���b�h���u���j�J�Ɉ�v���Ă�����B�ڎʂ����ł���1000F�p�����Y���t�����܂��B
���ʐ^��ق̃W�����N�{�b�N�X���琳�̕s���̎���A�_�v�^���@��o���܂����B�쐶�̊��ŁA����̓u���j�J�K�����낤�ƁB�����A��ƃ��V�R���}�E���g�A�_�v�^�ł����B���Ⴀ�x���[�Y�p�v���i�[���t������I
ECTL, �R���p�N�g�x���[�Y�AS-Planar 4/100, f5.6
�Ȃ�Ƃ������i��������[�Y����ł悢����ł��Ȃ����B���V�R���p�����i��A�_�v�^�͑��݂��Ȃ���ł���ˁB�Ȃ�Ƃ��D�D�D
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/05/22(Mon) 00:29 No.815
2017/05/22(Mon) 00:29 No.815
���FNikkor-P 200/4, f8�C1/30�C
���FNikkor-O 50/2.8, f11, 1/8
�E�FAis Micronikkor 55/2.8�Cf11�C1/40�C�i�V���i��PE3056�C�}�N���t���b�V���Z���T
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/05/27(Sat) 00:02 No.817
2017/05/27(Sat) 00:02 No.817
�@�f���炵���ł��I
�@�~�G�̎R�ł͎B�e���̂������ɂȂ�̂ɁA�܂��ďd�����u���j�J���̒��łƂ́B
�@�{�f�B�[�������Y���l����ςł��B
�@
 efunon
efunon  2017/05/31(Wed) 21:29 No.819
2017/05/31(Wed) 21:29 No.819
�@�摜�ɂ��F�X�Ǝʂ��Ă��܂����A���̋@�ނ̎���ׂ͍��ȃA�N�Z�T���[���S���S�����Ă��܂����B
�@�ʐ^�ł����������Ƃ̖����A�N�Z�T���[�̌����ɐG���ꂽ�̂͋M�d�Ȍo���ł������A
����������ۂ̑��슴���f���炵���A�����̃��J���b�`�@����ґ����\���Ă��܂����B
�@�u���j�J�t�����̃G�s�\�[�h���A�x�e�����̔Z����4���Ԃ������Ɖ]���Ԃɗ���Ă����܂����B
 efunon
efunon  2017/05/31(Wed) 21:58 No.820
2017/05/31(Wed) 21:58 No.820
����̃I�t���C���~�[�e�B���O�ł́C���͂R�c�v�����^�Ő��삵���A�_�v�^�i�O�ŃV���b�^�[�̌��������́C�����L�������Y�����t����L39�̃l�W���������́C52mm�̗Y�l�W�ɕϊ����邱�Ƃłe�}�E���g�̃����Y�����o�[�X�Œ��ڂ�����悤�Ȃ��̂Ȃǁj�������Ă����܂����D���������ŐV�̋Z�p�ƌÂ��J�������o����ĐV�������Ƃ��ł���Ƃ����̂��ʔ����Ǝv���܂��D
�Q�������������Ȃ��B
���Ē�����SQ�X�|�[�c�t�@�C���_�[���L���b�`�[�ł��BSQ�p���Ă������BETRS�̂͌������ƗL�邯�ǁB
���[�ɂ͌��̃v���Z�b�g�R�����[����a���B
100��135���A�A�܂����B�j�b�R�[��180/2.5�͂���܂������H
�����ĉ\�̃j�b�R�[��85/1.8���Ď��݂���̂��ȁH
���肰�Ȃ��E���1000F��Sonnar135,250���Q�Ă��܂��ˁB���͍D���ȋ@��ł����A�o��Ɠ����ɂ���ȏ�͂Ȃ��قNJ�������Ă���D�Ɗr�ׂ�Ɛ�����͌��n�I�ȋ@�B���Ǝv���܂��B
���Y�l��D�ɕt�����Ă���̂̓}�N���V���i�[120�ł��傤���B����]�݂���ō��̑g�ݍ��킹�ł��傤�B
�A�N�Z�T���[�������������Ƃ���ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/05/31(Wed) 23:55 No.822
2017/05/31(Wed) 23:55 No.822
��ݏ��̒���t�߂ɂ͗��h�ȗ��ق������āA�~���͂قƂ�ǂ��q�����Ȃ��̂ŁA���ɂQF�̑�L�Ԃ̑����J�������ĎO�r���ĂĎB�e���܂����B
�g�C��������z�������A���ꂪ���肷��܂ł��炭�҂��܂������A��{�I�ɂ͊y����B�e�Ȃ�ł��i��
�������~�����͎��Q���Ă��āA�[���ɉ��O�ʼnE��1�����B�e�����̂ł����A���Ⴂ�Ă��ĊO�ɂ�1���Ԓ��x�������炸�A���Ƃ̓r�j�[���ɃJ�����𖧕����I��h�~���āA�ʐ^���ԂƂǂ�Ă���܂����D�D�D
�����߂̂��h�ł���B�����Ă��܂��Đ\����܂���D�D�D
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/06/01(Thu) 00:14 No.824
2017/06/01(Thu) 00:14 No.824
�c�ɂ��Ă���̂̓A�|�}�N���V���i�[ 120mm �ŁC���������o�܂��i���������X�J��o���K�v������̂ŁC��������͗]����܂��j�D�u���j�J�̃x���[�Y�ɂ��Ă������ł����C���͓��l�̂O�ԃV���b�^�[�A�_�v�^�[��SL66�p�i����͋������ŁC�w���������́j�������Ă���̂ŁCSL66E �ɂ��Ďg�����Ƃ������ł��D���̏ꍇ���֕��������o����ԂŖ��������o�܂��̂ŁCSL66 �̕W�������Y�Ƃ͈قȂ薳�����ɑ��ăe�B���g���ł��C�~�j�`���A���ʓI�Ȏʐ^���ȒP�ɎB�e�ł��܂��D
�E�[���U�m�� 300mm F4.5
�E�j�b�R�[�� 300mm F5.6
�E�u���j�J �R�����[ 300mm F5
���L��܂��B�i�ꕔ300mm�ł͗L��܂��A�X�g��-�x��������A�A�X�g���S���A�����V�A�ɂ��L�����ƕ����������L��܂����c�j
�@���ꂼ��������L���āA
�E�[���U�m�� 300mm F4.5�F�ŒZ�B�e���� 4m 1800g
�@�ׂȕ`�ʂ����܂��B�[�z�̎B�e�ł��D�G�ł����B
�E�j�b�R�[��P 300mm F5.6�F5�Q 5���@�ŒZ�B�e���� 4m 810g
�@�y�ʂȃ����Y�ŁA�ƂĂ��k�P�̗ǂ������Y�ł��B
�E�R�����[ 300mm F5.0�iNo 30425�j�F3�Q 4���@�ŒZ�B�e���� 4.9m 1130g
(�����Y�{�� 480g + No30430 �t�H�[�J�b�V���O���j�b�g�U 650g)
�摜�����ɍi��̔��˂Ǝv����t���A�[���o�₷���̂ł����A��肭�J�b�g�o����ΈӊO�ɗD�G�ł��B
 efunon
efunon  2017/06/03(Sat) 22:29 No.833
2017/06/03(Sat) 22:29 No.833
�E�j�b�R�[��300�ɂ͎O�r�����L��܂���B���̕��y�ʂŎ��̂��Ղ������Y�ł��B
�E�u���j�J�R�����[�ɂ͎O�r���́h�L��h�̂ł����A���ۂɂ�300mm�g�p���ɂ͎��p�ɂȂ�܂���B
�E�[���U�m��300mm�͂��̃����Y�^�C�v����K���X�̋l�܂��������Y�ł��B�d�ʂ��L��܂��̂Ŏ莝���B�e�͏�����������Y�ł��B
�@�����Y���ʂɃx���g��ʂ���̂ł����A���͊O���Ă��܂��܂����B
�@�u���j�JS,EC�n�̖]�������Y�̒���300mm�͎g���Ղ������Y�ł��B
���ƂȂ��Ă͂Ȃ��Ȃ�������̂�����Ȃ��Ă��܂��܂������A�j�b�R�[���������Έ����ɓ���ł��܂��B
 efunon
efunon  2017/06/03(Sat) 22:43 No.834
2017/06/03(Sat) 22:43 No.834
����Nikkor�͌����L�����Ȃ��B
���肪�Ƃ��������܂��B
Astro Telastan300mmf3.5��1000F�}�E���g�������Ă��܂����A�t�����W�o�b�N���Ⴂ�����܂��̂Ńw���R�C�h��������V�삵�Ȃ��ƃu���j�J�ɂ͕t�����Ȃ��ł��傤����A�������Ƃ���ΐ������Ƃł��B
�����I�ɃA�X�g�������̃u���j�J��}�E���g�����������^��ł����A�����i�Ȃ牽�ł�����̐��E�ł��B
�����V�A�̃����Y�͎ւ̓��Ȃ̂ʼn����o�Ă��邩�킩��܂���B
�ꎞ�V�̖]�����V���b�v�H���t�����W�o�b�N�����������t���b�N�X500mm�A1000mm��̔����Ă����͂��ł����A�}�~���A�y���^�b�N�X�p���������B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/06/03(Sat) 22:56 No.836
2017/06/03(Sat) 22:56 No.836
�@3��̏œ_�����ɑΉ����邽�߂ɁA�摜�̗l�ɏœ_�������ɐF�������ꂽ�����w�W����]/�I�����ĎB�e�����Ɣ�ʊE�[�x��\���ł���l�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�g�p���@�̓t�@�C���_�[�ŃC���t�ɍ��킹����ԂŁA�g�p���郌���Y�̐F�̋����w�W���w���R�C�h�����O�̃C���t�ʒu�ɍ��킹�܂��B
�@�F�̎�ނ́A300mm�F���F�@400mm�F���F�@500mm�F��F�@�ł��B
�B�e�̂��߂Ɏw�W���Y�����Ă���܂����A�����ƐԊO�w�W�܂Ŕ����Ă��܂��B
 efunon
efunon  2017/06/03(Sat) 23:45 No.837
2017/06/03(Sat) 23:45 No.837
�@�A�X�g���̃u���j�J�����Y��
Tachar�ATelastan�AFern ��3�킪�œ_�����̉����ėp�ӂ���Ă����l�ł��B
�@�j�b�R�[����300mm�͓������猩�����܂���ł����B
�@�����̏�������Ă��������L��܂����A��ɂȂ��ď��߂Ď����ɐG�ꂽ���͉��i�������Ȋ��ɂ͌y�������Y���Ǝv���܂����B
 efunon
efunon  2017/06/04(Sun) 00:12 No.838
2017/06/04(Sun) 00:12 No.838
�c�O�Ȃ���Q���͊����܂���ł������A���������I�ɍs����Ƃ����ł��ˁB
�݂邵�̋@�ނ́A�o���邾���g�������Ȃ������Ȏ҂ł���
�ŋߐV�K�̋@�ނ�S������Ă���܂���B
�P�Ȃ�l�^��Ȃ̂��傾�������R�ł��B
�����ʔ����ۑ�͖����ł��傤���H
�U�U�J�������Ƒ��ɉ��������Y�Ȃǂ̕�@�Ƃ��đ������������Ȃ��̂�
�����I�Ƀu���j�J�ӂ肪���ƂȂ�܂����A���ۂɂ͐���������K�����������Ă��Ȃ��̂������B
���̒��ɂ͐����̃}�E���g�A�_�v�^�[�Ȃǂ��̔�����Ă��܂����u���j�J�p�͂قڊF���B
��͂���ɂ����@��Ȃ̂ł��傤�B
���̕��Ǝ��������o�������o���܂��̂Ō���b�オ�L��܂��B
�����ʔ����l�^�Ȃ��ł��傤���H
 �䂤�ꂢ
�䂤�ꂢ  2017/06/04(Sun) 09:26 No.840
2017/06/04(Sun) 09:26 No.840
�@��������͔N1���ڕW�ɍl���Ă�����̂ł����A����͓��e���\�z�ȏ�ɔZ�������̂Łi�`���[�g���g�p���������Y�̌������ʂ܂ōs���Ă��܂����B�j�A
�I����̘A���̒��Ŏ���͉����^�c���l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ƙb���Ă��܂����B��͂莟��͓����ŁI�Ƃ������N�G�X�g�����������l�ł��B
�@�u���j�J�̃}�E���g�A�_�v�^�[��SQ�������ƃn���h���C�h���������̂ł��傤���B�t�����W�o�b�N��102mm���炢�L��̂œ���̂����m��܂���B
 efunon
efunon  2017/06/04(Sun) 11:16 No.841
2017/06/04(Sun) 11:16 No.841
�����ŁA�䂤�ꂢ�l�̃u���j�J����30mm��q�������͂��Ȃ̂Ɏ��O���Ă��܂����B
���ꍛ��ƒv���܂��B�������҂��Ă���܂��B
efunon�l���������肪�Ƃ��������܂��B
Astro�Љ�T�C�ghttp://www.exaklaus.de/astro.htm
�ɂ�Bronica�Ə����Ă����ēǂݗ��Ƃ��Ă���܂����B�_��ȉ�Ђ̂悤�ł��ˁB
Telastan 300/3.5��6x6���]���Ƃ��Ă͈ٗ�ɖ��邭�A�L���m��FD�����i�ɔ���قǁB
���ɏ_�炩���F�������c���Ă��܂����A��g�債�Ȃ���Ε��͋C����摜�ł��BKilfitt��300/4��Sonnar300/4�̓V���[�v�Ȃ̂Ŏg��������ꂻ���ł��B
Bronica��Wiki�ɂ�Astro�CAstragon���ɂ���܂����BWiki�ɂ�Kilfitt�̈�A�̐��i��������Ă��āA������������Ȃ��ƃt�����W�o�b�N����Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă��܂��܂��B�������������o���l�b�g�̑���a�𗘗p���Ē��ɒ��ݍ��ނ悤�ȃA�_�v�^�Ȃ̂�������܂���B
�����������̂ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/06/04(Sun) 22:20 No.843
2017/06/04(Sun) 22:20 No.843
���܂�ɂ����\���Ⴗ���āD�D�D
�ȑO�䂤�ꂢ�l�ɂ��~�߂�ꂽ�Ǝv���܂����A����l���x�������̂ł�����o���Ă��܂��܂����B
���ʁA����l�ł������Ǝv���܂����i����
�V�O�}��3�{�e���R���B���X�̓j�R��F�A�I�X�̓u���j�J��o���l�b�g�B
35mmSLR�j�R��F�����Y��66�t���t�H�[�}�b�g�Ŏg����B
�i��͊��S�蓮�B
�����Y���S���������g���Ă��Ȃ��̂ŁAAPS-C�f�W�^���p�����Y�ł�6x6���J�o�[����B�������i�萧��̓}�E���g����O���Ď����i�背�o�[�Ƀ`�b�v�����ނ����Ȃ��Ƌ��l���܂��B
APS-c��10mm�A60mm�}�N���A
F�p14mm�A20mm�A35�C50�C55�C100�C180�C300�A�ȂǑ������Ă݂܂������A�Â����������s���g����Ȃ��O�d��B
�܂��J���ł͎����������Ăǂ��Ƀs���g���Ă邩�����Ȃ��B
�i��ƒ��S���班�����������юn�߁A�i��قǐ�s�x�����P���܂����A�[���ȃ��x���ɂȂ�O�ɉ�܂łڂ��͂��߁A�ǂ��Ƀs���g���Ă邩�����Ȃ��B
������x3�e���R���ł�����3�i��Â��Ȃ�A���肬��œ_�����킹���郌�x���܂ŋ��ʎ��������P���������ɂ͈Â����āif11��32����j�t�@�C���_�[�������Ȃ��B
�掿�̎���S���l���Ȃ��悤�ɂ���A10mm�Œ��L�p30mm�������i�^������10-24mm�̌Œ�t�[�h�ŏR���Ȃ����߂ɂ�12mm����ɂȂ�܂����j200mm���ƒ����^�y�ʂ�600mm�A300mm����900mm�I�܂��}�N�������Y���������{���ɁB�����ł͗L�蓾�Ȃ��Y�[���{���������B�ʔ�����ł���B�掿��������������D�D�D�D
���̋Z�p�ōĐv���āA���Xx2���炢�ɏo������ō��Ȃ�ł����ǂ˂��D�D�D
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/06/04(Sun) 22:42 No.844
2017/06/04(Sun) 22:42 No.844
Zodiac-8 30mm/f3.5�̍����ڂ��܂��B
�́A�a�J�̉��l�Q�ōw�����܂����B
kiev88�X�N�����[�}�E���g�̍��̕��Ȃ̂Ń��m�R�[�g�̃����Y�ł��B
���̌�̂l�b�̃����Y�Ƃ���r���܂������A�]�荷�͊����܂���B
��ʒ��ɑ��z���ʂ荞�ނƐ���Ƀt���A�[�����荞��Ə��X���ȑ㕨�ł��B
���̃����Y�̉����͂P�O���N�O�ɍs�����̂ł���
�F�l�ƎB�e�ɏo����������Ă��āA���̑O���ɓˊэ�Ƃ̔����ō��܂����̂Ŏd�グ���G�ł��B
���������Ǝd�グ�悤�Ƃ��v���܂������A��x�o���オ��Ɩʓ|�Ō��݂Ɏ���܂��B
�����A�茳�ɂ���l�b�̃��f���ł�������낤���ȁH
 �䂤�ꂢ
�䂤�ꂢ  2017/06/05(Mon) 01:04 No.845
2017/06/05(Mon) 01:04 No.845
>��������͔N1���ڕW�ɍl���Ă�����̂ł���
�Ȃ�قǎ�����L�肻���ł��ˁB
����ŗ͂��g���s�����Ă��܂��̂����ł����A�ň��X���C�h�I�t�݂����̂ł��y�������ł��B
����͐����ŁB
 �䂤�ꂢ
�䂤�ꂢ  2017/06/06(Tue) 21:04 No.850
2017/06/06(Tue) 21:04 No.850
�Q���҂͐��������͖��������̂ł����A�@�ނ�A�N�Z�T���[�������āA���̐�������ۂɃt�@�C���_�[��`���Ă��������A
���ۂɃ_�~�[�t�B�����ő��슴���������Ă�������̂ł����A4���ԋx�e�����ł���ƈꏄ���������ł����B
�@�����ŊJ�Â���ꍇ�͉����^�c���@���l���Ȃ��Ǝ��E�����Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂����B
���ɁA����Ȏ������Ă݂����Ƃ����Ă݂����Ȃ�ĊF����̈Ă��L��܂����狳���Ē�����K���ł��B
 efunon
efunon  2017/06/10(Sat) 08:29 No.851
2017/06/10(Sat) 08:29 No.851
�����m�̒ʂ�A�{�f�B�������ōi��D��AE�܂Ŕ�����D����̂ł��B
����ȑO�̃��f���ł̓t�H�[�J�V���O�X�N���[���͂���K���X�{�v���X�`�b�N�t���l�������Y�̍\���ł����B
EC�ȍ~�̓t���l����̂̃v���X�`�b�N�t�H�[�J�V���O�X�N���[���ƂȂ�܂��B
���̂������ŃX�N���[�����͖��邭�Ȃ�܂������A�V���Ȗ����N���܂��B
�t���l�������Y�̃s�b�`���r�����Ƃ��牽�����O���O���ȃt���l���̉e��������̂ł��B
����́A���̌�̂r�p���Ɣ�ׂ錩��肷��͔̂ۂ߂܂���B
S2�̓X�N���[�������̃��V�s���l�b�g��Ō��J����Ă���܂��̂Ŏ��{����Ă�����������Ǝv���܂���
EC-TL/EC-TLII�ł����Ѝ̗p�������̂ł����A����ς肱���ł���Q�������͂�����܂��B
�I�o�v�̃��[�^�[�\���ł��B
�X�N���[���̏㕔�i�����Y���j�ɐH�����ތ`�ŘI�o�v�̕\��������܂���
�X�N���[���ɒ��ڃV���b�^�[���x�̐��l�\�����݂����Ă��邽��
���̃X�N���[�����ڐA����ƂȂ�ƁA���̐��l�\�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�b���Y���ʁA�ȒP�ȕ��@�ʼn������邱�Ƃɂ��܂����B
�w�菑���ł��x
�P�K�L�j�ŃX�N���[���ɒ��ڕ����������~���ď������݂܂��B
�����T�C�Y�͂ƂĂ��������̂Ń��[�y�ȂǂŌ��Ȃ����Ƃ��K�v�ł��B
���Ȃ݂Ɏ��͐E��̎��̌������Ō��Ȃ����Ƃ��܂����B
���邭�āA���₷���X�N���[�����ƃt�@�C���_�[��`���Ă��邾���ł��y�����Ȃ�܂��B
 �䂤�ꂢ
�䂤�ꂢ  2017/06/17(Sat) 12:49 No.859
2017/06/17(Sat) 12:49 No.859
���Ȃ�x���Ȃ��Ă��܂��܂������A������ɎQ�����ꂽ�F�l�����b�ɂȂ�܂����B
���X�ł����A�悤�₭�t�B�������X�L�������܂����̂ł��v���܂��B
40mm�iNIKKOR-D��ZENZANON�j�c����ꂽ�ʂ�ZENZANON�̕������p���L���B�𑜗͂͋͂���ZENZANON�̕����ǂ��悤�Ɍ�����B
135mm�iNIKKOR-Q F3.5��KOMURA F2.3�j�c���ӂ̉𑜗͂�NIKKOR�̕����A�R���g���X�g��KOMURA�̕����ǂ��悤�Ɍ�����B
NIKKOR-Q 25cm F4�c�𑜗́A�R���g���X�g���ɑ�ϗǂ��B
NIKKOR-T 35cm F4.5�c���ӌ��ʗ����������AF8�ł��c��B�t�[�h�̃P�����ł͂Ȃ��Ǝv���B3���ʂ̊��ɁA�ӊO�Ǝ��ӕ��܂ʼn𑜂��Ă���B
 uccyan
uccyan  2017/07/03(Mon) 03:21 No.885
2017/07/03(Mon) 03:21 No.885
Photodiox Rhinocam�Ƃ��������i6x4.5cm�t�H�[�}�b�g�����B�e���u������A�I���W�i���̓n�b�Z���u���b�hV, �}�~��M645, �y���^�b�N�X645�̃}�E���g�������ł��B
APS-C�t�H�[�}�b�g�̃\�j�[�~���[���X�c�ʒu�ŏ㉺4���v8�����������܂��B1400����f��NEX-5���g���Ɩ�9000����f�ɂȂ�ɂ߂Đ��ׂȉ摜�������܂��B
�ŋ߃�7���g��6x6�B�e�o�����ʋ@�킪�o���悤�ł����������Ă��܂���B
Rhinocam�{�͍̂��ۋK�i4x5�o�b�N�Ƀt�B�����z���_�̂悤�ɑ����ł���K�i�ɂȂ��Ă���A����͂���𗘗p���Ă��܂��B
�u���j�J�̓}�E���g������ނ��d�w���Ă���S�ĂɑΉ�����ɂ�S2�^EC�̑�o���l�b�g���K���ł��B�o���ޗ��̓R�����[�e�����A�̃W�����N�ŁA���݂����邽�߃X���C�X���Ă��炢�A�ėp�����l���e�q�j�J4x5�{�[�h�ɌŒ肵�Ă��܂��B
���̌v�Z�~�X�œ����ǂ̑唻�{�f�B�ł����������o���̂�����ł������A�W�i�[�g�Ƀe�q�j�J�A�_�v�^�t�����i�W�i�[�n���f�B�Ɠ�����肩���j�{���Ȃ疳�������Ȃ��ߐڐ�p�̃R���p�N�g�x���[�Y�Ƒg�ނƒ��x�悢���Ƃ����������p�ɃS�[�T�C�����o���܂����B
������o���l�b�g�����Y�͍��㒲�����K�v�ŁA�]���n�̓w���R�C�h�X�g���[�N�������̂ő��v�ł����A��Ԏg����������LS105/3.5���Ȃ��Ȃ������o�������Ă��܂��B
�����Nikkor-H 50/3.5�̓R���p�N�g�x���[�Y�ɕt�����Ȃ����Ƃ������B�w���R�C�h�ɒ��ԃ����O�����ނ��ƂłȂ�Ƃ������B
�Ƃ������A�x���[�Y����Ȃ��Ă��A���ԃ����O�ł�������I
�����Ǝ莝���̏��o���l�b�g�����Y���e�X�g���܂������A�F�Ȃ��Ȃ��f���炵���掿�ł��B����Nikkor-P 75/2.8�̓��m�R�[�gcm�\�L93xxx�Amm�\�L132xxx�A180xxx�A�}���`P�EC259xxx��ʂ��ď����i��Ƒf���炵����s�ŁANEX-5��f����t�܂ʼn𑜂��Ă���A�����ԕW�����ߏグ�������̂��Ƃ͂��閼�����Y�ł����BNikkor-H�EC�͎��Ӊ掿���f���炵���A�V����̎���ɂȂꂽ�͂��̖������Y�ł��B
DDR�[���U�m����3�{�e�X�g���A��{��Nikkor�����鍂�掿�������A�J��������79�N�𗠕t���鐬�тł������A���2�{�͂���قǂł��Ȃ��A�̍����傫�����Ƃ��ĔF���B�܂�MC�[���U�m��80/2.4���ǍD�~���ł��B
�����Komura100/2.8�̍����\�ɂ͋�������܂����B
�[���U�m��150�̓m���^���g�v�R�����f���炵���B
�����܂ł���Ă����ĂȂ�ł����A�u���j�J�����Y��t����Rhinocam�͍�i����p�r���l���Ă��܂���B��Ƀ����Y���\�̊m�F�e�X�g��z�肵�Ă��܂��B
��͂��i�ɂ�1���ŘI������6x6���A�I���W�i���{�f�B���g��Ȃ�����˂ƁB�e�X�g�œ���ꂽ�����Y�������l�������i���삪����Ɋy�����Ȃ�܂��B
�摜�F���R���p�N�g�x���[�Y�A�����w���R�C�h�A�E�F�㕔����ʒu���ߗp�O���E���h�O���X�i�X�v���b�g���j�������Ƃ���
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/07/03(Mon) 19:01 No.886
2017/07/03(Mon) 19:01 No.886
��̌�����͂ƂĂ������������悤�ŁA�Q���ł������X���A�܂����ł��B
�����Y�̉掿��r�̂��b��ϋ����[���q�ǂ��܂����B
�����������Ă��Ȃ��R�����[����a�̔�r�͂��肪�����B
250��350�͑�ϗD�ꂽ���\�ł��ˁB350�̎��ӌ��ʒቺ�͌����Ă݂�Ίm���ɁB�ȑO�̉摜����������o���Ɩ��炩�Ɏl�����Ȃ��Ă��܂��B
�C�ɂȂ�Ȃ��\�}�ł����̂ŁA����ĔF���v���܂����B
���̃R�}�ł͖ڗ����Ȃ����̂�����A�L�^�Y��Ŋm�͂���܂��i��Ή��������̂����B
BronicaS, Nikkor-T 350mm�J��, 160NS, �O�r
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/07/04(Tue) 14:07 No.887
2017/07/04(Tue) 14:07 No.887
�@���v���Ԃ�ł��B�I�t���C���~�[�e�B���O�̍ۂ͂����b�ɂȂ�܂����B
�@�e�X�g����Ă��������͍ŒZ�B�e�ߕӂł����̂ŁA�F�X�ƃ����Y�ɂƂ��Ă̓L�r�V�C�����ł����ˁB
�@����ł����A�ȃ����Y�̈�[���_�Ԍ����ċ����ÁX�ł��B
���͐���INF�ł��ˁB���O�Ńe�X�g�ł���Ηǂ��ł��ˁB
 efunon
efunon  2017/07/04(Tue) 20:37 No.889
2017/07/04(Tue) 20:37 No.889
���m�|�b�h�g�p�ł��B
���X�ǂ����ė��j�b�R�[���B50�����ł��B
���̒l�i�ł��̃V�X�e������ɓ���̂͋����ł��B
�t�B�������Ȃ獡�ł��ˁB���N�̖��@���������ł��肪�o���܂��B
�������A���V��1���g���ăV���b�^�[�X�s�[�h�𑪒肵���Ƃ���1/1000�ݒ��1/400�߂��܂ŃX�s�[�h���オ���Ă���܂����B
���N�g���Ă��炸�O���X���ł��Ȃ��Ă����ł��ˁB
�s���g�����킹�鎞�ɂǂ����Ă������Y�o�����Ɏ肪�s���Ă��܂��A���Ă��܂��܂����B�ǂ��J�����ł��ˁB
 CLPO
CLPO  2017/07/08(Sat) 10:05 No.890
2017/07/08(Sat) 10:05 No.890
�X�e�b�`���9000����f�Ŋώ@����ƁA����Œቿ�i�̂Ƃ�����Όy�����Ă��܂������ȕW�������YNikkor-P 75mmf2.8�̐��\�͋����ׂ����x���ł��邱�Ƃ��킩��܂����B
�J��f2.8�́A�S�̂Ƀn��������ו��͟���ł��܂����𑜂͂��Ă���Ƃ����A�����̃j�b�R�[���ɋ��ʂ���ߏ��̌X�������������܂��B
�܂����ӌ��ʂ͎�ቺ���Ă��܂��B
���̉掿�̋ψꐫ�͋�������ŁANikkor-P�̒��S���̗ǂ��̓t�B�����ł��悭�b��ɂ������Ă��܂����A�f�W�^���ł͎l���܂Œ��S�ƂقƂ�ǂ����Ȃ����𑜗͂������܂��B
f4�ɍi��ƃr�l�b�e�B���O�͉������A���S�̃n�������Ȃ�����ĐF�ʃR���g���X�g���オ��܂����A�s�N�Z�����{�ł͎��ӂ̟��݂͊J���Ƃ����܂���B
f8�ł͑S�̂Ƀn���������A�l���܂ŋ�������̉掿�ƂȂ�Af16�ł��T�ˈێ�����܂��B
1���ɂ�8��I������K�v������A�܂������{���e�X�g�������߉�������f2.8-4-8-16��4�i�肵�������܂���ł�����f4��8�Ƃ̊Ԃ��ǂ��Ȃ��Ă���̂��͌���̉ۑ�ł��B
Nikkor-P�̓V���A��8���A13���A18���̃��m�R�[�g��Nikkor-P�C�������A�}���`���͂��ɋt�����i��̓V����t���A���}�����A�J���̐F�ʂ��Z�����ȂƂ������x�ŁAP�͓���ƌ����ėǂ��掿�ł��B
P�̃N�Z�m�^�[������K�E�X�ό`�ƂȂ���Nikkor-H�C�͑O�ʂ��傫��������P�̊J�����ӌ��ʒቺ�����P���ꂽ�ȊO�͂قƂ��P�ƕς��܂���B
f4�ɍi�����Ƃ�H�C�̂ق������Ӄn���͏�������������X���B
�i���Ă��܂���P��H�͕ς��Ȃ��B�t�B�����ł͖�i��{�P��H�̕����[���Ȃ̂�H�͖����l�Ƃ͂����܂��AP���������ꂽ�̂��킩��܂��B
���ƃr�I���^�[OEM�[���U�m��80mmf2.8�́A�J���n���͎����悤�Ȋ������]�v�ɏo�邩�Ǝv���܂����A�l���͏�������܂��B�܂�f8�ɍi�����Ƃ��̐ꍞ�ނ悤�ȃV���[�v�l�X�͓��M���ׂ��ł��B
�m���^��80mmf2.4�͊J���n���͑���f2.8�@��葽���ł����𑜗͂͂悭�A�i��Ɣ��ɗD�G�B
Nikkor-H50/3.5���J���n���X���͂���܂����A75/2.8���͏��Ȃ߁B���Ӊ掿��75mm���͊Â��Ȃ�܂����A�L�p�Ƃ��Ĕ��ɋψ�ő�L���łȂ�����e�͈́Af8�ł͗ǍD�ɂȂ�܂��B
Nikkor-O50/2.8�����l�ł����A3.5���͂��ɃV���[�v�ŐF�ʃR���g���X�g�������悤�Ɋ����܂����B���p�㍷�͂Ȃ��ł��傤�B
��芸�����A�{�f�B�̃I�}�P���x�ɂ����]������Ă��Ȃ�Nikkor-P75/2.8�ł����A�ō����̐��\�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
�J���n���̓|�W�Ȃ�}���C���ɘI������Ɩڗ����܂��A���m�N���Ȃ��掆�̃R���g���X�g���グ��Ή��������邩���B�����ʼn𑜗͂��ۂ���Ă��邱�Ƃ��d�v�ł��B
�i��Ζڂ����߂�悤�ȍ��掿�������܂��B
��7��35mmSLR�p�����Y����ʑ̂Ńe�X�g���Ă��܂����ANikko-P�قǎ��ӂ܂ō��掿���ψ�ȃ����Y�͂܂�ł��B
�摜�FRhinocam�@Nikko-P75mmf2.8(13����j�J���CNEX-5(1400����f�j8��I���X�e�b�`�A�k�����|���Ă��܂��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/08/10(Thu) 18:11 No.933
2017/08/10(Thu) 18:11 No.933
���{�������Ă���̂ł��������l�Ȋ����ł����̂Ń����Y�̐������Ǝv���Ă��܂������A�����Ƃ������Ȃ��̂ł��ˁB
�@�C���[�W�I�ɂ͏������ꂪ�o�銴���ł��������߂Ȃ���Ǝv���܂����B
�@�r�l�b�e�B���O�̓t�B�����ŎB�e���������ǂ����������܂��B
�L�b�g�����Y�̗l�Ȉ����� 75mmf2.8 �ł����A�����E�C�������������܂��B
 efunon
efunon  2017/08/13(Sun) 08:01 No.934
2017/08/13(Sun) 08:01 No.934
���͎����t�B�����ł́A���S�͔��ɐ�s�Ȃ��̂́A�J���ł͎��ӂ��s�\���Ȉ�ۂ��Ă��܂����B
���̓_�ł�Nikkor-H�̂ق�����ۂ͗ǂ��A�܂�Makina��80/2.8�������i��������i�ɂ͗ǂ��ƍl���Ă��܂����B
�Ȃ̂ō���f�W�^���̌��ʂɋ����Ă��܂��B
120�t�B�����̕��ʐ��ƊW������̂ł��傤���B
��芸�����A�f���͗ǂ������Y�Ƃ������Ƃ�m��܂����B
�ŏ��Ɏv�����̂́AMicroNikkor55/3.5���ő����Ȃ��ƁB
��ʉE���ӂ薳���H�s�N�Z�����{�N���b�v�������܂��B�����Ƃ������ɂȂ邩�ǂ������M������܂��D�D�D
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/08/13(Sun) 20:09 No.936
2017/08/13(Sun) 20:09 No.936
�@���̌�A25�N���J��������牓�̂��Ă��܂��܂������A2�N�O�f�W�^�����n�߂܂����B���X�}�E���g�A�_�v�^�[�V�т�����Ă��܂����̂ŁA�u���j�J-NIKKOR���g�������Ď���A�_�v�^�[�Ō��݂́A�y����ł��܂��B
����SLR���̌����u���j�JS2�ł����̂ŁA�u���j�J�{�f�B�ɑ��Ѓ����Y��t����A�_�v�^�͐F�X�Ǝ���v���܂����B
�z�[�X�}��8x8�{�[�h��S2�ɕt����Ȃǐڎʗp����ł��B
�t�Ƀu���j�J�����Y�𑼋@�ɕt����̂́A�o�b�N�t�H�[�J�X���Z�����ƁA�����Y�P�̂ōi�萧�䂪������Ƃ��玎���Ă���܂���ł����B
�����ڎʃ����O��f�ނɂ���Ύ����i��͊O���瓮�����܂��ˁB
�܂��ڎʃ����O�X���b�h�̓~�m���^SR�ڎʃ����O�Ƌ��ʂȂ̂�SR�}�E���g�ɂ͖����H�ŕϊ��ł������ȋC�����܂����A�œ_���ߋ@�\���ǂ����邩���ŁA�܂������Ă���܂���B
A7�ɕt���ĂȂ��Ȃ��i�D�����ł��ˁB�摜���珃���w���R�C�h�����g���̂悤�ł��B
��L�̂����育��������Ă��邩�Ɗ��S���Ă��܂��B����������I���������B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/08/26(Sat) 01:39 No.939
2017/08/26(Sat) 01:39 No.939
����ł̓}�E���g�A�_�v�^�[�̏ڍׂł��B
�u���j�J(S,EC)�p�����Y�������
1.�}�E���g�������C�J�lϳ�Ăɂ��܂����B�i���R�͌�q�j
���i�̏���
�����Y--�u���j�J�p�ڎ��ݸ�(C-A)--�u���j�J�p�w���R�C�h--�~�m���^�@MC135�p�t�[�h--�����e�@Concept® nikon-L/M�A�_�v�^�[
�ڎ��ݸނ���ꂽ�͍̂i��߂��邽�߂ŁA�u���j�J�g���̕��͈�ʓI�ɒm���Ă���Ǝv���܂��B�~�m���^�p�t�[�h�̓w���R�C�h�ɃW���X�g�T�C�Y�Ȃ̂ŁA4�_ȼގ~�߂ɂ��Ă���܂��B�Ȃ��t�[�h�̓J�b�g���Ă���܂����A���������o��l�ɒ����߂��܂����Bȼގ~�߂Ȃ̂Ō��ɖ߂��܂��Bnikon-L/M�A�_�v�^�[�ƃt�[�h�̐ڒ��́A�A�_�v�^�[�̋��������O���Ă���G�|�L�V�ڒ����Ă���܂��B
�u���j�J�w���R�C�h�ɍi��A���s�����t���Ă��܂����A���ꂪ����Ɩ��������o�Ȃ��悤�Ȃ̂Ŏ��O���Ă���܂��B
NIKKOR�����Y�̍i�蒲�߂͏o����l�ɂȂ�܂������Azenzanon 100mm��t�����ꍇ�̂ݒ����ݸނ̃��o�[�𑀍삵�Ȃ��Ƃ��܂������܂���ł����B
�Ȃ����C�J�l�}�E���g�ɂ����̂��ƌ����܂��ƁA�œ_�H�[������o�Ă��܂��ATECHART�i�e�b�N�A�[�g�jLM-EA7 ���C�J�l�}�E���g�����Y - �\�j�[��.E�}�E���g�d�q�A�_�v�^�[�q���ŃI�[�g�t�H�[�J�X�����悤�Ǝv��������ł��B
����ɂ��u���j�J�����Y���I�[�g�t�H�[�J�X�ŎB�e�o���܂��B
�g�p���������ł͓��ɖ��Ȃ��쓮���Ă��܂��B�������A�����Y�̏d��������̂ŁA���K�i�O�̎g�p���@�ł��B�œ_�H�[����ł�500g�܂ł̃����Y�d�ʂɂ��Ă��������ƒ��ӏ���������܂����A���ƋC�ɂ����ɉ��ł��t���Ă��܂��B
�莝����NIKKOR 75mmf2.8,50mmf2.8,50mm f3.5, zenzanon 100mmf2.8�ŃI�[�g�t�H�[�J�X�쓮�o����̂��m�F���Ă��܂��B
�B�e�͂��̏����Ői��ł��܂��A���������߂������Ǝv���܂��B
���C�J�l�}�E���g�ɂ����̂ŁA����Ȏg�������o���܂��B�ŐV�̃��C�J�l10�Ȃǂւ��t���Ǝv���܂����A�܂������Ă��܂���B�i��
�߂��̃t�N���E�̪�ł̎B�e�ł��B
���H���ăX�N�G�A�T�C�Y�ɶ�Ă��܂����B
�g���Ă݂������ł͒��]���ŎB���Ă��銴���ł��B
�܂��܂��B�e�̕��͏o���Ă��܂��A�u���j�J�p�ݽނŊy�����B�e�������Ǝv���Ă��܂��B
�Ȃ��u���j�J�{�f�B�́A�ŋ�EC����肵�܂����B
�NjL
�ŋ߃y�g��-���C�J�l�ƃ~�����_-���C�J�l������������܂����B��������I�[�g�t�H�[�J�X�B�e�Ŋy����ł��܂��B
�Ȃ�ƃI�[�g�t�H�[�J�X�I
����͑z�����Ă��܂����B
�m���ɍŋ߂̏œ_�͐l�Ԃ̔\�͂������x���v�������ʂ�����A�����x�����߂�Ȃ炻����A���ł��ˁB
�t�N���E�̖ѕ��́A�V���[�v�Ȓ��ɟ��݂����j�b�R�[���Ȃ�ł͂̉�������܂����B
50mm�̌����{�P�����S�ɉ~�Ȃ̂�������Ɗ����B
�A�_�v�^�[�����݂��Ȃ��}�E���g�����삳��Ă����A���炵���ł��ˁB
�y�g�����~�����_���A���肻���łȂ��ł����̂ˁB
EC�m�ہC���߂łƂ��������܂��B
EC�͂ƂĂ��@�q�ŗD�G�ȃ{�f�B�ł�����A�܂������e������K���ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/08/26(Sat) 17:02 No.946
2017/08/26(Sat) 17:02 No.946
�\���̓R�����\�e�����A��؍���H �� EF�}�E���g �ł��B
�i��A���@�\�͗L��܂���i�W�����N�i�ł����̂Łc�j
EF�}�E���g�ł��̂ŁAEOS��l�X�ȋ@��ɑΉ��ł��܂��B
�@�g�p�̍ۂ͔��A�S�����i��ɋ���F�X�ƍH���܂��B
�w���R�C�h���̓u���j�J�{�̂̂��̂��g���̂��֗��ł��B
�����R���Ȃ̂ŁA�����ƃ}�E���g�̒E���@�\�������Ă��܂��B���̂��߁A��o���l�b�g�̃����Y�ɂ��Ή��\�ł��B
 efunon
efunon  2017/08/26(Sat) 21:05 No.947
2017/08/26(Sat) 21:05 No.947
����������̓v���Z�b�g�]�������Ƃ��Ă���ő���Ɋ��p�o����ł��傤���A
�A���l�̂悤�Ɏ����i��̏��o���l�b�g�����C���ɐ�����Ȃ�A�O������i�葀��ł���ق����悢���ƂɂȂ�܂��B
�i������ԂŌŒ�ł��A�œ_���킹�̎������J���ɏo����̂��x�^�[�ł����A���炭�ł��֗��Ȃ̂̓R���p�N�g�x���[�Y�ł���܂��傤�B
���\�W�����}������A���̑̑��ł�����܂��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/08/26(Sat) 22:20 No.948
2017/08/26(Sat) 22:20 No.948
�@����ŊO����i��̑��삪�o�����ł��B�����Y�̍i�背�o�[�Ƀ`�b�v��t���܂��B
���o���l�b�g�u���j�J�j�b�R�[���̍i�背�o�[�͋@�\�����ł͂Ȃ��̂�����Ƃ���ł��B
���Y�搶�̃R�����g�ɂ��L��܂����A�P���ɍi�背�o�[�����������������ƍi��l�ɂ���ĕ��ׂ��ς���Ă��܂���ł��B
�A�_�v�^�[���v���r���[���o�[���ɂ��悤�ƍl���Ă��܂��B
�@�����A����135�p�Ɏg���Ă݂Ă̊��z�ł����A�������߂邩�ňقȂ�Ǝv���܂����A��͂�6�~6�Ŏg�p����ɉz�������͖������������܂��B
����ƃR�����[�̃v���Z�b�g�^�C�v�̃����Y�������Ă��āA���̃N�Z�̗L��`�ʂ��ʔ����̂Ő�p�A�_�v�^�ƂȂ����܂��B
 efunon
efunon  2017/08/27(Sun) 15:37 No.949
2017/08/27(Sun) 15:37 No.949
��������a���g�ݍ��킹�ł��ˁB��������͎���ł��傤���H
25�N�قǑO�Ƀy���^645���g���Ă���܂����B���̎��͏��������Y�݂̂ł������A45mm,75mm,120mm�ǂ���D�G���ݽނł����B300mm�͍������Ĕ����܂���ł����B
���͂��̃����Y�l�U�T�̈�Ԕ����w���R�C�h�ɂ҂�����͂܂��ł��B
�ł��̂ōi��̃��o�[������ē˂�����ł邾���ł��B
����Ŗ������܂Ŗ��Ȃ��g���܂��B
�U�S�T�y��Nikkor-D 40mm f4�ŎB�e������錧���`�����������́u�����̂�����v�ł��B
 ken
ken  2017/08/28(Mon) 22:46 No.954
2017/08/28(Mon) 22:46 No.954
�M�Z�̃V���A��740xxx�A���̃V���A����750xxx�Ȃ�ł������Y����z������Ə�2���͐��Y�N�x�̎̂ĔԂ�������܂���ˁB
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/09/08(Fri) 18:15 No.964
2017/09/08(Fri) 18:15 No.964
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/09/08(Fri) 23:19 No.966
2017/09/08(Fri) 23:19 No.966
�����Y��[�����V���o�[�����O�̌���^���m�F���Ă��܂��B�\�z�ł�(12000�`�j������^���H
�œ_������NIKKOR�Ɣ���ĂȂ��̂��A�킴�ƂȂ̂��͕�����܂��A�L�p�n�����ɕt����ꂽSUPER�̕������ւ炵���ł��B
��{�P�����悤�ƁA���@���B�e���Ă݂܂����B
�ǂ������ɂȂ���ł��傤���B
���̂Ƃ��̓R�����[100���܂������Ă���܂���ŁA��r�ł��Ă��܂���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/09/27(Wed) 22:30 No.978
2017/09/27(Wed) 22:30 No.978
�L���b�v��t����Ƒ��̃[���U�m���ƌ����������Ȃ��Ȃ�܂��B
�u���j�JS�A�[���U�m��MC50/2.8,�@�J���A�G�N�^�[100
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/09/27(Wed) 22:33 No.979
2017/09/27(Wed) 22:33 No.979
�u���j�J�p�̃X�g���b�v�͓���Ȏ~�ߋ�ɂȂ��Ă��Ĕėp�X�g���b�v���g���܂���B
OP/TECH �X�[�p�[�v���X�g���b�v�i�^�C�vB�j���g����Ƃ̎��ł����A�u���j�J�Ɏ�����Ȃ��̂ŁA�J�X�^�����邱�Ƃɂ��܂����B
���������n���ƃ~�m���^�̃X�g���b�v���]���Ă܂��B�i��
1.�܂��͐�p�~�ߋ�̐�[��͋Z�ŊO���܂��B
2.�X���C�h���̃��b�N�@�\�ł����A�o�N�Ńv�����ꂪ��������l�Ȃ̂ŁA�^�J�_�Œu�������܂��B
3.���O���d���p�e���g���ێ����܂����B
4.�Ō�Ƀ~�m���^�X�g���b�v��ʂ��Ċ����ł��B
�ӊO����ٰ���������Ă܂��B�i��
�����̃z�b�N��AS2A�̍��AEC�ȍ~�ƌ`��͕ϑJ���Ă��܂����{�f�B���̃��O�`��͋��ʂ��Ǝv���܂��B
��ʂ�Op/Tec��B���g���܂��B�����g���Ă���ARB��Rollei�Ƃ����p���Ă��܂��BHassel�pA���g���Ă��č������Ă��邩������܂��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/10/13(Fri) 03:41 No.983
2017/10/13(Fri) 03:41 No.983
���̓x50mm����o���܂����B�{�̕]���ł̓R���g���X�g�͂���قǍ����Ȃ��A�F�����͏a���B�@�l���̕`�ʂ͔j�]�̖����Č��B
����ٌ^�̘c�݂͂�����̂̋C�ɂȂ���ł͖����B
�_�炩�����x���̂���`�ʂŌ��݂��ݽނł͍�낤�Ǝv���Ă����Ȃ�����Ӗ����ʂƂ̎��ł��B
�t�����n�����𒍈ӂ��čs���A�r�V�b���Ǝʂ�܂��B
�����A�Õ��̔S��̓j�b�R�[�������L�銴���ł��B
���̂��߃x���r�A�̗l�ȃn�C�R���g���X�g�t�B�����Ƒg�ݍ��킹��ƃo�����X���Ƃ��̂����m��܂���B
�@����ȉ摜�ł�DSLR�ŎB�����l�ɂ͎ʂ炸�Ɂh�t�B�����ŎB��܂����B�h�����o��͉̂��̂ł��傤�B
 efunon
efunon  2017/10/15(Sun) 11:23 No.986
2017/10/15(Sun) 11:23 No.986
�ߋ��̎G�����ł͒�R���g���X�g�ōʓx���Ⴂ�ƍ��]���ꂽ�����Y�ł��B
�@�B�e��EC-TL�̎����I�o�ł��B
 efunon
efunon  2017/10/15(Sun) 11:35 No.987
2017/10/15(Sun) 11:35 No.987
>>�ߋ��̎G�����ł͒�R���g���X�g�ōʓx���Ⴂ�ƍ��]���ꂽ�����Y�ł��B
���͒���Ă��D���Ȃ̂ŁA�����Ƃ͎v���܂���Bkomura for bronica�͂����ƕ]������ėǂ��Ǝv���܂��B
�ʐ^�@super komura 45mm (�t�W160�l�K�J���[�j
�i���Y�l�̂��Љ�Əd�����܂��̂ŁA��������܂����Q�Ƃ��肢���܂��B�j
�t�B���^�[�a67mm�A���ɓx���ア���j�X�J�X�P�ʓʃ����Y�ŁA�œ_������3700mm�B
�u���j�JC�ȍ~�̃w���R�C�h�����^��200mm������ƁA�ŒZ�B�e������3.3m�ɂȂ�܂��B
150mm�ł�2m�ŁA����ł������ł���200mm�̓|�[�g���[�g�Ƃ��Ă��o�X�g�A�b�v�����B�e�o���܂���B
200mm��p�N���[�Y�A�b�v�����Y���t�B���^�[�X���b�h�Ƀl�W���ނƁA3.7m����1.85m�͈̔͂ŏœ_�������悤�ɂȂ�܂��B
�ŒZ���Ƃق�40cm����t�ɓ���܂��B
�x���ア���ߋ��ʎ����̑����͍ŏ����ƍl�����܂����A�G�N�X�e���V�����`���[�u�ŋߐڂ����摜�Ɣ�r�������Ƃ��Ȃ��̂ō��x����Ă݂܂��B
�����܂ōŒZ�������X���b�h�a��67mm�̒����]�������Y�͂��܂�Ⴊ�Ȃ��̂ő��ɗ��p���h���A�i35mm�J�����Ȃ炠�邩���j���\�����ŏ���Ȉ�ۂł��B
150mmf3.5�̍ŒZ��2m�Ȃ̂ł���قǖ𗧂������ɂ���܂��A300mmf5.6�̍ŒZ��4m�Ȃ̂ŁA���p�ł��邩������܂���ˁB
���˂Ă���^�₪����܂��āA���̃N���[�Y�A�b�v�����Y��S����ɂ������̂ł��傤���B���n��𗝉��ł��Ă��܂���B
�j�b�R�[��200mm�O���^�t����Wiki�ɂ͋L�ڂ���Ă܂��B
�s���Ȃ̂ŁA200mm�O���^�̓u���j�JS�Ƃǂ��O�サ�Ă����������܂���B
D��S�͌J��o���ʂ��w���R�C�h��蒷�����ߍŒZ�������Z���A2.8m�Ȃ̂ł��̃N���[�Y�A�b�v�̏œ_����3700mm�͔@���ɂ�������ȋC�����܂��B
C�ȍ~�̃w���R�C�h�Ȃ�ŒZ3.3m�ɑ��N���[�Y�A�b�v3.7m�ƁA�����N���X�����g���₷���ݒ肩�Ǝv���܂��B
�����Č���^�̓Z�b�g�̔�����Ȃ������̂ł��傤���B����������������^�i�ّ��200�̓t�[�h�Ƀ��[���b�g����̌���j�͂��̃N���[�Y�A�b�v�ƃZ�b�g���ꂽ���Â������o��������܂���B�O������T�ʔ��肳��Ă��邱�Ƃ������悤�ł����B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2017/12/05(Tue) 00:33 No.1067
2017/12/05(Tue) 00:33 No.1067
�@S�^�̏����̓j�b�R�[��25������35�����̎���Ȃ̂ŁA�܂�200�����̓J�^���O�ɗL��܂���ˁB���Ȃ݂ɃJ�^���O�f�[�^��
�@18�����͍ŒZ�B�e������1.5���ŎB�e�{����2.40�{
�@25�����͍ŒZ�B�e������2.3���ŎB�e�{����3.33�{
�@35�����͍ŒZ�B�e������4.0���ŎB�e�{����4.67�{
�Ȃ̂ŁA��ʓI�Ȏg�p�ł̓N���[�Y�A�b�v�����Y�͕s�v�ł��B
�@200�����Ń|�[�g���[�g���B��ꍇ�A����3.3�����N�Z���m�ł��B
 efunon
efunon  2017/12/05(Tue) 20:35 No.1071
2017/12/05(Tue) 20:35 No.1071
�����m�ł����炷�݂܂���B
Fisheye-NIKKOR 30mm F4�ŁA�V��o���l�b�g�ɐڑ��B���̖{�ɂ���3�{�̂ݎ��삳�ꂽ�Ƃ̂��ƁB
�䂤�ꂢ�l����̃]�f�B�A�b�N�ƎB���ׂ����c�ł������A���m�߂��܂��ˁB
�{�̓��e�̓J���m����A�j�^�[����Df�܂ŁA�o�ዾ�⌰���������蕝�L���ł����A�u���j�J��D�t���Z�b�g�A�V�^����o���l�b�g�̖]��NIKKOR�A�K���X�g�b�N�Ȃǂ�����܂��B
D�p�̌���N�����N�͐������ł����������Ƃ�����܂���ł������A�����̑��݂��m�F�ł��܂����B
 uccyan
uccyan  2018/01/31(Wed) 13:40 No.1158
2018/01/31(Wed) 13:40 No.1158
�ȑO�A�J�����G���ɍڂ��Ă����摜�̗l�ł��ˁB���Ȃ�S���b�Ƃ����O�ς������I�ł����B
�@
�@�L���v�V�����ɂ͉�p��180���ƂȂ��Ă��܂����A���̃t�[�h�ƃ����Y�O�ʂ�R����l����ƁA180���͓�����Ȋ��������܂����ǂ��Ȃ�ł��傤�ˁB
�@�w���R�C�h�̑��o���ʂ���l����ƁA�g���f���i�C�ڎʂ��\�ł��傤�B
 efunon
efunon  2018/05/13(Sun) 09:21 No.1231
2018/05/13(Sun) 09:21 No.1231
�t���ɋ����A�͋�����������Ƃ����ʂ�ł��B
�������Ńj�R����[���U�m����50/2.8�������o���Ă��Ȃ��̂ł킩��܂��A������{�P��������ȊO�͌������Ɩ����ł��B
�t�B���^�[���Ȃ��ƃt�[�h�����ߕt�������������A�p�ɂɃt�[�h�������Ă��܂��̂ŕ|�����ǁA��a�t�B���^�[�̂悢���̂͂Ȃ��Ȃ�����܂���B
�t�[�h������Ȃ̂ŁA�������̎ʐ^���t�[�h�Ȃ��B�ł��t���ɂ��Ȃ苭���A���O����I���ɎB�e�ł��܂��B
�A�N���X�̓g�[�����悭�o�Č������₷���A�J�[�����O�������Ȃ��ǂ��t�B�����B
�������Ȃ��ƕ]������������܂����A�̑�Ȓ��f�ł��B�ł������ȃt�B�����ł�����A�f�B�X�R���͎c�O�̈ꌾ�ł��B
Bronica S, Nikkor 50/3.5, f11, 1/60, Acros
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/05/27(Sun) 12:29 No.1252
2018/05/27(Sun) 12:29 No.1252
�@�ǂ��]����h�S�[�X�g�ɋ����h���A���݂̃����Y�Ɣ�r����ΓG���܂���B���̕ӂ�}�̂̋L���������Ƃ�������Ă��銴�������܂��B
�@��x�I�[�o�[�z�[����������A�����Ɏʂ肪�ς���������Y�ł����B
�����ƎՌ�����Ώ\���Ȑ��\���Ǝv���܂����A��͂�N���V�J���ȕ`�ʂɂȂ�Ղ����������܂��B���͍̌̂��Z�x������������C���ł��B�����������l����Η��h�Ȃ��̂ł����B
�@
�@
 efunon
efunon  2018/05/29(Tue) 21:51 No.1253
2018/05/29(Tue) 21:51 No.1253
�����͍ň��Œ�̋t���サ�����Y���g���Ă��܂��̂ŁA����Ɗr�ׂ���ꡂ��ɗD�G�i��
����50/2.8�������Ă���Əo�Ԃ�����Ă��Ȃ��̂ŁA�u���j�JS�̏C����̌�e�X�g�ɂ͂��̃����Y��{�t���čs���A���ʂł͐ϋɓI�ɋt���^���ߌ��������܂����B
���A�ŃT�M���߂��ɗ��Ă�����Ȃɏ����������ʂ�Ȃ��D�D�D
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/05/31(Thu) 21:22 No.1255
2018/05/31(Thu) 21:22 No.1255
�@�u���j�JS�ł̎B�e�Ƃ͌����Ƃ��܂����B���炵�܂����B
�u���j�JS�̏C�����Ă����Ƃ��낪�L��̂ł��ˁB�f���炵���B
�@�����グ�m�u�Ɠ����̑��o���@�\�́A�E�G�X�g�����F���t�@�C���_�[�Ƃ̐e�a���������A���슴���G��ł��B
���̕ۑ�������@��ł����A����g�������ĉ�����
�@50mmF3.5�̍\���́A���܂����g���t�H�[�J�X�����Y�̗l���ɂ��đI���̕������Ȃ��������̌��샌���Y���Ǝv���܂��B
�@��ʂ̋��X�܂ł�������Ƃ��Ă��Ĕj�]���������A�e�̕����ɂ������Ƒ��������܂��ˁB�����Ă����Ƌ�ɂ��~�����c���Ă��܂��B�t�B�����B�e�炵�������ł��B
�Ƃ���ŁA����͔���ł����H
 efunon
efunon  2018/05/31(Thu) 22:23 No.1256
2018/05/31(Thu) 22:23 No.1256
�ʂ̃J�����œ�������ʂ����摜����悤�Ǝv���Ă�����A�������Ă��Y������摜������܂���B���������ăL���b�v�����܂ܘI�������H
���̎��n�тɂ͑傫�Ȑ�ƒ��^�̔�������A���Ɋ��ނ����܂��B�����^���ǂ���J���Z�~�����܂��B
�������ꒆ��ł��ˁB
�]�k�Ȃ���A�r���̓��ŁA���H�̘e�ɎO�r��̂��̂ŗ���������5-60cm���炢�̍\�����������A������˂��ݎ�背�[�_�[���I�I�Ɨ�⊾�������܂������A�ʂ�߂��鎞�ɃS�C�T�M���Ƃ킩��܂����B�c�ɓ����Ȃ��D�D�D
>�@�u���j�JS�̏C�����Ă����Ƃ��낪�L��̂ł��ˁB�f���炵���B
>�@�����グ�m�u�Ɠ����̑��o���@�\�́A�E�G�X�g�����F���t�@�C���_�[�Ƃ̐e�a���������A���슴���G��ł��B
>�@���̕ۑ�������@��ł����A����g�������ĉ�����
���肪�Ƃ��������܂��B
�Z�b�g���ꂽ�����Y���~������2��ڂ���ɂ��܂������A���炭������X�^�b�N���Ă��܂��܂����B�ŏ���1��͍D���ێ����Ă��܂��B
�_�����Ƃŋߏ��ɑŐf������1�����قNJ|�����čĉғ������Ă���܂����B���Ȃ��S���ꂽ�Ƃ̂��ƁB
�����Ƃ������g����悢�Ƃ����C���ŁA����͌����܂��V���b�^�[�_�C�����̃N���b�N���Ȃ��Ȃ�����A�����グ�̂������Ƃ������G���_���ɂȂ�����A�ς�����_�͂���܂��B
��������B�e�����͈͂ŘI���ɂ͖�薳���A���l�Ŏg�������镪�ɂ͋C�ɂ��Ȃ��ł������Ǝv���Ă��܂��B
>�@50mmF3.5�̍\���́A���܂����g���t�H�[�J�X�����Y�̗l���ɂ��đI���̕������Ȃ��������̌��샌���Y���Ǝv���܂��B
���b�p�Ƃ�����肨�M�ŁA50/2.8��蒼�a���傫���̂ŁAefunon�l�͂��ߊF�l�̂��]�����܂ł͍w���Ώۂł͂���܂���ł����B
�ŋ߂悤�₭���_�I�]�T���ł��ď��߂Ď�ɂ��Ă݂�ƁA�J�����ɕt����ƈӊO�ɐ�����Ȃ���ۂł��B
50/2.8���I�o���̑O�㒷���Z���̂������Ă���悤�ł��B
>�@��ʂ̋��X�܂ł�������Ƃ��Ă��Ĕj�]���������A�e�̕����ɂ������
>�@�Ƒ��������܂��ˁB�����Ă����Ƌ�ɂ��~�����c���Ă��܂��B
f11�ł��̂ŁA�[�܂ʼn𑜂��Ă���邱�Ƃ����҂��܂����B�悩�����ł��B
Acros�͈����₷���ł��ˁB
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/06/16(Sat) 22:41 No.1262
2018/06/16(Sat) 22:41 No.1262
���܂���Amazon�Ńj�R���}�E���g�ɂ���A�_�v�^�[�������܂��āA�l���I�ɔ����Ă݂܂����B
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01GP27RBG/ref=ppx_od_dt_b_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
��������ۏ؏��̗ނ͖����A���̒��ɂ̓r�j�[���ɕ�܂ꂽ�{�i�����邾���ł��B���L�͎����g���m�F���������Ō����ł͂���܂��炲���Ӊ������B
�u���j�J���͑�o���l�b�g�}�E���g�Ȃ̂ŁA�ʓr�w���R�C�h�����O���K�v�ł��B
�O�㋤�ɂقڃK�^�������t�����܂����B���x�͗ǂ��悤�ł��B�ق�̏����I�[�o�[�C���t�H�܂��A�_�v�^�[�ł�����I�[�o�[�ɐU��͎̂d���Ȃ��ł��ˁB
�i��͘A�����܂���B�A�_�v�^�[���̃s���i�o�l�ŕΘ߂����e����悤�ɂȂ��Ă���j�ɂ��펞�i�荞�܂�Ă��܂��B
�i��l�̈Ⴂ�������Y�����ŋz������^�C�v�͈�a����������ł��܂����A�i��l�ɂ��i��s���̈ʒu���ς��^�C�v�͊J�����ɉۂɃo�l�̒�R�ŏd���Ȃ�܂��B
�w���R�C�h�����O�͖�肠��܂���ł������A�V��o���l�b�g��ZENZANON 300mm F4.5�͓r���Ŏ~�܂��Ď��t�����܂���ł����B�i��s���̉ғ���̈Ⴂ�ɂ����̂�������܂���B
���[�W�o���l�b�g�A�_�v�^�[�������Ă��Ȃ��̂ŁA����o���l�b�g�����Y�̎g�p�̉ۂ͕s���ł��B
�w���R�C�h�͋����\������ɗ������ɍi��l�͎߂ɃY���Ă��܂��܂��B����҂ɂƂ��Ă͍i��l��苗���\���̕����d�v�Ȃ̂ł��傤�B
�����ɂ͎O�r��������܂��B�荞�݂�����̂ŁA�����Ă��Ȃ��̂Œf��ł��܂��A���J�X�C�X�݊��̂悤�ł��B
�L���m��EOS�}�E���g������悤�ł��B
https://www.amazon.co.jp/Fotodiox-Pro-Lens-Mount-Adapter/dp/B01JJHED8O/ref=sr_1_38?s=photo&ie=UTF8&qid=1546607716&sr=1-38&keywords=bronica
 uccyan
uccyan  2019/01/04(Fri) 22:07 No.1488
2019/01/04(Fri) 22:07 No.1488
�������낢�B���x�����������o�Ă���悤�ł������Ƃł��B
�t�H�[�}�b�g���k������Ă��܂��̂Ōl�I�ɂ͎c�O�ł����A�܂�RB67-�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�������݂��܂�����A�j�[�Y�͂����ł��傤�B
�t�WGFX�p�A�_�v�^���o���肵�āB���A�j�R��F-GFX�͊��ɏo�Ă��܂�����A���ł��t�����܂��ˁD�D�D
�t�Ƀ}�E���g�A�_�v�^�[���o���r�[�ɒl�オ�肵�Ďs�ꂩ����ł�����������Ƃ������܂��A�����u���j�J�͂���Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ɗy�ς��Ă��܂��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/01/06(Sun) 10:12 No.1489
2019/01/06(Sun) 10:12 No.1489
�@���^�x���[�Y����t�ɐL���������2.7���ʂ܂Ńs���g�����܂��̂ŁA���傤�Ǘǂ������ł��B
�@�A���A�^�J�����̃o���������Y������ƁA���Ȃ�̃g�b�v�w�r�[�ɂȂ�܂��B���̃����Y�ʂ��d�ʓI�ɂ͌��E���Ǝv���܂��B
 efunon
efunon  2019/01/19(Sat) 22:00 No.1493
2019/01/19(Sat) 22:00 No.1493
�P�CD, S�p�C�O�̃A�I���@�\����B���o���l�b�g�����Y��p�B���������Y�ł͖����͏o�Ȃ��B
�Q�CS2�p�u�x���[�Y2�^�v�F�O�̃A�I���@�\����B���o���l�b�g�����Y��p�B���������Y�Ŗ������瓙�{�܂ŁB
�R�CEC�p�u�x���[�Y2�^�v�F�Q�Ƃقړ�����������ύX�_������B�����͏o�Ȃ��B75mm�W�������Y�ł�4.2m���瓙�{�܂ŁB
�S�CECTL�p�u�x���[�Y2�^�v�F�R�Ɠ��������A�E�葤�V���b�^�[���o�[�ɉ����č��葤�ɍi�荞�ݑ����p���o�[�����݂��ꂽ�B
�T�C�R���p�N�g�x���[�Y�F�A�I���@�\�͂Ȃ��A75mm�W����60cm���瓙�{�܂ł��J�o�[����B�Q�|�S�܂ł͍i�荞�݃��o�[�͏펞�X�v�����O�ōi������Ƀe���V�������|�����Ă���A�w�Ń��o�[���Ĉꎞ�I�ɍi��J���ɂ���悤�ɂȂ��Ă��邪�A�T�̓��o�[�ŊJ���ɂ���ƃ��b�N����A�_�u�������[�Y�܂��̓��b�N�����{�^���������ƃ`���[�W���ꂽ�X�v�����O�ŏu���ɍi������p�I�@�\�������Ă���B
�Q�ƂR�܂��͂S�̕ω��͂悭�F������Ă��Ȃ������������Ǝv���A����Љ��B
�ʐ^��̍���S2�p�h�Q�h�A�E��ECTL�p�h�S�h
���ʂ��猩��ƑO���������̃X�C���O�����A�h�S�h��5mm�قǍ����Ȃ��Ă���̂��킩��BEC,ECTL��S2���{�f�B���ʂ�������܂ł̋����������Ȃ��Ă��邽�߂����A���̕�����EC,ECTL�p�h�R�C�S�h��S�Q�������ꍇ�AS2�p�h�Q�h��胉�C�Y���ꂽ��ԂɂȂ�B�@�\��t�H�[���͂ł��Ȃ��B���̂��߃��b�N�s�j�I�����k�߂Ă����ƁA�x���[�Y���Ō�ɘc��ł��܂��A�O�ƃ{�f�B���ڐG����قǏk�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�t�̏ꍇ�͂ǂ����낤���B
�h�Q�h��ECTL������ƁA�O���t�H�[�����ꂽ��ԂɂȂ�B���̏ꍇ�͑O��K�ʃ��C�Y�����EC�EECTL�̌����ɍ��킹���邽�߁A�x���[�Y�͘c�܂��ɍŌ�܂ŏk�߂邱�Ƃ��ł���B��L�̂悤�ɁA�h�R�C�S�h�͂����Ƃ��k�߂Ă�4.2m���炵���œ_������Ȃ����A�h�Q�h�ł�EC�CECTL�ł����������o��B�������A�x���[�Y�̃I�X�}�E���g�㕔�ɓ��ʔ��˖h�~�̃V�F�[�h������AEC�n���쓮���������~���[�Ɋ����邩�m�F���Ă��Ȃ��B�����Đl���ɂȂ�̂��S�O���Ă���B
�ʐ^���Ƀx���[�Y���{�f�B�Ɛڂ���ڐG�ʂ������B
���h�Q�h�ɂ́AS2�ꕔ�̉~�`�ˏo�ɑΉ����A�~�`�̌E�݂�����B���̕��Œ�l�W�̓ˏo�����Ȃ��AEC,ECTL�Ƀl�W���ނƃl�W��R���炢�������܂Ȃ��B
�E�h�S�h�̓{�f�B�ڐG�ʂ̓t���b�g�ŁAEC/ECTL�{�f�B�ʒu���ߌ��̂��߂̃s�����O��ɗ����Ă���BS2�͂��̃s���ɐڐG���Ȃ��`��Ȃ̂ŁA���ʂɑ����ł���B��L�̂悤�Ƀ��C�Y��ԂɂȂ�̂����B�h�S�h�ɂ́h�Q�h�̂悤�ȃ}�E���g��̃V�F�[�h�͂Ȃ��̂ŁAS�Q�~���[���͂��Ȃ��ƍl������B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/07/27(Sat) 02:04 No.1540
2019/07/27(Sat) 02:04 No.1540
���u���j�JEC+�h4�h
S2�̓}�E���g�t�����W�̓{�f�B�O�ʂ������ɂ���A�x���[�Y�ƃ{�f�B�Ԃ͂قƂ�nj��Ԃ������Ȃ����AEC�Ɓh�S�h�̑g�ݍ��킹�ł̓x���[�Y�ƃ{�f�B�̊ԂɃN���[���̃����O���ώ@�����B
�������AEC�͌��X���X�}�E���g�ʂ��O����1mm�قǘI�o���Ă��āA���ꂪ�t�����W�ʂȂ̂�4.2m���炵������Ȃ����ƂƂ͊W���Ȃ��B
�h�S�h�̃I�X�}�E���g�������A�h�Q�h���1mm�قnj㑤�ɒ����̂������ɍ���Ȃ����R���낤�Ǝv����B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/07/27(Sat) 02:20 No.1541
2019/07/27(Sat) 02:20 No.1541
��ϗL�p�ȏ������肪�Ƃ��������܂��B���̐́A�u���j�J�̂��ꂱ����Љ��z�[���y�[�W����������i�Q�O�N�قǑO�����H�j�A���ՂɃu���j�J�̃A�I���t���x���[�Y�͖��������o��Ə����Ă��āA���ɂ���Ă͏o�܂���Ǝw�E�������ďC���������Ƃ��v���o���܂����B�����ȈႢ�Ƃ����܂����AEC�p�ł����Ă����Ȃ蔖���Ȃ��Ă����ƃ`�F�b�N���Ȃ��Ɓi�����ł�����Ǝ������x�ł́j���������o�Ȃ��̂͂킩��܂���̂ŁA��������Ă�����Ǝʐ^�t���ł܂Ƃ߂Ă���������ƂƂĂ��L�p���Ǝv���܂��B
����ł́A�Ȃ�EC�p�ł͖��������o�Ȃ��Ȃ����̂��A�ł����A�~���[�̊������ł���Ί����镔�i�̌`���ς�����������̂͂��ł��B���̍l���ł́AEC�p�ł̓V���b�^�[�{�^���̕����ɏ����N���A�����X��݂���K�v�����������߂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�Ƃ����܂��̂́A���ʊW�͂��܂����Ă킩��Ȃ��̂ł����A�́AS2�p�̃x���[�Y��EC�ɂ��Ă��ĉ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��邽�߂ł��B
���������Ă���S2�p�̃x���[�Y��EC�ɂ��Ďg�����Ƃ��o���܂������i��������̌`��̈Ⴂ�ɂ��Ă͏����H�v���K�v�ł����j�A�V���b�^�[�{�^�����͂��ɉ����ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��āA���̂��߂�EC�����̃V���b�^�[�쓮�\���m�C�h�����M�E�f�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��BEC�ł̓V���b�^�[�{�^�����킸���ɉ����ƃV���b�^�[�쓮�\���m�C�h�ɂ܂��ʓd����i�㖋���Œ肳��j�A����ɃV���b�^�[�������Ɛ斋������܂��B��莞�Ԍ�ɒʓd����������ăV���b�^�[�㖋������܂��B�����^��EC�ł͓d�r�����Ղ����ꍇ�ɂ̓V���b�^�[����Ȃ��Ƃ��������i���S�@�\�j������܂����A����́C���̐��I�Ȓʓd�ɂ��V���b�^�[���b�N���������Ă���悤�ł��B�Ƃ�����A�V���b�^�[���������܂܂ŕێ�����Ƒz��ȏ�̒����ԁA�\���m�C�h�ɒʓd������A���M�E�f�������̂��Ǝv���܂��B���̈��ʊW�͎��̐����ł����A���ۂɃ\���m�C�h���f�������͎̂����ł��B
�Ƃ��������̂悤�Ȃ킯�ŁAEC��S2�p�x���[�Y�������ł��ē�������Ƃ����āA�t���Ȃ��ق��������Ƃ����̂����̍l���ł��BEC-TL��S2�p�̃x���[�Y���t���Ďg����ΘI�o�v�����łȂ������I�o���g���A�܂�SL66E/SL66SE�����֗��ő�ϒɉ��Ȃ̂ł����E�E���������ꍇ�̓~���[�̊��̑��ɃV���b�^�[�������ꂽ��ԂɂȂ�Ȃ�������`�F�b�N���Ă݂Ă��������B
 ���Y
���Y  2019/07/27(Sat) 12:19 No.1542
2019/07/27(Sat) 12:19 No.1542
�����ƈȑO�A�V���b�^�[�{�^�����������ɂȂ���Ɋւ��Ă��f���������Ƃ�����܂����ˁB�������C�����܂��B�ł��Y��Ă��܂���m(_ _)m
�������̂Ȃ̂������̂��߉��߂čl���āAETCL�p�ɘI�o�v�v���r���[�{�^���p�̃��o�[�݂������炩�H����ɂ��Ă�EC�p�̃����[�Y���o�[�����̋@������������Ȃ����Ƃ̐������o���Ȃ��A�ƔY��ł��܂����B
����͓d�r���ĕۊǂ��Ă���EC���g���܂����̂Łi�K�������������j�������ʓd�ɂ��ăX���[���Ă��܂������A����m�F�����Ē����܂��B
4.2m����̖��A���Y�l���w�E�̒ʂ�A�����ł͑S���F���ł��܂���B���O�̖��������������ď��߂ċC�t�����̂ł��B
���������b�N�s�j�I���̓w���R�C�h�ɂ���ׂē������傫�����߁A�ق�̋͂��̈ړ��ʂ̍��ł��B
�}�b�g�ʂł͂فu�����Ă����Ȃ����H�v�Ǝv������x�B�X�v���b�g�C���[�W���Ȃ���ΊO��Ă���Ƃ����m�������܂���B
���̒��x�Ȃ班���i�荞�ނ����Ő[�x�ɓ����Ă��܂��͂��ŁA�J���ł��Ȃ���h�R�C�S�h��������g���Ă����p���薳���ł��傤�B
�ł��x���[�Y2�^��1kg������ASL66�̂悤�ɏ펞�t�����ςȂ��Ŏ��������̂͂�����ƁD�D�D�i��
ECTL��AE���g����̂̓A�h�o���e�[�W�ł��ˁB�����f�B�X�v���[�X�����g�Ō��������S����O�ꂽ�Ƃ��ɐ��������������̂��͌��������Ƃ�����܂��B
�����D,S�p�́u1�^�H�v�ƃ_�u�������[�Y�ŃZ�~�����ɂȂ�R���p�N�g�x���[�Y�����|�[�g����\��ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/07/27(Sat) 18:57 No.1543
2019/07/27(Sat) 18:57 No.1543
�u���j�J�̓V�X�e����������ڎʑ��u�Ƃ��ď��}�E���g�����̃X�N�����[�ɑ������钆�ԃ����O�Z�b�g�ƂƂ��ɁA�{�i�I�ȃx���[�Y��p�ӂ��Ă����B
D�ES�^�p�x���[�Y�h�P�h�́A�N���V�b�N�ȈÔ����v���o������悤�ȑO��2�i�L���\���ŁA�ŒZ7cm����Œ�21cm�܂ʼn������ł���B
�h�P�h�̓x���[�Y�Ƃ��Ă̓I�[�\�h�b�N�X�ȁA�����Y�}�E���g�����Ń{�f�B�Ɛڑ�����B���̌�̃��f���ƌ݊������Ȃ��`���D�ES�̊O�}�E���g�ŁA180mm�A250mm�A350mm�]���Ƃ����ʂł���AS2�ȍ~�̋@��ɐڑ�����}�E���g�A�_�v�^�[���������ꂽ���T���͓̂����������Ȃ��B�i250/4�ɂ������Ă�����̂���Ɍ��|����j
�W��75mm�������A�x���[�Y�������Ƃ��k�߂ĎB�e�����̓t�B�����ʂ���31.5cm�A�����Y��[����13cm�Ŕ{��1:1�i����6cm����ʈ�t�Ɂj����A�ő�ɐL���ăt�B�����ʂ���œ_�ʂ܂�40.5cm�A�����Y��[����7cm�ɂ����Ĕ{��3:1�i��2cm����t�Ɏʂ�j�ł���A���̌�̃��f�����ő�{��1:1�܂łɗ��߂Ă���̂Ɣ�r���A�{�i�I������@�\�ł���B
S2�Ȍ�̋@��̂悤�Ƀw���R�C�h���j�b�g������\���ł͂Ȃ����߁A�ǂ����Ă��t�����W�o�b�N���傫���Ȃ��Ă��܂����ʁA�ŏ��{��������1:1�����邪�AD�ES�^�ł͂���ȉ��̔{���͒��ԃ����O�Z�b�g�����S���邱�ƂɂȂ�B
�������A����ł��ŏ�1:1�`�ő�3:1�Ƃ����̂͂��܂�ɂ��}�j�A�b�N�ł���A�̔����͏��Ȃ������Ƒz�������B
�ʐ^�F�u���j�JS�A�x���[�Y�h�P�h�A�j�b�R�[��75mm
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/07/29(Mon) 22:33 No.1546
2019/07/29(Mon) 22:33 No.1546
���ʂ��猩�āA�����Y�}�E���g�㕔�ɍi��J�����o�[������A��ɍi������Ƀe���V�������|�����Ă��āA����ɋt����ĊJ���ɂ��A��𗣂��ƍi����B
���S�����ɃX�C���O���̃X�N�����[�m�u������B���C�Y�A�e�C���g���Œ肷�鍶�E�̑�a�l�W�́A���葤���t�l�W�ɂȂ��Ă��āA���E�̑O���]��������v�����Ă���B�������슴�ɕ������C�������Ă���̂��킩�邪�A���l�W�Ɋ��ꂽ��ɂ͗]�v�Ȃ����b�Ƃ����Ȃ����Ȃ��B
D�ES�̉E��m�u�ɂ��œ_���߂́A�ꉞ�������Ӗ��͂Ȃ��A�œ_�̓x���[�Y���ō��킹��B
��i�L�����[���́A�㕔2�{�̓��b�N���o�[���ɂ߂�ƃt���[�ɂȂ�A��܂��Ȕ{�������߂�B�O��1�{�̓��b�N�s�j�I���ŌJ��o�����B
�ʐ^�F�u���j�JS�A�x���[�Y�h�P�h���C�Y�{�X�C���O�A�j�b�R�[��75mm�A
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/07/29(Mon) 22:34 No.1547
2019/07/29(Mon) 22:34 No.1547
�h�P�h���l�Ƀ{�f�B�ɂ̓����Y�}�E���g�݂̂Őڑ�����A�אg��2�{���[����p���A�A�I���Ɩ����������75mm�����Y��60cm���瓙�{�܂łƋ@�\���i���ďd��450g�ƌ��I�Ɍy�ʉ�����A�h�T�h�̓A�E�g�h�A�ł����Ƃ��g�p�p�x�������B
�������@�\����邾���ł͂Ȃ��A�_�u�������[�Y�p����ƃZ�~�����i��ɂȂ�A�J���i��ŏœ_���킹�����A���̂܂܃����[�Y����X�v�����O�ő����ɍi�荞�܂�A�����Ȃǂ̓��̂ɂ��Ή��o����قǂŎg������͊��S�����i��̃w���R�C�h�ɔ�����̂ɂȂ�B
�c�O�Ȃ��ƂɃ_�u�������[�Y�͓���Ȍ`��ŁA�V���b�^�[�{�^���p�i�ʐ^���j�͈�ʓI�ȃe�[�p�[�l�W�����A�����i��t�@�C�A�p�͎ʐ^�E�̂悤�ɍג����s�b�`���ׂ����X�g���[�g�l�W�ł���A�����ȊO�ł͑�ւ��ł��Ȃ��B
�����[�Y���g��Ȃ��Ă��A�l�W���ׂ̗Ɏ蓮�����[�X�{�^�������Ă���̂ŁA������������㑬�₩�ɃV���b�^�[�����[�Y����A�莝����2�^�������肵�đ����i�荞�ނ��Ƃ��ł���B���͉��O�Ŏ莝������Ƃ��́A�_�u�������[�Y���g�킸�ɂ��̂悤�ɂ��ĎB�e���邱�Ƃ������B
�h�T�h��S2�ɂ��g���邪�AETCL�̏u�ԍi�荞��AE�Ƃ̑������ǂ��A���ɕ֗����Ǝv���B
�ʐ^�F�u���j�JEC�A�x���[�Y�h�T�h�A�u���j�J�_�u�������[�Y�A�j�b�R�[��75mm�A�E�Ƀ����[�Y��[������
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/07/29(Mon) 22:36 No.1548
2019/07/29(Mon) 22:36 No.1548
�@�����S�����Ȃ肭���т�Ă��܂����̂ŁA�ǂ����m���L��Ǝv���Ă����Ƃ���Ɏ荠�ȁh�s��S"���L��܂����B
�@S�^�Ȃ̂Ō���̔��ł��B
�e�X�g�t�B�����Ƒւ��}�K�W���������čs���A�`�F�b�N�����Ă��炢�܂����B
�Ă̒�A�s���̌����̓}�K�W���ɗL��l�ŁA�t�B�����X�g�b�v�������܂���B���̒��x�Ȃ牽�Ƃ��Ȃ邾�낤�Ǝv���A�����A��܂����B
�@�i���Ȃ݂ɁAS�^�̃}�K�W���p�_�[�N�X���C�h�́A�}�K�W���̏����ȃ|�b�`�������ΊȒP�Ƀ��b�N���O��Ĕ��������\�ł��B���̃X���C�h�̓��肪����Ď����������ςł��B���̎����Ă��郂�m����܂ɂ��l�̂������œ���ł��܂����B���ӁX�j
�@�����̃}�K�W���ɂ͗L���ȃt�B�����ْ��@�\�������Ă��܂��̂ŁA���̖��͂ɍ~�Q�Ŏ����A��܂����B
���̃}�K�W���͂��̂܂܃C�X�g����֓��@�ł��B
 efunon
efunon  2019/08/10(Sat) 10:33 No.1554
2019/08/10(Sat) 10:33 No.1554
�ւ��ۂ��e���l�̏��ɓ��e�����摜�ł����A���������ł��傤����Ē��܂��B
�F�l�̂��Q�l�ɂȂ�Ή����ł��B
��S�p
��S2�p�CA4�v�����g�����Ό����ɂȂ�͂��ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/08/11(Sun) 11:56 No.1555
2019/08/11(Sun) 11:56 No.1555
S2 �N�قǎg�p���Ă����̂ł����A��������Y�����t����ۂɈ�a�����������̂ʼn������܂��ɊO���Ă݂�ƁA�ꕔ���i���E�����Ă���̂����܂����B
�����i��Ɋւ��镔�i���낤�Ƃ������Ƃ͕�����̂ł����A���X���ǂ����t���Ă������̂���������܂���B
�������̕�����������Ⴂ�܂����狳���Ă��������܂��H
���펞�͂��������ӂ��ɂȂ��Ă���Ƃ������ł����肪�����ł��B
���i�̎ʐ^�Fhttps://twitter.com/kakkun61/status/1180332816522809345
�����i�肪�@�\���Ă��Ȃ��l�q�Fhttps://twitter.com/kakkun61/status/1180337234114830338
 ��������
��������  2019/10/22(Tue) 17:20 No.1622
2019/10/22(Tue) 17:20 No.1622
�������w���R�C�h�����Ă݂܂�����A�����\���̂��̂�����܂����i����������ƋÂ������i�������^�C�v������܂����j�B���}�� twitter �̂ق��ɕԐM�Ŏʐ^�ƃ��[�r�[���ڂ��Ă��܂��B���̔�̃p�[�c������������ꏊ�ɍ������ݒ����Č����Ă͂ǂ��ł��傤���B
 ���Y
���Y  2019/10/22(Tue) 18:19 No.1623
2019/10/22(Tue) 18:19 No.1623
�Q��ނ̍i��A���@�\�̃��[�r�[���ȉ��ɍڂ��܂����B
https://shiura.com/camera/mednikkor/bronica/link.mov
���������̂��Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B
�������A���v���C�̃J�E���g�������Ă��܂����A�c�C�[�g�����邱�Ƃ��ł��܂���B���������Č��A�J�E���g�������肵�܂����H
 ��������
��������  2019/10/22(Tue) 18:32 No.1625
2019/10/22(Tue) 18:32 No.1625
���悪������₷�������ł��B
������Č�����悤�ɕ��i����ꍞ�Ƃ��떳�����܂����B
�{���ɏ�����܂����B���ӂ��܂��B
 ��������
��������  2019/10/22(Tue) 18:39 No.1626
2019/10/22(Tue) 18:39 No.1626
�����̃��f���ŁA�u���j�JS�̊O�}�E���g�ɑΉ�����BS2�Ȍ�Ƃ͈قȂ�}�E���g�B
�����Y�w�b�h300mmf5�C400mmf6.3�C500mmf7���X�N�����[�}�E���g�Ō�������B
�{�f�B�Ƃ̎����i��A���͂Ȃ��A���ʍi�背���Y�B
�J��o���ʂ�3.7cm�B
�ŒZ��300mm�ł�5m��A400mm��5.5m�A500mm��9m��i�ڐ���菭�����j
�����]����菬�^�y�ʁB���̂����ŒZ�������Ȃ��Ă��܂����B
�R�����[�͑��ɋK�i������A��L�œ_�����ł����̃��j�b�g�ɍ���Ȃ����̂�����B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/12/26(Thu) 19:10 No.1638
2019/12/26(Thu) 19:10 No.1638
300�͔��A400�̓I�����W�A500�͗ŐF��������Ă���킩��₷���B
��]�\�ȎO�r�����W����������Ă���B
��t�ʒu�����L�ȃw���R�C�h������Ȃ̂ŁA�J��o���ɉ����ďd�S���{�f�B���Ɋ��B
�����Y���j�b�g������Ȃ�A�{�f�B�����������肷��͂������A�����Y���y�ʂȂ̂ŁA���̈ʒu�ŌŒ肷��͎̂g���₷���Ƃ͌�����B
�܂����̌̂�����������Ȃ����{�f�B�ƃo���l�b�g�}�E���g�̐ڑ��ɃK�^��������Ǝv���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/12/26(Thu) 19:16 No.1639
2019/12/26(Thu) 19:16 No.1639
���̗l�ȃw���R�C�h�����j�b�g���L��̂ł��ˁB���߂Ĕq�����܂����B
�@�u���j�JS�̃{�f�B�[���}�E���g�͉����S���ƂȂ��\�����ȂƎv���Ă��܂����B
�@���N��35�p�Ȃǂ����ƂȂ��s�V�b�I�Ƃ͕t���Ȃ������ŁA�̍��Ȃ̂��ȂƂ��v���Ă��܂����B
 efunon
efunon  2019/12/27(Fri) 23:01 No.1641
2019/12/27(Fri) 23:01 No.1641
400mmf6.3�p�Ȃ̂ɁA�i��l�\����8����n�܂�̂́H�@�Ǝv���Ă��܂������AII�������Ȃ̂ł��ˁB
���ʂɍl����ƁADX, S�p��III�^�Ȃ̂ɁAS2, EC�p��II�Ȃ͕̂s�v�c�Ȃ��Ƃł��B
�}�E���g�̃K�^�́A������250mm��350mm�ł͂���قǑ傫���Ȃ����߁A�R�����[�̐��쐸�x�̖��Ȃ̂��A�o�N�ω��Ȃ̂��悭�킩��܂���B
�ł��AS2, EC�̑�o���l�b�g�̂ق����A�ڐG�ʂ��傫���K�^�����Ȃ��Ȃ邾�낤�Ǝv���܂��B
DX, S�̊O�}�E���g�́A�j�R��S�C�R���^�b�N�XRF�̊O�o���l�b�g���g�債���悤�ȍ\���ł��B
DX, S�p�O�}�E���g�����Y��S2, EC�ɃA�_�v�^�[�Őڑ��ł��܂����ADX, S�ɑ����o����]���́A�����������̑��ɂ͂��̃R�����[���j�}�E���g�����I����������܂���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2019/12/28(Sat) 00:22 No.1642
2019/12/28(Sat) 00:22 No.1642
�@�u���j�JD�͎����Ă���܂���̂Ńu���j�JS�ɑ������Ă݂܂����B
�@�{���̋L���ɂ��L�ڂ���Ă��܂����AS�^�̓{�f�B�[���Ƀ_�C���N�g�ړ_�������̂ŃA�_�v�^�[��
�^�[�~�i���͎g���܂���B���̓_�A�p�r������ꂻ���ł��B
�@����ƈӊO�Ɏ����d��̂���A�N�Z�T���[�ł����B
 efunon
efunon  2020/02/27(Thu) 21:04 No.1665
2020/02/27(Thu) 21:04 No.1665
Carl Zeiss Jena ZENZANON MC�̕\�L���嗬�ŁA���Ȃ��Ƃ�����Biometar�̕\�L�͌������Ƃ�����܂���B����Ƃ����b�͕����܂����A�O�[�O���̉摜�����ɂ����͏o�Ă��Ȃ��悤�ł��B
�����炭����͒������Ǝv���܂��B�u�N���V�b�N�J�����j���[�X�v�劲�̈���l���S���Ȃ��Ĉꕔ���s��ɏo���R���N�V����EC�ɕt�����Ă��܂����B
���ƃC�G�i�c�@�C�X�́A�����Ƀr�I���^�[��A�o����ہ@Jena Bm�̕\�L���������オ����A���̋K���ɂȂ���Ă���̂ł��傤�B
�O�ς͏����^�Ȃ̂ŁA����������Ǝ��삩��s���Y�^�H
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2020/03/29(Sun) 09:54 No.1678
2020/03/29(Sun) 09:54 No.1678
�@�����������Y�̓��肨�߂łƂ��������܂��B
����ZEISS�̃[���U�m�������Y�͐l�C�̂��ߓ��肪����ƕ����Ă��܂��B
�@�z���g�Ƀr�I���^���̂܂܂Ȃ̂��A���f�B�t�@�C���Ă���̂��A
�܂��A�n�b�Z����[���C�̃v���i�[�Ƃ͂ǂ��Ⴄ�̂��������L��܂��B
 efunon
efunon  2020/04/19(Sun) 17:51 No.1681
2020/04/19(Sun) 17:51 No.1681
��886�Ŋ��ɓ��e���������Y�ł����D���X�Ɏ��炵�܂����D
����DDR�r�I���^�[�ł����C�y���^�R���V�b�N�X�p�ƒ��ڔ�r�������Ƃ�����܂���̂ł킩��܂��A���f�B�t�@�C������̂��Ȃ��̂������[���Ƃ���ł��D
�u���j�J�p�ł����C�O�ς��Ⴄ�O������ƁC��ł�������������Ⴂ���e�X�g���ĊT�˓����`�ʌX���ł���Ȃ���C�O���^MC���ł��V���[�v�ł����D
���ꂪ�̍��Ȃ̂��C�C���܂ߌo�N�ω��Ȃ̂��͂킩��܂���D�J�������Ղ́C�ǍD�ȑO�����f���̂ق��ɂ���̂ł��D
P6�p���o�[�W�����ɂ���Ď�����ɍ�������Ǝw�E�����T�C�g������܂��āC�����[���ȂƎv���܂��D
���O���^�@�E����^
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2020/04/21(Tue) 01:56 No.1682
2020/04/21(Tue) 01:56 No.1682
�@�Ƃ����Ă��O�Q�͕��ݕi�Ȃ̂ł�����Q���J�r�J�r�ł����B�������l�Ő��|���ł��܂����̂ň��g���Ă��܂��B
���Č�Q�̐��|�ł����A�����Y����둤���猩��Ɠ�d�̉�����������Ǝv���܂��B���̉����̓������ɂ߂�ƃ����Y���O���܂��B
�ƂĂ����������Ȃ̂ŁA�����O���ꍇ�ɂ͏\�������ӂ��������B
�@
 efunon
efunon  2020/11/06(Fri) 18:24 No.1763
2020/11/06(Fri) 18:24 No.1763
�����炭�t�H�[�J���u���j�J �ł����Ƃ������\���掿�ȃ����Y�ł͂Ȃ��ł��傤���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2020/11/06(Fri) 21:25 No.1765
2020/11/06(Fri) 21:25 No.1765
�@�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�X�^�C���̗ǂ������Y�ł��ˁB�ŋ߃}�~��C��105mmF3.5 DS ������ł��܂����̂ŁA�B���ׂł����Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂��B
�@�ŋ߂͉��i���オ���Ă��܂��A��������Ƃ͔����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B
 efunon
efunon  2020/11/07(Sat) 10:18 No.1766
2020/11/07(Sat) 10:18 No.1766
�@�Ȃ��Ȃ��C�ɓ��������m�Əo��܂���ł���������ƌ����܂����B�����Y�P�̂ł͌�����܂���ˁB
�u���j�J�̕W����ł͌Q���č�������������ł��傤���B�����������Y�\���Ȃ̂ŋC�ɂȂ��Ă��܂����B
 efunon
efunon  2021/03/20(Sat) 00:24 No.1813
2021/03/20(Sat) 00:24 No.1813
���[���CTLR�̃v���i�[�݂�����1���ڒ��荇�킹�́C���ʂ���Ȃ��\���ł��B
HC��PC�Ɣ�ׂĖ��炩�Ɏ��Ӊ掿�����P����Ă���Ǝv���܂����B
���S���APC�̂ق����V���[�v�Ƃ����b�������܂����A�̍���������܂���
�ّ��HC�͒��S����PC�ɏ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂����B
��p���ĐM���ł��鍂���\�����Y�ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2021/03/20(Sat) 10:57 No.1814
2021/03/20(Sat) 10:57 No.1814
�@�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
���̂��A�摜���C�����Ă����f����Ă��Ȃ��l�Ȃ̂ŁA�Čf�ڂ������܂��B
�����ڂ͂�͂�ς��܂��ˁB�摜�̓u���j�JS�Ȃ̂ł����A�o�����X�I�ɂ�EC�n�̕����ǂ����������܂��B
 efunon
efunon  2021/03/21(Sun) 13:39 No.1815
2021/03/21(Sun) 13:39 No.1815
�@�Â��J�����E�����Y�������炢�ɂ����f�[�^�炵�����m��������܂���B
�u���j�J�p��50mm�͎��v�����������l�ŁA��r�I����̂��Ղ������Y�Ȃ̂ŁA�����ɂȂ������������Ǝv���܂��B
��r�I�ǐS�I�ȉ��i�ōw���\�ł��B
����50mm�Ɣ�r����ƁA�J���ł͏_�炩�����w�i�����₷���̂ł����A��������̈�ł��B
 efunon
efunon  2021/03/21(Sun) 16:02 No.1816
2021/03/21(Sun) 16:02 No.1816
Nikkor-Q400mmf4.5
Nikkor-P600mmf5.6
Niikkor-P800mmf8
Nikkor-P1200mmf11
�̃����Y�w�b�h���˂�����Ŏg�p����w���R�C�h�B
��]�\�ȎO�r�����B
���̌�A�}���`�R�[�g����C�}�[�N�������w�b�h���������ꂽ�B
600�C800�C1200��ED�����Y���������ꂽ���f�������邪�A�u���j�J �̃J�^���O�ɂ̓��C���i�b�v����Ă��Ȃ��B�������u���j�J �p���j�b�g��ED���f���͑����͉\�B
�ʐ^��ECTL�{Nikkor-P800/8
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2021/04/01(Thu) 01:07 No.1837
2021/04/01(Thu) 01:07 No.1837
�j�b�R�[��200mmf4�{�w���R�C�h�Ɠ����ȉ��̏d�ʂł��B
�ŒZ4m�C�V�����J�������傤�Ǎ��E�����ς��Ɏʂ�܂��B
����������肽�����́A��o���l�b�g�̂��ߒ��ԃ����O��x���[�Y�͎g���܂���̂ŁA
�N���[�Y�A�b�v�����Y�����Ȃ��킯�ł����A���傤�ǃj�b�R�[��200mm�p�̏œ_������4m�ŁA
�������悤��300mmf5.6�̍ŒZ�ƁA10cm���Ⴂ�܂���B
�x�����Ɏア�̂ŁA���ʎ�����c�ȂȂLj��e���͍ŏ����x�ł����ւ�V���[�v�ȑ������т܂��B
��ʂɕ��y���Ă���œ_�����͍ʼn���1m����ŁA����ł�4m�Ƃ̃M���b�v���傫�����A�g�嗦����قǍ�����]���Ȃ�����g���Â炢�ł��傤�B
���肵�ɂ����ł����]���p�̃N���[�Y�A�b�v�A2m�̂��̂����݂��܂��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2022/01/13(Thu) 19:35 No.1935
2022/01/13(Thu) 19:35 No.1935
�N���[�Y�A�b�v�����Y�́A�~���[���X�J�����̃J�o�[�K���X�̉e�������邽�߂ɂ��낢�뎎�������Ƃ������āA
http://monoblogue.nikomat.org/article/167401705.html
http://monoblogue.nikomat.org/article/167888343.html
���̎��ɓx���ア�̂�T���Ă����������܂����B���̎��̃��T�[�`�ł́A�ł��ア���̂̓P���R�[�� No.05 �ł����if = 2000mm�j�B
�ŁA�U�N�قǑO�͕��ʂɕς����̂ł����A������� amazon
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B001CNC1QA
�ł͎戵�Ȃ��ɂȂ��Ă���A���ł�������Ȃ��悤�ŁA�ǂ����f�B�X�R���ɂȂ��Ă�����ۂ��ł��ˁB�c�O�E�E
�g�����Ȃ̂Ŏg���ɂ����ł����ǁA�P�Ȃ镽�ʃ����Y�ł���Ό��w���i���[�J�Ɏ�舵��������悤�ł��B�V�O�}���@�Ȃ�J�^���O��ł͒��a50mm�ŏœ_����4000, 5000mm �Ȃǂ���܂��B
 ���Y
���Y  2022/01/13(Thu) 20:27 No.1936
2022/01/13(Thu) 20:27 No.1936
�~���[���X�Ƀr�I�S��21/4.5�{�j�R���N���[�Y�A�b�v�̋L���A�n�C�u���E�������Ӗڂł����B
�m���Ƀr�I�S��21/4.5��AGR21/3.5�̎��ӂ́Aa7R�ő�ϗ���̂ő�ϗL�p�ȃ��|�[�g�ł����B
����ZM21/2.8�͑Ώ̌^�Ƃ����Ȃ���A�~���[���X�Ŏ��ӂ����I�ɂ悭�Ȃ��Ă���A�ŋ߂̃����Y�͑����l���Đv����Ă���Ȃ��Ɗ��S���Ă��܂��B
���ăP���R�[��72mm�N���[�Y�A�b�v0.5�A�����^����Ɏv�������т܂������A���w�E�̒ʂ�A�}�]����h�o�V�ł͍w���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��āA��͂�f�B�X�R���ł��傤���B
�ŋ߂̃����Y�͍ŒZ���Z���Ȃ��Ă���A���͂��ڂ��I�����̂����B
�^������28-200�p�̏œ_����2m�N���[�Y�A�b�v���茳�ɂ���A1�͐�p�o���l�b�g�ł����������72mm�ł��B���������ăP���R�[��OEM�Ȃ̂��ȂƎv���܂����B
�o���l�b�g��}�E���g����Ă��Ȃ��ʃ����Y�́A���������킹�邱�Ƃ�������ŁA�S�O���Ă��܂��B
�j�b�R�[��300mm�́A��X�C�O�ʔ̂ŏo�Ă����̂Ŏ���o���܂������A�����ł͎肪�o�Ȃ������ł��傤�B
�ʔ������ƂɃu���j�J200�p�N���[�Y�A�b�v������ƁA300/5.6�������ʒu�ŁA�����Y�P�̂̍ŒZ4m�Ƃقړ��������ʒu�ŏœ_������̂ł����A���{����������Ə������Ȃ�܂��B
�ʃ����Y��t������Ώœ_�������Z�k���邽�߁A�l�����瓖����O�̂��Ƃł����A��p�I�ɓ����ł͂Ȃ��̂ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2022/01/13(Thu) 23:18 No.1937
2022/01/13(Thu) 23:18 No.1937
35mm�p�́A85-210mm�Y�[���p�ɏœ_�����s��(���Ԃ�3.5-4m)��58mm�N���[�Y�A�b�v�����Y������܂����B�ėp�Ƃ��ă�49mm�ɂ�S40�CT80, T160������܂��B�悭��������̂�No1�Ƃ������̂ŁA��L�̏œ_�����̌n�ł͂Ȃ��A�W�������Y�ɒ��ԃ����ONo1�������Ƃ��Ɠ������x�̊g�嗦���疼�t����ꂽ�Ƃ����܂��B
�E�����܂����B
�u���j�J�Ɏg���ɂ̓�67mm���]�܂����Ƃ���A���x�y���^�b�N�X6x7�����SMC�N���[�Y�A�b�v�����YS82, T132, T226�Ƃ���2���\���̏d���Ȑ��i������܂��B
�掿�I�ɂ����҂ł������ł��ˁB
�u���j�J �j�b�R�[��PC300mmf5.6�ɑ����������̎B�e�͈�
�u���j�J�j�b�R�[��200mm�p�@�œ_����4m�C�����B�e�͈�60cm�C�ŒZ�͈�24cm
SMC�y���^�b�N�XT226 �œ_����226cm�A�����B�e�͈�38cm�A�ŒZ�͈�21cm
SMC�y���^�b�N�XT132 �œ_����132cm�A�����B�e�͈�22cm�A�ŒZ�͈�13cm
S80�͕W���p�Ȃ̂Ŋ����ăe�X�g���܂���ł����B
�ȏ��3��������x�X�g�ł����A�Œ�4m��132�ŁA�قڔ{���̐�ڂȂ��ɎB�e�\�ɂȂ�܂��B
�܂��A�P���R�[�N���[�Y�A�b�v0.5�͏œ_����2m�Ȃ̂ŁA�j�b�R�[��200�p�Ƒg�߂������ڂȂ���20cm�̔�ʑ̂܂ŎB�e�\�ɂȂ�ł��傤�B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2022/01/14(Fri) 22:25 No.1938
2022/01/14(Fri) 22:25 No.1938
�u���j�JDX�A�܂���S����ɋ������ꂽ�O�}�E���g�ɑ�������]�������Y�B
S2�Ȍ�̑�}�E���g�Ƃ͈قȂ�A���ڂ̌݊����͂Ȃ����AS2�Ȍ�ɐڑ�����u���[�W�o���l�b�g�A�_�v�^�[�v�����݂���B
Nikkor-H 18cmf2.5�@2080g�@�ŒZ1.5m�@�t�B���^�[82mm
Nikkor-Q 25cmf4.0�@1200g�@�ŒZ2.3m�@�t�B���^�[67mm�i�t�[�h��82mm�X�e�b�v�A�b�v�j
Nikkor-T 35cmf4.5�@2050g�@�ŒZ4m�@�@�t�B���^�[82mm
�����Nikkor-T 50cmf5�����邪���͎����Ă��Ȃ��B
�����̃����Y�͂��ł�1951�N�i25cm�j1953�N�i18cm�j1959�N�i35cm�j�Ƀj�R�������W�t�@�C���_�[�J�����p�~���[�{�b�N�X�Ɏg�p����]�������Y�Ƃ��Ĕ�������Ă���A�u���j�J�ɐڑ�����A�_�v�^�[�����݂����B1959�N��18cm��25cm���u���j�J�p�_�C���N�g�}�E���g�Ɏ蒼������ċ������ꂽ�B1960�N���̃u���j�J�iDX�j�̍L���ł͂���2�{�̂ݏЉ��35cm�̋L�ڂ͂Ȃ��i�j�R���J�����̏��l�^�l�u�u���j�J�p����a�]�������Y�v�̍��Q�Ɓj�B1961�N�ɔ������ꂽ�u���j�JS�̃J�^���O�ɂ�35cm��50cm���f�ڂ���Ă��āA������RF�p�Ƃ���قǎ��ԍ��Ȃ��o�ꂵ���悤���B
�摜�F�u���j�JS�CNikkor-H 18cm
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2023/02/27(Mon) 23:33 No.2187
2023/02/27(Mon) 23:33 No.2187
���ׂăv���Z�b�g�i�肾���A35cm�����͋����Ƀ����[�Y�\�P�b�g������X�v�����O�ōi�胊���O���u���ɍi�荞�܂��Z�~�I�[�g�ɋ߂��@�\�ňӊO�ɑ��ː��������B
18cm�̓K�E�X�^�\��4�Q6���ŃK���X���d���A�����35cm�Ƃقړ����d�ʁA�������{�f�B���d���B�c�@�C�X�̃I�����s�A�]�i�[18cmf2.8�����閾�邢�����Y�B�K�E�X�^�̃V���[�v���Ə_�炩�������������`�ʂ����҂ł���BRF�p�ɂ݂͂��Ȃ��o���l�b�g�}�E���g���̎O�r��������Ă���B�܂������t�[�h�̒�����RF�p���Z�����̂��������ꂽ�B
25cm��18cm��肸���ԂԂ�Ōy���A�O�r���͂Ȃ����{�f�B�Ƃ̃o�����X���悭�莝���B�e���\�����Ȃ���B�G���m�X�^�[�^3�Q4���ő�σV���[�v�B�����t�[�h�͐[��nikon RF�p�Ɠ����Ɍ�����B
�摜�F��25cmf4�A�E18cmf2.5�@25cm�͂����Ԃ����B�w���R�C�h�����O�ɂ����F�̖_�͋N�������ăt�H�[�J�V���O���o�[�ɂȂ�
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2023/02/27(Mon) 23:40 No.2188
2023/02/27(Mon) 23:40 No.2188
���[�W�o���l�b�g�A�_�v�^�[��EC-TL�ɑ����B�u�ԍi�荞�ݑ����ƃX�v�����O�i��̃R���r�l�[�V�����Ŏ����I�������K�B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2023/02/27(Mon) 23:43 No.2189
2023/02/27(Mon) 23:43 No.2189
�O�܃}�E���g�����Y�̓v���Z�b�g�Ȃ̂Ń{�f�B�Ƃ̘A���@�\�͂Ȃ��A�P���ɂƂ���邾���B
��ύ����x�ŁA�K�^�Ȃ������ł���B
�㕔�Ƀt���A�J�b�^�[����������Ă���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2023/03/09(Thu) 23:18 No.2201
2023/03/09(Thu) 23:18 No.2201
�u���j�J�j�b�R�[���̏������`�b�N�}�[�N�t��������A���܂������Ă��郌���Y�̒��ő������̂Œ��܂��B
DX����͑��������������ł��傤���AS��������`�b�N�}�[�N�t�����g�܂ꂽ���͕�����܂��A���\��������̂ł����Ԍ�ɂȂ��Ă��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
75�C50�C135�`�b�N�}�[�N�t���B�O�ɏЉ��180�C250�C350���`�b�N�}�[�N�Ƃ͌�����قǒ������C����������Ă��܂��ˁB
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/11/10(Sun) 00:56 No.2635
2024/11/10(Sun) 00:56 No.2635
�O����S2������t�߂���A�����ECTL�̍��ɂ͓���ւ���Ă����Ǝv���܂��B
�[���U�u���j�J�p���]���́ADX���ォ��̃j�b�R�[��135mmf3.5�ƌ�シ��`�ɂȂ�܂����B
�O���i4�Q6���j�̐����̓m���^���w�炵���Ƃ����Ă��܂����A�m���^66�̌��������Y�Ƃ͈Ⴄ�X�y�b�N�ł��B
����i5�Q6���j�͐��������͂�����Ƃ��Ă��܂���B�������w�����ɏオ���Ă��܂����ǂ��ł��傤���B�܂������ETR�p�[���U�m��MC�Ɏp���ꂽ�\��������܂��B
���\�͂ǂ�����D�G�ł��B�𑜗͍͂b�����������B�O���̕����J���ł��_�炩���A����̕����R���g���X�g��������ۂł��B����͎���^���Ŗ���������������ӐF�����������C�����܂����A���p�I�ɂ͑傫�ȍ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B
135mm�����サ�����ł����A�m���ɖ]�����ʂƂ��Ă�150�̂ق��������A�܂����C�o���̃n�b�Z���u���b�h��1000F�����135mm����500C��150mm�ɂȂ������Ƃ����̈����������܂���B
�������A�w���R�C�h���p�����Y�ł�����A�]���n�͍ŒZ�B�e�����������Ȃ�͎̂d�����Ȃ��A150����135�̂ق������Ĕ{���������Ȃ�܂��B
�ߐڂ̓|�[�g���[�g�̃o�X�g�A�b�v�܂łŏ\���Ȃ�A2m�O���150�ł����i3.3m��200mm��肸���Ǝ��p�I�j�킯�ł����A����������肽���ꍇ��135�̂ق����L���ȏꍇ������܂��B
�n�b�Z���u���b�h�̃]�i�[C150/4�̍ŒZ�B�e������1.4m�ŁA���̓_�ł͏����s���ł����C�J��f�l�͎�[���U�m���̂ق������邢�̂ŁA�����{���̃{�P�͓�������L���ł��傤�B
���O���^�A��������^�A�E�Q�l�܂Ńj�b�R�[��Q135mmf3.5�i3�Q4���j�P���ȃe�b�T�[�^���œ_�̃j�b�R�[���̂ق����G���m�X�^�[�[���U�m����蒷���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/11/10(Sun) 14:19 No.2638
2024/11/10(Sun) 14:19 No.2638
�������ꂽ80mmf2.4�ƈӏ��͎��Ă��܂��B
���炩�̗��R�ŁA����f2.0���X�y�b�N�_�E������f2.4�ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƒz����痂������Ă��܂��B
�܂�Ai�摜���H�Ńt�F�C�N���C�y�ɍ��鎞��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA���݂���\���͍����̂ł́B
���a�́A�j�R���̃��^���L���b�v���ʂ��Ă���̂ŁA50/3.5�Ɠ�����82���A50/2.8�Ɠ���77�̂悤�Ɍ����܂��B
�ȑO�̑z���ł́A�m���^��80/2.0���u���j�J�ɂ��K�������悤�Ƃ������A�}�E���g�a�̖��ŕs�\����������A2.4�ɏk�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂������A���̉摜������Ƃ����P���ł͂Ȃ��A��U�u���j�J���o���l�b�g�ɍ��킹��f2.0���f�������삳��A��������Ƃ��̑O�ʌa�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������Ƃ��ƁB
����Ŕ������Ă������ꂽ�Ǝv���܂����D�D�D
���邢�̓����Y�V���b�^�[105mm�̂悤�ɁA��o���l�b�g��p�Ƃ��āA�����Ɛ��Ȃ�����a�v�����Ă��悩�����̂ł́B
���p�Ƃ����_�ł́A���s���C���ő傫�ȕs���͂Ȃ��A���܂�ɏœ_�[�x���ƃt�B�����ʂ̖�������܂��̂ŁA�悢�]������ꂽ���͋^��ł͂���܂����A�c�O�ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/11/10(Sun) 15:30 No.2639
2024/11/10(Sun) 15:30 No.2639
1970�N�J���������J�^���O
�h���z�̉�ʃT�C�Y6�~7���h��僁�[�J�[���J�������J���[����̃v���̃J�����A�@�����͔��Q�A���^�J�����Ȃ݂Ɏg�����Ȃ���^�J�������ӎ������܂���B���E�ɗނȂ��V�����v���T�C�Y�A�v���t�F�b�V���i���ނ��̒�������^���t�V�X�e���ł��B
�@�Ɖ]�������Ŏn�܂�A�T�q�y���^�b�N�X6�~7��1969�N��4�{�̃����Y�Ƌ��ɔ��\����܂����B
1970�N�̃J�^���O�ɂ�MAMIYA RB67�̔��\���L��܂��̂ŁA�قړ��N�iRB�̕����������x���j��6�~7�@�����������ɂȂ�܂��B
��ȃX�y�b�N��
�E��ʃT�C�Y�F55mm�~70mm�i���̒l�j
�E�V���b�^�[�F�d�q����t�H�[�J���v�����@X.B.1�`1/1000
�E�t�@�C���_�[�F�e������\
�y���^�v���Y�����A�C�����F���i���엦 90�� ���{�� 1.0�i105�����j ���x 2D
�Œ�s���g�t�[�h�A�܂肽���݃s���g�t�[�h
�E�����グ�F���o�[���Z���t�R�b�L���O�@100�x1�쓮�����グ�@�\���p10�x
�E�����Y�����F��p�_�u���o���l�b�g��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� 35�`300�~��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�� 400�`1000mm
�E�傫���F 84�~149�~91mm
�@�@�@�@�@�@177�~152�~91mm(TTL�y���^�v���Y���j
�E�d�ʁF2380g�i105mm�j�@�{�f�B�[�̂�1290��
���������Y�i1969�N�j�@�X�[�p�[�^�N�}�[
�E 75mm F4.5
�E105mm F2.4
�E150mm F2.8
�E200mm F4.0
�i1971�N�����j
�E35mm F4.5�@�i�t�B�b�V���A�C�^�N�}�[6�~7�j
�E55mm F3.5�@�i�X�[�p�[�^�N�}�[�j
�E75mm F4.5�@�i�X�[�p�[�^�N�}�[�j
�E300mm F4.0�@�i�X�[�p�[�^�N�}�[�j
�E400mm F1.0�@�i�^�N�}�[�j
�E600mm F4.0�@�i�^�N�}�[�j
�E800mm F4.0�@�i�^�N�}�[�j
�@���ꂪ1977�N�̑����J�^���O�ɂ̓A�T�q�y���^�b�N�X6�~7 �~���[�A�b�v�t���ƂȂ�܂��̂ŁA�~���[�A�b�v�@�\����������^�C�v��1976�N���̔��\�ɂȂ�Ǝv���܂��B
���̌�A1989�N�ɁhPENTAX 67�h�@�ƂȂ�B���S�̕ύX��������܂��B
�������āA1998�N��AE��I���\�ȁhPENTAX 67 �U�h�ɂȂ�܂����B
PENTAX 67 �U
�@�����ɂ킽���Đ������ꂽ67�ł����A�d���n���A�i���O����f�W�^������ɑ���A���[�U�[�̒��N�̑z���������āA�i��D��AE�����ڂ���܂����B
�@�����Y�͂�����ォ�狤�p�ŁA���[�U�[�ɉߓx�ȏo��������Ȃ��l�ɔz������Ă��܂��B
�E�����I�o�FTTL�J��6������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�����͈́@EV2�`21 �i105mm F2.4 ISO100)�@�I�o��͈́}3EV(1/3�i���j
�@�@�@�@�@�@�@�@1/1000�`30�b
�@�@�@�@�@�@�@�@�X�s�[�h���C�g�@TTL�����I�o
�@�@�@�@�@�@�@�@�iAF360FGZ�g�p�ɂ��A�n�C�X�s�[�h�A�斋�A�㖋�V���N���A���ʔ䐧��j
�E�V���b�^�[�F�d�q����z���V���b�^�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�}�j���A������ 1/1000�`4�b�@B(�p���[�Z�[�u�j�AX�i1/30�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���t�^�C�}�[����
�E�t�@�C���_�[�F���엦90���@���{��0.75�{�i105mm F2.4)�@+2D
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�����@�\�i-5D�`+3D)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t�@�C���_�[���\���@�i��l�A�X�s�[�h���C�g���A�I�o��o�[�O���t�A�}�j���A����O/U�\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������[���b�N�A�t���[���J�E���^�[�A���������\��
�E�����グ�F�����グ�p190�x�@�\���p7�x
�E�傫���F185.5�~151�~106�~��
�E�d�ʁF2380g�i105mm�j�@�{�f�B�[�̂�1290��
�@�l�X�ȃA�N�Z�T���[���p�ӂ���A��������V���i���d���p�������i���T�[�h�p�[�e�B�[�i���L��܂����B�j�܂Ő��E���ōL�������ꂽ�J�����ƂȂ�܂����B
�i�����Y�͎����Ă��܂��B�j
�@��낵�����肢�������܂��B
 efunon
efunon  2018/07/29(Sun) 17:13 No.1288
2018/07/29(Sun) 17:13 No.1288
�A�_�v�^�[�ɂ͋����ڐ�������ŒZ2.5m�A�P�Ȃ�w���R�C�h�Ŏ����i��͂Ȃ��B
�C�}�S���͐�O1931�N���炠��ÓT�I��1�Q2���\���̋��ʎ����𗘗p������œ_�����Y�ł���B
�@�]�k������O�͐F�����𗘗p������œ_�����Y�����������A���J���[�ʐ^���嗬�ɂȂ�Ə����Ă������B�C�}�S���������c�����̂͐F�������ꂽ���ʎ����\�t�g������ł���B
120mm����360mm�i�̂͂����ƒ����̂����邩���j�܂Ŋe��œ_����������A�y���^�b�N�X6x7�p��200mm���̗p���Ă���B
����200�Ȃ̂��A�����͖]���߂���̂ł͂Ǝv���Ă����B
120mm��6x6�ɑ����������̂��ʂ��ė����ł����B���ӂ����ꂷ����̂��B6x7�Ȃ�200�̉�p���K�����낤�B
���[�f���V���g�b�N�����A�ʌy���^�b�N�X6x7�p�̋������������Ă������Ƃ����J�^���O�ŏ��߂Ēm�����B���̌`��͈����w�̃C�}�S���A�_�v�^�[�Ƃ͎��Ă������Ȃ��B200mm�͂��̑��A�y���^�R���V�b�N�X�A�}�~��M645�A�n�b�Z���u���b�h2000FC�A�t�H�[�J�X�v���[���u���j�J�A���[���CSL66�A�}�~��RB67�p�̋��������[�f���V���g�b�N���狟�����ꂽ�B�n�b�Z��500�n�ɂ͐����T�|�[�g�͂Ȃ����A�R���p�[�V���b�^�[�g�ݍ��݂Ŏg�p�\�ł������B
���[�f���̃w���R�C�h�̓X�g���[�N�������A�ŒZ1.1m��1:4.3�܂Ŋ���炵���B
�C�}�S���͓��ʍi����g�p���Ȃ����߂��i���o�[���g���Ȃ��B���ʂƃ\�t�g�ʂ��R���g���[�����邽�߃����R����ɑ����̌����������O���b�h���g�p����B�Z�b�g�ɂ̓O���b�h3���iH5.8-7.7, H7.7-9.5, H9.5-11.5)�܂���2���i�O��2��j��NDx4�t�B���^�[�A�t�[�h���܂܂��B
�O���b�h�͒����̑傫�����Ƃ�������͂ޑ����̏����Ȍ�������A��������]���A���͂̏������ӂ����Œ����̌������ɂ��邱�Ƃ��ł���B�S�J�����Ƃ���H�l��5.8�Ȃ�A���������ɂ�������H7.7�ɂȂ�B
���ʎ����̓����Y���ӂقǑ傫���v�Ȃ̂ŁA�i������Y�����������g�����ߎ����͏������A���������ă\�t�g�x�����͏������V���[�v�ɂȂ�B
���͂̏������J���Ă���قǃ\�t�g�x�����������Ȃ�B
�������邳H7.7�ł��A���������J����H5.8-7.7��H7.7�����AH7.7-9.5��H7.7�̂ق����\�t�g�x�������傫���Ȃ�B
�\�t�g�ʂ́A�������x�����ōׂ��������ł���͂������A����ł���قǑ@�ׂȒ����͓���̂ŁA�S�J���S�ł������͎g�����Ȃ��Ȃ��B
�O���b�h���O���Ă��܂��ƁAf3.5���炢�̖��邳�ɂȂ�A���ʎ������ɒ[�ɑ����ӂ�ӂ�̑��ɂȂ�B
���E�O���b�h���g�p���郌���Y�ɋ��ʂ��āA�_���������ɔώG�ȃ{�P��������B�܂���{�P�͋ɂ߂ĉ����B
�܂��A�\�t�g�t�H�[�J�X�����Y�͋��ʎ������������߁A�݂����̔�ʊE�[�x����ϐ[���A�A�E�g�t�H�[�J�X�͂ڂ��ɂ����B
����͔w�i�����g�p���鎺���X�^�W�I�|�[�g���[�g�܂��͏��i�B�e��z�肵�������Y�ł����āA���O�̕��G�Ȕw�i���ڂ������Ƃ͂����炭�l���Ă��Ȃ��i�܂��͒��߂��j�Ǝv����B
���͉��O�ł͒��S�̌������g��Ȃ����A�O���b�h���O���Ďg���B
�̂��Ƀ��[�f���V���g�b�N�ʐ^�p���w���i�̑㗝�X�́A�����ɂ����A���̂��߂��͂킩��Ȃ����y���^�b�N�X67�̃J�^���O����C�}�S��200mm�͗������B���̂����ɁASMC�y���^�b�N�X�\�t�g120mmf3.5���o�ꂷ��B
�摜�F�y���^�b�N�X67II�A�C�}�S��200mm�O���b�h�O���A�t�W�v��400
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/08/05(Sun) 00:24 No.1294
2018/08/05(Sun) 00:24 No.1294
���̍ۂɐV����67�p�����i���SMC�y���^�b�N�X67�\�t�g120mmf3.5�����C���A�b�v���ꂽ�B
�C�}�S��200mm����p���L���A���邭�A�O���b�h�ł͂Ȃ��i��ŘI���ʂƃ\�t�g�ʂ��R���g���[�����邽�߁A�����₷�����p�͈͂��L���Ȃ����B
���̃����Y�̍\���̓C�}�S�����l1�Q2�������A���X�̐��藧���́A�y���^�b�N�X�f���^���}�N��100mmf4�p�̃N���[�Y�A�b�v�A�^�b�`�����g���w���R�C�h�ɑg�ݍ���ŁA�H�R�����Y���ɒ��ꂽ���p�\�t�g�����Y���D�]����������1986�N�ɐ��i�������ASMC�y���^�b�N�X�\�t�g85mmf2.2�����^�ł���B
�i��J������f8�܂Ń\�t�g�x�����������w�W������Af8�ȍ~�͕��ʂɃV���[�v�Ɏʂ�A�Ƃ���Ă��邪�A���S�Ƀt���A���Ȃ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ��ו��ɉB�����̂悤�ȃt���A���c��B
�������P���ȍ\���̂��߂��A�\�t�g���ʂ��o��i��ł͎��Ӊ掿���ǍD�Ƃ͌������A�e���R���o�[�^�[�Œ��S��p���g���Ă��������������ƕ����B
�H�R�����Y�����A85mm��x1.4�e���R���o�[�^�[�Ŏ��ӂ��J�b�g���Ă����������B
�l�I�Ȋ��z�Ƃ��ẮAf3.5�`f8�͕��ʍi��Af8�`22�͎����i��ƃy���^�b�N�XFA�\�t�g85��FA28�\�t�g�Ɠ��l�̑��쐫�ŕ֗��A�`�ʂ��Y��ł����J���̎��Ӊ掿�ƌ��a�H�ɋC������ׂ����Ǝv���܂����B
Pentax67II, SMCsoft120/3.5 f3.5�CAE�Cpro400
�j��I�ȃC�}�S���O���b�h�O���Ɗr�ׂĂ����Ԃa�����`�ʂł��ˁB
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/08/05(Sun) 02:05 No.1295
2018/08/05(Sun) 02:05 No.1295
�����N�͒肩�ł͂Ȃ����A1988�N���ɒ����y���^�b�N�X67�ƃ}�~��M645�}�E���g�ŁAVK105R���o�ꂵ���B105mmf4�ƁA6x7���ł͕W����p�ł���B
VK70R�͂܂��Ƀx�X�P�̕����ł���A�J���ł͎��ӂ̓_�����{�P�����ˏ�ɔ��������A���ӂ̃{�P���������ƈقȂ�`�ʂ����̂܂܂ł���A�g�����Ȃ��y���݂����邪�Ȃ�����B�܂����]����p�͋�������Ƃ����]��������AVK50R�͒P�ɍL�p�����ꂽ�����ł͂Ȃ��A�_�����{�P�͌����ɋώ��ɑ����Ă���A���ӂ܂ŋψ�ȃ\�t�g�`�ʂŔ��ɐ������ꂽ��œ_�����Y�Ɏd�オ���Ă���BVK105R�͂��̗�������݁A�J�������ϒ[���ȕ`�ʂ�����B
1�Q2���{�O�ʕی�K���X1���A�ŒZ1m�A�����ɂ͋����w�W�����B�i��ɂ��\�t�g�ʒ��߁B
�C�}�S��200�A�y���^�b�N�X�\�t�g120�Ɗr�ׂ�VK105R�͊J���̃\�t�g���͂��Ȃ艟�������Ă��܂����A�L��p�Ŏg���₷���A�����i��l�őO�Q�҂Ɣ�r���ĕȂ��Ȃ��A���͒����\�t�g�̂Ȃ���VK105R�������Ƃ��C�ɓ����Ă��܂��B
VK50R���f���炵���`�ʂł����A�œ_�������Z�����߃t�H�[�J�X�̒��S���킩��Â炭�A�����w�W���Ȃ����ߎB�e�ɂ͏�����J���܂��BVK105R�͏œ_�������������߂��t�H�[�J�X�̐c�����F���₷���A�y���^�b�N�X67�̍��킹�₷���œ_�Ƒ��܂��ĉ��K�ȎB�e���ł��܂��B
Pentax 67II, Kiyohara VK105R 105mmf4�@�J���@AE, Pro400
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/08/05(Sun) 08:30 No.1296
2018/08/05(Sun) 08:30 No.1296
�@��ϋM�d�ȉ摜�����肪�Ƃ��������܂��B
�L���n����105mm��70mm�������Ă���̂ŁA�C�ɂ͂Ȃ��Ă����̂ł����A�����Ȃ��Ă��܂��܂����B
�@�y���^�b�N�X��85mmF2.2�͂Ȃɂ������܂Ńt���A�[���o���Ȃ��Ă��Ǝv���Ďg���Ă��܂������A������Ǝ��ɂ͎g���h��������ۂł��B
�@�Ȃ��A���Y�\�t�g�t�H�[�J�X�����Y�̃t���A�����͂���Ȃɑ傫�����Ă��܂��̂��H��������Ȃ��Ɣ���Ȃ��̂��ȂƎv���܂��B�Â��A�T�J���̕ʍ��ɍڂ��Ă����h�N�O�ʐ^�h���v���o���܂��B
�@�l�I�ɂ̓R�}�G�N�̊J���t�߂̗l�Ȕ����ȟ��݂��~�����̂ł����A�ȊO�ɋ͂��ȟ��ݗʂ𐧌䂷��̂�����ł��B
�@�ŋ߁A120mm�����i�\����Ȃ����i�Łj�����̂ł����A�����{�f�B�[�������Ă��邾�낤�Ǝv���Ă���̂ł����A�{�f�B�[�������̂ɁA�L�p�`���]���܂ő����Ă��܂������ł��B
�@�y���^�b�N�X67�ɂ͌Â�����L��135mm�̃}�N���Ɣ�r�I�ߔN��100mm�}�N�������Y�i������搂��Ă��Ȃ��̂��H�j���L���āA�ډ��C�ɂȂ��Ă���Œ��ł��B
 efunon
efunon  2018/08/05(Sun) 09:38 No.1297
2018/08/05(Sun) 09:38 No.1297
>�y���^�b�N�X��85mmF2.2�͂Ȃɂ������܂Ńt���A�[���o���Ȃ��Ă��Ǝv����
��{�I�ɂ̓N���[�Y�A�b�v�A�^�b�`�����g�ł��̂ŁD�D�D
��X�f���^���}�N���Z�b�g�������Ă��܂����̂ŁA�H�R���ɓ͂���ꂽ�Ƃ������̂��Č����Ă݂܂������A�i�肪�Ȃ��̂Ŏv����_�炩���A����ō��ł��鎩�M�Ȃ���ƁA���X�ɂ炵�ăA�^�b�`�����g�ɖ߂��܂����B
<�@�Ȃ��A���Y�\�t�g�t�H�[�J�X�����Y�̃t���A�����͂���Ȃɑ傫�����Ă��܂��̂��H��������Ȃ��Ɣ���Ȃ��̂��ȂƎv���܂��B�Â��A�T�J���̕ʍ��ɍڂ��Ă����h�N�O�ʐ^�h���v���o���܂��B
�ʔ����X���ł��ˁB
�z�胆�[�U�[�����{�ł̓A�}�`���A������ł��傤���B�C�}�S���̐�����������Ɖ��Ăł̓v�������Ƃ�����ۂŁA��{�P�����v���̎B�e�����Ȃ���Ȃ��ł��傤�B�����v�������ł͑������邱�Ƃ͂ł��܂���ˁB���̂����100�N�߂����������A���{�Ƃ͐^���̎v�z�ł��ˁD�D�D
>�@�l�I�ɂ̓R�}�G�N�̊J���t�߂̗l�Ȕ����ȟ��݂��~�����̂ł����A�ȊO�ɋ͂��ȟ��ݗʂ𐧌䂷��̂�����ł��B
�唻�e�b�T�[�^�A�_�S�[���^�͊F�J���t�߂ł̓n����������݂܂����A�����ȍD�݂�����Ǝv���܂��B
�w�������y�̃J�b�v�����j�R��FE�ɃP���R�[�\�t�g���ŎB�e���A�t�@�C���_�[�Œ��x�ǂ��Ǝv����6��ɐL���ƂƂ�ł��Ȃ��t���A���̂����摜�ɂȂ���������Ƃ�����܂��B
���i����g������ł��Ȃ�����A�����ȉ�ʂł̓\�t�g�͉ߏ��Ɍ�����Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂���ł����B
�唻�ł����Ă��A�t�@�C���_�[�X�N���[���Ŏv���܂܂Ƀ\�t�g�ʂ��R���g���[������̂͑����N���Ɠ��@�́A���C�e�B���O�̃Z���X���v��̂��������܂��B
>�@�ŋ߁A120mm�����i�\����Ȃ����i�Łj�����̂ł����A�����{�f�B�[�������Ă��邾�낤�Ǝv���Ă���̂ł����A�{�f�B�[�������̂ɁA�L�p�`���]���܂ő����Ă��܂������ł��B
���͂́I�I
����ȉ��i�ŏo�Ă���Ƃ����g�������Ă��܂��܂���ˁB
�ŋ߂̓{�f�B�����\�肪�Ȃ��̂Ɍ��l�����ɂ���Ă��܂��d�ǎ҂ɁB�����l�ł��D�D�D
�w�r�[���[�U�[�̕��͊F�����ƌ��������̂͂��Ŏ����o�����͙̂G�z�ł����D�D�D
�L�p�̔����͂�͂�75/2.8AL�ł��BFA35/2AL���f���炵���ł����A���S�ɂ���̊g�唻�A�J������掿�͕ʊi�ł��B
35/4.5����A40/4���D�ꂽ���ʂ������܂����B
55/4�͊O�ϐF�X�o�[�W����������܂����A�`�ʂǂ��Ȃ�ł��傤�B
�y���^67�ł́ARB��GS�ɂ͂Ȃ��L�x�ȃY�[�����g���Ă݂����āA�^�����55-100���m�ۂ��܂����B�Z�œ_�ȏ�Ƃ͌����܂��A�܂��܂����Ǝv���܂��B
>�@�y���^�b�N�X67�ɂ͌Â�����L��135mm�̃}�N���Ɣ�r�I�ߔN��100mm�}�N�������Y�i������搂��Ă��Ȃ��̂��H�j���L���āA�ډ��C�ɂȂ��Ă���Œ��ł��B
135�̓^�N�}�[�������Ă��܂��A�������͊J���ł�150,165�Ɗr�Â��A�ߐڂł͗D�G�A�܂�������O�ł����B4x5�̃v���i�[135�ŋߐڂ����薾�炩�Ƀ^�N�}�[�̂ق����V���[�v�ł��B
135�P�̂�1/4�{�܂ŁA6x7�ł�����B�e�͈͂��L�����������g��ɂȂ�܂���B�`���[�u���p���K�v�ł��BP67�̃`���[�u�͔�r�I�y���̂ł��قǏd�ʕ��S�ɂ͂Ȃ�܂��B
100�̃V���[�v�l�X��1�i��Ɋ����܂��B���������җ�ɗǂ��ł��B��p�N���[�Y�A�b�v�A�^�b�`�����g�œ��{�Ƃ����d�l�͓����̗��s�ł��ˁB1/2�{�͒P�̍ŋߐڂ̂ق����A�^�b�`�����g���ʼn��������ǍD�ł��B�����������O�ł��ˁB
���̃A�^�b�`�����g�̓�49mm�ŁA�X�e�b�v�_�E������đ��Ѓ}�N���ɂ��֗��Ɏg���܂��B������SQ110mmf4.5��A�A�|�W���}�[90�ɛƂ߂Ă݂܂����B���ɐ��\�e�X�g�͂��Ă��܂��A�����Ȃ��Ǝv���܂����B
pentax67II, macro100/4, closeup attachment, Benbo Trecker�ł̐ڎ�
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/08/05(Sun) 10:47 No.1298
2018/08/05(Sun) 10:47 No.1298
�@�\�t�g�����Y�̗��������́A�t�@�C���_�[�ł̌������Ǝ��ۂ��قȂ镔���������ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�@�ȑO�G��܂������A�\�t�g�����Y���i���Ďg���Ɖ]�������I�Ȏg���������܂��B���̂킸���ȕ����ŕ`�ʂ��R���b�ƕς���Ă��܂��Ƃ��낪����ł��B
�@135mm�̓J�������肽���Ɏv�����̂ł����A35�����J�����Ƃ͈Ⴄ�l���������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂����B
�@���{���������ł��A�t�@�C���_�[�ł�135���������������܂��B����Ɣ�ʊE�[�x�ł��ˁB������i���Ă�����Ȃ����炢�ł����B
 efunon
efunon  2018/08/05(Sun) 11:10 No.1299
2018/08/05(Sun) 11:10 No.1299
���Ђ̋ߎ��œ_���������Y�Ɣ�r���ďd�߂̋@�������܂����A���̏ꍇ�͑���a�ł��B
�ŏ����X�[�p�[�^�N�}�[���ォ��p�ӂ��ꂽ���̃J�����̑�\�I�W�������Y�A�K�E�X�^105mmf2.4��6x7���ȏ�̈�ʎs�̕i�ł́ARF�J�������܂߂čő���a���ւ�܂����A����ɂ��Ă͑�Ϗ��^�y�ʂł��B
�y���^�b�N�XS2����̐v�ł�����Õ��ł͂���܂����A�J������\���ɍ��掿�ŏ����i�邾���Ŕ��Q�̃R���g���X�g�Ƌψꐫ�ɂȂ�܂��B
105mm�ł͂��������߂Ɗ���������́A�قƂ�Ǖς��Ȃ����邳��90mmf2.8������܂��B�����SMC�^�N�}�[���ォ��o�ꂵ�܂����B�������g���t�H�[�J�X�I�\���ł����A105���S�����Z���y�ʂŁA�g���₷����p�ł��B�掿���\���悢�Ǝv���܂����B�\����܂��g�p�o������Ɍ�{�P���܂������C�ɂ��Ȃ��̂ŁA���̕ӂ�̃R�����g�͂ł��܂��B
SMC�y���^�b�N�X�������ɂȂ��āA100/4�}�N���A300/4ED�A400/4ED�A800/6.7ED�A55-100��90-180�Y�[���ȂǂƑO�サ��75mmf2.8AL���o��A�ʂ��̗p���J�����炫��߂č����掿�������A�{�����������B
75/2.8�͏]����75/4.5�Ɗr�ׂăT�C�Y�������ȉ��ɏ��^�y�ʉ�����A90/2.8���ɂȂ����B
���邢���]���́A�X�[�p�[�^�N�}�[���ォ��150/2.8���p�ӂ���Ă����B�J���ł̓n����������ς��炩���掿�����A�����i��Ɛ�s�ɂȂ�BSMC�y���^�b�N�X�����150�ƌ�サ��165/2.8�͊J������N���A�Ő�s�A�S�����i���Ⴄ2�{���g�������Ă��ǂ��Ǝv����B
�y���^�b�N�X6x7�~���[�A�b�v�ASMC�^�N�}�[90/2.8�J���A3���i���������j�t�W�v��400
�@���N�E��̋߂��Ōu�B�e����̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B
���̂Ƃ��́A��p���L�߂Ŗ��邢�����Y��90mm���������Ă��Ȃ������̂ŁA������g���܂����B
���������x�t�B�����̑I���������܂����̂ŁA���邢�����Y���g���A�Â���ł��œ_�����킹�₷���y���^�b�N�X67�n�͑ウ��@��ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/08/05(Sun) 17:09 No.1300
2018/08/05(Sun) 17:09 No.1300
��̔���蔒���^���`���E�d���̔��F���ʂ郌���Y�ƌ����t�B�����S������ɂ͂��̃����Y�Ń^���`���E�d���̎ʐ^���B�����������������ꂽ�Ƃ��B
�ʐ^�͎g���Ȃ��Ȃ蒆�Âł��`���ꂵ�����̂W�O�O���������Y�ł��B
�U�V�U��1.4�{���A�R���{2�{���A�R���̂Q�Q�S�O�������P�W�D�W�ɂ�����Ԃł��B
�y���^�b�N�X�U�V�͂��̋���ȃ~���[�V���b�N�ɂ�������炸�u���ɂ����J�����ł���ŎB�e���Ă��Ԃꂽ���Ƃ͂���܂���B
���ɂW�O�O�����Ƃ��Ă͂��S�����Y������܂���������͂d�c�����Y�ł͂���܂���B
�ȑO���S�x����Ńy���^�b�N�X�̍Ō�̍ɂƎv����W�O�O�������S��3�{�o�Ă܂����B
1�{18���~���炢�ł����̂łق��������̂ł��������Y�P�̂łP�V�D�V��������ŒZ�B�e�������Q�O���Ǝg���ɂ����̂Œf�O���܂����B
 ken
ken  2018/08/06(Mon) 07:47 No.1302
2018/08/06(Mon) 07:47 No.1302
�v���r�A�S�O�O�ŎB�e���Ă܂��B
�e���R��2�t�ł��𑜗͂����炵���ł��B
�����Ƃ��Ă��邱�Ƃ����҂ł��Ȃ��쒹����̎B�e�ł����s���g���f�������m�ɍ��킹���Ă܂��B
�f�W�^���J�����ł̓e���R��3�t�S�S�W�O�������R�V�D�U�ŎB�e�������Ƃ�����܂����悢�ʂ�ł��B
����ŎB�e���Ă���Ƒ��̐l����ϋ����A�{���ɂ���Ŏʐ^���B����ł����ƕ����Ă����܂����������Ǝʂ��Ă܂��B
 ken
ken  2018/08/06(Mon) 07:52 No.1303
2018/08/06(Mon) 07:52 No.1303
�y���^�b�N�X�U�V�͓��̂��B�e�ł����ԑ傫�ȃt�H�[�}�b�g�̃J�����������̂ł��̃����Y�͂Ă�����p�B�̃����Y�����������ł��B
�U�V�U�Ƀx���r�A�P�O�O�Ŏ莝���B�e�ł��B
 ken
ken  2018/08/06(Mon) 07:56 No.1304
2018/08/06(Mon) 07:56 No.1304
�@�h�U�V�U��1.4�{���A�R���{2�{���A�R���̂Q�Q�S�O�������P�W�D�W�ɂ�����Ԃł��B�h
�@67�U�ł͂���ȂɈÂ��Ă��s���g�����킹����̂��Ȃ̂ł��ˁB�t�B�[���h���[�N�ɏd��Ă���̂�����܂��B
�摜��q�����Ă��A�R���g���X�g�̒ቺ�͉]���Ȃ��Ă͔���Ȃ��ł��B�L���v�V������ǂ�ŋ����܂����B
�@400mm���莝���Ƃ����̂����x�ȑ̗͂ł͂Ȃ��Ƃł��܂���B
 efunon
efunon  2018/08/06(Mon) 15:48 No.1305
2018/08/06(Mon) 15:48 No.1305
���オ�V�����A���a��91.5mm��������57.5mm�A�d��485g�Ƃ��̃X�y�b�N�ɂ��Ă͔��ɃR���p�N�g�B�W��105/2.4���Z���y���B
�����Ƀe�X�g���Ă��Ȃ����J������l���܂ő�ϐ�s�ȕ`�ʗ́B�t���Ŏg�������������L�p�����ɁA���Ȃ�t���A���o�ɂ����w�i�ɓV����������Ă��R���g���X�g�������B�M�����Ďg���Ă���B
Pentax67, smc45/4, f11, 1/125, Fuji RDPIII
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/08/09(Thu) 21:15 No.1308
2018/08/09(Thu) 21:15 No.1308
�@���̎���̒������t�̒��L�p�ɂ́A��͂�L����x�̌��E���L���āA����������߂Ă���l�ȂƂ��낪�L��܂����B
�@���A��������Ă���̂́A��͂�D�G�Ȑ��\�ɗ��t�����L�邩��ł��傤�ˁB
 efunon
efunon  2018/08/09(Thu) 22:50 No.1309
2018/08/09(Thu) 22:50 No.1309
�����͋ɂ߂ėD�G�ȑΏ̌^�L�p�����C�o���ɂ��˂Ȃ�܂���B
�c�ȂȂǂ͂͂Ȃ��瑊��ɂȂ�܂���B
���ʁA�ߐڎ��p�����b�N�X���Ȃ��œ_���킹���e�ՂŁA�S�[�X�g�t���A�̎��O�m�F���ł���ȂǁASLR�̗��_���\������܂��B
��������ƁA�̗��s�ł͕W���]����SLR�A���L�p��Ώ̌^�Ŏ��Q���Ă����������������ł��B
���ɂ̏���������Ƃǂ����Ă��Ώ̌^�ɂ͕������Ⴄ��ł��B�i�y���^�b�N�X67�L�p�͂܂��Ώ̌^�ƃK�`��r�͖����{�ł����j
�ł��ŋ߂́A������҂茇�_�ɖڂ��Ԃ�A���\�g�����Ȃ��H�ƍl�����ς���Ă��܂��B
�y���^�b�N�X45mm�́A���̒��ł����_���ڗ����Ȃ��悢�����Y�̂悤�Ɏv���܂����B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/08/09(Thu) 23:48 No.1311
2018/08/09(Thu) 23:48 No.1311
�t�@�C���_�[�}�X�N�����Ă����̂Ńt�@�C���_�[�����Ȃ���B�e�ł��܂��B
���_�����߂��͂ł��܂���̂Ń_�[�N�o�b�N�ɃJ���������ăt�B���������o���Ċ����߂��K�v������܂��B
�ʐ^�̓y���^�b�N�X�U�V�ɃA���T�b�g�R�O�������R�D�T�ŎB�e�������{��B
�t�B�����̓v���r�A�P�O�O�ł��B
�[�̍��������̓A���T�b�g�̃t�[�h���ʂ��Ă܂��B
�y���^�U�V�̃x���[�Y�{�X���C�h�R�s�A�Ƀf�W�J���ŕ��ʂ��Ă܂��B
 ken
ken  2018/08/14(Tue) 13:42 No.1316
2018/08/14(Tue) 13:42 No.1316
135�̃p�m���}�̓V�l�X�R�̉�ʂ����Ă���l�ŁA���Ɋ������܂��B
�����̃A�_�v�^�[���L�����̂ł��H�@�����܂���ł����B
 efunon
efunon  2018/08/14(Tue) 20:56 No.1317
2018/08/14(Tue) 20:56 No.1317
���������Ǝv���܂��B
�ʐ^�̂悤�ȍ\���ł��B
�t�@�C���_�[�����ł͖����{�̗p�ɂ��}�X�N����܂������ǂ����Ɉ��������Ďg�����Ő������������O��ăV���b�^�[����ꂽ��|���̂ł�����͎g���Ă܂���B
�ł��̂łR�T�����t�B�����̑��茊���ʂ��Ă��܂��܂��B
�{�̗p�̃}�X�N��t������̕����͘I�����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă܂��B
 ken
ken  2018/08/14(Tue) 23:39 No.1318
2018/08/14(Tue) 23:39 No.1318
���Âōw�����܂������U�V�Ńt�B�����̕��ʂ͂��邱�Ƃ͂Ȃ��f�W�J���R�s�[��p�Ŏg���Ă܂��B
 ken
ken  2018/08/14(Tue) 23:44 No.1319
2018/08/14(Tue) 23:44 No.1319
1980�N������P67��t�WGW690��35mm��ɃR�_�N���[�������ăp�m���}�B�e����鎩��@���J�������r���[�Ɍf�ڂ���Ă��܂������A�������ʎY�����̂ł����B
������Ɨ~�����Ȃ�܂����B
�����A�p�[�`���[�}�X�N���t�B�����K�C�h�����˂ĕ��ʐ���ۂ悤�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����A������q����������ɕK�v�Ƃ����킯�ł��Ȃ��悤�ł��ˁB
���������R�ƃA���T�b�g35�����t���ɂȂ��Ă���̂��������ł��B
P67�p�x���[�Y�͍��l����ŁA�Ȃ��Ȃ�����o���Ă��܂���B
��ς������肵������ŁA�l�i�����R���Ǝv���܂��B
�ّ�ɂ̓L���t�B�b�g�̃x���[�Y�������������̂������āA�ł����������Y�̓x���[�Y�ɕt�������Ƃ�����܂���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/08/15(Wed) 12:37 No.1320
2018/08/15(Wed) 12:37 No.1320
67�t�H�[�}�b�g�ł̓}�~��RB, RZ�ƕ���ŋM�d�ȋ�����Y�B
�}�~����萏���R���p�N�g�ŁA�����o�����ɗL���B
���a102mm�@���@�O�㒷73mm�@�d��920g�@�ŒZ0.45m
������d�����A�O�㒷�͕W�������Y��菬�����B
������Y�œV��B�e�ɛƂ��Ă�����������C���傫�ȃt�H�[�}�b�g�̋����T���čs�������܂����B����͂ǂ̃��[�J�[�ł��D�G�ŁA1:1�ł��������r���Ȃ��ƗD���F���ł��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�܂�1�{�Ŏg���Ă������͕s�����łȂ��킯�ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/08/16(Thu) 22:58 No.1323
2018/08/16(Thu) 22:58 No.1323
�y���^�b�N�X67�p300mm�́ASMC�^�N�}�[300mmf4�A�ӏ���ύX����SMC�y���^�b�N�X67�@300mmf4�ɑ����āCPentax 67II����ɓ��œ_(IF)���AED�����Y�g�p�̏�L�����Y���������ꂽ�B
�T�C�Y�d�ʂ͔�ED��93x186mm�A1425g����AED93x210�A1650g�ɑ�^���������A�O�r���̏d�ʕ����Ǝv���B
�ŒZ�B�e�����͑S�̌J��o��5m����IF�̌��ʂ�2m�܂ŒZ�k���ꂽ�B
�F�����̒ጸ�ɗL�������A�J���[�t�B�����łȂ��Ǝ������ɂ�����������Ȃ��B�܂����^������Ȃ�ɒᕪ�U�K���X���g�p����A�S������ł��Ȃ��B
��ED�V���[�Y�͂��̏��400mm�ŋ��ɑ�^������̂ŁA�莝���\�ȃ��C���Ƃ��Ă͂����܂ł��Ǝv���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2020/02/23(Sun) 18:59 No.1664
2020/02/23(Sun) 18:59 No.1664
�j�R��F�E�u���j�JS2�]���p�t�H�[�J�V���O���j�b�g���������ꂽ���̂͊F�l�悭��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����́A�t�H�[�J���v���[���u���j�J������D,S�^�O�ܖ]���A�j�b�R�[��18cmf2.5���y���^�b�N�X67�}�E���g�ɉ������ꂽ���̂ł��B
�����͕s�t�ŁA���j�I���l�͑��Ȃ��Ă���̂ŃI���W�i����萏�������ɕ]������Ă��܂����B�i�܂��I���W�i���͖ő��ɏo�Ȃ��̂ŁA����Ȃǂ͑��݂��Ȃ��̂ł����j�ł���̓u���j�JS�Ŏg�����������ł����A���傫�ȃt�H�[�}�b�g�Ŋy���߂�͈̂�������܂���B
�Y��ȉ����Ƃ͂������A�y���^�b�N�X67�p���o�[�X�A�_�v�^�[�𗘗p�������̂ŁA���x�͂���Ȃ�Ɗ������A�C�����Ĉ����܂����A�^�N�}�[150/2.8��y���^�b�N�X165/2.8�ȂǂƔ�ׂđ�Ϗd�ʂ�����̂ŁA�U��悤�Ȑ^���͂ł��܂���B
�掿��6x7���\���ɃJ�o�[���l���܂ŗǍD�ł��B���̂�����̏œ_�����́A���₷���̂��N���V�b�N�����Y�Ƃ����Ă��D�G�ł��ˁB
�Ƃт���d���̂œ����̕��͍��f���ꂽ��������܂���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2021/09/05(Sun) 13:40 No.1903
2021/09/05(Sun) 13:40 No.1903
��i�Ƃ��Ă͂ǂ����Ǝv���܂����O��{�P�̋���킩��₷���̂ł�����������܂��B
�[���l������A�D�G��165/2.8��\�t�g�Ŗʔ���150/2.8�������œ���e�ՂȂ̂ł�����A�d���j�b�R�[�����g�킸�Ƃ��悢�̂ł����D�D�D
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2021/09/05(Sun) 14:37 No.1904
2021/09/05(Sun) 14:37 No.1904
35mm�J������50mmf1.4�ɑ������������Ƃ����܂��B
����Super Takumar�͍����܃g���E���O���X���g��ꌻ�݂ł͉��ς��Ă��܂����ASMC Takumar�����肩��z�b�g�O���X�͎g��ꂸ�J���[�o�����X�͗ǍD�ł��B
Takumar����SMC PENTAX�O���܂Ń��^���t�H�[�J�V���O�����O�ŁA�ŏI�^�̓r�j���n�u���b�N�p�^�[���̃t�H�[�J�V���O�����O�ɂȂ�܂����B
���\�͔��ɍ����A�J���͑����n��������܂����A�t�H�[�}�b�g���傫�����Ƃ�����A�\���ɗǍD�A�����i�邾���ŃR���g���X�g���オ��A�����ȉ掿�B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/11/03(Sun) 23:58 No.2632
2024/11/03(Sun) 23:58 No.2632
105mm������߂Ɗ�������Ȃ�90�͗ǂ��I���B
Super-multi-corted TAKUMAR 6x7 ����́A�����Y�V���b�^�[�����Ă����B
SMC-PENTAX 6x7�ɂȂ��Ă��烌���Y�V���b�^�[�ł͂Ȃ����ʂ̃����Y�ɂȂ����B
�t�����N�Z�m�^�[�{�㕔1����5�Q6���Ƃ�������ȍ\���B
���̂�PENTAX���������^���t�H�[�J�V���O�����O�̒������̂̂悤�ŁA�摜�����ł̓u���b�N�p�^�[�������o�Ă��Ȃ��B
6x7�p�����Y�Ƃ��Ă͍ł����邢���̂̈�ŁA�Â������ł͋M�d�ȋ@�ށB
���Ɍu�̎B�e�ł͔�r�I�L����p���d�܂����B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/11/04(Mon) 00:24 No.2633
2024/11/04(Mon) 00:24 No.2633
�y���^�b�N�X645N
�R���^�b�N�X645AF
�u���j�JETRSi
�}�~��M645�v��TL
���W�������̂ŁA���ʂ��郌���Y���r�ׂĂ݂܂��B
��������≖�t�B�����ŏI�^������ɋ߂��A�~�n�����@�\�������Ă��܂��B
�����g��Ȃ��|�W�t�B�����A�v���r�AIII�����A�I�o��œ_���x�͎��s���悤���Ȃ��قLj��肵�Ă��邱�Ƃ��m�F���܂����B
���̕ӂ̋@�����p����Ȃ�A�|�W�������Ȃ��Ɖ��߂Ďv���܂��B
�܂�120mm�N���X�̃}�N�������Y���r���܂��B
��ʑ̂����߂�6�����ɓ��ꂽ�t�B�������悤�₭11���ɎB��I���A������ɂȂ�܂����B
�T�ˎO�r�ɌŒ�A�A���J�X�C�X�݊��N�C�b�N�V���[�͑�ϕ֗��ł��B���A�}�N�����ƃJ�����ꕔ��������܂ł̋������Ⴄ�Ɛ����Y���������A�G���x�[�^�[�Œ������Ă��܂��������̃p�����b�N�X�͂��������������B
�܂��y���^�b�N�X645N�A�y���^�b�N�XA�}�N��120/4�J��
�ꎞ���͕W���Z�b�g��10���]�T�Ő邭�炢�ł����̂ɁB
�y���^�b�N�X�]�������͏����I�[�o�[�ڂɘI������悤�ł������肵���F���ł����A�R���^�b�N�X�͊��ɂ����Ă�n�̌X��������܂��B
�A�|�}�N���v���i�[120mm�͍ŏ�����AF�������MF�ł��B
Contax645AF�@Macro-Planar120/4
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2015/11/23(Mon) 12:34 No.72
2015/11/23(Mon) 12:34 No.72
���f�������ɂ̓y���^�b�N�X�Ɏ����ŃY�[�������Y���[�����Ă��܂����B
�}�N���[���U�m��105mmf4.5�̓^���������u���j�J��������ɔ������ꂽ���{�}�N���ł��B
35mm�ōD�]�ȃ^������90mm�̗�������ނƊ��҂���郌���Y�ł��B
���Ђ̓��{120mm�Ɗr��Z�œ_�ł��薳�����̉�p�͓��R�L���̂ł����A�ߐڎ��̓t���[�e�B���O�������ČJ��o���ʂ����Ȃ��R���p�N�g�Ȕ��ʁA�J��o���ɔ����œ_����������ɒZ�k���Ă��܂��܂��B
�������Y�Ɣ{�������킹��Ɣw�i�����傫������܂��B
Bronica ETRSi, Macro Zenzanon 105/4.5
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2015/11/23(Mon) 12:43 No.73
2015/11/23(Mon) 12:43 No.73
���̓t���b�V���ڎʍD���Ȃ̂ł킴�킴TL���f�������߂܂������A��ʂɂ͂ǂ�M645�ł��卷�Ȃ��B�e�o����ł��傤�B
�g�т̂��߂ɃE�G�X�g���x����t���Ă��܂��B���̏�Ԃł͌y�ʃ����Y�ɂ��������Ĕ��Q�Ɍy���ł��B
����̓y���^�b�N�X�A�u���j�J�͎��OAE�A�}�~���̓R���^�b�N�X�̘I���l�ɍ��킹�܂����B
�����}�N���Ń|�W�I������Ȃ�}�~����AE�t�@�C���_�[���~�����Ȃ邩������܂���B
Mamiya M645proTL, Sekor Macro 120/4
���ɂ���R�̔�ʑ̂Ŕ�r���܂����B�摜�Y�t���P���X��1���Ȃ̂ōT���Ă��܂����D�D
����������̃����Y����ς��炵���A�ǂ�������o���Ă��[���ȏ�ɖ����ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2015/11/23(Mon) 12:54 No.74
2015/11/23(Mon) 12:54 No.74
�@���͂��̒��Ń}�~���ƃy���^�b�N�X��120mm�������Ă��܂��B
�ߋ��ɃA�_�v�^�[�����K-01�ɑ������Ă݂������L��܂��̂ŁA���̎��̉摜�ł��i�i��͊J���ł��j�B
�@�}�~���̕�����R���g���X�g�������A�y���^�b�N�X�̕����k�P���ǂ������͂��܂����A�����ǂ���������l�Ȃ��̂ł��B
�@���炩�ɒ��S���̕`�ʂ�APS-C�Ŏg�p���Ă��]�T���������܂��B645���t�͐������ґȂƎv���܂��B
 efunon
efunon  2015/11/23(Mon) 21:50 No.78
2015/11/23(Mon) 21:50 No.78
�����炱����r�摜�����肪�Ƃ��������܂��B
�t�B�����J�����S�������i����Ȍ������Ȃ���j�ɏo�������}�j���A���t�H�[�J�X���{�}�N���́A�t�B�����p�Ƃ��Ă͋��ɂ̐��\�Ǝg������������Ă���@��ł��傤�B
����ł���̌��͌���邩������܂���ˁB
�����̍���f24x36�t�H�[�}�b�g�f�W�^���J�����ŎB�e����ƁA�ו��̉𑜗͂�645�𗽉킷����̂�����܂��B�����Y�ɂ���Ă�4x5�ɕC�G���郌�x����������܂���B
�������g�嗦���l�����645�̃g�[���Ɣ�ʊE�[�x�ɂ�鉓�ߊ��͎̂Ă��������ł��B
������͒����T�C�Y�̎B���f�q�Ɏ��ʂ��Ă����̂�������܂��A�t�B����������o���邤���͎g���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
���̃y���^�b�N�X�ƃ}�~���A�����ł��B�m���ɂ�����̍��ق͂킩��܂����A�ǂ������邩�ƌ�����ƁA���̍���\���ɉ��p�ł��邩�ł��ˁB
���ǖL�x�ȃY�[�������p���@���I�ȎB�e������T��}�N�����ƂȂ�ƃy���^�b�N�X�B
�y�ʂƖ��͓I�Ȗ]���Z�œ_���d������Ȃ�}�~���A
�}�~���Ƃ͕��������قȂ��p�œ_�����̌��t�ɂ��Â炢�`�ʐ��Ȃ�R���^�b�N�X�A
���^�y�ʂŃ����Y�V���b�^�[�̗��_�ƃ^�������Y�[����I�ԂȂ�u���j�J�Ƃ����C���[�W�ő����Ă��܂��B
�ܘ_�ǂ̃V�X�e�������\���������̂ŁA���̃V�X�e���ł͎B�e�o���āA����ł͏o���Ȃ��Ƃ����̈�͂قƂ�ǂȂ��Ǝv���܂����D�D�D
�n�b�Z��H/�t�WGX�͂��܂�ɋ��������Ȃ��A�܂������o��������܂���B�ǂ��݂����ł����ǂ��D�D�D
����ɃL�G�t645�́A�ڌ����܂����������E�C������܂���ł����D�D�D
Contax645, Distagon 35/3.5, �J���CPro400-220
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2015/11/24(Tue) 17:23 No.79
2015/11/24(Tue) 17:23 No.79
����܂ł̃Y�[���͒������[�U�[�ɂƂ��āA�ǂ����Ă��Ϗœ_�������K�v�ȏꍇ�ɉ掿���䖝���Ďg�����̂ł������A��L��2�{�͉掿�I�ɒP�œ_�ɕC�G���A���i�I�ɂ��肪�͂����x���ő傫�ȓ]���_�������Ǝv���܂��B
���̌セ��ɒǏ]����悤�ɃR���^�b�N�X645�ƃu���j�JETRS�p��45-90mm����������܂����B
�t�B���������ŏI���ɏo�����������ɁA��������j�]���Ȃ����\�ƁA���I�ł͂Ȃ��T�C�Y�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B
���ʂ����摜���Љ�܂��B
�܂��̓y���^�b�N�X645�pFA45-85mmf4.5�@�J���i��AE�CRVP100
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2015/12/02(Wed) 21:15 No.87
2015/12/02(Wed) 21:15 No.87
f�l�ω������e���������ɏ��^�y�ʉ������������Y�B�Ƃ����Ă��O�ʂ�95mm�B
�̂�グ��3�{�͂�������ŒZ�B�e����0.5m��35mm�p�Y�[���Ɠ����̎g������������A����p�r�Ƃ������ėp�t�����ςȂ��ł��g���郌�x���Ɏd�オ���Ă��܂��B
3�{������Ɓi�����������͈͓��ł��̂Ō̍��͔ے肵�܂���j
�y���^�b�N�X�͍ł����^�y�ʂŎ��p�I�A�𑜗͂̓o���I�]�i�[�Ɏ����A�t���ɂ͍ł��ア�B
�R���^�b�N�X�͍ł��傫���d��������B�𑜗́A�t���ϐ��͍ł��D�G�B
�u���j�J�͉𑜗͈͂�ԉ��i����ł��D�G���ψ�Ȃ̂Ŗ��͂Ȃ��j�����t���ϐ��̓o���I�]�i�[�Ƌ͍��ŋ����B
�c�O�Ȃ���}�j���A���t�H�[�J�X�}�~��645�ɂ͓����̃Y�[���͗p�ӂ���Ă��Ȃ��̂Œ��܂���ł����B
645�t�H�[�}�b�g�͒����̂Ȃ��ōł��������A�g���~���O�ւ̗]�T������܂���B
���̂��߃Y�[����66��67�����L�����ƍl�����܂��B
�Y�[���䂩����A35mm�p�̂悤�ȍ��{�����\�����Y�ł͂Ȃ��A�g���~���O�̑���ɍ\�}�����������ړI�ŗp��������̂ł��傤�B
�y���^�b�N�X��33mm�`300mm�܂ŃY�[���ŃJ�o�[�ł��A�掿�ɂ���]������܂��B
FA45-85��80-160�́A�f�W�^��645Z�ł��J�^���O�摜�Ɏg���l���܂őf���炵���掿�������Ă��܂��B�������33�̕]���͍��ЂƂ̂悤�ł����D�D�D
ETR��Contax�p�̃f�W�^���o�b�N�܂��̓A�_�v�^������悤�ł�����A�t�B���������łȂ��܂��܂��g����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2015/12/02(Wed) 21:36 No.89
2015/12/02(Wed) 21:36 No.89
�E�y���^�b�N�X�̓z�e���̕������N�b�L�����Ă��܂��ˁB�S�̂��ώ��Ȋ��������܂��B
�E�o���I�]�i�[�͑S�̂�����ƃz�e���̗��̊����ǂ������ł��B������Z�x���Z���̂Œ��܂��Č�����̂����m��܂���B
�E�u���j�J�͎���̐F�����̉e���ł��傤���H�P�_�̐��Ƀu���[�̃n���[���o�Ă���̂��������Ă���̂����m��܂���B�ł��z���b�Ƃ��������̓N���X�}�X�ۂ������ł��B
 efunon
efunon  2015/12/03(Thu) 21:04 No.92
2015/12/03(Thu) 21:04 No.92
���������33�̕]���͍��ЂƂ̂悤�ł����D�D�D
�y���^�b�N�X�̂R�R�|�T�T�������S�D�T�������Ă܂��B
flickr�ɂU�S�T�c���g���ĎB�e�����ʐ^���グ���Ƃ���O���̕�����M���̃����Y�̓y���^�b�N�X�łȂɂ����������̂ł����ƕ�����܂����B
������O�ꂪ����̂�������܂���B
�U�S�T�m�Q�ɂR�R�|�T�T�������S�D�T�ŎB�e�����ʐ^�ł��B
�x���r�A�T�O�ł��B
 ken
ken  2015/12/08(Tue) 12:52 No.104
2015/12/08(Tue) 12:52 No.104
 ken
ken  2015/12/08(Tue) 12:53 No.105
2015/12/08(Tue) 12:53 No.105
33-55�ɂ��Ă͎��͑S���o���������A�`���݂̂ŕ]�������̂͋��k�ł��B
���J�������J�����̃e�X�g���|�[�g�̎���ł��B
���������肪�Ƃ��������܂��B
33-55�̓t�B����645�p�ōŒZ�œ_�Ȃ̂ŁA�ꎞ�����[���l�����ċ��܂������A���̋L����ǂ�Ŏv���Ƃǂ܂��Ă��܂������̂ł��B
���������ۂɂ̓f�W�^���ł��ǍD�Ȍ��ʂ���̂ł��ˁB����͋��낵�����Ƃ��Ă��܂��܂����B�܂��T���͂߂Ɂi��
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2015/12/08(Tue) 22:20 No.106
2015/12/08(Tue) 22:20 No.106
�s�N�Z�����{���ƒZ��2m�߂��ɋy�т܂��̂Ŕ��I�ȏ��������Ă��܂��܂��B
�L�p���́A33mm�J���Œ��S���璼�a�Scm�͈͔̔͂��ɐ��ׂł����Tcm�̊O�͗���C���œ��Ɏl��2-3mm�͌����ł��B����60cm���x�̊g�嗦�ł́A�Ȃ�ƂȂ��Â����ȂƂ������x�ł��B
f8�Cf16�ƍi��ɏ]���Â��͉��P���A�����獂���R���g���X�g������Ɉ������܂�܂��B�l���̗���͊��S�ɂ͏����܂���B
40mm�A45mm�Ɖ�p�����߂�Ǝl���̉掿�ቺ�͌����Ă����A45mm�ł�FA45-85mm��45mm�ʒu���ނ��됮�������ł��B
50-55mm��͊J�����炩�Ȃ�ǍD�ŁA�����l���ȊO�͓��ɒ�����t����قǂł͂Ȃ��A������FA45-85��55mm�ʒu���Ǒ��ł��B
�G���̃e�X�g���|�[�g�Ɠ��l�ɁA�L�p���ӕ��͍i��Ȃ��ƊÂ�����������܂����A645D�ł͂����͎g���܂��A�t�B�����ł������I�Ȋg�嗦�F��S�����x�G�Ȃ�w�ǖ��ɂȂ�Ȃ���������܂���B
��ω�p���L���̂ŁA�����ɐ����ăg���~���O���邱�ƂŃV�t�g�����Y�̂悤�Ɏg�������\�ł����A���̍ۂ͒[���g�傳���̂ŁA�i�荞�܂��ɑ�g�傷��̂͒��ӂ��K�v�ł��B���ʂ͎O�r�𗧂ĂĐ�������g���i�荞�ނł��傤���炱������͏��Ȃ��ł��傤�B
�L�p���ȊO�͔�̑ł��������Ȃ��A����45-85mm��荂���\�ŏ�p�����Y�Ƃ��ēK���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�y�����B
�摜���33mm�J���X�e�b�`�摜�̏㔼�����k���B�J���ł̃r�l�b�e�B���O�͂��̒��x�B�i�������͌l���ɂȂ肻���Ȃ̂ŃJ�b�g�j
�摜���͏�L�摜�̉E�[�̈ꕔ���o������ł��傫������̂ŏk���B�[�̗���͊m���ɂ���B�i��Ə������P���邪f16�ł����킴�킵����_�������ۂ�����͎c��B���S�͊J������f���炵���B��p�����߂Ă����Ɨ��ꕔ���͌����Ă����B
���ł��v��������g���~���O�O�ł͍���2m��2.7m���炢�̔��I�g�嗦�Ȃ̂ŁA�t�B�����ł͕ǖʓ��e���Ȃ����茰�݉����Ȃ��Ǝv����B
645��33mm�Ƃ����L�p�͑��ɗႪ������r�ł��Ȃ����A�Z�R�[��35/3.5���J���ł͒[���Â��̂ŁA�W���I�Ȃ̂�������Ȃ��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/03/22(Thu) 17:26 No.1189
2018/03/22(Thu) 17:26 No.1189
���͂悤�������܂��B
�y���^�b�N�X�ɂ̓f�B�X�R���ɂȂ��Ă��܂����Âł�����ɓ���Ȃ��Ȃ�܂������c�e�`�Q�T�������S������t�B�����U�S�T�ł��g���܂��B
���Зǂ����̂�����Ύ�ɓ���Ă��������B
�U�S�T�m�Q�ɂc�e�`�Q�T�������S�ŎB�e�����ʐ^�ł��B
����U�S�T�ȊO�i��͂��炦�܂����ʂɎg���܂��B
�x���r�A�T�O�ł��B
 ken
ken  2018/04/02(Mon) 07:53 No.1201
2018/04/02(Mon) 07:53 No.1201
���킠�A�َ����̉𑜂ł��ˁD�D�D
�R�����Ă�l���F�E�����Ȃ�������Ȃ��D�D�D
�f�W�^���p�ɏo�������Y�͂ǂ�������̐��\����Ȃ��ł��傤���B
���[��A�Ƃ��Ă��܂��ƕ|���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2018/04/02(Mon) 21:56 No.1203
2018/04/02(Mon) 21:56 No.1203
���C�J���B�]�t���b�N�X�̓t�����W�o�b�N�������A����ɃC���[�W�T�[�N�����傫�ȃ����Y���������߁A�t�����W�o�b�N���Z�������J�����Ŗ��������邢�͎��p�I�ȗL����������œ_���������Ƃ��ȑO����m���Ă��܂����B
���B�]�t���b�N�X1�͓��Ƀt�����W�o�b�N�������n�b�Z���u���b�h��y���^�b�N�X67�A�_�v�^�Ƀw�N�g�[��135��e���[�g200�������ł���A�_�v�^������܂��B
���B�]�t���b�N�X2�C3�͂�����t�����W�o�b�N���Z��������܂���
�Ⴆ�}�~��M645�Ƀ��B�]2�C3�p�̃Y�~�N����90mm��A�G���}�[65mm����������g�p�ł��邱�Ƃ��Љ��Ă��܂��B
����y���^�b�N�X645�ɓK�������}�E���g���g�p���邱�Ƃ��ł��܂����B
�y���^�b�N�X645�̓}�~��M645����t�����W�o�b�N�������A�����������Ȃ��Ɩ����͂ł܂���B���C�c�̃V���[�g�w���R�C�h���l�߂Ă���܂��B�X�g���[�N��RF�p�Ɠ����ł�����A�ŒZ��1m�ɂȂ�A���t�̗��_�ł���ߐڂ���������A�������邢�̓y���^�b�N�X�̒��ԃ����O�p����K�v������܂��B
����͏�����M�^�p�Y�~�N����90mmf2�ŁA���B�]2�܂��̓��C�J�t���b�N�X�Ŏg�p���Ă����w�b�h�𗬗p�������̂ł��B�����X�N�����[�}�E���g�̃G���}���[�gM135mmf2.8�̃w�b�h���g�p�\�ł��B
���ẮA�����̃����Y��645�Ŏg�����Ƃɉ��^�I�ł������A���������Ƃɖ���������A�R���Ȃ��A�l���܂Ŋ����ɉ𑜂��A�܂��r�l�b�e�B���O���قƂ�ǔF�߂܂���B
�Ȃ�Ƃ������ʂȃC���[�W�T�[�N���������Ă���̂ł��傤�B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2022/03/12(Sat) 22:07 No.1969
2022/03/12(Sat) 22:07 No.1969
�y���^�b�N�X645N�A�Y�~�N����90mmf2�A����AAE�A���ԃ����O2�A�C���t�H�[�h�p��F
���������Y�ł������\���͂ł��邩������܂��A���͓I�ȏœ_�ʂƃA�E�g�t�H�[�J�X�`�ʂ��Ǝv���܂��B
�J���[����낵���ł����A�����t�H�[�}�b�g�̃��m�N���t�B�������g����̂͑�ϊy�����B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2022/03/12(Sat) 22:14 No.1970
2022/03/12(Sat) 22:14 No.1970
�����^�Y�~�N����90/2�w�b�h�Ɠ����X�N�����[�}�E���g�ŁA�y���^�b�N�X645�A�_�v�^�[�ɑ����\�B
645�t�H�[�}�b�g���\���ɃJ�o�[����C���[�W�T�[�N��������B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2022/03/17(Thu) 21:06 No.1973
2022/03/17(Thu) 21:06 No.1973
�]���@�͕��s�ړ��ŕ����B�e����̂ɑ��AVertex�͕ΐS�f�B�X�N�Ƀ~���[���X�@�����A90�x����]����4���B�e���܂��B�c�����݂���4���̉摜���ł���\�t�g���K�v�ł����A��ό����I�ŁA�]���@�Ɣ�r�����I�ɏ��^�y�ʉ�����Ă��܂��B
���̔��ʁA�v���r���[�̂��߂̃t�H�[�J�V���O�X�N���[�����ȗ����ꂽ���߁A���̃f�o�C�X�����ł̓t���[�~���O���ł��܂���B
�ǂ̂悤�ȎB�e�͈͂ɂȂ�̂��܂������킩��Ȃ��̂ŁA���炩�̎�i���K�v�ł��ˁB������ǂ����邩�͍���̉ۑ�ł��B
������̃X���b�h�ł͂���ɂ��Č@�艺��������A�B�e���ʂɂ��Đ������܂��B
�����Y���̃}�E���g�́A6x6�@�ł���n�b�Z���u���b�hV�ɉ����y���^�b�N�X67�i�t�WGFX�ŎB�e�ł���j���p�ӂ���Ă��܂����A������������邱�ƂɁA�}�~��645�A�y���^645�A�n�b�Z��H�A�u���j�JETR�Ȃǂ�645�@�}�E���g���L�x�ł��B�܂�EOS��j�R��F�Ȃǂ�35mm�����Y���A�t�W��L���m��M, �\�j�[��APS-C�ŕ������鐻�i������܂��B
M645��P645�̃����Y�ʼnʂ�����6x6���J�o�[�ł���̂ł��傤���H
�܂��A�ǂ�����n�b�Z��V�A�_�v�^������܂�����A�����ƂȂ�Εϊ���������ł��ˁB
����͖`�����āA�D�G�ȃY�[���������Ă���y���^645�̃}�E���g�𒍕����܂����B
���_�������A33-55�C45-85�C80-160�C150-300�̃Y�[���ƁA75/2.8�A120/4�A200/4�ɂ��ẮA���p��6x6�����S�ɃJ�o�[���Ă���ƌ��킴��܂���B
�S��ʂ��炵�����𑜗͂ł��B
�~�������A�g�傷��ƁA33-55��150-300�̊J���掿�Ŏ��ӂ͒��S�Ɣ�ׂė��Ă��܂����A�����i�荞�߂Ή������܂��B���̋@�ނ̎g�����Ƃ��Ă͎O�r�Œ�ōi��̂����ʂł��傤������Ȃ��Ǝv���܂��D
�摜�͌��\�j�[��7R, 4������9500x9500�s�N�Z���i9000����f�j���k���D�y���^�b�N�XFA�Y�[��33-55mm�A33mm�J���D�r�l�e�B���O�͑�������܂����A�i��قƂ�NjC�ɂȂ�܂���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2023/02/26(Sun) 23:53 No.2186
2023/02/26(Sun) 23:53 No.2186
������Viso1�̃t�����W�o�b�N��91.1mm����iViso2��68.8mm�j�A������ׂ��A�_�v�^�[�����߂Β����J�����ł����������瑕���ł���B�悭�g���Ă���̂̓}�~��M645�i64.0�j�����A���̓x�y���^�b�N�X645�i70.87�j�p������ł����̂ŁA���炭�g������ł���B�C���[�W�T�[�N�������Ή��ł���A�y���^�b�N�X67�i84.0�j�ł��Ή��ł��邾�낤�B
24x35�p�����Y�ł��邪�A�J������645�S�ʂ��J�o�[���掿���D�G�BRF����̐��i�̂��߁A�ŒZ�B�e�����������A�ߐڗp�ɒ��ԃ����O��������Ă���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/09/14(Sat) 22:07 No.2599
2024/09/14(Sat) 22:07 No.2599
�t�W�t�B�����@GF670
�`�� 6x7cm�@�X�v�����O�J�����A6x6cm�ɐ�ւ��\
��� �t�W�t�B����
���� 2009�N4��-2017�N12���A�N���[���ƒx��Ĕ����̃u���b�N������B�C�OVoigdlander�u�����h�͍��̂݁B
�����Y EBC Fujinon 80mm f3.5 �i4�Q6���j
�V���b�^�[ AE, 1/500-1, B�C�d�q����A�i�J���Cf4�܂ōō���1�^250�Df5.6〜1/500�j
�t�B���� 120�C220�C�X�^�[�g�}�[�N���@�E��R�͕��m�u�����グ
��Ꭾ�����v�A���t�@�C���_�[�B�p�����b�N�X������̌����u���C�g�t���[���A�ŒZ�B�e����0.9m
�d�ʁF1kg
�����F
�P�C�t�H�[���f�B���O�ŃR���p�N�g�ɂȂ�B
�Q�C�Z�~�I�[�g�}�b�g�A�Z���t�R�b�L���O�A�i��D��AE�A�����v�A���ƁA����̎g������B
�R�C�ɂ߂č����\�̃t�W�m��80mm3.5�A�֕��̌��ʂ�����t���ɋ����B
�S�D���C�JM�ɕC�G����RF�������w�̍����x�t�@�C���_�[�B
�Z���F
�P�C67�X�v�����O�ɂ��Ă͎�啿�B
�Q�C�d��CR2x1�́A���Y�̏\���ɓd�����c���Ă�����̂łȂ��Ɠ��삵�Ȃ��B
�R�C���o�[�ł͂Ȃ��m�u�����グ�Ȃ̂�6x7�������̂ɉ�]�ʂ��������ʐ����Ȃ��B
�S�C�V���b�^�[�����ɂ߂ď������̂͂悢�������̒��ŃV���b�^�[���ꂽ���ǂ����킩��Ȃ��B
�T�Cf2.8�͂ق��������B
�R�V�i�Ƌ����J���A�����炭�B��̍i��D��AE�֕��t�H�[���f�B���O�J�����i�V���b�^�[�D��AE�̓X�[�p�[�R�_�b�N620������j�B�t�@�C���_�[�̓x�b�TR�̐v�����ɂ��Ă���Ǝv����B����Ɖ��B�������i��Voigdlander Bessa 667�C�܂���Bessa III���ł���Ƃ���A�f�U�C���A����n�͉��N��Bessa II�̃I�}�[�W���F���Z���B
����Bessa II���x���g�|�[�`�ɓ���đ唻�̃T�u�Ɏ��Q���邪�AGF670�̓t�@�C���_�[�����ȕ��{�f�B�T�C�Y���傫���A�x���g�|�[�`�ɓ���Ȃ��B�t��Bessa II�͖{�̂ɃX�g���b�v���t�����Ȃ���GF�͏c�݂�X�g���b�v������̂ŒĂ����Ă������̂����B�����GF�͎������~�߃Z���t�R�b�L���O�AAE�i�V���b�^�[��������AF���b�N�j�ƑS���B�e�ɋC���g��Ȃ��̂ŁA���C���J�����Ƃ��Ă����łȂ��T�u�Ƃ��Ă��D�G�B�������t�H�[�}�b�g��6x9�ł͂Ȃ��̂ŁABessa II�̏o�Ԃ��Ȃ��Ȃ�킯�ł͂Ȃ��B
�d�r�͎��������A�d������������A������C�O��CR2�ł͍쓮���Ȃ���������̂ŁA��ɍ��Y�V�i�d�r��\���Ɍg�т��Ă����ׂ��B
�t�W�t�B������GA, GX�V���[�Y�ō̗p�������[�_�[�y�[�p�[��̃o�[�R�[�h�ɂ��ISO���x�ƃt�B����120�^220�����Z�b�g�@�\�͓��ڂ���Ă��Ȃ��͎̂c�O���B
GF670�ɂ͐ڎʃL�b�g�͗p�ӂ���Ȃ������B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/08/11(Sun) 09:18 No.2561
2024/08/11(Sun) 09:18 No.2561
�`�� 6x7cm�@�����Y�Œ�A6x6cm�ɐ�ւ��\
��� �t�W�t�B����
���� 2011�N9��-2015�N5���@�N���[���̂�
�����Y EBC Fujinon 55mm f4.5 �i8�Q10���j
�V���b�^�[ AE, 1/500-1, B�C�d�q����A�if�l�ɂ�鐧���Ȃ��j
�t�B���� 120�C220�C�X�^�[�g�}�[�N���@�E��R�͕��m�u�����グ
��Ꭾ�����v�A���t�@�C���_�[�B�p�����b�N�X������̌����u���C�g�t���[���A�ŒZ�B�e����0.7m
�d�ʁF1.1kg
�����F
�P�C6x7cm���̃��C�h�J�����Ƃ��Ă̓R���p�N�g�B
�Q�C�Z�~�I�[�g�}�b�g�A�Z���t�R�b�L���O�A�i��D��AE�A�����v�A���ƁA����̎g������B
�R�C�ɂ߂č����\�̃t�W�m��55mm4.5�B
�S�D���C�JM�ɕC�G����RF�������w�̍����x�t�@�C���_�[�B
�Z���F
�P�C�t�H�[���f�B���O�J�����ł͂Ȃ��Ȃ����B
�Q�C�d��CR2x1�́A���Y�̏\���ɓd�����c���Ă�����̂łȂ��Ɠ��삵�Ȃ��B
�R�C���o�[�ł͂Ȃ��m�u�����グ�Ȃ̂�6x7�������̂ɉ�]�ʂ��������ʐ����Ȃ��B
�S�C�����Y�Œ�ɂ���Ȃ�f3.5�͂ق��������B
�T�C�l�I�ɂ͂��������L�p�̂ق����D�݁B
GF670�ɒx��邱��2�N�œo�ꂵ�����C�h�J�����B�����Y�Œ�ɂȂ����B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/08/11(Sun) 09:19 No.2562
2024/08/11(Sun) 09:19 No.2562
�����Y�X�y�b�N�͏�L�̃��C�h�J�����Ƃ����ނˋ��ʂ��āA�J��f�l�����ɈÂ����邱�Ƃ͂Ȃ��B�l�I��90�N��-2000�N��ɂ����Ă͒ኴ�x�t�B�����ɂ�������Ă��āA�����܂�ƊJ��f�l���Â������Y�̓V���b�^�[���x���莝�����E��������āA�g�яd���̃t�B�[���h�J�����Ƃ��Ă͎g�����肪�����Ɗ����Ă������A�ŋ߂͍����x���m�N����̂Ȃ̂ŁA�v���悤�ɍi�荞�߂ăX�g���X�������Ȃ��B
�v�̐i���ŃX�y�b�N�͕ς��Ȃ��Ă��A���N�̗L�����L�p����t�����Y�Ɣ�ׂĒ��������^�ɂȂ��Ă��āA���ɓ�����̃}�~��7�̍L�p�n�Ɣ�ׂĂ����^�Ȃ͈̂�ۓI�����A�}�~��7�͌��������Y�Ȃ̂ŁA����قǏ��^���ɍS��Ȃ������̂�������Ȃ��B���\���ō��N���X�B ���ɉ��N�̒��L�p�͊J���t�߂Ŏ��ӌ��ʒቺ���傫���C�i�荞�ݑO��Ɗ����邪�A���̃t�W�m���͊J������\�����p�ł���B
�����v�A��0.7m�͈͊O�ɂ��J��o����悩�����Ǝv�����A���̕ӂ̓��[�J�[�̎p���ɂ�邾�낤�B
�f�W�^���������̎���Ő��Y���Ԃ��Z���A���܂�s��Ō������Ȃ��̂���Ԏc�O�B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/08/11(Sun) 09:20 No.2563
2024/08/11(Sun) 09:20 No.2563
��ύ����\�ł������A���J�j�J���J�����̂ق����g���Ă��Ċy�����i�ґ�ł��ˁj�̂ł��x���`�����߂邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂����B
GF670�ɂ��ẮA����6x7�t�H�[�}�b�g�͂��܂�D�݂ł͂Ȃ��A��ɂ��Ă����Ƃ���A�\�z�ʂ�A������Ǝ肪�͂��Ȃ����x���ɒl�オ�肵�A�w������Ă��܂������A2�N�O�m�l����I�t�@�[���A畏����Ȃ���펯�I���i�������̂Ŏ֕�GF670���������܂����B
��B�̊F�l����^�����ʂ�A�ʂ�ɂ��Ă͑S�����傪����܂���B���S���Ăǂ̌�����Ԃɂ��Ή��ł��܂��B
�ŋ߃��m�N�����ƌ�������̂ɂȂ�A�����̋@�킪���ӂƂ���J���[�ʐ^�Ƃ͂���Ă�C�����܂����A��R�A��o���Ă��܂��B�����xAE������A220���Ή��ł���̂ŁA�Ƃ̗Ⓚ�X�g�b�NRDP������Ă�������������܂���B
���N�ʂ̗F�l���炢������������o����ƕ����āA�������ł�肭��ł��鉿�i�ɂ��Ă����������}�L�i67���������Ȃǐߑ�������܂��A�����Ɉ͂܂�čK���ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/08/11(Sun) 09:37 No.2564
2024/08/11(Sun) 09:37 No.2564
�����̋@��A���������C�h���������őA�܂�������ł��B���b�ɂ��}�L�i6�~7���B
�����t�@���Ƃ��ẮA�Ƃ��߂����b�ł��B����A���闢�̂��X��GF670�̋ɏ�i�̔��������Ȃꂽ���i�ŏo�āA畏����Ă����Ƃ���A�����Ƃ����Ԃɔ���B�܂��������v���Ă��܂��B���B�ł����̂��������i�ł��ˁB
�x�b�T�U,�X�[�p�[�C�R���^6�~9�����[�_�[�T�m���Ă��܂�����������o���܂���B
�lj��̍����X���������炨�肢�������v���Ă��܂��B
�u���[�j�[�t�B�������Ă����ł��ˁB��낵�����肢�\���グ�܂��B
���̋@��́A�t�B�����@�Ƃ��Ă͍ł��㔭�̕��ނ����ɁA�����܂ł��Ȃ�����̂��悤���Ȃ����\�Ȃ݂̂͂Ȃ��܂����m�ł��B
���݂̒��É��i�������������I�Ȃ̂ŁA�������ɓ����̂̓n�[�h���������ł����A���ꂩ��l���ꂷ�邩������܂���̂ŋC���ɍ\���邵���Ȃ����Ǝv���܂��B
�����Ƃ��D�ꂽ�����́A��͂�g�ѐ��ł��傤�B2�䎝���Ă��e�q�j�J70���y�ʂŁA���s�Ɍg���Ă��ǂ��Ǝv���邭�炢�ł��B
�ŋ߂́A���m�N���[���t�B������ς߂邱�Ƃ������Ȃ�A�t�W���{�̂�����J���[�̉摜�͂킸���ŋ��k�ł��B
�ܕS�����D�t�W�t�B����GF670W, �t�W�J���[160NS, AE
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/08/31(Sat) 16:57 No.2585
2024/08/31(Sat) 16:57 No.2585
�����ɍ��������e�����������肪�Ƃ��������܂����B
����[�A�Q��܂��ˁB�y���ɂ�����AE�ŋC�y�ɎJ���Ă��̃N�I���e�B�B
�M����Ԃő{���s�����܂��ƁA�o����ނ͖̂ڂɌ����Ă��܂��̂�
�A�\�ʂ�A��Â�ۂ����܂��Ԃ������ĒT���Ă݂����ł��B
���肪�Ƃ��������܂����B
���̓x�C���M�����[�œ���o���܂����B�I�[�o�[�z�[���ς݂Ȃ̂ň��S���Ă܂����A�t�B������ʂ��܂Ńh�L�h�L�ł��B
�E�F�X�g���x���t�@�C���_�[���~�����Ǝv���Ă܂����A�o�����Ȃ��Ȃ������悤�ł��B
���[��������邩�H
�E�G�X�g�����F���Ɍ��������ۂ̓V���b�^�[�_�C�A���̃I�t�Z�b�g�p�[�c���M�d�Ȃ̂Łi�C�O�ł͍����ȃp�[�c�ł��ˁB�j�������Ȃ��l�����ӂ��������B
���A�Ԃ���ƃ_���[�W���傫���ƕ��������Ƃ��L��܂��B
����A�C���v�������肢�v���܂��B
�@
 efunon
efunon  2017/10/21(Sat) 10:57 No.992
2017/10/21(Sat) 10:57 No.992
�s���g���킹�̎��A���Ă̎R���݂͂ɂ�����ۂł��B�A���A�V��̉e�������邩���m��܂���i��j
�����2���グ�͊���Ȃ��ƁA�V���b�^�[���ꂸ�Q�Ă܂��B�u���[�j�[�Ȃ̂ł��͂����銴���ł��B
�V���b�^�[�V���b�N�͎キ�Ԃ�銴���͂��܂���ł����B
noritar 80mm�͍ŒZ��85cm�Ȃ̂ʼnԂ��B�鎞�́A���܂���B�ނ���X�i�b�v�B�e�����̃����Y���Ǝv���܂��B
�܂��A1�����ギ�炢�Ɏg�p���ȂǒNjL���܂��B
�v������肤�܂������܂����B�܂����g�Ȃ̂Ŕ��������K�v�ł��B
techart�Ɍq���ăI�[�g�t�H�[�J�X�����o���܂��B
�������ʒ��B
80mmf2�͂Ȃ��Ȃ������Ȃ��X�y�b�N�B6x6�ł͍��Y�ōł����邢1�{�ł��傤�B
���g���b�N66����̃��g����80mmf2���疼�̕ύX�ň����p���ꂽ���́B
���\�ɂ��ċ����ÁX�ȂƂ���ł��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2023/03/04(Sat) 15:45 No.2195
2023/03/04(Sat) 15:45 No.2195
�L���t�B�b�g�@�}�N���L���[�C�u���j�J�p�Ƃ�������ŁB
�������Ă݂�ƁA�L���t�B�b�g���Y�[�}�[�ł��������Ƃ͖��Ȃ��̂ł����A
�u���j�J�Ƃ͎��Ă������Ȃ��A�_�v�^���t���Ă��܂����B
���̂����������̂͂��ꂩ��25�N�キ�炢�B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2023/03/11(Sat) 23:08 No.2202
2023/03/11(Sat) 23:08 No.2202
RI ��Rittreck��RI�A���g���b�N66�p�}�E���g�ł��B�܂��Ƀm���^66�Ɏp���ꂽ���́B
�m���^66�ɑΉ����������Y���[�J�[�́A�L���t�B�b�g�����ł͂Ȃ��ł��傤���B
���ɒ����pWE�}�E���g�́C�n�b�Z���u���b�h1000F�A�y���^�R���V�b�N�X�������Ă��܂��B���������N��̐��i�Ȃ̂ł��ˁB
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2023/03/11(Sat) 23:10 No.2203
2023/03/11(Sat) 23:10 No.2203
���b�N�s�j�I���ƃw���R�C�h�p���A300mm�ɂ��ւ�炸�A1�F3����g�嗦��B�����Ă���B
�p���e���L���[300mm��1957�NM39��AN�}�E���g�Ŕ����A1971�N��Zoomar co.��Kilfitt��������̓X�N�����[�X�s�S�b�g��WE�}�E���g�ɓ��ꂳ��Ă���B
�܂�Kilfitt����͐Ԑ�3�ہi�A�|�N���}�[�g��H�j������Ă��邪�AZoomar����ɂ͏ȗ����ꂽ�B
��σV���[�v�ȗD���������Y�ŁA�M�����������B
�i��̓v���Z�b�g�B
���̌̂̓A���t���b�N�X�}�E���g�ŊC�O���o���B�g�����N��TV�ǂ̖��O�������Ă���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2023/03/15(Wed) 22:31 No.2204
2023/03/15(Wed) 22:31 No.2204
����͊e�БΉ��ɔ����A�����Y�V���b�^�[��������������Y����������܂����B
�m���^�͎�L�p�C����70mmf3.5�ɁA1/500-1/2�܂ł̃����Y�V���b�^�[��������܂����B
�ŒZ�����́C0.8m�B
���Ђ̓��N���X�Ɣ�ׂĂ��傫�����������Y�ł��B�L���b�v��77mm�p�̔킹�A�t�B���^�[��67mm�ł��B
����
�V���b�^�[�`���[�W�O�̓����Y�V���b�^�[�����Ă���̂Ńt�@�C���_�[����͐^���Âł��B
�V���b�^�[�`���[�W���o�[���ƁA�V���b�^�[���J���ăt�@�C���_�[�摜��������悤�ɂȂ�܂��B
�����Y�V���b�^�[���x�����߂܂��B
�{�f�B���V���b�^�[�͕K���o���u����B�\�Ȃ烌���[�Y�Ń��b�N�����ق��������ł��傤�B
�V���b�^�[�{�^���������Ă��班���Ԃ�u���ă����Y�V���b�^�[���쓮���邽�ߑ��ʐ��͂���܂���B
�����Y�V���b�^�[���쓮�����̂��m�F���ăo���u�V���b�^�[����܂��B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/06/06(Thu) 17:32 No.2539
2024/06/06(Thu) 17:32 No.2539
���̃Z�b�g�Ŕ̔����ꂽ�B
�m���^66�ɂ̓x���[�Y���Ȃ��̂ŁA���{���ڎʂɂ̓`���[�u���g�����ƂɂȂ�B
����55mm-160mm�܂Ńt�B���^�[�a62mm�̃N���[�Y�A�b�v�����Y���g�����Ƃ��ł���B
�`���[�u�͌X�ɃX�s�S�b�g�}�E���g�ƁA�����i��s��������āC�S���ڑ����Ă������i��͌y���ɍ쓮���A���ɉ��K�ɎB�e�ł���B
1968�[72�N������̃t�H�[�J���v���[��66�J�����ŃN���b�N���^�[���Ǝ����i��A����������G�N�X�e���V�����`���[�u�͑��݂����A77�N�n�b�Z���u���b�h2000FC���ǂ����A���Ќ㑱�͂Ȃ������i66�����Y�V���b�^�[SLR�͂���������B�j
�������ǂ�����ÓT�I�V�X�e���Ȃ̂ŁA�`���[�u�ɘI�o�v�A���@�\�͔�����Ă��Ȃ��B
80mmf2�W�������Y�ɒP�̂őg�ݍ��킹�����̎B�e�����͈ȉ��̒ʂ�B
�����Y�P�̂ł͍ŒZ����0.85m�̂Ƃ���A
No.1: 40-55cm
No.2: 32-35cm
No.3: 29cm
�S���ڑ�����ƁA80mm�Ŗ�1.5�{�܂Ŋg��ł��A���[�L���O�f�B�X�^���X��5cm�قǂɂȂ�B
�m���^�[��80mmf2��35mm�J�������Z50mmf1.2�ɕC�G�����ʊE�[�x�Ǝ�����Ȃ̂ŁA�ߐڂ���Ƌ��ʎ�������ϑ����Ă��܂��A�{�P�{�P�̉摜�ɂȂ�Ƒz������邩������Ȃ����A���̐��\���D�G�Ȃ̂ŏœ_���킹�ɋꗶ����قǂł͂Ȃ��A�i�荞�߂Ώ\���ɃV���[�v�ȉ摜��������B
�`���[�u�Ƀ{�f�B�L���b�v���t�����Ă���A�����J�����M39�ȂǑ��Ђ̋ߐڐv�����Y��A���o�[�X�}�E���g������ł��邩������Ȃ��ƈ�u�������A����̓m���^�ł��˂Ȃ�Ȃ����Ƃ͂Ȃ��u���j�JS��SL66�ōs���悢�B�M�d�ȏ����L���b�v����������̂͗ǂ����ƂɎv���Ȃ��B�m���^�̓m���^�����Y���y���ނ��߂Ɏ����Ă��鏃���Z�b�g�Ŏg�����Ǝv���B
 ��܂ɂ�
��܂ɂ�  2024/06/27(Thu) 14:24 No.2542
2024/06/27(Thu) 14:24 No.2542

 efunon
efunon