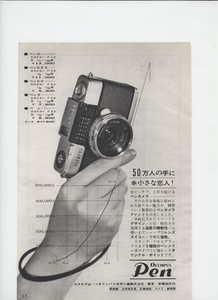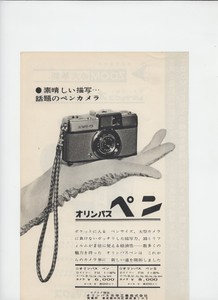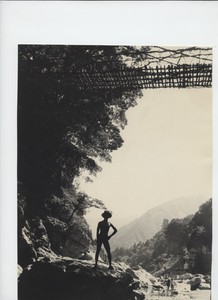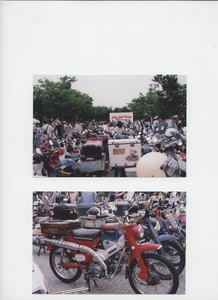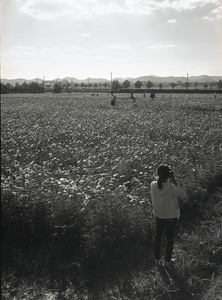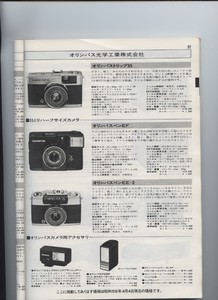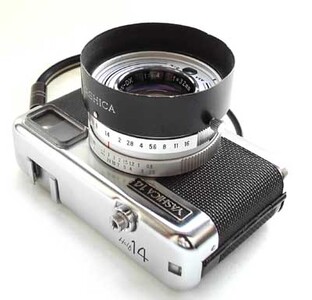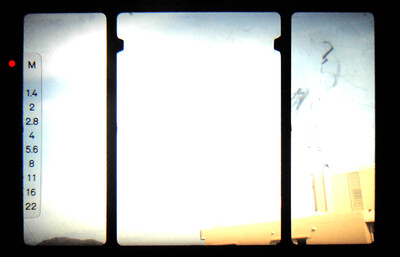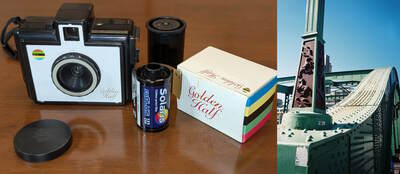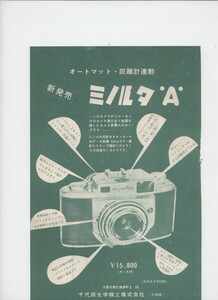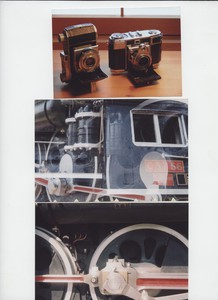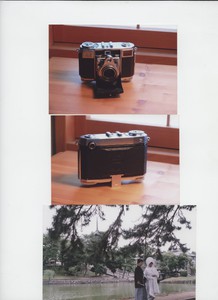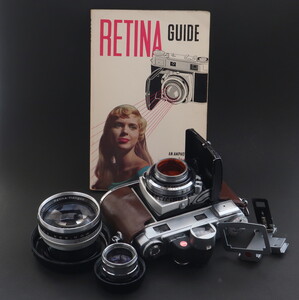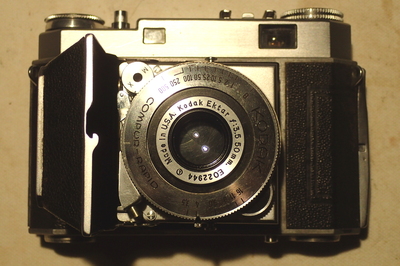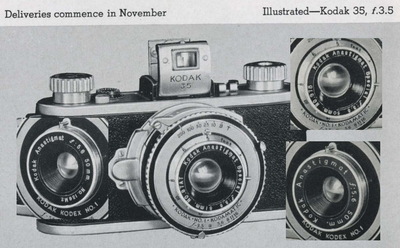多分、オリンパスペンに関しては、れんずまにあ様の方が詳しい。
先日、ホルガ関係の若者より、使いやすい銀塩カメラ?と相談を受けた。
デジはほぼスマホ。120ホルガは持っているが、フイルムが問題。
と言うことで、私、ハーフのペンを勧めた。
最終のEE3を勧めたのですが、同じこと考える人が多いのか、これ結構高い。程度の良いものは1万程する。
と言うことでジャンクを探す。EE2なら2160円程であった。
私が、小学生の頃、初めて買ってもらったのはペンS。モルトを張り替え整備、未だ使用可能。
59年、初期型ペン発売。28mmF3,5、200sシャッター。
最初期の物は、アイトレットが1つ。
60年、ペンS。30mmF2,8、250sシャッター。私の個体は64年なので、初期型ではない。
初期型のペン。表面の表示が、ORYMPUS。後の物はORYMPUSーPEN。
62年、ペンEE。F3,5レンズ、60s単速EE。
63年、ペンEES。F2,8レンズ、30Sと250sプログラムEE。3点ゾーンホーカス。同年EEもプログラムEEに。
同じく63年、ペンD。32mm、F1,9レンズ、500sシャッター。セレン露出計付。
ペンの生産は長く、生産数も多い。その為、変化も多い。
私、Dは初期の物と後期の物、2台持っている。何故か、初期の方が程度が良い。
中学生の頃、ペンF使っていたが、Dは目測であるが、ほぼ同じ写り。
EEは後期、ELに成ってからの物。程度も良く、セレンも生きている。何の問題も無く良く写るが、ASAが200迄しかない。
EE系。光不足なら、ファインダーに赤ベロが出るのが正常。
今と成っては、シャッターの固着やセレンの劣化で、赤ベロが出なかったり、其の儘シャッターが切れたり(正常露光ではない)が。
フラッシュ用に、30sでの絞りがある。ASA100フイルム使用で、
F11〜8辺りなら使える。400フイルムで、開放なら夕景も可能。
今回、知人のEE2探していて、初期型EESと、EES2見つけた。どちらも2160円。思わず買ってしまった。
EESはセレンが生きており、赤ベロが出る。EES2はシャッターは切れるが、何故か赤ベロが出ない。
EES,D迄は、ロライ35の様に、裏蓋が外れる。EE2以降は、裏蓋は普通に横開き。EE系はASA400に対応。アクセサリーシュー付。
EES2は4点ゾーンホーカスに成り、鏡胴部で変更。
73年、EE3。EE2の廉価版(と言っても機能は同じ)生産が長く、途中から、40sと200sのプログラムシャッターに変更。
初期の物は、シャッターボタンが銀色。後期の物は黒色。
EES2。EE2と共に生産中止となったが、EE3の途中で再生産している。
再生産品は、EE3後期型と同じプログラムシャッター。黒色シャッターボタン(此れは珍品)
今回は此処まで。
無限に撮影出来るスマートフォンで撮影に入った方が、昨今値上がりしたフィルムで精々36枚しか撮れないと不満でしょうが、ハーフなら多数枚撮影で満足できるでしょう。
もちろん何千枚もは無理ですが、ダイヤル巻き上げが巧くリズムを作ってくれますから、そんなに連続しては撮れず却って1枚を大切にされるのではと思います。
EE、EES系は、詳しくは全く存じませんので、大まかな初代,2,3の中に、そのような変遷があったとは目から鱗が落ちるようです。
ついでにペンDにもそんな初期と後期があるとは全く存じませんでした。
ハーフサイズを愛好するグループを拝見すると、今もってEE系をご愛用される方が多いことがわかります。
酸いも辛いも噛み分けたベテランが、感度以外は弄るところがないEEで傑作を次々ご発表され、今更にカメラ操作とは何かを考えさせられています。
EEは以前検証したとき、メーカーの言うとおり距離3.2mに固定されていることがわかりました。最終モデルEFは2.8mです。
ただし常識的な撮影距離を常識的なフィルムで撮影し、常識的な引き伸ばしを行う限り、ほぼピンぼけを意識することはないと思います。
注意する点は、大まかに1m、厳しく見て1.5mより近接では焦点が甘くなり、数十センチの近接は特別なデバイスがないと無理ということくらいでしょうか。
EESは前玉回転式の焦点調節機構を持っていますね。
米谷技師のこだわりによるペンやペンD系の全群繰り出しからは多少妥協されたモデルだとは思いますが、実用的には問題になったことはないのではないでしょうか。
EEラインで私が持っているのはEFだけですが、最近赤外線フィルターを貼り付けて楽しんでいます。
厳密には赤外光は露出計では測れないのですが、ASA25に合わせると日中は誤差範囲で適正露光が得られています。
軽く、気軽に多数枚撮影出来、余りの楽しさにすっかりはまってしまいました。
赤外での焦点のズレは、被写界深度でカバーされ、さらに遠距離方向にずれるためEFの近距離寄りの固定焦点が却って遠距離に強くなるように思っています。
Olympus Pen EF, D Zuiko 28/3.5, ASA25, Rollei Superpan200, Fuji SC72 filter, Fujidol 20d 6min
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/11/07(Wed) 23:56 No.1423
2018/11/07(Wed) 23:56 No.1423
裏面の張革に、オリンパスマークのスタンプがある。初期型ペンと同じ。
Sは表面の表示が、最初からORYMPUSー PEN S。63年製造品迄は、初期型と同じ様子。
65年、ペンS3,5。F3,5レンズ、250sシャッター付。
Sと付くが、初期型ペンの後継品。此れにはスタンプが無い。
64年、ペンW。ペンS本体に、25mmF2,8広角レンズ付き。
軍艦部も黒塗装。此れは珍品。本体が傷だらけでも、今では2万程。
最初期、片耳の三光ペンと共に、コレクターズアイテム。
リコーオートハーフも25mmレンズ。此方の方が安い。
EE,EES共、張革が、グレー、格子柄。初期の物の方が、色が濃い。
初期ペン、ペンS、W共、張革は黒のシボ仕上げ。Dは初期型から黒の格子柄(以後のペンは全て格子柄、ビニール)
裏蓋が横開きの物。ファインダー接眼部に。プラスチック枠が付く。
此れは、ペンFと同じ。アクセサリーシューはダイレクトタイプ。
64年、D2。Dのセレン露出計を、Cdsに変えた物。低輝度対応。
65年、D3。Dのレンズを、F1,7に改良した物。
どちらも、水銀電池(代替電池)が必要。この辺り、結構お高い。
Dを含め、どれも、単独露出計なので、動かなくても撮影できる。
目測タイプ。0,8mまで寄れる。しかしDの開放付近では、メジャーが必要(0,8mはコピースタンド使っての、コピー用?)
D3、既にFが発売された後の製品。Fの普及品でもある。
然し、目測F1,7は大口径のあだ花。目測で開放は?
D2。発売期間がほぼ1年。結構数が少ない。
幾つかペン弄ってみて、モルトが弱い。ほぼダメになっている。
レンズがズイコーなので、曇っている物も多い。
セレン回り、当たりがある物がある。フイルターは付かないが、レンズには影響ない(今回見つけた、初期型EESも当りが有るが、撮影には問題い)
EE、EES、トリップ35共にサークルセレンは共通。シャッター関係を含め、交換可能。
フジの業務用フイルム、結構硬い。ハーフのペンに打ってつけ。
時間がかかるが、片耳、Wを含め、全部集めても、場所取らない。
ペンの木作っても、デジタルライカ1台より安い。
集めてよし、写してよし(もう私にはそこまでの気力が無いが)
 ナースマン
ナースマン  2018/11/08(Thu) 08:00 No.1425
2018/11/08(Thu) 08:00 No.1425
ペンとペンSとの価格差は、30%以上。レンズとシャッターがグレードアップしたとは言え相当の差ですね。
そしてEEはペンSよりさらに高価でペンの1.5倍。EESはペンの2倍。驚くほど高価。
今EEは普及機という印象ですが、当時は相当の決断を迫られたことでしょう。
価格と価値は比例するわけではなく、ペン初代は戦略的な価格設定だから余計に安いのでしょうが。
ペンDは別格の価格、でもEESと近い。
ケース800円は、本体価格との比率からすると結構高かったかも。簡単なジッパーに入れるだけの構造だけど、良いなめし革にベルベットの内張で丁寧な作りではあります。
とはいえ、ニコンF辺りのケースならペン本体が買えてしまうくらいだったかもしれませんね。
ペンD,Fズイコー32mmf1.9、f8、1/30、ローライインフラレッド400、SC72フィルター
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/11/09(Fri) 07:17 No.1426
2018/11/09(Fri) 07:17 No.1426
ケース。初期の物、黒シボ革にベルベット張り。
ペンとSがグレーの内張。EE、が赤、Dが青の内張です。
(私の手元の物はそうでした。然しサイズは同じなので、内張が、グレー、赤、青の3種類有ったのかも?)
S3,5からビニール製になる。
ストラップ。初期のペン、Sは、黒革の編み込み。
D、EE、EESはビニール。
EE3とEES2の再生産品は布製の編み込み。
レンズキャップ。初期の物、筆記体表示でPen。
ペン、S用の小型とEE、D用の大型の2種類。
後期の物(何時からかは不明)活字体表示でORYMPUS。
トリップ35は勿論ORYMPUS。
ペンF。初期型Fの標準レンズの物、花文字記載でF。
交換レンズ、FT,FVの物はORYMPUS表示。
広告画像は、初期型ペンとそのストラップです。
 ナースマン
ナースマン  2018/11/09(Fri) 09:00 No.1427
2018/11/09(Fri) 09:00 No.1427
横に並べた2つのプリズムとロータリーシャッターによる1眼レフ。
63年、ペンF。レンズを向かって右に寄せ、左にシャッターダイアル。
初代コンタックスのスタイル。標準レンズは38mmF1,8シャッターは500s。シャッターダイアルに、専用Cds露出計がセットできた。
セルフタイマー無し、アクセサリーシューはオプション。
右隅にFの花文字。90度のDS巻き上げ。
66年、ペンFT。FにCdsを内蔵。TTLにした。
Fのピントグラスはマット面だけであったが、FTは中心部マイクロプリズム付き。ピントグラス左隅にTTLNo表示、これを読み取り、鏡胴に移す。
Fの花文字が有った所に、セルフタイマーが付く。150度SS巻き上げ(刻み巻き上げはできない)
ミラーを大型化し、ミラーショックを減らす。
67年、ペンFV。FTのTTLを外した廉価版。
シャッターダイアルにペンF同様のCds露出計装備可能。F系最終品。ロータリーシャッターなので、ストロボ全速同調ですが、何故か最後迄、アクセサリーシューがオプション。
私、中学期にF購入、高校期まで使った。大阪万博の時は、枚数が多いので活躍した。
然し、旅行には、小学生の時買ってもらった、ペンSの方が便利だった。
38mmでマット面。暗い所では使いにくい。FTのマイクロプリズムが羨ましかった。
巻き上げ。私手が小さいので、FのDSの方が使いやすかった。
(今も使っているライカM3もDS)
高校生の時、父が使っていたスーパーフジカ6をもらい受けた。
4切迄なら、Fでも何とか成るが、半切になると、明らかに差が。
フイルムサイズの差を、実感した。加えて私、RFの方が使い安い。
そんな訳で、キャノン7購入。ペンFは、35mmF2レンズの下取りに成った。
以後ペンF系は使っていない。今使うなら、FVと思う。
価格はFTと変わらないが、数が少なく、見つけるのが大変。
FTはTTL使うために水銀電池(代替電池)が必要。動きも遅く、どっこいしょ状態。
F、FVは電池が必要ない(FTも電池無しで使えるが)
FTレンズ。鏡胴の絞り表示、一般用の絞りと、TTLNo表示の両方がある。切り替えて使う。
初期Fの物は、TTLNoが無い。
1眼レフなので、レンズ交換できる。
珍しく、鏡胴側に解除ピンがある。上部に2つの角が有り、抑えて回す。
角が小さく、押さえるのが重い。指が痛くなる。
私、ハーフ1眼レフは、別にコニカオートレックスP持っている。
フルサイズとハーフ切り替えできる、フルサイズ1眼レフ。
ペンFより、はるかに大きく重い。然し、ヘキサノンレンズの中心部だけ使うので、写りは抜群。
画像は祖谷のかずら橋。4切で。高校生の私。
 ナースマン
ナースマン  2018/11/10(Sat) 08:32 No.1428
2018/11/10(Sat) 08:32 No.1428
ペンFはセルフがありませんが、単体セルフをお使いか、どなたかに撮ってもらったのでしょうか。
ペンFは我が家初めてのレンズ交換式カメラで、父が出張旅行に携えて行くために奮発したものでした。といっても最初の出張では標準40/1.4の他には手が回らず、2度目に100mmf3.5を追加していました。「広角は要らないの?」と訊くと、「広角はプロのもの。広範囲を写すだけなら何枚か繋げばいい、遠くを撮るのはそうはいかない」という持論を聞かされました。
FTの標準は他社に較べコンパクトだけでなく非常に寄れるので、重宝したようです。
父の遺品としてFと40,100は大切に置いていますが、作動はスタックしてしまいました。
今FVとFTを使っています。一時期露出計要らないとFVを求め頻用していましたが、昔使用中にミラーが衝撃で破損したFTをレストアしてもらったら、ファインダーの程度が良いので手元のFVより明るいのでちょっとショックです。全反射ミラーのFVを買った意味がない...
1971年頃父がモスクワで撮影、ペンF+40/1.4
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/11/11(Sun) 01:25 No.1430
2018/11/11(Sun) 01:25 No.1430
三脚で設定。友人と変わりばんこで撮った物です。
当時、こんな画像に凝っていました。私は標準1本でした。
でも、単車の旅行では、ぺんS持ち出すことが多かったです。
これは近年まで同じ。画像は京都での、カブカフェに参加した時の物。
私のもう1つの趣味、古いカブです。正にペン、メモ代わりの画像にもってこい。この時は、ペンEEです。露出もペン任せです。
でも最近は、ルミックスGF1にオリンパスの17mmが多いです。然し、サイズも重さも、ペンDの方が小さく軽い。
 ナースマン
ナースマン  2018/11/11(Sun) 11:19 No.1431
2018/11/11(Sun) 11:19 No.1431
ペンに関しては、以前コレクターが詳細なHP掲載していたのですが、残念なことに、削除されてしまった。
コピペも無いので、私なりに少し調べてみた。
58年、試作品。ORYMPUS−18表示。
59年10月、三光ペン。当時販売価格を6000円設定したが、原価償却が?との事で、下請けの三光商事から、先行販売してみた。
価格はケース込み6800円に。お結び型の片耳、シャッターの溝が横3本。
グレーシボ革、裏面にオリンパスマーク、表示はORYMPUS。表示を除いて、試作品とほぼ同じ。
60年5月まで生産。27000台ほど生産。ペンのNo、頭1が捨番。
60年6月、オリンパス生産品。丸形片耳、シャッター溝が縦5本。
61年12月迄製造。84257台製造。通しNo頭が2になる。
62年1月〜64年11月、量産型ペン。両耳、154500台製造。
60年7月、ペンS。61年8月、ペンEE単速型。62年6月、64年9月、ペンW。此処までが、量産型ペンと同じシボ革外観。ストラップも革。
単速型EE、65940台製造。
62年4月、EEプログラムシャッター、EES。62年6月ペンD。64年9月、S3,5、D2。65年9月D3。此処から、格子張革に。
66年。フイルム受け軸がEL、表示がORYMPUS−PENに。
68年3月、EE2、EES2。裏蓋横開き。セレンが、二重円に。
73年5月、EE3。格子黒革。
EE3後期型、及びEES2再生産品。40s、200s2速シャッター。シャッターボタンが黒。生産時期不明。83年製造終了。
私の個体。S、13万代。Sは初期型のシボ革。ORYMPUS−PEN表示(Sは最初からORYMPUS−PEN S表示)
EES、16万代。D、28万代。EE、30万代。ORYMPUS表示。格子革。
D、66万代。EE(EL)100万代。ORYMPUS−PEN表示。
EESー2、360万代。No底面表示。TRIP35、278万台。黒格子革、布ストラップ。
何故か、S,EE、D共に古い物の方が、調子が良い。
特に、オリジナル、S、D、は構造に無理が無い。見事な設計。軍艦部も開きやすい。整備は簡単。
EE系は、ほぼセレン劣化かシャッター不調。但し、先に述べたように、初代EEから、ほぼ同じ部品。交換は簡単。
私の、2速型、初期のEE。劣化しているが、ASA100に対して、64設定で、良好露出。
400入れて、200設定では、快晴で、露出オーバー。
但し、晴天、無限遠景。F22まで絞るので、ピントが来る。
ピントが甘いと言われる。固定焦点を、劣化したセレンのまま、絞り制御しているので、開きすぎに成っていると思う。感度を調整するとましになる。
葉書までなら、スマホの画像に劣らない。
1700万台製造された、オリンパスペン。此れも最後まで残る銀塩カメラだと思う。
 ナースマン
ナースマン  2018/11/23(Fri) 07:01 No.1444
2018/11/23(Fri) 07:01 No.1444
以前からお世話になっていたオリンパスペンに関するファンサイトは次々にサーバー休止に伴い閉じてしまわれ、大変残念です。
資料的な価値は大変高かったし、気になることがあれば直ぐに辞書のように引くことができましたが、サイトオーナー様の個人的な負担に頼るところが大きく、閉じられるのを責めることはできません。
どんなに立派なサイトも、所詮電子情報、書籍のように何時までも手元にあるわけではないことを実感しています。
さて初期ペンは、私はほとんど存じません。
先日カメラ店で、シャッター不安定のペンが500円で売られていて、レンズは綺麗に見えたので手に取ると、シャッターボタンが横溝でアイレットが一つ、これ三光ペンじゃない?と驚き思わず買って帰りました。
拙宅にはペンS3.5があるので復活を急いではおりませんが、ぼちぼちと直して撮影してみたいと思っています。
ネットオークションがなかった30年ほど昔、雑誌の巻末「求む譲る」コーナーを利用していくらかのハーフサイズカメラを入手した中に、ペンWとS3.5、D3があって、性能の高さに驚かされました。
しばらくハーフ撮影から遠ざかっていましたが、最近モノクロフィルム現像を再開し、経済的で気軽に撮影出来るペンを積極的に起用したのは、その高性能のためです。
初めて使うフィルムや、現像処方のテストにも、ハーフなら気軽に多数の条件を試せますし、途中で切って現像すれば、多すぎる撮影枚数も気になりません。
後ほど個々の機種に触れる予定ですが、特にS3.5のD.ズイコー、WのE.ズイコー、DのF.ズイコーは信頼しています。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/11/25(Sun) 22:06 No.1447
2018/11/25(Sun) 22:06 No.1447
三光ペンなら、枚数表示部の中心が真鍮。金色です。
オリジナル系。レンズ以外、ばらせば整備できます。レンズは持病の白濁が、此れも交換は簡単です。
私の新しい方のD。レンズに指紋が付いていて、オキシフルでも取れません。
EE系はセレンとシャッターが問題。基本劣化しています。
私のEE(EL)ほぼ問題なく使える。2速初期のEE、先に述べたようにセレンが劣化している。
先日手に入れた、EES。シャッターが粘っている(赤ベロ出ない)
EES2シャッター切れるが、開いていない(赤ベロ出ない)
どちらも、ばらせば何とかなりそう。最悪2個1。
それと、全てのペンに言えるのは、モルト劣化。交換が必要です。
三光、W、S3,5、D3、少数派ほぼすべて押さえている。加えて、FT、FVも。既にペンコレクターですね。
後、片耳初期型ORYMPUS。更に、幻のペンSブラック。
黒格子革、軍艦部黒塗り。S3,5の時代に、2,8レンズ付けた黒塗り有った?新聞記者用の特注品?との噂。
ネットオークション等に、時々黒のSが出ている。然し此れは初期型の黒シボ革。後塗りか否か不明。黒格子革の物、私見たことが無い。
 ナースマン
ナースマン  2018/11/26(Mon) 06:45 No.1448
2018/11/26(Mon) 06:45 No.1448
発売当時はあまり人気がなく、生産量は少ない。
重量380g
レンズ:E-Zuiko 25mmf2.8 3群5枚ヘリアタイプ,35mm判換算35mm
フィルター径22.5mm
シャッター:コパル#000、1/250-8,B,X接点あり。
ペンSの本体にE-zuikoを入れ、ファインダーブライトフレームを25mm用にしたもの。レンズの突出はペンS3.5同程度でペンSより突出が少ない。
元々ペンに付いていたテッサータイプのD-Zuiko 28mmf3.5は素晴らしい性能ですが、開放近くで四隅までの周辺画質は僅差でWのE-Zuikoのほうが端正だと思います。
35mm相当の画角が魅力です。ただし28mmと25mmでそんなに変わるか?と言われると、両方のファインダーを両目の片方ずつで見たら、ファインダーフレームの範囲はごくわずかの違いしかなく、画質も絞り込んでしまえば殆ど差が無く、わざわざ高価なWを探す必要性は少ないかなという気もします。
私は1985年頃に懇意な方から譲渡されましたが、そんなに数が少ないとは存じませんで、2000年頃の価格高騰に度肝を抜かれました。最近は少し落ち着いているようですが、下げ止まりしているかもしれません。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/12/03(Mon) 21:33 No.1456
2018/12/03(Mon) 21:33 No.1456
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/12/03(Mon) 21:36 No.1457
2018/12/03(Mon) 21:36 No.1457
1967年発売、プログラム露出の簡単操作カメラながら、新設計の32mmf1.7大口径レンズをつけたカメラ。
オリンパス製プログラムシャッターはf1.7〜22、1/15〜1/500の間で、絞り兼用シャッター。
絞りをAから外すと1/15固定のフラッシュ用モードに切り替わり,絞りをマニュアル設定できる。
感度ASA12〜400、CdSによるEE
距離目測。ヘリコイド焦点合わせ、最短撮影距離0.8m、
重量430g
フィルム巻き上げ背面ワインディングギア。カウンター自動復帰。
EMの後継機、EE系の最高級機、D3の自動露出化という側面を持つ。
デザインは従来と大きく異なる角張った形状。
D3とレンズのスペックは同じだが、コパル000シャッターに設計が制約されたD3と異なり新設計で画質は大変高い。開放近くでは少しハロがあるが日中では滅多に開放にならない。
撮影の印象ではシャッター羽根の作動がゆっくりしていて、同じ速度でも動体を写し止める能力は若干低いように思われる。手ぶれについて慎重に保持する必要がある。
フラッシュモードは1/15と遅いのは、当時まだ使われていたフラッシュバルブにも対応できるようにしたのだと思うが、多分高速でもX接点なら同調できるはず。
夜景は1/15で絞りマニュアル撮影を行う。1/30なら手持ちでも大きくぶれずに写せるが、1/15は手持ちにはきつい。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/12/06(Thu) 19:15 No.1458
2018/12/06(Thu) 19:15 No.1458
1965年発売、高級ラインのペンDシリーズ最終機種。
重量420g
レンズ:Fズイコー32mmf1.7
シャッター:コパル#000,1/500〜1/8,B
ヘリコイド目測焦点合わせ,最短距離0.8m、3mにクリック
非連動CdS露出計
巻き上げ背面ギアワインディング、カウンター手動セット
ペンDはFズイコー32mmf1.9、セレン露出計、D2はFズイコー32mmf1.9、CdS露出計。
D3はさらにf1.7に発展した。
性能は同じ絞りではf1.9バージョンと変わらず、大変高性能。f1.7開放は少しハロがあるが十分実用可能。
シャッター音は1/500まで出るにも関わらず極めて静粛で、昔暗い講演会会場などでも廻りを気にせずに撮影できた。却ってワインディング音の方が気になるほど。
私の個体はモルト劣化で漏光があり、整備待機中。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/12/06(Thu) 22:24 No.1459
2018/12/06(Thu) 22:24 No.1459
私、Dの1,9でも、近接0,8mではピント外しました。1,2mF2,8がやっとです。もっとも、1眼レフのペンFのF1,8でも、マット面のファインダーでは、少し暗いと、ピントが?でした。
F1,9解放では、やはり隅が流れますね。F2,8 に絞り、3mなら、ペンSの開放と差が有りません。
F1,7はF1,9の改良?だと思いますが、其の辺り如何ですか?
F1,9は、少なくても、ペンFのF1,8とは差が無いと思いました。
 ナースマン
ナースマン  2018/12/07(Fri) 20:06 No.1460
2018/12/07(Fri) 20:06 No.1460
>目測F1,7、無理が有りませんか?
無理と言えば無理だと思います。短焦点ではありますが、仰る通り今なら許されないでしょう。
昔、寝る前に一眼レフを弄りながら、目測の訓練をしました。
近距離で1枚を確実に合わせられるかと聞かれたら、勿論自信ありませんが、チャレンジした中で幾つかは合ったときは嬉しいので、それも醍醐味かと思っています。
確実性が必要なら複数枚撮影でカバーということも。
実践では、暗い室内、3から10m程度の距離でスクリーンに映されるスライドを撮影した際には、サービス版で字が読める程度の尖鋭さは確保できていて、上司に資料として差し上げたら大変喜ばれました。
> 私、Dの1,9でも、近接0,8mではピント外しました。1,2mF2,8がやっとです。
近接のなかでも、腕を伸ばして届くか、指の先あと何センチか、など目測しやすい距離は却ってわかりやすいです。
同様に歩幅で測れる範囲も与しやすいですね。
私ポケットに百均の1mメジャーを忍ばせています。家具などの買い物に便利ですが、撮影にも使います。
難しいのは1.5-2m、または触れない被写体です。
知人に、ペン用の名刺サイズ距離計を自作されたかたが居られます。
そのカードを手に持ち、腕を一杯に伸ばして片目で基準目盛りを被写体に合わせて保持し、次にもう片方の目で見たときの被写体の位置に応じた距離目盛りを読むというもので、近距離であれば結構な精度があるようです。私も真似したいので適当なプラスチック板を探しているところです。
> もっとも、1眼レフのペンFのF1,8でも、マット面のファインダーでは、少し暗いと、ピントが?でした。
マットで短焦点は山が難しいですね。マグニファイアが欲しいこともあります。
> F1,9解放では、やはり隅が流れますね。F2,8 に絞り、3mなら、ペンSの開放と差が有りません。
Dを山積みジャンクの中から救出し、最近使ってます。でも赤外専用にしていて、f5.6-8以外の絞りを使いません。
昔Dを借用したときは、隅の乱れはあまり認識できませんでした。
大昔にOPGに投稿した内容が残っていました。恥ずかしながら...http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/1262/lenstest/D01.htm#TOP
> F1,7はF1,9の改良?だと思いますが、其の辺り如何ですか?
最近使っているコピーフィルム超軟調現像で、超高解像度のテストをしていませんので断言はできませんが、Dのf1.9とD3のf2は見分けが付かず、焦点距離は違いますがFの38/1.8も同レベルで開放としてはかなり良い画質です。
絞り込んでもこの3者は同じように画質が締まっていきます。D3のf1.7は,同じD3を半段絞ったf2と較べてハロっぽくコントラストが落ちますが、解像力は保っている印象です。
D3のf1.7は,同じ絞りでのDf1.9レンズの画質を落とさないで口径比を広げたことが改良だったのではないかと思います。
ご指摘を受けましたので四隅に関して再度検討させてください。
> F1,9は、少なくても、ペンFのF1,8とは差が無いと思いました。
昔フジクロームベルビアで撮影し、顕微鏡で確認した範囲では私も同意見です。
多分ミニコピーでは解像力がベルビアの倍以上ですから、もっとよくわかると思いますので後日報告致します。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/12/07(Fri) 22:33 No.1461
2018/12/07(Fri) 22:33 No.1461
重量370g
レンズ:Dズイコー28mmf3.5
シャッター:コパル#000,1/250〜1/8,B
直進ヘリコイド目測焦点合わせ,最短距離0.6m
巻き上げ背面ギアワインディング、カウンター手動セット
シャッター最高速がS同様1/250に上がり倍数系列となったため使い勝手は初代より上がっている。
レンズは定評がある初代を踏襲している。実際に極めて高解像力で、信頼性が高い。
Wとは甲乙付けがたく、ごく四隅のみWのほうが端正かという程度。
また以前Sを試した時、30mmf2.8は28mmf3.5より僅かに甘い印象を受けた。個体差の範疇だったかもしれないが、個人的にS3.5に傾倒するのに十分だった。
このDズイコー28/3.5はペンEEシリーズに3.2m固定焦点として、またペンSのDズイコー30/2.8はペンEESシリーズに前玉回転として装着されている。
そのためEEは距離3.2mではS3.5と同等の高解像力を発揮する。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/12/07(Fri) 23:58 No.1462
2018/12/07(Fri) 23:58 No.1462
重量280g(電池なし)
レンズ:Dズイコー28mmf3.5、固定焦点2.7m
定常光はセレンによるEE、ASA25-200
シャッター速度1/250,1/30二段自動切替。
絞りf3.5-22
フラッシュ:GN10(ASA100)オートストロボ。ASA100と400切替、絞りは開放固定。背面に到達距離指標あり。単3x1本。
巻き上げ:リアワインディングギア。カウンター自動復元順算式。
プラスチックボディで軽量化されたEE、
他のEEシリーズが3.2m固定焦点なのに、これだけは2.7mとより近距離になっている。
開放近くで遠景を撮るとさすがに甘いが、f8以上に絞られることで遠景も被写界深度に入る...が、拡大するとやはり合ってはいない。サービスサイズでは十分以上。
2.7mではペンS3.5同レベルの高解像。
裏蓋は右側ヒンジで開く。
フィルムカウンターが順算式、裏蓋で自動復元
巻き戻しボタンを一回押したら次の巻き上げまでずっと有効。
この3点で決定的に近代的な使い勝手になった。(前モデルは裏蓋分離式、カウンター手動逆算式、巻き戻し中ボタンを押し続けるクラシックさ)
オートストロボ内蔵。これは原始的な並列式オートなので常にフル放電してしまうため、チャージ時間は近距離発光でも節約出来ない。
私の固体はストロボが液漏れで作動せず、500円だった。セレンは元気で、もとからフラッシュを使うつもりがないのでこれで十分。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/12/09(Sun) 18:51 No.1464
2018/12/09(Sun) 18:51 No.1464
重量:420g
レンズ:Fズイコー32mmf1.9、フィルター径43mm
シャッター:1/500-1,B,倍数系列
距離合わせ:直進ヘリコイド、最短80cm(クリックなし?)
セレン単独露出計内蔵。ASA10-400、測光範囲EV7-17
電池不要のセレン露出計内蔵、高速シャッターと大口径レンズが特徴。
ボディサイズは従来のペンシリーズと共通。
レンズは開放からシャープで実用的な像を結び、咄嗟に持ち出しても電池切れの心配がないセレンとメカニカルシャッターが高い信頼性になっている。
レンズアタッチメントサイズ43mmはDシリーズすべてとペンFの交換レンズ大部分とも共通で、システムとしての一貫性がある。
ところが同じオリンパスでも24x35コンパクトカメラは43.5mmという特殊なフィルターサイズを採用しており、今となっては困っている方が多い。
ただし現行品当時、どちらのフィルター径が主流だったのかはよくわからない。偶々43mm機がよく売れたのでデファクトスタンダード化した可能性もある。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/12/10(Mon) 23:16 No.1467
2018/12/10(Mon) 23:16 No.1467
後期の物は、ORYMPUSーPEN表示ですね。
私、両方持っていますが、初期型の方が調子いいです。
セレン露出計、少々劣化してますが、実用可能です。
先にも記したように、開放0,8mは曲者です。
43mmフィルター。EEと同じ。此れが元で、D系も、F系も、同じものに統一したと思います。トリップ35は、43mmです。
 ナースマン
ナースマン  2018/12/12(Wed) 16:36 No.1470
2018/12/12(Wed) 16:36 No.1470
ファインダー表面が黒塗り、裏面にペンFと同じプラスチックの枠付き。
張革は、黒の格子柄。シャッターボタンが黒塗り、40sと200sの2速プログラム。
ダイレクトシュー、4769〜台、ほぼ最終品。勿論、裏蓋横開き。
セレンも生きており、赤ベロもでる(赤ベロが出ても、其の儘シャッターが切れる>初期の物は赤ベロが出ると、シャッターが切れないが、ASA400対応の物は切れる)
純正ストラップが布、ケースがビニール、レンズキャップはOLMPUS表示。
何と、ブックオフで2480円。奈良にハードオフが新装開店。
旧い方のハードオフが、ブックオフに吸収された。
基本、ハードオフとブックオフは別系列。販売方針も違う。
ハードオフでは、動作確認可能であるが、ブックオフは一切お断り。
鍵付き陳列なので、外観には問題ないが、此れでは機械式カメラを買うのに勇気がいる。
掃除の序に、動作確認はした。ASA400迄可能なので、取り合えず、記録用フイルム入れて、写してみるか。
何せ、83年迄販売。総数1700万台生産のペン。此れが最終形である。
 ナースマン
ナースマン  2019/01/12(Sat) 15:03 No.1490
2019/01/12(Sat) 15:03 No.1490
ハーフサイズの集まりではEE-3の愛用者は結構多いようで、程度が良いものが残っているからでしょうか。それと400が使える。
EE-3はベロが出てもシャッターが切れるとは知りませんでした。
ちょっと上級者向けかもしれませんが、ネガカラーのラチチュードを考えると、少々露光不足しても撮影出来た方がよいのでしょう。
件のハーフ愛好家達の作品を見ると、8つ切りなら固定焦点でも相当良い画質です。
何も全コマ全紙に伸ばせる品質を追求する必要はないのですから、自らの不見識を恥じています。
ブックオフでもカメラを置きだしたのですか。というかハードオフを併設じゃなくブックオフに吸収とは。
知らない人が弄って壊し、「これ壊れてますよ」とか言われるのを避けたいのでしょうか。それと使い方を教えられる店員は居ないから、店員が壊しちゃうのか。
ちゃんとした人がいないのに物品を販売できる今のシステム、安いかもしれませんが危うく、初心者への間口が狭いですね。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2019/01/13(Sun) 21:51 No.1491
2019/01/13(Sun) 21:51 No.1491
フラッシュ用の絞り表示以外に、専用ストロボの距離表示有ります。
多分、ストロボ用に、新しいシャッターに変化したと思います。
ASA400フイルム使って、明るい時は、200s。暗い時は、40s。もっと暗い時はストロボ使用。赤ベロは、ストロボ用の目安だと思います。
フイルム、現像の価格が高騰。銀塩として、1本で40枚撮影は強み。
葉書大までなら、これで十分。デジ、スマホに差が無い。
否、デジには無い柔らかさがある。精密だが、硬いだけのデジ。
隅が流れたり、ピントが甘い銀塩。若者にはこれが逆に新鮮?
と言う私も、最近ズマールとかズマリットに凝っています。
昔は精密なズミクロンが主だったのですが、デジ使うと、少し硬い?
隅が流れたり、全体が柔らかいレンズの方が、銀塩の価値?と思ってます。
画像は、81年のカメラショーのカタログです。
カタログによると、EFもEE−3も250s、30sのプログラムと成っている。
特にEE−3は黒のシャッターボタン。
一体何時から200s、40sのシャッターに変わったのか?
この時期のシャッター、赤ベロが出たら、シャッターが切れなかったのか?
この辺り、ご存知の方、掲示願えれば幸いです。
 ナースマン
ナースマン  2019/01/15(Tue) 18:04 No.1492
2019/01/15(Tue) 18:04 No.1492
発売1963年
18x24mmフォーマット(ペンサイズ)一眼レフ、ペンFマウント、完全自動絞り。
背面レバー90度二回巻き上げ,クランク巻き戻し。
正立正像ポロプリズムファインダー0.8倍、スクリーンはマットのみ
チタン製ロータリーシャッター。シャッター速度1/500-1,B
シャッターダイヤルに連動する外部CdS露出計別売。適正絞り値が表示される。
70年父が欧州出張のため40/1.4付きで導入した我が家最初の一眼レフ。
結局最後まで露出計は購入せずフィルム箱の露出ガイドに従って勘露光していた。
私はこれがカメラ初体験だったので,レンズを通じていないファインダー像のRFカメラや、トップカバーにペンタプリズムが屹立する通常の一眼レフ形状には長い間馴染めなかった。
巻き上げ機構に負担を掛けないよう90度二回巻きはそんなものだと思えば問題ないが、速射性は劣るだろう。
ポロプリズム光学系のためかファインダー像が暗いが、f1.4レンズのためそれほど気にならなかった。
のちに20mm広角を購入した時、ファインダーで焦点合わせすることは難しかった。写真術に慣れると、ごく短焦点は目測の方が却って精度が良くリズミカルに撮影できることを知った。
父は出張で多数の撮影を見越してハーフサイズを選択したと言っていたが、既にFTは発売になっていたはず。当時裕福とはいえなかった当家では、価格がこなれた旧型を選択したのだろうと想像している。
その代わり出張では当時フジよりかなり高価だったコダカラーIIを奮発して行き,報告にはコマを選んでポジ反転スライドを提出していた。なので、30年以上経って私がスキャナ導入し全コマ画像化した時、父は「こんな写真撮ったかな、新鮮だ。」と感心してくれた。亡くなる数年前でささやかな親孝行だったと思う。
73年2度目の出張には,100mmf3.5を加えていた。この頃はFT用のTTLNo.付きレンズになっていたが、もちろんペンFではTTLnoは使わない。
G.Zuiko40mmf1.4の性能は鋭く、小型軽量の上最短撮影距離が短く、一般使用においてはマクロレンズや近接デバイスがほとんど不要。
価格:26500円(Fズイコー38mmf1.8つき)ボディ15000円
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:40 No.2991
2025/09/15(Mon) 23:40 No.2991
発売1966年
CdS素子によるTTL露出計内蔵。ASA25-800。測光範囲:ASA100、f1.4でEV3-17
電源:水銀電池MR9(1.3V)
ペンFの改良型。外形は変わらないが、TTL露出計を内蔵、レンズには自動絞り以外の連動機構はなく、シャッター速度に連動しファインダー内に表示される0から7までの「TTLナンバー」を、レンズ絞り環の数字に移し替えると適正露光になる。外部露出計用のバヨネットは省略された。
FT同時発売のレンズには、従来のf値表示とTTLナンバーを切り替える機構がある。またf値のみ表示の旧型レンズ絞り環に貼り付けるTTLナンバーのシールが供給された。
TTLナンバーはf値と完全一致せず、レンズの透過性や画角による露出計への入射角の違いを含めて誤差が起きないように設定されている。
他に、ファインダースクリーン中央マイクロプリズム+マット、三脚座位置がボディ端から中央に移動、セルフタイマー内蔵、レバー150度1作動巻き上げなど細かい変更が行われている。
オリンパスが1971年にM-1(OM-1)に移行したのち、中古は非常に安価で、ニコンFEのサブシステムとして、78年ごろ1万円くらいで購入した記憶がある。
当時私は近接撮影に入れ込んでいて、露出倍数計算を省略できるTTL露出計が欲しかったが、実際にはそれほど実用しておらず、もっぱら旅行や記録撮影に使っていた。本格的に使い出したのは、ペンスケッチ展に参加した頃かもしれない。最近はフィルム価格高騰により、愛用の一角を占めている。
価格:32000円(F1.8つき)39800円(F1.4つき)46000円(F1.2つき)ボデイ22200円 ブラックボディは千円高
20mmf3.5。システムでは最も広角、フルサイズ換算で28-29mm相当。ペンサイズは縦位置基本なので、左右の画角が狭く感じられる。f3.5と無理がない明るさで性能は高い。リバースマウントすれば最も高倍率が得られるが、25mmf4と拡大率はそう変わらず、逆付け画質もかわらない。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:45 No.2992
2025/09/15(Mon) 23:45 No.2992
発売1967年
FTから内蔵露出計を省略、かわりにペンFメーターを装着できるようシャッターダイヤル基部にバヨネットを復活したモデル。
ファインダー光路に設置されたCdSにレンズを通った光を導くハーフミラーが全反射ミラーとなったためファインダーが明るくなったとされているが、実際に比べると個体差の方が大きいようだ。
FTのシンクロM/X切り替えが、Xのみとなった。
価格:24000円(Fズイコー38mmf1.8付き),31700円(60mmf1.5つき)ボディ14200円 ケース1900円
左からFT, FV, ペンF。FとFVにはシャッターダイヤル基部に露出計を固定するバヨネットラグが見える。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:50 No.2993
2025/09/15(Mon) 23:50 No.2993
FTのみ電池室がある。
Fの三脚座は端によっていて、三脚固定時の重心に問題があった。
米谷技師はスクリューライカ使いなので、ここでもいいと思ったのかもしれないが、
重量がある望遠レンズがラインアップされると問題になる。
もう一つ、電池室を設ける際に位置を開け渡す必要があったのかもしれない。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/15(Mon) 23:57 No.2995
2025/09/15(Mon) 23:57 No.2995
小型軽量のペンFマウントレンズの中でも小さく携帯に有利。
フルサイズ35mm相当。f4と暗く、短焦点で被写界深度が深いこともあり、元から明るくないペンF系ファインダーで焦点合わせするのに苦労する。
距離目測、ファインダーはフレーミングに集中すると効率よく撮影できる。
TTLnoなしで発売され、FT後もTTLnoつきが継続された。性能は最高レベル。
ペンFとTTLnoなしの25/4。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 00:06 No.2996
2025/09/16(Tue) 00:06 No.2996
フルサイズ140ミリ相当で、最もよく目にするペンF用交換レンズ。
性能は鋭く、OM用100mmf2.8をアダプタ装着した画質に勝るとも劣らない。
ペンFT発売にあわせ、TTLnoつきに切り替わった。
74年父が東欧に出張した際に、片手で100mm付きペンFを撮影していたところ、現地人が、すごい、これと交換してくれないか、とライカを差し出してきたという。
まだ先が長い旅先で使い慣れないカメラと交換するのは不安だと断ったが、残念だったかもしれないと言っていた。
今から思うと、ライカではなくゾルキーあたりだったかもしれず、交換しなくて正解だったのではないか。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 00:16 No.2997
2025/09/16(Tue) 00:16 No.2997
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 00:17 No.2998
2025/09/16(Tue) 00:17 No.2998
高性能揃いのペンF交換レンズの中でも群を抜いて高解像力の1本。
最短15.6cm、フルサイズ等倍に等しい範囲が画面いっぱいに写る。
クセノター型、無限遠も非常に先鋭で夜景でなければ万能に使える。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:08 No.2999
2025/09/16(Tue) 01:08 No.2999
フルサイズ100mm相当の大口径望遠。85mm相当の60mmf1.5の影に隠れて人気がなく、現存本数が少ない。
ガウス型で開放は柔らかいが解像力はあり、少し絞ると先鋭になる。
60mmと比べると細身で、100/3.5を短くしたような形状。
60mmも一時持っていたが絞り故障し修理に出したが治らないため手放した。
今では60も70も高騰してしまい、再び入手するのは困難になってしまった。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:11 No.3000
2025/09/16(Tue) 01:11 No.3000
極小レンズだが、優秀な38ミリf1.8を2.8に絞った画質と比べてごく四隅以外は同等の高性能。
惜しいことに最短0.8mは我慢せねばならない。テーブルトップの料理を、立ち上がって撮影する必要がある。
ペンFレンズにはもう一種類38mmf2.8がある。パンケーキは5枚構成E-ズイコーだが、他方はサイズは38mmf1.8と同じで、テッサー型4枚構成Dーズイコー。記念モデルのため数は少ない。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:15 No.3001
2025/09/16(Tue) 01:15 No.3001
フルサイズ210mm相当の望遠。自動絞りペンFレンズの中で最も長焦点。
性能は非常によく、フルサイズ200mmと同等の解像力。
遠距離の昆虫など動体の接写目的で入手したが、クローズアップレンズと併用しても大変高性能。
シグマ望遠ズーム用アクロマチックマクロレンズ(クローズアップレンズ)を装着している。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:21 No.3002
2025/09/16(Tue) 01:21 No.3002
接写では大変有利で、絞りが制約を受けない。
ただしフルサイズ用のフラッシュは大きく、小型軽量のペンFシステムに似合わないが、小型フラッシュは機能的に物足りないことが多い。
今最も便利に使っているのはパナソニックPEー28Sと、こちらに紹介するリングフラッシュ。
リングは、単3x2とモデリングライト用の単4x2、GN不明だが十分な露光量を得られている。サイズが小型で、モデリングライトが焦点合わせに有効。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:28 No.3003
2025/09/16(Tue) 01:28 No.3003
ただしデジタル用レンズは絞りリングを持たないため、マウントアダプター側で絞りを調整する機能が必要。
ペンFマウントはさまざまなマウントアダプターがあるが、純正アダプタでは対応できない。
Muk Select製のEOSーPenFアダプタを介して、NFG-EOS、またはPentax DA-EOSアダプタを使用すると、マウント側での絞り制御ができる。
ただし、絞り値を知ることはできない。したがって露光はペンFTのTTL露出計を基準にすることになる。
デジタル用に制作されたレンズの解像力は非常に高く、使用する価値はある。またペンF現役当時には存在しなかった高倍率ズームや、20mmよりも短焦点を利用できる。
ペンタックスDA15mmを装着。フルサイズ21mm相当。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 01:38 No.3004
2025/09/16(Tue) 01:38 No.3004
ベローズには2種類あり、初期からのモノレール簡易型「Olympus PenF Bellows」と、後期の2本レールを備えた「Olympus PenF Bellows 2」で、初期型220g、後者でも360gと十分小型軽量なので携帯にはありがたい。
それぞれにスライドコピアと、フォーカシングステージ「カメラスライダー」が接続できる。
最後まで手動絞りで自動絞りにはならず、ダブルケーブルレリーズによる絞り込みにも対応していない。
いずれも繰り出し長は25mmから100mm。撮影倍率:繰り出し長÷レンズ焦点距離;なので,38mm標準で0.65倍から2.6倍(ヘリコイド伸ばせば2.9倍)、25mmなら等倍から4倍少しになる。ペンサイズ18x24mmを画面いっぱいにする等倍は、フルサイズで同じ範囲を画面いっぱいにすれば1.5倍に相当し、大変拡大率が高いことになる。
画像はベローズ2型、カメラスライダー、リバースリング(後述)+ズイコー20/3.5
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:30 No.3005
2025/09/16(Tue) 22:30 No.3005
ベローズは基本的にペンFマウントレンズを正向きに装着する設定だが、無限遠基準で設計されたレンズを想定以上に繰り出すと画質が劣化する。ある程度は絞り込みで改善するが、専用設計レンズにはかなわない。
しかし、専用拡大レンズは用意されなかった。
他方、顕微鏡にカメラボディを接続するアダプターはあったが、RMSマウントアダプターはなかった。M39アダプタは存在しているので引き伸ばしレンズは使用可能。
簡便的に拡大撮影には、標準から広角系レンズを逆向けに装着する「リバースアダプター」を使う。
一眼レフ用の逆望遠レンズをリバース装着すると、対称型の拡大レンズと比べてバックフォーカスが長くとることができる。
レンズ対物側をクランプし、ボディマウント側に接続するリングと、レンズマウントに接続し、自動絞りレバーを押した状態で固定するリングのセット。普通絞りで使うことになる。
ベローズ2型7500円にくらべリバースリングセット3000円は結構高価。
リバースリングを分解した。左ボディ側、レンズ先端をクランプ。右レンズマウント側。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:35 No.3006
2025/09/16(Tue) 22:35 No.3006
残念ながらベローズ同様、自動絞りではない旧式のアクセサリのため、残念ながら活用範囲は広くないが、フルサイズに比べてレンズの焦点距離が短いため、リングの長さは短くても十分に拡大率が得られる。
初期の「中間リング」は、ニコンのK2リングと同様にネジで分解でき、組み合わせにより4種の倍率が得られる。のちに追加された「中間リング2型」は初期型より少し短い、中庸な長さの一体型。
いずれもメスマウントに自動絞りレバー固定ラグがあり、普通絞りで使用する。初期型のオスマウントにはロックボタンがなく、マウントにフリクションだけで固定されるため、不用意に外さないよう注意が必要。
手前左:中間リング2型、右:「中間リング』、奥はT2マウント
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:37 No.3007
2025/09/16(Tue) 22:37 No.3007
ビデオやカメラ一般用にフロントコンバージョンレンズを供給している老舗レイノックスが出していた、
x1.5と、x2.5の複数枚構成クローズアップレンズセット。x6,x12,x24の高倍率「ミクロ探検隊」もあった。
アタッチメントサイズ37mmと、43mmがあり、43はペンFズイコーにちょうど良いが、大きすぎるので37ミリを使う。
37-43ステップダウンリングで直接レンズに装着しても良いが、上記に紹介した小型リングフラッシュのマウント部に37mmコンバージョンレンズを接着したので拡大撮影が容易になった。
なぜ上記の専用マクロシステムがあるのに簡易型とされるフロントコンバージョンレンズを使うのか?
もちろんレイノックスマクロコンバーターの性能が良好で、少し絞るだけで十分先鋭な画質が得られるのは大前提だが、フィールドで、細かく動く被写体を追って手持ち撮影するならば、ほぼ自動絞りが必須であるためだ。
ペンFシステムには残念ながら自動絞りを維持しつつ繰り出し量を延長するアクセサリは存在しない。クローズアップレンズなどフロントコンバータに頼るしかないのである。
これについては同時代の他社も似たり寄ったりで、オリンパスを責められない。
そして初めて高倍率接写専用レンズで手持ち自動絞り撮影を可能にしたのはOMだった。ただOMレンズをペンFアダプタで装着できても普通絞りになってしまうのだが。
手前がマクロ探検隊。レンズに装着しているのはスーパーマイクロx6
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/09/16(Tue) 22:41 No.3008
2025/09/16(Tue) 22:41 No.3008
35mmハーフフレームカメラ
24mm×18mmフォーマットのハーフフレームカメラを挙げてみる、というのを始めたいと思います!
国内では1960年頃から70年代前半まで大きな市場を持ち、一時はフルフレームのカメラよりも出荷台数が多かったというハーフカメラ達。
現在使っていなくても何処かに仕舞い込んでいた機体、まだ稼働できる昭和のハーフカメラを集めたい、見てみたいと思いスレッドを立てます。
その中でも、Belomo AGAT18Kについては日浦様が詳細なレポートをされています。またオリンパスペンについてもナースマン様が史料価値の高い解説を載せていらっしゃいますので、それら以外を挙げて行こうと思います。35mmハーフフレームカメラ
24mm×18mmフォーマットのハーフフレームカメラを挙げてみる、というのを始めたいと思います!
国内では1960年頃から70年代前半まで大きな市場を持ち、一時はフルフレームのカメラよりも出荷台数が多かったというハーフカメラ達。
現在使っていなくても何処かに仕舞い込んでいた機体、まだ稼働できる昭和のハーフカメラを集めたい、見てみたいと思いスレッドを立てます。
その中でも、Belomo AGAT18Kについては日浦様が詳細なレポートをされています。またオリンパスペンについてもナースマン様が史料価値の高い解説を載せていらっしゃいますので、それら以外を挙げて行こうと思います。
キヤノン
1965年発売の35mmハーフフレームカメラ 28mmと50mmのレンズが付属されていた。
レンズはキヤノンSD 28mmF2.8(3群5枚)同50mmF2.8(6群7枚)
シャッターはセイコーシャL B及びプログラム式(1/30 F2.8〜1/250 F22)フラッシュ時1/30
重量はいずれも実測で、ボディ330g 28mmレンズ53g 50mmレンズ92g
ハーフフレームのコンパクトカメラでは恐らく唯一のレンズ交換式かと。望遠が欲しいならペンFを手に入れればと思うものの、本体+レンズ2本でも結構なお値段。そこでこのデミCという選択肢が出て来ました。
汚れやすく清掃が困難なファインダー以外は特に欠点も無いカメラです。マウント外側リングでフィルム感度を合わせ、セレン電池式の露出計の針に合わせて露出ノブを回すだけで撮れます。
レンズ交換はレンズ本体もリアキャップも小さいので扱いは慎重に。金属製レンズキャップも落としやすいです。
同じセイコーシャLシャッターを積むフジカハーフはマニュアル操作が出来るのに対しデミCはプログラム式のみとなるのが残念な点か。
栗林写真工業
1960年発売の35mmハーフカメラ
レンズはACオリコール28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.7m〜∞
シャッターは自社製カーペルS B・1/15〜1/250
露出計無・セルフタイマー無 重量は385g
栗林写真工業は国内ではコニカに次いで古くからカメラ製造するメーカーでした。戦後は主に他メーカーよりも安価なカメラを製造販売し、輸出にも積極的でした。
ペトリハーフはオリンパス・ペン発売の翌年にに発売。露出・SSはマニュアルのみで個性的なグリーンに着色されたファインダー、レンズ下部にトリガー巻上げを持っています(巻上パーツの一部に金属製チェーンが用いられていることでも有名)。
私の個体はアメリカの商社DeJUREが米国内で販売したDeJRE COMPACT名で里帰り品の様です。
1990-95年ごろハーフフレームカメラのマイブームでして、主に月刊カメラマン誌の求譲コーナーで集めました。
その頃の個人売買は、昨今のようなゴミをつかまされることがほとんどなく、珍しい機種でも非常に安価に、完全動作状態で入手できたのは今思えば僥倖でした。
いくつかご紹介できそうなのでまた嬉しいです。
デミCもペトリも所持しておりませんので重ならなくてよかった。
demiシリーズはキヤノンらしくソツがない仕様が多いですが、望遠レンズが使えるCは異色です。これ以前にはレンズ交換ビューファインダー機は散見されますが、同時代には新規で登場したものはCだけではないでしょうか。(AF機にアタッチメントはありますが)
望遠の性能など興味津々です。フォーマットは違いますが、前玉が大きくなっているところペンタックス110の50/2.8を思い出します。
ペトリは別項でご紹介でしたが、こちらの方が皆さんにわかりやすいですね。トリガーが立った状態で落下させて畳に刺さったという話を聞いたことが(笑
各社各様に作られていて画一的な35ミリコンパクトより冒険ができたのかもしれませんね。
元々父のペンFがカメラ初体験だったこともあり、ハーフは馴染み深いものでした。ただ同様に一眼レフでないとカメラではないという刷り込みもあり、色々一段落するまでビューファインダー形式のコンパクトカメラには手を出しませんでした。
旅行のサブカメラにと、たまたま店舗の片隅でまだ高騰していなかったオリンパスペンWを入手、その猛烈な解像力に参ってしまい、試しに明るいレンズの機種を入手するとそのどれもが優秀な画質を示し、病みつきに。10台を数える頃、もうそろそろ使いきれないと我に返って現在に至ります。
このスレッドも長く続きますよう、皆様どうぞよろしくお願いします。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:39 No.2921
2025/07/13(Sun) 16:39 No.2921
1961年7月 理研光学製
レンズ:リコー25mmf2.8(4-3テッサー型,オートハーフと同じ)
シャッター:セイコーシャ#000 1/250-1/4,B
サイズ:112x69x33.5mm
重量:390g
価格:10,800円
61年から62年まで1年間のみ販売され,オートハーフと交代した.
全自動のオートハーフとは対照的な,セレン単独露出計(ライトバリュー表示あり),絞りとシャッターをしっかり設定できるカメラ.
フルサイズ35mm相当の当時としては広角レンズを装備する珍しいハーフサイズカメラで,オリンパスではペンWに相当する.
オートハーフにも引き継がれたレンズは大変高画質で,開放でもごく四隅を除いて超高性能で名高いペンWのE-Zuiko25/2.8にも勝るとも劣らない解像力.オートハーフは近距離固定焦点なので,焦点調節ができるキャディは目測撮影できるユーザーには嬉しい.
巻き上げギアは背面下部,シャッターを押しっぱなしにして巻くと連続撮影になるが故障が心配なのであまりやらない方が良さそう.
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:41 No.2922
2025/07/13(Sun) 16:41 No.2922
焦点距離が短いレンズは絞りすぎない方が解像力が良く、性能を発揮できます。
ガンマが高くなる傾向があり、ハイライトが飛びやすくフレーミングに注意する必要がありますが、隅々まで解像し大野ぼしに耐えるネガが得られます。
他にもイルフォードパンF50は使いやすく、反対に汎用性を狙ってT-MAX400も良い結果が得られました。もちろんフジカラー400で夜景もよかった。
Richo Caddy, Richo 25/2.8, f4, 1/60, Minicopy HRII(EI12), Rodinal x416, 24dig, 40min
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:50 No.2923
2025/07/13(Sun) 16:50 No.2923
1966年発売
株式会社ヤシカ製,価格16,800円
レンズ:ヤシノン32mmf1.4
サイズ:116x68x59mm
重量:530g
シャッター:CdSプログラムEE, f1.4-1/15---f13-1/500, 絞りをマニュアル設定すると1/15固定, B
電源:MR9(LR44で動作している)
ハーフフレームコンパクトカメラでは最も明るいf1.4を装備した.
それなりに鏡胴が太く(フィルター55mm!),重量もあるが使うと気にならない.
背面下部ギア巻き上げの操作性は悪くない.
レンズ製作は富岡というネット情報もあるが,リンクス後期のf1.4レンズはズノー光学という情報もあり,私にはよくわからない.当時から目測でf1.4の焦点合わせは難しいのではないかと言われていたようだが,焦点距離が短いので案外外さない印象がある.
問題はフラッシュ用マニュアルシャッター速度が1/15なので保持に気を遣う.ブレることも多々あるものの,開放描写は素晴らしく,積極的に夜の撮影に持ち出している.また昼間に絞られた条件でも非常に繊細な画質で,素晴らしいレンズだ.
惜しむらくは,2枚構成プログラムシャッターのため絞ると開口部が菱形になり,アウトフォーカスの点光源に影響する.これは開放で撮影すればコマ収差を除いて解決する.
前モデルヤシカハーフ17はセレンメーターで,ズノーSLRを手がけたGKデザインが担当しているだけに流麗なフォルムだが,残念ながら不動になってしまい手放した.他社に見られない反射率が高いクロームメッキと曲面の軍艦部はハーフ14にも受け継がれている.14はその太い鏡胴が全体の印象を決めていて,如何にも大口径を主張しているが,実際のレンズ径は小さいので,シャッター機構がスペースを占めているのかもしれない.
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:52 No.2924
2025/07/13(Sun) 16:52 No.2924
大口径だが、フルサイズ換算で45mm相当の準広角で、コンパクト機としては使いやすい画角と思う。
ネットでは完動品がないという評価だが、完動状態で譲渡してもらった幸運に感謝したい。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 16:59 No.2926
2025/07/13(Sun) 16:59 No.2926
1964年7月発売
コニカ初のハーフフレームコンパクトカメラ.
レンズ:ヘキサノン30mmf1.9
サークルアイ方式のセレン光電池によるプログラムEE(f1.9-1/30---f16-1/800)
サイズ:111x68x45mm
重量:420g
ファインダー情報は充実していて,近距離補正マークつきブライトフレームの左側にヘリコイド連動の距離指標,右にEEシャッター速度指針が表示され,十分高級機である.EEシャッター速度が限界以下になるとシャッターロックされ撮影できないため,フラッシュ使用を促す仕様になっている.このセーフティ機構はETE3になって省略されたらしい.
Konica EYE 2
1967年3月発売
レンズがヘキサノン32mmf1.8と,若干長く明るくなった.
CdS受光素子によるプログラムEE
電源:H-C(LR44でも動作,少し電圧が高い分アンダー露光になるかもしれないが,もはや誤差範囲と思う)
その後1968年11月にEYE 3(セルフタイマー付き)にモデルチェンジしたが,同年12月C35が発売され,大変生産数が少ない.
C35の劇的な人気と,当時ハーフではカラー画質が不十分の上,おそらくフィルム消費量が少なく営業上不利のため短命に終わった.
どちらのモデルも大変高性能の大口径レンズで,目測ではあるが焦点距離が短いためほぼピントを外すことはなく,
夜景で開放でも高いコントラストを誇る.
フラッシュ用に1/30固定で絞りを選択でき,私は夜のスナップでは開放絞りで楽しんでいる..
巻き上げは,オリンパスペンが一貫してギアに対し,キヤノンデミやこのアイはレバー式で高級感はあるが,ストロークが少なく,これならギアで十分じゃないかとも思う...
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 17:02 No.2927
2025/07/13(Sun) 17:02 No.2927
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 17:07 No.2928
2025/07/13(Sun) 17:07 No.2928
年発売
レンズ:キヤノン30mmf1.7(4群6枚)最短1m
絞り:f1.7-16 AUTO/マニュアル絞りあり.
シャッター:1/500-1/8,B メカニカル
シャッター優先EE(EV4.5-17)ASA25-400
サイズ:117x71x48mm
重量:445g
電源:H-D(MR9)
焦点調節が直進ヘリコイドによる目測ゾーンフォーカス(山10m,家族3m,バストアップ1m)ヘリコイドに距離目盛あり)である以外は35mmビューファインダーカメラに遜色がないフルスペックの高級機。
レンズは新種ガラスを4枚用いたハイスペック。
ファインダーに距離ゾーン指標、EEでの絞り値が表示される。またマニュアル絞りでも露出計として適正絞りが表示される。
セルフタイマーが内臓されている。
サイズはコニカC35(112x69x50,370g)よりも大きく重いくらいで、ハーフフレームの存在意義が問われるだろう。
キヤノンらしくソツがないカメラ。
レンズは期待したが、そこそこ優秀だが私の個体はペンDやコニカアイより優れていない気がする。
絞りが4角形なので、背部に4角のボケが現れてややうるさいことがある。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:37 No.2929
2025/07/13(Sun) 19:37 No.2929
完全目測またはメジャーによる測距で、フレーミングはできないが、おおまかに撮影することはできる。デミEE17のマニュアルにはフィルターについて紹介はあるがクローズアップレンズの紹介はない。34mmは変わった規格なので、これ以外に用途があったのだろうか。
このような近距離が測定できるフランス製の距離計がある。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:38 No.2930
2025/07/13(Sun) 19:38 No.2930
1983年FT-1 motor発売同時期に,同ボディのアパーチャを規制し72枚カウンターを装備した特殊モデル.
学校や企業など,大量に個人肖像写真を撮影する目的で,業務用ルートで販売された.一部,(ディノスだったか?冊子形式の)通販で一般販売もされたことを覚えている.この手の機種としては多数販売されたか,比較的入手が容易な印象.
コニカは以前コニカ35IIIM,オートレックスおよびオートレックスPというフルサイズ/ハーフ切り替え式モデルを一般販売していた.そしてFT-1の後にも一般機種のバリエーションとして,ヘキサーおよびヘキサーRFの業務用ハーフモデルが用意されていたが,個人的には一眼レフの機能が必要だったのでその2機種には手を出さなかった.
販売:1983年(?)FT-1motorは1987年終了.おそらくハーフは初期に限られたロットが作られ,売れ残りが通販に流れたと考えられる.
スペックはFT-1motorと同じ
重量:570g
サイズ:143x91x46mm
シャッター:縦走メタルフォーカル,1/1000-2秒,B,シンクロ1/100,シャッター優先AE
感度:ISO25-3200
電源:単4x4(オプション単3x4)
世界初電動モーター内蔵SLRのFS-1の後継機FT-1は,連写機能とAEロックが追加され,外観が洗練された.秒間2コマのモーター巻き上げはFS-1と同じ.
露出計制御がAFマウント純正レンズに連動しており,アダプターで他社レンズを装着すると正確に測光されるか懸念されるページも見るが,元々自動絞り開放測光での話だと思うので,絞り込み実絞り測光マニュアル露出では問題にならないと思われる.
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:46 No.2933
2025/07/13(Sun) 19:46 No.2933
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:49 No.2934
2025/07/13(Sun) 19:49 No.2934
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 19:53 No.2935
2025/07/13(Sun) 19:53 No.2935
しかし使って楽しいカメラでもある
Vivitar 55mm f2.8 macro(Konica AR), 1/60 AE Kodak Gold 200
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 20:02 No.2936
2025/07/13(Sun) 20:02 No.2936
私もキャディ愛用しています。ペンより出番が多いかもです。
ヤシカハーフ14凄い!私も幾つか手にしましたが、結局動く機体には出会えていません。
デミEE17もいいなぁ・・デミシリーズでマニュアル可なのはこれだけ?
特殊用途の一眼まで登場とは・・。これは見たことないです。そういうニーズが有ったのも知らなかった。以前にニコンFM10のハーフ改造も投稿されてましたよね。どちらにせよ超希少種ですね。眼福です。
資料を調べてまた投稿します。
1963年キヤノン発売,24x18mm(デミサイズ)
価格10800円 ケース1000円,ストラップ300円
サイズ:115x68x37mm
重量:320g
レンズ:キヤノンレンズSH 28mmf2.8(3群5枚ヘリア型)画角55度
フィルター径:27mm(被せ32も使える)
目測ゾーンフォーカス.ヘリコイド全群繰り出し.15m〜0.8m
シャッター:ビハインド,プログラムf2.8-1/30--f22-1/250,B, フラッシュ1/30時に手動絞り.
セレン追針式露出計.
ケプラー型実像式プリズムファインダー.0.41倍
オリンパスペン大成功を受けて、やや高機能、簡単操作を特徴として、流麗なデザインで登場した。
プログラムシャッターはメカニカルに連動しており、マニュアルに近い感覚で操作できる。
操作法は、大きなリングを回して三角マークを、電光マークまたはBから外し、30-250表示に合わせると、シャッター速度が無段階に動き、軍艦部の露出計指針と、下側の絞り表示に連動するようになり、追針を合致させると適正露光になる。
この際は絞りレバーは任意に設置できないが、電光(1/30)またはBにすると1段ずつクリックが効きマニュアル設定できる。
シャッターリングをどん詰まりからさらに力をいれると感度設定ができる。
焦点合わせは目測で、レンズ鏡胴リングのゾーンマークに合わせる。ゾーンの具体的な距離はカメラ背面のプレートに表示されている。最遠距離は山マーク15m、それよりわずかに遠距離側に回るが、無限にあっているかどうかわからない。大伸ばしでなければ被写界深度に入ってしまうだろう。
アクセサリーシューは作り付けでなく、側面の金具にスライドで取り付ける。キヤノンRFカメラや初期SLRと同じような機能。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 22:45 No.2940
2025/07/16(Wed) 22:45 No.2940
1967年4月発売、
初代デミやデミCに使われているSH28/2.8を採用し、サークルアイ型セレン光電池によるプログラムEEになった。
説明書では「デミサイズ」ではなく「ハーフサイズ」と書かれている。
価格:11300円、ケース1200円、リストストラップ300円
サイズ:116x69x39mm
重量:290g
レンズ:デミと同様。フィルター径27mm
目測ゾーン:デミと同様。中距離3m(親子3人マーク)が緑色;常焦点マークになった。
シャッター:ビハインド、プログラムEE f2.8-1/30---f25-1/300、手動絞りにすると1/30固定。Bは省略された。
EE範囲:EV8-17.5、感度設定ASA25-400
ファインダー:採光式ブライトフレームファインダー、シャッター速度指針表示。
アクセサリーシューが軍艦部に設定された。
フィルム枚数計が、デミでは2コマに一回すすんでいたが、EE28では1コマ一回進むようになった。
デミは習作のようなところがあったが、EE28はかなり使い勝手が良くなっている。正直初代デミのような指針プログラムシャッターなら、EE28のように自動化しても結果は同じだし、EEのほうが圧倒的に確実。少し軽く、私は初代より信頼して使っている。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 23:12 No.2941
2025/07/16(Wed) 23:12 No.2941
kentmere 400(800増感)
ファインダー内露出計表示はEEのシャッター速度を示すため、30はf2.8-1/30(ASA100でEV8)、60はf5.6-1/50(EV11)、125はf11-1/125(EV14)、・はf22-1/250(EV17)、300はf25-1/300(EV17.5)です。
フラッシュモード1/30固定の場合、指針が30に来ればf2.8で適正、60ならf8で適正、125ならf22で適正になり、マニュアル撮影の参考になります。
実際には明るいところはEEに任せれば良いので、暗いところの判断に役に立つと思います。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/16(Wed) 23:16 No.2942
2025/07/16(Wed) 23:16 No.2942
いいカメラですよね。ペンWとどっちを持ち出そうと迷います。
最近はペンDと併用ならW、ペンは赤外線撮影目的が結構ありますので、単独ならキャディかな。
しかし当初元気だった露出計が最近不動になりまして、まあ全部ヤマカンなんですが動かないのも悲しいものです。
デミシリーズは全然詳しくありませんけど、なんとなくEE17だけフルマニュアルできるような気がします。
初代デミも、なんとなくマニュアルで合わせたうような気になるカメラですが、結局プログラムAEを手動でやってる変な操作性です。裏から見ると絞りがシャッターとは別にある、絞り兼用シャッターではない。これがEE28では絞り兼用シャッターへと単純化されてます。
初代はシャッターが粘っていて修理が必要になりました。EE17とEE28は元気元気。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/17(Thu) 16:25 No.2943
2025/07/17(Thu) 16:25 No.2943
カメラと2本のレンズが収納できて、内張はビロードのような布が貼られています。しかも革製です。
ハーフカメラにしては随分と贅沢な造りです(古びてますが・・)
れんずまにあ様に言われて気付いたんですが、50mmで撮った写真は?
ハーレーはともかく鳩の写真がそうかも、と。ピント外れていて背景がボケていることから開放に近いと思いますが、どうでしょう。
50mmはレンズがかなり前に出ているので晴天下ではかなりフレアっぽくなります。フードを付ければいいのですが、キヤノン独自の48mmフードです。
キヤノン
1964年発売の35mmハーフフレームカメラ
レンズはキヤノンSH 30mmF1.87(4群6枚)
シャッターはセイコー/プログラム式 B・1/8〜1/500 フィルム感度はASA25〜400
重量は実測410g
れんずまにあ様がご紹介くださったデミEE17のひと世代前の高性能機種。
キヤノンのHPによると「露出計の指針位置に追針を合わせる追針合致式、適正のシャッタースピード値と絞り値の組み合わせが決まるプログラム式」とのことですが、SSと絞りダイヤルが別々にあります。この二つのダイヤルが例えばLVリングのように連動しているような、してないような・・あ、絞りとシャッターの羽は別々のタイプです。
私は故障している個体なのかと思いましたが、この連携した動きがプログラムなのでしょうか。
取り敢えず撮ってみた感じ(リングの連動は意識せず)では良く写っていました。
>キャディ記事を横取りしてしまいすみません
そんなことお気になさらず、他にお手持ちがありましたらドンドン出してくださいね。れんずまにあ様の守備範囲が広いのは皆さんもご存じでしょうから、なかなか目にすることの出来ない機種が出て来るんじゃないかと期待してしまいます。
キャディ、やっぱりいいですね。私も旅行に出る時は必ずハーフを1台持って行きますが、ペンS、キャディ、AGAT18K、AGFA PARAT-1(コンテンツ作成中)の4台から選びます。どれもシャープに写りますし72枚撮れると思うと気楽だから。
AGFA
1963年発売のマニュアル操作35mmハーフフレームカメラ
レンズはAGFA COLOR-APOTAR30mmF2.8(3群3枚)
シャッターはB・1/30〜1/125 セルフタイマー無
重量は実測297g カウンターは手動セット・減算式(2枚撮って一度に2枚分進む)
私にとって初めてのドイツ製カメラ(笑)。有名カメラ店のジャンク箱から救出したのですが、使ってビックリ!とても良く写るのです。
ペンよりほんの少し大きく軽い本体は、軍艦部以外ほぼプラスチック製で裏蓋は取外し式。露出計を持たず、SSはバルブ以外3速しかない最もベーシックな仕様ですので、割り切れば使い勝手は良いです。
シリーズは他にセレン電池連動オート機能のみのPARAMAT、セレン電池連動オートとマニュアル機能を持ち、1/500までのシャッターとSolinarレンズを備えたOPTIMA-PARAT(テレコンバーターも用意された)が有りました。
富士写真フイルム
1964年発売の露出計連動35mmハーフフレームカメラ
レンズは3mの固定焦点でフジナーK 25mmF2.8(3群3枚)
シャッターは1/125単速 セルフタイマー無
重量は実測280g カウンターは手動セット・減算式
女性向けに設計・デザインされたコンパクトなハーフカメラ。
サイズはBelomo Agat18Kと同じかやや小さいくらい。ただ全金属製なので見た目よりは重く感じます。レンズ前面のフィルターは本来もう少し濃い紫色ですが本機はやや退色しています。アイレットにはネックレスのようなお洒落なチェーンが付いていました。
ただメーカーの予想に反して余り売れなかったようで、1年ほどで販売終了。翌年にはニューフジカミニとして黒色一色のモデルが輸出されました。
本機は固定焦点ですので、レンズ周りは絞りリングです。リングを回して露出計のガラスビーズ(それぞれの色がフィルム感度を表す・ASA25〜200)に針を合わせることで適正露出になる仕組み。巻き上げは軍艦上の銀色の円盤と底部をつまんで「カメラをひと振り」するのだそうです。危ないなぁ・・
日中であれば、やや広角ということもあって大概は上手く写ります。
富士写真フイルム
1964年発売のセレン電池連動35mmハーフフレームカメラ
レンズはフジノン2.8cmF2.8(3群3枚)撮影距離0.6m〜∞ フィルム感度ASA12〜200
シャッターはセイコーシャLでB・1/30〜1/300有 セルフタイマー有
重量は実測515g
ゼンマイによるシャッターチャージ・巻上げが特徴のハーフカメラ。
シャッターはSS・絞りを個別に操作できる。絞りダイヤルをA位置にするとSSダイヤルも自動的にA位置となりプログラムオートに切り替わる。
セルフタイマーは個性的で、巻き戻しクランク外周がゼンマイになっていて、背面のL・SスライドSWをL側がゼンマイロック、S側にするとタイマーがスタート。この時レリーズボタンは押す必要はない。
巻き上げのゼンマイは18枚分巻けるそうですが、60年を経たメカの耐久力を考え、ほどほどに巻いて使うのが吉かと。
レンズの描写も良く、オート/マニュアル撮影にも対応していて良いカメラだと思うのですがペンシリーズに人気には太刀打ち出来なかったようです。
富士写真フイルム
1965年発売の35mmハーフフレームカメラ
レンズはフジノン33mmF1.9(4群5枚)撮影距離0.9m〜∞ フィルム感度ASA25〜400
シャッターはセイコーシャB・1/8〜1/500セルフタイマー有
重量は実測490g
フジカハーフシリーズの高性能モデル。セレン電池による合致式メーターはファインダー内にある。レリーズボタン前方のダイヤル回転で絞りを操作出来るので、カメラを構えたままメーター合わせが出来るスグレモノ。
ファインダー内にはメーターの他にフォーカス距離のピクトグラム、SS、絞り値が確認できて非常に便利。
恐らくペンDやヤシカハーフ17に対抗したモデルと思います。非常に良く造り込まれているのですが、あまり見かけないので販売数は少なかったのかも知れません。ハーフカメラとしてはやや重量があるからでしょうか。
ヤシカ 1961年発売
非連動露出計搭載35mmハーフフレームカメラ
レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.8m〜∞
シャッターはコパルSV B・1〜1/500 セルフタイマー有 フィルム感度ASA10〜800
重量は実測530g カウンターは自動リセット・順算式
ヤシカとしては初のハーフカメラです。本体は鉄製で重く、ストラップ穴は無し、三脚穴は有。セレン電池は天板に有り、前側のメーターでLV値を読み取って露出を決めて操作する。側面右手側下方に巻上げ金具が有り革製ストラップが付いていて、それを引くと巻き上げ・チャージが行われる仕組みです。フィルムはスプロケットが直接巻き取るのでコマ間隔が徐々に開いていきます。
縦位置で横長写真を撮ろうとすると、レリーズが右手下方になるのでホールドし難いですね。
ユニークな構造が祟ったのか約1年で製造は終わったようです。
ヤシカ 1962年発売
非連動露出計搭載モーター巻上式35mmハーフフレームカメラ
レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)撮影距離0.8m〜∞ フィルム感度ASA10〜800
シャッターはセイコーシャL B・1/25〜1/250 セルフタイマー無
重量は実測680g(本体のみ、専用グリップは100g) カウンターは手動セット・減算式 使用電池は単3型×3本 脱着可能の大袈裟なグリップが付属
ヤシカとしては2作目のハーフカメラです。独ILOCA ELECTRICと並んで最初期の電動モーター巻上カメラとの事です。本体は鉄製で重く、ストラップ穴は無し、三脚穴は有。露出計のLV値を読んで鏡胴リングで合わせる方式になります。フラッシュ使用時のマニュアル絞りは可。
側面の扉を外すとフィルム室、後部の扉は電池ケース収納室です。フィルムは巻取りパトローネに引掛けてセットしますが、ラピードと同じく巻き太りでコマ間隔が広がって行くタイプ。
天板に露出計メータとワンタッチで開く透視ファインダーが有ります。レンズ下のレバーはL型がレリーズ、凸型がシャッターロックです。1秒間に2枚の連射が可能。側面下方の丸いボタンは巻き戻し用のロック解除、カウンターにSTOP表示が出るまで撮影するとモーターの電源がカットされます。巻き戻しは手動です。
モーターの劣化か駆動ギアの問題か、最初の十数枚で動作不能になってしまいました。ネットでの情報も少なく、修理は暗礁に乗り上げています・・
フジカドライブは一時期所有しましたが、故障してしまい店舗に返品してしまいました。
その上位機種の1.9は完全に初見です。すごいカメラがあったものですね。
ヤシカラピードは、アグファのラピッドシステムのカメラだと思っていましたが、普通の135パトローネ使用なんですね。
ヤシカは当時のメーカーの多分に漏れず、8ミリシネカメラに重点を置いていたでしょうし,当時のユーザーもそれに慣れ親しんでいたでしょうから、35mmの本来のシネカメラフォーマットである縦送り横長、モーター送りの発想に至るのは理解できます。
それをコンパクトカメラのサイズでやるのは大変でしょうけど。
大きく重くなるけど、操作は簡便というより触るところがないのも、当時の初級8mmカメラと同じですね。
もはやフィルムが入手困難なダブル8と違って、まだ135はあることはあるので、動けばさぞ楽しいでしょう。私はスキルなしなので応援しかできませんが、良い結果になりますように...
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/08/09(Sat) 17:55 No.2970
2025/08/09(Sat) 17:55 No.2970
変なカメラばかりですみません、名機は先輩の皆様方にお任せして、私は迷機担当という事でお許し下さい(笑)…
セクエルは純粋に写真機として興味深いです。二眼レフに近いかと思ってましたが、確かに8ミリシネカメラの方が近いてすね。でもこの時代の小型モーターとマンガン電池にはフィルム巻上げと機械式シャッターのチャージまでさせるのはやや無理があるような…
ILOCA Electricも故障が多かったようですから。
ヤシカ 1962年発売
非連動露出計つき35mmハーフフレームカメラ
レンズはヤシノン28mmF2.8(3群4枚)最短撮影距離0.8m
シャッターはコパルX B・1/8〜1/250 フィルム感度はASA10〜400
重量は実測375g カウンターは手動セット・減算式 セルフタイマー無
あまりに意欲的な造りだったラピード・セクエルからの反省か、オーソドックスなデザインとなったヤシカ3代目のハーフカメラです。
露出計は針の指すLV値を盤面から読みとって鏡胴の値と合わせる方式で、先代の機種と変わらずオート機能は有りません。
レリーズボタンは誤動作が少ない形状。巻き上げは背面下方に、巻き戻しはカウンターと一緒に底面にあります。三脚座はカウンターの中心にあり。
オリンパスペンと比べるとやや安っぽく、機種名がプリントというのもこの時代らしくない。
マニュアルのペンよりはシャッターダイヤル・絞りリングも厚みがあって操作しやすいです。
ヤシカ 1964年発売
露出計連動の35mmハーフフレームカメラ
レンズはヤシノン32mmF1.7(4群6枚)撮影距離0.8m〜∞
シャッターはコパル製プログラム式でB・1/30(F1.7)〜1/800(F16) フィルム感度はASA12〜400
重量は実測445g セルフタイマー有 カウンターは自動セット・順算式
ヤシカのハーフフレームカメラは4代目で自動露出になりました。絞り羽はシャッターと兼用の2枚羽です。
フラッシュ撮影用に手動で絞りが設定でき、この時にはSSは1/30固定。ファインダー内に露出計の指針と撮影距離のマークが出ます。丸みを帯びた本体は手に良くなじみます。難を言えばカウンターの文字が小さ過ぎて老眼には辛いところ。
良く写りますが、持ち歩く時にハーフとしてはやや重いです。
京セラ1987年発売
レンズは25〜75mmF3.5〜4.3(10群12枚)最短撮影距離1m
シャッターは電子式プログラムで2sec〜1/500
重量は実測で600g(電池別)電池は2CR5×1ケ セルフタイマー有 デート機能は2017年まで フィルム感度設定はDX式
1980年代中頃にコニカから「レコーダー」が発売され再びブームとなったハーフフレームカメラたち。本機はオリンパスPEN-F以来のハーフフレーム一眼レフカメラです。とは言え、所謂ブリッジカメラと見るのが正しいかも知れません。1988年カメラグランプリ受賞(とグリップにプリントされてます)。フィルムが縦送りなのはヤシカ時代のセクエル以来となります。
位相差検出式TTLオートフォーカス、2分割SPD素子による測光など当時のAF一眼レフとしてベーシックなメカニズム。ファインダーは視度補正があります。残念なことに全てオートで撮影者の意思で露出等を変更できるモードはありません。
片手で保持して人差し指でレリーズするスタイルですが、ズームボタンが遠いので結局両手で構える事になります。ズームはモーター式ですがのんびりとした速度。AFはやや迷うことが多いです。
シャッター音とレスポンスが良いのでいつのまにか沢山撮っていることが多いです。写りも当時のズームレンズとしては大口径で明るいので良好かと思います、
本機の後に4倍ズームモデルのX4.0、小型化されたサムライZ、更にはAPSフィルム用モデル(形状が似ているが一眼レフではない)も発売されました。
キヤノン1988年発売
レンズは35mmF3.5(3群3枚)内部テレコンによる60mmF5.6(6群6枚)最短撮影距離0.63m
シャッターは電子式プログラムで1/60(F3.5)〜1/350(F19)4秒までのバルブモード・インターバル撮影モードあり
重量は実測で290g(電池別)電池は2CR5×1ケ セルフタイマー有 デート機能は2029年まで フィルム感度設定はDX式
ごく普通のAFプラカメに見えますがフルフレーム・ハーフフレーム切替の出来る唯一の2焦点オートフォーカスコンパクトカメラです。
テレ6の「6」は別売りのテレコンレンズを取付けることで3×2=6通りの撮影ができるという意味。フルフレームでは35mm・60mm・75mm、ハーフで50mm・85mm・110mmとなります。フォーマットの切替はフィルム室内の黄色いレバーで変わり、ハーフ時にはマスクが出ます。ハーフ時には背面液晶に「×2」の表示も出ます。
レンズカバーは常時閉じていて、レリーズボタン押下すると開き、すぐに閉じます。
AF性能も写りもコンパクトカメラとしては上々の出来。途中切替は出来ませんが偶にハーフで撮りたい、という時には重宝する一台かと思います。
10年ほど前に税込み108円で購入しましたが、現在はそのマニアックさが再評価されて高価になっているようです。別売りのAF対応テレコンレンズはなかなか見つかりませんが。
マルマン 1990年代前半か
レンズは固定焦点の24mmF4(構成不明)※エクスプレスのみ3段階の絞りあり
シャッターは単速で恐らく1/125程度
重量はどちらも205g前後 使用電池はCR-P2×1ケ又は単4型×4本
時計バンドやライター、ゴルフ用品などを販売していたマルマンから発売されたハーフフレームカメラです。8コマ/秒という高速連射が可能(言い換えればそれだけ)なのが特徴です。
エクスプレスはASA100/200と400にお天気マークが割り振られていて絞りの変更が可能、Ⅱではこの機能は省略されていますのでASA400専用ということかと。
写りは決して悪いということもなく、晴天下では良い結果が得られました。
いい加減な造りではないようです。
マルマンというメーカーは短い期間しかカメラを販売していませんでした。明らかに他メーカー製OEMと思われる機種も有ったようなのですが、エクスプレスに関しては他社から同様な機種が発売されていないと思われます。
パワーショベル 2007年発売
レンズは22mm明るさ・構成は不詳 絞りはF8.5・F11の2種類
シャッターは機械式で1/100或いは1/125 セルフタイマー無
重量は実測87g ホットシュー有 三脚座有
何度目かのブームの際に発売されたプラスチック製35mmハーフフレームのコンパクトカメラ
単速シャッター・ノブ巻上のシンプルさですが、一応絞りは2段階切替可能です。晴れマーク・フラッシュマークがF11、雲マークがF8.5です。レンズ構成は不明ですがシャッター前後にレンズが確認できます。
フィルム1本とカメラ本体をブリスターパックに詰めて主に書店や雑貨店などで販売されていました。同梱のフィルムの中身は伊フェラーニア製Solaris FG Plus400でした。
ボディの色は黒色以外にも多種存在したようです。白色の「ハローキティ」バージョンは現在もオークションで見かけます。
販売者のパワーショベルは2000年代にアナログカメラをカルチャーとして広め、ロシアカメラやこのカメラのようなプラ製トイカメラを次々に市場に出していました。アグファフィルムの日本総代理店でもあったようです。残念なことに現在活動しているのかは不明です。
コンパクトかつ軽量でそこそこ写るのは立派です。
理研光学工業→1963年よりリコー
ゼンマイによる巻上げ、シャッターチャージを装備しセレン電池による自動露出のハーフフレームカメラ。オリンパスペンと並んでハーフカメラブームをけん引しました。
生産終了まで十数年ものあいだ基本的なメカニズム構成に変更が無かったのは驚き
レンズは富岡光学製固定焦点25mmF2.8(3群4枚)※ゾーンフォーカス機を除く
シャッターはセイコーシャBS11で1/125・1/30(フラッシュ使用時)
重量は写っている物の実測で初代290g・E2が325g・EF2が電池別で375g
小型化の為か三脚座は側面に有り
1962年初代オートハーフ発売
1963年オートハーフゾーンフォーカス発売。3点ゾーンフォーカス機
1965年Sを発売。裏蓋をヒンジ式、レリーズボタンが天面に移動し、やや厚みが増えた。セルフタイマーを装備
1966年Eを発売。Sからセルフタイマーを書略したモデル
1967年SEを発売。変更点不詳
1970年SLを発売大口径レンズ(35mmF1.7、4群6枚)を搭載、ゾーンフォーカス機
1976年SE2、E2(セルフタイマー省いたモデル)を発売。アクセサリーシューを装備
1977年EFを発売。内蔵フラッシュを装備。プラ製ボディに見えますが殆ど金属製
1979年EF2を発売。EFのフラッシュをポップアップ式とした(シリーズ最終機)
フォールディングまたは沈鏡胴カメラは大変好きですが、時代が降ると主流は固定鏡胴カメラに移行します。
ある意味携帯性や内面反射、さらに操作の楽しみの点で退化ではあるのですが、同時に撮影機能や信頼性では進化した面もあり、純粋に撮影酷使するなら見逃せない機種群だと思います。
一応オートフォーカス(電子的な.戦前の意味ではなく)あるいは自動巻き上げ以前の機種を想定しています。
機械式に限定する手もありますが、露出に関して適度な電子化が入ってくる時代でもあり、手動巻き上げ機種はまだ多様性を保っているため、自動露出も含めてはどうかと思いますがいかがでしょうか。
時代的にはおおまかに以下のように進んできたように思います。
1,沈胴フォールディングカメラをコスト削減のため固定鏡胴にしたモデル。
2,距離計連動や大口径レンズを装備するため固定鏡胴を採用したモデル。
3,1,2に単独または連動露出計を装備したもの。
4,絞り優先またはシャッター優先自動露出を装備したが、マニュアル露光機能も残したもの。
5,絞り優先またはシャッター優先自動露出専用で、マニュアル露出はできないもの。
6,プログラムシャッター機
7,フラッシュ内蔵機
わたしは沈胴フォールディング機も含めて、どの機種もそれぞれに特色と得手不得手があって、性能が十分なら嫌いな機種はありませんが、使って楽しいのは2,3,4かしら。
これに少数のレンズ交換できる機種も加わりますが、特に全群交換タイプはフォーカスプレーン機と重なりますから、別項にしたいと思います。
画像はVitomatic IIICS
レンズ:Color-Skopar 50mmf3.5(f2.8モデルあり)フィルターかぶせ32mm。
最短撮影距離1m,目測
シャッター:Prontor SVS, 1/300-1秒、B
レバー巻き上げ、ノブ巻き戻し。
セレン露出計は感度を合わせて背面ボタンを押して離すと適正露光表示で固定される、
特異な形式で見やすく、かなり暗い所でも正確に表示しているようです。
カメラ革ケース裏面にセレン受光部にかぶせる入射光アダプターが付属していて、ローライ並のサービス。
正直この機種のユーザーで入射高露出計を使いこなしていたのか、使われた形跡がないのがそれを物語っています。
カラースコパーは目測だが焦点が合えば非常にシャープ。このレンズを使いたいために入手しました。
以前所持していたフォールディング型のVito IIは気に入っていましたが、レンズの平行性に懸念があって手放したところで、この固定鏡胴は信頼がおけます。
ファインダーは素通しガラスです。
フォールディングと比べて鏡胴が突出していて嵩張るのは当然ですが、撮影体勢に迅速に入れて、フィルターをつけたままケースに入るのが利点です。
このモデルはストラップアイレットがあるけど特殊で、ケース併用が基本でしょう。少なくとも底ケースがないと困ります。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/02(Sun) 11:22 No.1719
2020/08/02(Sun) 11:22 No.1719
この機種に興味があったのはもうひとつ、このアクセサリーの存在があります。
普通近接には距離計連動部分もカバーするデバイスが主流ですが,フォクトレンダーはパララックス補正だけを行うクサビプリズムを出しています。
これはスーパーイコンタなどに使われたカイルプリズムと同じ。
二つのくさびプリズムをそれぞれ単独に距離指標に合わせると、本体ビューファインダーの光路が曲げられて、適正な視野が得られるものです。
(なんでわざわざ2枚別々に合わせる?ツァイスは互いに逆回転するよう連動しているのに?特許でブロックされたのか?)
近接で画角が狭まるところはフォローされません。
距離はというと、実測するのです。カメラ固定が望ましいでしょうが、上手にやれば手持ちもいけそうです。
レンズにFocar(クローズアップレンズ)を装着した時のチャートが説明書に載っています(Proxirectの説明書だけでなく、VitoBLの説明書にも載っている)
装着してみると、このBLには少しプリズムの中心がずれるようで、本来は大窓機に適合しているような。でもVitomaticIIIには装着できない。Vito専用なのか。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/02(Sun) 11:34 No.1720
2020/08/02(Sun) 11:34 No.1720
小型軽量ボディ、距離計連動、ヘキサノン38mmf1.8つき。最短0.9m、フィルター径49mm
機械式シャッター、1/500-1/8秒。
シャッター優先EE。EE時絞り値はファインダー内に表示される。
レリーズボタン半押しで針押さえされるので露出ロックができる。
電池がなければすべて絞り開放になる。
元々はMR44(1.35V)、形状は現行LR44, SR44(1.5V)と共通だが電圧が異なり露出不足になる可能性があるが、ネガで使う分には全く問題ない。
ホットシューにフラッシュをクリップオンすると、ファインダーに緑指針が出る。レンズ周囲にフラッシュのGNをセットし、距離とシャッター速度に応じて移動する緑指針と絞り指針を合わせると、日中シンクロフラッシュマチックになる。
大口径レンズつき距離計連動コンパクトカメラは一時期肥大して、ライカMなみのサイズにまで巨大になったが、反省されたか、Rollei35ショックの影響か、その後小型に立ち返ったが、C35FDは開放f値2以下のカメラで最も小型軽量な一台。
大口径開放にしてはハロが少なく、距離計を駆使して暗所で雰囲気がある写真が撮れる。
旅行のサブカメラとして持参したところ大変結果がよかった。かさばらず信頼性が高い。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/02(Sun) 15:36 No.1721
2020/08/02(Sun) 15:36 No.1721
コニカオートアップ2
φ49mmにクランプできる汎用品で、C35FDには少しファインダーがずれる。
距離計はカバーしているので実用的には問題ない。
この状態で1mから50cmまで距離計連動する。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/02(Sun) 15:39 No.1722
2020/08/02(Sun) 15:39 No.1722
距離計連動35mmコンパクトカメラ
プラスチック外装で軽量
電子制御プログラムシャッター 1/1000-15秒
レンズ:アグファ ゾリター40mmf2.8、最短1m
いろいろと特徴が多いドイツ製コンパクト。
巻き戻しはギアを切り替え巻き上げレバーで行う。
アグファのラピッドカセットを彷彿させるイージーローディング。
0.8倍もあるアルバダブライトフレームつきファインダー。
この時期のアグファの特徴、「センサースイッチ」という赤い大きなシャッターボタン。非常に軽く切れるが機械式。
日本には1976年から、同シリーズの目測機である535(シャッター1/500まで)と,
1035(同1/1000,セルフつき)が導入されていましたが、距離計連動の1535は国内広告で見た覚えがありません。
スペックは良いが、感触はきわめてプラスチッキーでスカスカです。
でも十分しっかり写ります。近距離は距離計があると安心です。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/06(Thu) 22:59 No.1723
2020/08/06(Thu) 22:59 No.1723
世代的にはキヤノネットやハイマチック等の時代よりはちょっと下って,オリンパスXAの時代のカメラと思いますが,そのころの距離計連動カメラは大好物ですし..
 日浦
日浦  2020/08/07(Fri) 08:46 No.1724
2020/08/07(Fri) 08:46 No.1724
・ボディー :小型金属製重量級。アイレット付き。 専用マガジン使用可能(*未確認) 132×80×64 760g
・ファインダー :アルバダ光像式 補色型距離計連動ファインダー。 パララックス補正マーク付き 倍率 0.7倍
・レンズ :Hexanon 48mm F2.0 5群6枚構成 最短0.9m フィルター径 35.5mm
・シャッター :SEIKO MXL B.1.1/2.1/5.1/10.1/25.1/50.1/100.1/250.1/500 LVタイプ。(セルフタイマー付き)
・フィルムカウンター:順算式自動復元
・フイルム巻き上げ :ボディー前面のレバーによる2回巻き上げ セルフコッキング
・フィルム巻き戻し :クランク式
KONICAⅠ型から丁寧に改良を加えていったとても使い易いカメラです。なぜか市場での評価があまり高くなく、安価に
購入できるのも利点です。
一番の特徴はボディ前面のレバーアクションで、好き嫌いがハッキリわかれるスタイルですね。でも使ってみるととて
も使い易い機構です。
発表当時の流行だったLVタイプのシャッターは、これも賛否わかれますが、今となっては楽しいギミックです。
レンズは大口径のF2.0が奢られています。さすがに絞り開放ではフレアーぽく、紫外線の影響も受けやすい印象です。
UVフィルターの使用が良いかも知れません。良いレンズフードが欲しいと思いました。
良く整備された個体であれば、うっすらと部分的にパープルの視野の中にほんのりイエローな距離計像が映ります。
残念ながらⅡ型まで受け継がれてきたレンズの沈胴機構は省略されていて、かえってモダンになるほんのちょっと手前
のスタイルがノスタルジックです。ただし夏みかんよりも重いボディーは落下させない注意が必要です。
 efunon
efunon  2020/08/07(Fri) 17:53 No.1725
2020/08/07(Fri) 17:53 No.1725
オプチマシリーズはマキナとデザイナーが同じだったと聞いています。
そうすると、特異な巻き戻し機構もデザイン上の一貫性が見える気がします。
ミニマキナと思うと、使うのが楽しくなりますね。
efunon様、ご参入ありがとうございます。
コニカI〜IIIのクラシックなデザインと、優秀なレンズはこの機種を選ぶ大きな理由です。
軍艦部上面のサムレバーに収斂してしまう以前の巻き上げ機構は百花繚乱で、それを使うのも楽しみの一つです。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/08(Sat) 23:51 No.1726
2020/08/08(Sat) 23:51 No.1726
1970年発売
エレクトロ35シリーズの中で,若干小型化され,35mmf1.8ともっとも広角。
距離計連動、最短0.8m
絞り優先EE、感度ASA25-500
シャッター速度1/250〜8秒だが、ファインダー内はオーバーとスロー警告ランプのみで速度は表示されない。
電源:4SR44
重量550g
そこそこコンパクトで、4群6枚ガウスの大口径広角という魅力的なスペック。
若干重量が大きく、シャッターストロークが長い。
二枚羽シャッターのボケ味を指摘されることがある。
操作する感触の気持ちよさは、C35FDのほうが若干勝るかな?
この状況ならこの程度のシャッター速度が切れてるな、という勘所が身についている人に勧めます。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/08(Sat) 23:53 No.1727
2020/08/08(Sat) 23:53 No.1727
1972年発売(ブラックは遅れて73年)
エレクトロ35系で最も軽量コンパクト。4群4枚 40mmf2.8レンズ。
距離目測、最短0.9m
絞り優先EE, 感度ASA25-1000
シャッター速度1/500-4秒
電源:4SR44
重量365g
これこそヤシカからのローライ35に対する回答だと思う。
固定鏡胴だが前面への突出が少なく、なによりセットアップする必要がなく速写製が高い。
巻き上げ、巻き戻し、ヒンジで開く裏蓋など操作配置は標準的でとまどうことは何もない。
操作感触は、高い高級感こそないが金属なりの確かなもので、気に入っています。
レンズの描写は、そこまで使い込んでいませんが十分にシャープだと思います。
CDS測光範囲がEV1-17なので4秒のスローをどこまで信頼できるかわかりませんが、たいしたものですね。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/08(Sat) 23:55 No.1728
2020/08/08(Sat) 23:55 No.1728
Mライカとあまりかわらない重量で、気軽に持ち出せるとはいえませんが、当時の日本メーカーの高い志が伝わってくるようです。
当時L39機の開放f値競争があったのですが、レンズ固定機にも波及したか、この次の機種IIIAの後期からf1.8に拡張されましたね。
ヘキサノン48mmf2は、同時代の例えばKalo35のProminar50mmf2と比較して、開放ハロは僅差で多いけれども、まろやかな印象で特に後ボケがざわつかない、解像だけを追い求めない高次の設計思想で作られている気がします。
以前どこかでヘキサノン48/2はレチナIIのエクター47/2に範を取っていると読んだ気がしますが、写比べると全く異なる傾向で、開放ハロはヘキサノンのほうが随分少なくシャープな気がしました。焦点距離の印象だけで語っているのではないでしょうか。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/20(Thu) 00:59 No.1732
2020/08/20(Thu) 00:59 No.1732
1954年発売,東独カールツァイスイエナ製、リーフシャッター・ビューファインダーカメラ
この機種は目測、近距離補正マークつき黒線フレームが視野に張り付くような実像ファインダー。
鏡胴周りのリングを回転させて巻き上げ・シャッターチャージを行う。
レンズは1Qマークつきテッサー50mmf2.8、カールツァイスイエナ、最短0.9m
シャッターは東独製PRESTORで、スプリングアシストなしで1/750〜1,Bという野心的なリーフシャッター.巻き上げ時に全開になるため遮光用シャッターと二重になっているが、ここが壊れているものが多く修理に難儀するらしい。シンクロつき。
レンズのカバーはシャッター、ヘリコイドも覆う釣鐘状で逆付するとレンズフードになる。
フィルム交換は底蓋と繋がった裏蓋を下に引きぬくタイプ。
巻き戻しノブは底面に目立たなくあり、軍艦部はシャッターボタンのみ。巻き上げ機構が目立たないのを極力生かして外側にほとんど突起がないデザイン。
私の個体も例に漏れずセルフキャッピングができず、修理店に断られたため巻き上げごとにレンズ前面を覆うか服に密着させて光線漏れを防いでいる。
写りは非常に良好。
この後距離計連動モデルや露出計内蔵、レンズ交換式に発展、シャッターは安定したコンパーが人気。
私はシンプルな初期型が好み。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/20(Thu) 01:01 No.1733
2020/08/20(Thu) 01:01 No.1733
1956年発売,西独アグファ 距離計連動ビューファインダーカメラ。
35mm判普及機ジレッテシリーズの上位機、距離計連動/トリプレット型カラーアポターまたはテッサー型ゾリナーつきスーパージレッテが1955年発売、後を追って1956年にガウス型Solagon 50mmf2つきが追加された。
レンズ:アグファ ゾラゴン50mmf2、最短0.9m
シャッターは最上位機シンクロコンパー、ライトバリューつき1/500-1,B
シンプルな操作系、同時代日本製のf2クラス固定鏡胴機に比べコンパクトにまとまっている。
反面ファインダーはフレームなし素通しで旧世代の印象。
巻き上げは予備角なしのレバー1作動、巻き戻しはノブ。
裏蓋はヒンジで開閉するオーソドックスな方法。
シャッターの切れはフォーカルプレーン高級機に及ばないが、機能的にはそれに匹敵する。
Solagonは評判が高いが、同時代のXenonやHeligonとは同傾向の画質で、明らかな優劣は感じられない。朴念仁なので。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/20(Thu) 21:28 No.1736
2020/08/20(Thu) 21:28 No.1736
1963年発売、小西六写真工業製(Konica社名変更は1987)レンジファインダーレンズ固定機。
従来の高級機コニカIIIシリーズから、大幅に設計変更コストダウンしたコニカSを1959に発売、セレンメーター指針がファインダー内で確認できるSII(1961)を経て、レンズを伝統の48mmf2から47mmf1.9に変更したSIII(1963)となった。自動露出のオートSと同年発売。
コニカIIIA同様パララックス,画角自動矯正、採光窓ブライトフレームファインダーを受け継いている。
操作系はSから招き猫レバーから、ライカMに準じるオーソドックスなものに変更され、個性は失った。
アクセサリーシューはホットシューではない。
当時の標準的レンジファインダー機、例えばキャノネットよりやや小型で、セレンはサークルアイ方式ではないのでフィルター補正は手動だが、デザイン的には高級感がある。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/22(Sat) 17:27 No.1737
2020/08/22(Sat) 17:27 No.1737
1959年富士写真光機製 距離計連動 セレン露出計連動 ビューファインダーカメラ
レンズ:フジノン4.5cmf1.9(4群6枚ガウス型)背面ダイヤルによる焦点合わせ 最短0.8m
シャッター:シチズンMLT 1/1000-1,B、ライトバリュー、カップリング解除可能。
セルフコッキング,底面レバー巻き上げ,クランク巻き戻し
採光式ブライトフレームファインダー、パララックス自動補正、
重量:770g
当時の高級機。フジノン45/1.9の性能は開放から大変良く、距離計基線長も長く、若干の画角の差はあるが、ライカMに50mmf2しか付けないなら、ほぼ同じ結果が得られると思う。
今となってはセレンメーターは当てにならない場合もあるが、あって困るほどのスペースも重量も食っていない。焦点合わせは右手背面のダイヤル、距離は軍艦部上面の回転指標、隣に露出計指針窓。
巻き上げは底面右手、巻き戻しはギアで90度傾けて左肩にクランクがあり、上面は大変すっきりしている。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/26(Wed) 23:49 No.1738
2020/08/26(Wed) 23:49 No.1738
カプセルカメラXAシリーズの3番目(XA:1979, XA2:1980)
レンズ:D.Zuiko 35mm f4, 4群4枚(?),固定焦点(∞〜1.5m)実際の焦点位置は記載がない。多分XA2が常焦点とした3m程度と思う。
レンズ周りのセレン光電池によるプログラムAE。
感度ASA100と400の二段階、連動範囲EV9-17(ASA100)
シャッター速度は1/250と1/30の2速
レリーズはストロークが長めで、押し込みで絞られる。
上位機種にあったセルフタイマーは省略された。
1/30、f4でカバーできない光量ではファインダー内に赤ベロ表示が出てレリーズロック
専用ストロボA9M装着,電源オンで暗所レリーズロック解除.上位機種A11/A16はオートストロボだがA9MはマニュアルGN9のみ。
フルサイズ化したペンEE3,または固定焦点化したトリップ35という機能のカメラ。
XA2:27800円,XA1: 23800円(A9Mつき)*これでXA1を選ぶ人はよほどの解脱者でありましょう。
レンズはXA2のテッサー型f3.5を固定絞りでf4に規制したものだと思っていましたが、ネット情報はあまりはっきりせず4-4との記載があります。とすると独自設計?宿題にさせてください。
XA, XA2, XA1と使ってきて、どれも素晴らしいカメラなのですが、へそ曲がりな私はXA1が好きです。日中屋外スナップなら無敵といってよいほど。2-10m程度の完全に深度に入った被写体のシャープネスは見事なもので、35mmをはめたライカと同じ仕事を、この頼り無さげなプラスチックカメラが立派に、いやそれ以上にやってのけます。
そして電池切れを心配しなくて良いのが最高です。いついかなる時でも即応してくれます。もしレンズが接合面がない4-4ならなおのこと、炎天下の車中ダッシュボードに常備していてもバルサム切れを起こす心配がありません。
XA2-XAと高級化するにつれ、テクニックを活用できるようになりますが、割り切った用途ならXA1はお勧めの一台です。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/27(Thu) 00:14 No.1739
2020/08/27(Thu) 00:14 No.1739
現役時代からXAのレンズはXA2に比べて無限遠の周辺画質が低いので風景では絞り込む必要がある、あるいは直裁的にXAはXA2より低画質である、という評価をよく聞いており、長い間敬遠していた理由でした。
1980年代にXAを使っていた友人たちも同様な感想を抱いていたようで、しばらく使った後XAを「卒業」してローライ35SEなどに移行、ローライのハイコントラストで先鋭なカラー画像を褒めそやしていました。
ところがジャンク千円で救出したXAをコピーフィルムで試写すると、多少周辺は先鋭さが落ちるものの、画面の大部分は開放からかなり繊細な描写をしておりコピーの解像力に負けていません。80年代皆が使っていたカラーポジの解像力はコピーフィルムの半分以下のはずで、なぜ背反した結果が出たのか悩むところですが、考えられる理由は、コピーフィルムはガンマが高いため、コントラストが低いレンズでも解像力さえあればよい結果が得られるのに対し、カラーポジではよい印象がなかったのではないかと思います。
左からXA1, XA2, XA。バリアのレンズカバー部分の形状が、XA1では球の一部、XA2は卵、XAはオーバルサーキット状。またXAは上面がフラットで、XA1,2はやや台形に盛り上がっている。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/08/27(Thu) 00:16 No.1740
2020/08/27(Thu) 00:16 No.1740
ただ周辺光量低下が大きめかもしれません.全長を短くするために望遠タイプになっており,レトロフォーカス型のような周辺光量増大効果がないためかと思います.しかし,この周辺の明るさの落ち方も相まって玄人好みのする,雰囲気のある描写ができるカメラだと思います.
XA のレンズの評価が実力よりも低めになった原因としてもう1つ考えられるのは,絞り優先オートだからだというのもあると思います.XA2などですと,プログラムオートなのでどうしても割と絞られてしまうのですが,XAは開放絞りを頑張って使えてしまうので,そうすると,あらが目立ちやすいのだと思います.
XA では絞り羽根が2枚で,ちょっと絞ったときのボケが余りきれいでないのと,絞り込んだときの輝点があまりきれいに写らないのは,上記の諸問題よりも気になります.しかしまあ,これは,廉価なカメラなので仕方がないのではありますが.この点についてはやはりCONTAX Tは優れていますし,もうちょっと古い固定鏡筒カメラや,その前の蛇腹型(レチナとか)の出番になります.焦点距離が長く口径も大きくてよくボケますしね.結局,いつものことながら,使い分けでしょうか??
 日浦
日浦  2020/08/27(Thu) 00:45 No.1741
2020/08/27(Thu) 00:45 No.1741
1957年マミヤ光機製 ビューファインダーレンズ固定機
レンズ:トプコールM35mmf2.8(4群6枚ガウス型)
シャッター:セイコーシャMXL(ライトバリュー)1/500-1,B
セルフコッキング,レバー巻き上げクランク巻き戻し,カウンター自動復元
距離目測、最短0.6m
オリンパス35が先鞭をつけ、流行した35mmレンズ固定装着のオーソドックスなビューファインダーカメラのひとつ。国産では最も早くライトバリューを採用。ただしシャッターは倍数系列ではなく、絞りとの連動もしていない。単独露出計の目盛りを移し替えるだけ。今となっては絞りシャッターカップリングはないほうが便利なのでこれでいい。
同時発売のマミヤワイド(距離計連動)とともに、通常は新種ガラス使用と銘打たれたセコール35mmf2.8(4群6枚)が付いているが、ワイドEにはトプコールが装着されたものがある。
ワイドにもトプコール付きがあるとするサイトがあるが、現物も画像も見たことがない。
マミヤは多くの他メーカーにボディを供給していたが、逆にマミヤボディにセコール以外のレンズ銘柄は、マミヤシックスのズイコー、シムラーがある。
さて、ホースマンプレス104に装備されたマミヤセコール105mmも東京光学製といわれていて、マミヤワイドのセコールはマミヤ自社製なのか、東京光学製の刻印違いなのか、別とするとなぜ東京光学から供給を受けたのか、自社製供給が不足するほど当時人気だったのか?大変疑問がある。
写りは大変良好だが逆光に弱くゴースト、グレアが出やすい。当時の広告では内部の迷光対策を宣伝しているが、しっかりしたフードは必需品。
このスペックにしては過剰な重量で、ライカM+35mmよりだいぶ軽いのだが、レバー巻き上げに予備角がなく操作感は滑らかさに欠け、Mライカより持ち重りがしてしまうのは不思議。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/09/02(Wed) 22:22 No.1742
2020/09/02(Wed) 22:22 No.1742
RFの最初期型が55年のAです。本体に厚みがあり、ビハインドシャッター。
テッサー型45㎜F3,5は、レンズ交換型ミノルタ35の梅鉢レンズにほぼ同じ物。
レバー巻き上げ、セルフコッキング。57年にはブライトフレーム付きのA2になる。レンズも45mmF2,8になる。
58年、100mmのレンズと、45mmの交換できるようになったのが最終型。(この間細かな改良がある)
私の個体は、シャッターがコーナンフリッガーから、5枚羽のシチズンに成った、後期型F3,5のAです。レンズほぼ梅鉢なので、写りは良い。コートの問題で、カラーには強くない。
本体に厚みが有る。加えてレバーの巻き上げ角が大きい。保持性は悪い。
 ナースマン
ナースマン  2020/09/26(Sat) 10:16 No.1750
2020/09/26(Sat) 10:16 No.1750
スプリングのパール。48年135に成り、沈胴のコニカⅠ。ヘキサーF4,5、3,5,2,8付。
51年コニカⅡ。此れはダブルヘリコイドと言われる半沈胴。
ヘキサノンF2,8付。補色RF。シャッターチャージは手動。
曲線型のレンズボードのエプロンが特徴。55年レンズをヘキサーF3,5、2,8にした普及品ⅡB。
56年ⅡA。レンズをヘキサノンF2へ、Ⅱの半沈胴にストッパーを付け、やっと固定鏡胴へ。普及品としてヘキサーF3,5付ⅡBm(此れは、ⅡBと違い、固定鏡胴)
57年Ⅲ。前面レバー巻き上げ。セルフコッキング。ブライトフレーム付。58年ⅢA。パララックス修正の生きているファインダーへ。
私の個体はⅢA。ノブ巻き上げ、シャッターチャージだが、Ⅲより小型。私Ⅲも持っているが、前面巻き上げよりⅡAの方が使いやすい。(Ⅱ、ⅡAは、アイトレットが無い、ケースが必要)
ⅡAもⅢも48㎜F2ヘキサノン。此れはズミクロン並みに使えるレンズ。ⅡAは私にとって現役カメラ。
画像はⅡです。
 ナースマン
ナースマン  2020/09/26(Sat) 11:43 No.1751
2020/09/26(Sat) 11:43 No.1751
現物写真よりも、当時の広告の方が貴重かもしれません。
ミノルタAは、学校の先生がお持ちでしたので印象に残っています。持たせていただくとごろっとして驚きました。
45mm梅鉢は、24x32用設計のために、ライカにつけると四隅の解像力が不足するという話を聞いたことがありますが、レンズシャッター機は一足先に24x36だったのでしょうか。描写はいかがでしょう。
コニカIIAは、程度が良い個体はなかなか見かけません。
ヘキサー50mmは、4枚玉かと思っていましたが、ヘリアー型5枚玉だったんですね。認識を改めました。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2020/10/04(Sun) 11:01 No.1752
2020/10/04(Sun) 11:01 No.1752
カメラ発売当時の広告。細かいデータと共に、企業の当該機の特徴が、端的に表現されています。確実な一級資料だと思います。
梅鉢レンズ。(ミノルタ35の梅鉢は24×32なので、周辺が流れる)此れは、使ったことのない方の偏見?
ニコンS(24×34)とS2。同じレンズで、問題ありません。
ミノルタAのレンズ。レンズシャッター機ですが、ビハインドシャッターなので、ミノルタ35の梅鉢とほぼ同じ時期の設計と思います。梅鉢にはF2,8の後期型が有ります(A2にもF2,8がある)
本家のテッサーもF2,8は周辺が流れます。均一に流れさすか、中心部を鮮明にするか。この設計思想の差だと思います。
F3,5モノクロは良いのですが、カラーは?です。F2,8はカラーも良いので、コートが変わった?のだと思います。
ヘキサノンF2,8。PHOTOGRAPHYの広告はⅡAの物ではなく、Ⅱの物です。従ってレンズはヘキサノンF2.8です。コニカは周辺部の流れを均一にするため、テッサー型のヘキサーではなく、ヘキサノンにしたと思います。
 ナースマン
ナースマン  2020/10/05(Mon) 13:13 No.1756
2020/10/05(Mon) 13:13 No.1756
1970年 富士フィルム製 セレン光電池によるプログラムEEレンズシャッター機
レバー巻き上げ,クランク巻き戻し
1967年発売の初代フジカコンパクト35を、プラスチックと軽合金により軽量化(440g→360g)
レンズ:フジノン 38mmf2.8、4群5枚、前玉回転、目測。
シャッター:セイコーLA (プログラム1/250-1/30、B、マニュアル絞りはX接点:1/30固定)
フィルム感度ASA25-200
当時としては軽量の初級機.キヤノンデミのようなモナカ構造。
レンズ周辺や感度表示はプリント。操作感触は極めて安っぽい。
ただ当時のカメラ毎日カメラ白書の成績が、驚異的な高画質だったので興味を持ちました。
レンズ突出量はそれなりにありながら、5枚構成というのは小型化のための多数枚構成ではなさそうで期待できます。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2021/01/30(Sat) 21:39 No.1786
2021/01/30(Sat) 21:39 No.1786
とは逡巡したのですが先述のⅢ型をお話するにはこの機種にも触れませんと片手落ちと思いましたので、ご紹介いたします。
コニカⅡBは四年ほど前に発表されたコニカⅡの普及機として1955年にⅡ型のラインナップに加わった機種です。
詳しい説明はWeb上にいくつか見る事が出来ますのでご参考にされると良いと思います。
Ⅰ型の武骨な印象を和らげるために、エプロン部に曲線が取り入れたデザインがこのカメラのモダンさが表れています。
レンズはヘキサ―50mm F2.8と画像のF3.5 です。
このレンズをWヘリコイドの沈胴式鏡胴に入れています。
シャッターは定評の有るコニラッピッドS B、1〜1/500です。
先行したⅡ型にはTが用意されていましたが、ⅡBは普及機の位置づけで省略されています。
昭和30年にF3.5付きで27,000円。今日ならざっと五十数万位ですかね。フルサイズ機に標準域のズームレンズ付きの値段くらいです。
工作精度が素晴らしく、少しの整備で実用になる個体も多いと聞きます。美しくて小さくて少し持ち重りのするカメラです。
 efunon
efunon  2021/01/31(Sun) 00:43 No.1789
2021/01/31(Sun) 00:43 No.1789
れんずまにあ様が投降した、ライトコンパクト以前に、コンパクトが有ります。コンパクト35と、ライとコンパクト。レンズ、シャッター共同じですが、重さ以外に差が有ります。
ライトコンパクトは、プログラムシャッター。Aを外すのは、フラシュ用。30sでの絞りだけです。
これに対して、コンパクト。Aを外し、絞り、シャッター速度共にマニュアル設定ができます。
当時のセレンが不安定な現在、コンパクトは、マニュアル撮影ができる。今と成っては、此方の方が生き延びている。
ライトコンパクトS,コンパクトSはRSを装備、F2,5にアップグレイドしている。(加えてセルフシャッター装備)コンパクト35、ライトコンパクト(コンパクト35S,ライトコンパクト35S)共に写りは抜群。コンパクトカメラを発売したフジの意気込みが感じられる。
私、コンパクト35とライとコンパクト35S持っている。がコンパクト35Sが手に入らなかった(数が少ない)コンパクト35S,めぐり合うと速買いだと思う。
当時のフイルムの性能。これ等のカメラ、ASA設定が200迄しか無い。現代の400フイルムは使うのが厄介。現代では、記録用の100フイルムがベストと思う。
 ナースマン
ナースマン  2021/02/01(Mon) 17:05 No.1795
2021/02/01(Mon) 17:05 No.1795
此れは、昭和29年発売のニコンS2のコピー版(一般にRFコンタックスのコピーと言われれが、時代背景を考えると、私はニコンS2のコピーだと思う)
フォーカルシャッターを、コパル500sのレンズシャッターに、レンズを固定式にした物。
外観は、ほぼニコンS2に類似。但しファインダーは、等倍ではなく0,7倍。仕上げもニコンには劣る。
レンズが2種類。ヤシノン45mm、F2,8付(4群5枚、12500円)とF1,9付(6枚玉、18000円)共に富岡製。
F2,8でも5枚玉のクセノター。当時から写りには、評判が。
私の個体は、F2,8の方。確かに写りは良い。然し、価格の差、ニコンとは差が。
私、別に父の形見、ニコンS持っているが、仕上げが遥かに劣る(特にメッキ、作動感)
とは言え、後のセレン露光のヤシカリンクス(F2.8)CDS自動のエレクトロ35(F1,8)の基礎を作ったレンズである。
 ナースマン
ナースマン  2021/02/01(Mon) 17:47 No.1796
2021/02/01(Mon) 17:47 No.1796
コンパクト35はマニュアル露光ができるとは、認識していませんでした。
当時のEE、任せ切るには不安があり、またマニュアル露光の腕に覚えがある方がまだまだ多かったと思います。
当時距離目測も当たり前のように使いこなしていたのでしょうね。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2021/02/01(Mon) 18:31 No.1798
2021/02/01(Mon) 18:31 No.1798
1955年、フイルム会社の団体が<芽生えカメラ>を構想。
57年これにフジが呼応したのが、57年のフジペット。
此れは120フイルムを使った66ボックスカメラ。
小学生対象と言うことで、黒、赤、黄、緑、グレー、橙、金のカラーも有った。61年にはセレンEEのフジペットEEも出来た。
57年、此れを135にしたのがペット35。こちらはフジペットの兄貴分。
中学生用?45㎜F3,5フジナーK、200sコパルシャッター。目測前玉回転3枚、此れは光学ガラス3枚玉。
プラスチックとアルミ製で300g。本体もフジペットより小型。
このカメラ、フジが本気で作った、コンパクトフジカの元祖。
レンズがしっかりしている 。隅は流れるが、なだらか。
ノバー付きのイコンタ35と差が無い。いかにも銀塩と言う画像。
現代の高級フイルムより、記録用フイルム辺りが、よく合う。
全て手動であるが、銀塩写真機の基礎が学べる。
構造が簡単で、故障が無い。私のように目が悪い老人にも使える。
此方も黒、赤、緑の3色ある。私の個体は緑。
 ナースマン
ナースマン  2021/09/02(Thu) 16:51 No.1901
2021/09/02(Thu) 16:51 No.1901
大学時代、年上の後輩がFuji Petで写真入門したと話しておりました。
当時は裏紙つきロールフィルムがとりわけ安かったこともあり、今では想像できない子供用ブローニーカメラが成立したのでしょう。
単玉70mmf11でシャッター速度1/50とB、多分晴天屋外ではネオパンSSでf16からf22の条件でしょう。
そうすると固定焦点でも被写界深度が深く、6x6の大画面で拡大率が低く、露光不足や過度による諧調の低下を救ってくれる。
大伸ばしはしないので多少のボケは気にならない。
ペット35はブローニーの有利さを捨てた代わりに、短焦点のメリットを最大限使って明るいf3.5でも実用距離を十分深度に入れられます。
しかもお子様用ではもったいなさすぎるほどの3枚玉。
だってツァイスイコンやレチナのベーシックも3枚玉なんです。似た対象ユーザーのフェラニアは単玉です。
最近トリオターやカッサーなどの3枚玉を高く評価していますので、フジのこだわりは素晴らしい。
絞りの選択肢が大幅に広く、開放なら屋内や夕方でも撮影可能でしょう。
コニレットと競合するでしょうが、汎用フィルムが使えるペット35が圧倒的有利かと思います。
総じて、子供用とは思えないほどの高いスペック。
こういうのを投入してくるのは、やはり日本人の凝り性、子供を軽視しない真摯さでしょうか。
将来のヘビーユーザーを養成する意図は、ナースマン様を拝見すると、完全に果たされたと確信します。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2021/09/02(Thu) 18:39 No.1902
2021/09/02(Thu) 18:39 No.1902
ここではすでに1型が紹介されていますが、僕としては距離計搭載機の精度にしびれました。もちろんファインダの明るさや繊細なフレーム、ボディの小ささ、美しさ、巻き上げ操作の軽さなども。
特に、入手したIII型がシンプル形状を保ったまま距離計を内蔵しており、かつ、コンパーシャッターという最高の仕様でした。窓枠もなし、革も緑で、僕の理想のモデルです。ただし要整備(シャッター粘り、距離系ズレだけですが)なので、どうするか考えているところです。
定点露出計内蔵の最終期、Werramatic や、オートアップと同等のアクセサリも順次届く手はずになっています。
拙宅にもいくつかありますが,十分使いこなせておりません。
交換レンズがまた魅力的ですね。
近接デバイスがあったとは全く知りませんでした。本編でも深く掘り下げられるのでしょうから、楽しみにお待ちしております。
計画経済ならではの仕上げの荒さが少し目につきますが、愛すべきシステムと思います。
初期型のテンポールシャッターを修理してくれるところがないかなあ...
Werra5, Tessar 50mmf2.8, 開放,1/30, 富士フィルム業務用400
 れんずまにあ
れんずまにあ  2024/08/31(Sat) 17:15 No.2587
2024/08/31(Sat) 17:15 No.2587
すでにかなり、情報過多ですが・・
https://shiura.com/camera/werra/index.html
シャッターですが、検索すると、修理ノウハウのありそうな修理屋さんが、数件、見つかります。
「ヨコタカメラ」さんはウェブでPrestorの修理をされた記録を記載されています。
https://yokota-camera.com/wp/werra%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%81%AE%E4%BF%AE%E7%90%86/
「まつむらかめら」さんは X でバックシャッター付きのシャッターをいじるのが好きだと
書いておられるので、Prestor は対応できるのではないかなと思います。
https://x.com/search?q=%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%A9%20from%3Aclassicalcamera&src=typed_query&f=live
うちは、ジャンク4台セットを買ったのですが
I : Vebur シャッター粘り --> 修理した
III : Compur シャッター粘り --> プロに依頼するか検討中
V : Prestor 1/500秒仕様 完動
mat : Prestor 1/750秒仕様 シャッター不動、メータ不動
という具合でした。mat は部品取りにお譲りしてもいいかもです。吊り輪も欠品ですので。
I や mat は少し整備のため分解しましたが、ボディ、裏蓋、距離系フレームなどがダイキャストで、
プレス部品の箇所を裏打ちするように入っており、思った以上に硬派な作りだと思いました。
レンズもまちがいないものですし、なかなか合理的な設計になっている感じがします。
ただ、シャッターが確かに難点かもですね。
接写アクセサリは添付画像のようなもので、2種類あり、これは寄れる方です。
 日浦
日浦  2024/08/31(Sat) 22:31 No.2588
2024/08/31(Sat) 22:31 No.2588
といってもX入ってないので見られなかったのですが(笑)アメーバブログやってはおられるようです.ぼちぼち検索していきます。
オートアップは今まで見たことがない形状で、とてもそそられますね。
続々色々と到着予定ですね。記事を楽しみにしています。
私も久しぶり引っ張り出して動かそう...
拙宅には1型とWerramaticが,稼働しています。
シンプルな1型は、PRESTORシャッターの遮光機能が故障しており、巻き上げで全開してしまうため、レンズを覆ってやる必要があります。
まあそれは、セルフキャップが故障しているフォーカル機でも同じなので、ちょっと面倒だな程度ですけど。
WerramaticのPRESTORシャッターは大変快調で、露出計も動いているので操作して楽しいです。ただし交換レンズが薄い曇りがあり、標準だけで使うのなら,非常に快適な上下像距離計に後ろ髪を引かれますが、とりあえず1型でいいのかなとも。
しかしこれで大衆機なんですよね。すごいなあ。
Werramaticと交換レンズ35mm,100mm
 れんずまにあ
れんずまにあ  2024/09/01(Sun) 21:16 No.2590
2024/09/01(Sun) 21:16 No.2590
この種のEEコンパクトカメラは初代キヤノネットからしてF1.9で、その後もスペック競争のため F1.7 近辺のレンズを搭載した大きく重いカメラが主流でした。写真のフジカコンパクトデラックスもフルマニュアル撮影が可能ですが、約650g とかなり重いです。
しかし、コニカC35(じゃ〜に〜コニカ)の出現により小型化へかじを切ります。コニカC35やフジカGER(330‾350g)のように軽量化が進みますが、多くはEE専用機でマニュアル露出ができないとか、電池がないと動作しないものがやはり多数派です。
そのような中で、メカニカルシャッターを搭載し、電池がなくても動作する限られた機種が、オリンパス35RC(410g)と、このリコー500G/GS/GX(420‾440g)になります。初代キヤノネットや前述のフジカコンパクトデラックスからすると F2.8 へと暗くなりましたが重さが 2/3 以下に軽量化され、ボディの幅やレンズの突出量も相当短くなりました。
35RCに対するリコー500系の利点は、マニュアル露出時も露出計が動作すること(ファインダ内で適正絞り値が指針表示される)、シャッター速度の低速側が 1/8 まであること(オリンパス35RCは1/15まで)の2点が大きいと思います。
リコー500系共通の特徴
・メカニカルシャッター 1/8〜1/500秒, B(ビハインドシャッター・ビハインド絞り)
・針押さえ式シャッター速度優先EE
・4枚羽根絞り(猫の目でなく辺の丸い正方形) F2.8〜F16 手動設定可能
・露出計がマニュアル露出時も動作
写真のモデルは500GSで、500Gとはデザインが違うだけです。500GXになり、シャッターロック、バッテリーチェック、シャッターチャージインジケーター、多重露出機能が追加されます。
さらに興味深い点として、ほとんど国内では見かけられない(よってあまり知られていない)ようですが、台湾リコー製の類似機種があります。スペックはほとんど変わらないようなのですが、よく調べるといろいろ違いがあります。
・台湾製はフレームが樹脂化されている(フィルムレールが樹脂の黒色になっている)
・台湾製はボディの構造が違う(国内製はキヤノンデミに似たモナカ構造で、裏蓋もアイピースごと全体が開くが、台湾製は深堀りのトップカバーと、普通の裏蓋構造になっている)
・台湾製にはワインダーが取り付けられる!(スプリングモーター)
前述のように国内製で比較するとオリンパス35RCが最軽量なのですが、調べると、RICOH 500RF が公式380gで最も軽いようです。
国内生産 RICOH 500G, 500GS, 500GX 420〜440g
台湾生産 RICOH 500RF, 500ME, GX-1 380〜400g
リコー自身のリスト https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/ricoh-filmcamera/cameralist/1961-80.html
こちらには 500ME しか書かれておらず、500RF, GX-1 が出ていません。
外観参考 https://www.flickr.com/photos/zombiebirdhouse/9629430674
500ME に関する記事、貴重なスプリングワインダー装着時の画像 https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/2018/06/500me-b1bb.html
500RF に関する日本語記事 https://blog.goo.ne.jp/tomys800/e/9a3ef176080b4f3ad87863800885cc6b
500RF の取扱説明書、末尾に重量 380g と書かれている https://www.cameramanuals.org/ricoh_pdf/ricoh_500_rf.pdf
距離計連動の35mmフルサイズメカニカルカメラで最軽量は、この500RFではないかという気がします。
手元の500GSは、リコーエルニカFと2台セットで送料込み1,000円のジャンクで購入しました。向こうが見えないぐらいファインダが曇っており、露出計不動とありましたが、ファインダは清掃でとてもクリアに。露出計も動作しております。裏蓋のモルトなど整備してから試写してみる予定です。全体に操作系が素直で操作感も軽く、シャッターも針押さえ式らしくストロークは長いが落ち方もよく、(試写結果はまだですが)なかなか良いカメラです。同じカメラが SEARS や HANIMEX ブランドでも売られていたようです。
 日浦
日浦  2024/10/20(Sun) 00:25 No.2617
2024/10/20(Sun) 00:25 No.2617
1955年頃発売の距離計連動カメラです。レンズは富岡光学TRI-LAUSAR 4.5cmF3.5
シャッターはコパルで B・1〜1/300 セルフタイマーあり。
枚数カウンターは手動セット・順算式。ノブ巻上げ、巻き戻しでセルフコッキングではありません。
1950年代半ばに現れ、4〜5機種の35mm距離計連動式カメラを発売した後に姿を消してしまったメーカーの最初の製品のようです。35IIAという機種が存在する為、35ISを35(大文字のアイではなくローマ数字のI)Sとする説もあります。
しかし情報が少ないですね。海外のオークションサイトにもチラホラ現れますので、さほど小さなメーカーだったとは思えないのですが。
レンズ・シャッターとも当時としては、割と上級品で組んであると思います。ただ、内部の歯車やアーム類は薄めの真鍮製で、耐久性には問題があるかも知れません。
私は、このカメラの造形が気になって手に入れました。軍艦部の直線と曲線が混じりあった段付きの柔らかいな姿、カメラ本体を薄く見せようとフィルム圧板の取り付け部をわざわざ裏蓋をプレスで押し出している努力。どちらも他より綺麗に見せようとする熱意を感じ、どこか海外からの品のような個性を感じます。
どなたかこのカメラメーカーについてご存じでしたら、何かご教示頂けると嬉しいです。
かつてのカメラコレクターズニュースに執筆された方々のような、真のコレクターでいらっしゃいますね。
私は戦後黎明期の産業について全くわかりませんが、カメラレビューも無くなり、粟野様も身罷られた現在、このような高度な情報の行き場がなくなっています。
受け皿があればよろしいのですが...
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/02/08(Sat) 22:20 No.2722
2025/02/08(Sat) 22:20 No.2722
申し訳ありません。私はカメラコレクターと言われるほどの者ではございません・・。その証拠に最も高価なカメラでも1万円台、殆どはワンコインから数千円で手に入れた物ばかりです。「何だかボロっちぃけど、動くかな?」というブツをリサイクルショップで手に入れ、撮ってはバラしの繰り返しをするのが好きなだけです。ですから自慢できるようなカメラは持っていません。私が変わったカメラばかり投稿するのがいけなかったのかもしれませんね。今度はもっと一般的なカメラも混ぜてご投稿しますね。
ただ、フィルムカメラに関するコンテンツが確実に減りつつある現在、こちらのような素晴らしい情報交換の場が存在するのに便乗し、「こんなカメラもあったよー、こんな風に動くよー」とご紹介する事でフィルムカメラの楽しみを一人でも多くの方に共有していただきたかっただけです。
1958年発売の距離計連動35mmカメラ
レンズはヘキサノン48mmF2.0(5群6枚)
シャッターはセイコーシャMXL(B・1〜1/500)
重量は800g(実測)定価34,700円
巻き上げは鏡胴脇のレバー2回押下
発売数か月後により明るい50mmF1.8レンズ搭載機が追加されました。
一度は覗いてみたくなる「生きているファインダー」のコニカIIIAです。
III型の軍幹部を大幅に改めてプリズムブロック3ケとレンズで等倍ファインダーを実現しています。ブライトフレームはパララクス補正に加えてフレームの大きさまで変化させるという複雑な動きをします。ブライトフレーム採光窓を追加し、重なり合った2枚のマスクフレームが移動することで画角の変化を表現しています。
プリズムを使用していることでファインダー内への埃侵入や曇りの発生が抑えられており、製造から60年以上を経ても視界はとてもクリアです。接眼部・対物側ともプリズムが露出していますね。
IIIA・IIIMで使われたプリズム式のファインダーは後継のSシリーズではコストと重量削減の為かガラスとミラーの組合せ式に戻りました。
またIIIAになってセルフタイマーレバーと「猫の手」巻上レバーのデザイン、巻き戻しノブが変更されています。
1959年発売の距離計連動・露出計連動35mmカメラ
レンズはヘキサノン50mmF1.8(5群6枚)
シャッターはセイコーシャSLV(B・1〜1/500)
重量は825g(実測)定価36,500円
巻き上げは鏡胴脇のレバー2回押下(ハーフ時は1回)
IIIA発売の翌年、セレン電池式連動露出計とハーフフレーム撮影機能を追加したIIIMが発売されました。IIIMには48mmF2.0レンズを搭載したモデルは存在しなかったようです。
セレン電池パネルは大型の跳ね上げ式で、折り畳むとファインダーや採光窓を塞ぐ形になります。ただ、このヒンジがセレン電池パネルの枠と一体の薄いプラスチック製で、開閉には気を使います。事実、出回っているIIIMのほとんどの機体ではヒンジ部分に破損やヒビが見られます。ストラップで首から下げる時も引掛けないように注意しています。
ハーフフレーム撮影には付属のハーフマスクを使用しますが、これも失われていました。このマスクの造りは、アパーチャーのマスク部分とアームを押すためのツバが一体化されていて結構剛性の高いもの。巻取りスプールの上部にあるアームがツバで右側に押されると、猫の手1ストロークでハーフ分巻上げとシャッターチャージが同時に行われます。ハーフ使用時には背面の窓に赤マーク出ます。ただ、ハーフで撮ると中望遠になってしまうので、どれくらい需要があったのか・・。
またこのIIIMでホットシューが装備されました。
コニカIIIAの後に発売されたIIIMではシャッターもセイコーシャMXLからSLV
へと変更されました。
これは新設された露出計のメーター部分がIIIA迄のセルフタイマーのスペースに設置された事が理由です。MXLはシャッター内部にセルフタイマーが内蔵出来ないこと、SLVは当時新しい製品だったことで採用されたと言われています。
シャッターの変更に伴い、外観はもとよりシャッタースピード系列も変更されました。
MXLはB・1・1/2・1/5・1/10・1/25・1/50・1/100・1/250・1/500
SLVはB・1・1/2・1/4・1/8・1/15・1/30・1/60・1/125・1/250・1/500
大陸系列から倍数系列になり、1速増えています。
更にLV値でのリングの連動が無くなり、絞り・スピードも単独で操作できるようになりました。LV値は鏡胴下に表示されます。
IIIMは最終型しかもハーフ切り替えなので以前から気になっていましたが、ハーフマスク紛失個体が多く、近所にレンズ程度が良い個体があるものの、セレンカバーが破損欠損していたりで結局手にしたことがありません。
マスクは自作すればなどと気楽に考えていたら、そんな複雑なシステムなんですね。紛失個体に気軽に手を出さないでよかったかも。
その点ではオーソドックスな最終発展型のIIIAの方が現実的かもしれません。
レンズはf2とf1.8の描写の差など興味深いです。
実用上1/3絞りが大きな違いにはならないと思いますが、セールスでは大差になった時代なのでしょう。
それよりも、シャッター速度が倍数になった方が大きいですね。まあ今使うにあたって大陸系で困ることは少ないのは確かですが...
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/02/23(Sun) 10:05 No.2740
2025/02/23(Sun) 10:05 No.2740
私もマスク部分は自作するとして、アームを押すのにどうすればよいのか思いつきません。軍幹部を開けて対処するにも、戻すのが面倒ですし。
わずか5mm程度水平に押すだけなのですが、結構左方向へ押し返す力が掛かっています・・。純正のマスクが付いている機体を探すのが一番かと思いますね。
1959年発売
フジの35mm固定鏡胴マニュアル露出コンパクトカメラ。
シャッターはコパルで B・1/25〜1/200
レンズは3群3枚フジナーK 4.5cmF3.5 最短撮影距離は0.5m弱
定価はケース付きで¥41,000 重量は実測295gです。
枚数カウンターは手動セット・順算式。シャッターはレンズ鏡胴脇のレバー左手側を下げてコッキング、右手側を下げてレリーズ。その後、背面の小さなレバーを右にスライドさせてフィルム巻止め解除となります。このレバーはフィルム巻き戻しの時にも使用します。
貼革は他に赤・緑色も確認、機種名はレンズ右上ボディに刻印されていますが、少数ながら機種名をプリントしたシールを貼付した機体も存在を確認しましています。
言わずと知れた35mm子供用カメラの決定版、ペット35です。定価41,000円は当時の物価を考えれば現在の5万円くらいになるでしょうか。
スペックだけで見ればコンパクトなサイズで必要最低限の機能、35mmフィルム入門用としても十分の出来だと思います。3枚玉の写りが良いのは現在も多くのファンがいることで証明されています。私もファンの一人です。ストラップが使えるようアイレットが両側に付いているのもポイント高いです。
フジペットシリーズは、ブローニー版は固定焦点の単玉レンズ、シャッターがBと1/60だけで絞り動作のみフジペット(1957年発売)は手動、フジペットEE(1961年発売)はセレン電池により変化するものでした。
フィルム室に貼ってあるシールには「ネオパンS〜SSS」のイラスト。「SAFETY FILM」の文字も確認出来ます。その意味はネットで調べるまで分かりませんでした。
1958年発売 レンズ固定式35mmカメラ、BALDESSA-1に連動式距離計を追加装備したモデル。1bでは更にセレン電池による非連動式露出計を備えます。
レンズはColor-Baldanar 45mmF2.8(3群3枚)
シャッターはプロンターSVSでB・1〜1/500、LVによるSSと絞り環のカップリング有り、セルタイマー有り。ハーフミラー処理をされたファインダーにはブライトフレーム。枚数カウンターは底面の巻上レバーの影に有り、手動セット・減算式。
全体的に丸々とした可愛らしいデザインを持っています。やや独特な操作系を持っています。軍艦部にはアクセサリーシュー以外何も無し。レリーズは鏡胴脇、フォーカス操作はその上のダイヤル回転で行います。
底部にコニカパールに使われてたような形状の巻上げノブ(折り畳み式)が配置され、これを起こすと枚数カウンターが見えます。巻上げノブ半回転で1枚巻上げ。カメラのスタンドを兼ねるT-RレバーをR側にスライドさせると固定されていた巻き戻しレバーがパっと立ち上がります。突き出た三脚穴の金具にはフィルムリマインダーの小さな窓が有ります。
本機は使って見ると見易いファインダー、フォーカス操作も慣れれば右手人差し指で出来るなど、変わってはいますが良く練られたカメラかと思います。少々傷のあるレンズですが、実写はヌケも良く華やかに写りました。
機能的にはレチナIIISと同じですが、皆様ご存知の通りマウントが微妙に違っていてレチナとは互換性がありません。
標準クセナー50mmf2.8の写りは満足行くものでしたが、数年後海外通販でテレクセナー135/4を入手できた以外全く交換レンズが入手できず、諦めて行きつけ店舗で下取りに出したところ、135でも珍しいのか即座に買い手がついたようです。
おそらくご紹介のバルデッサと同じボディで、独特の操作性ですね。
ごろごろしたハンドリングで、ケースがあったので取り落とすことはありませんが、底部のキーでフィルム送りするので裸で使うとちょっと怖い。
最近トリプレットがすごくよく写ることを再認識し、各社のベーシックな小型カメラに興味が向いています。
画像バルダマチックIII バルダクセナー50/2.8開放,1/30,フジカラー業務用400
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/03/15(Sat) 18:56 No.2762
2025/03/15(Sat) 18:56 No.2762
レンズ交換式があったのですね!写真を見ると確かに同じボディのようです。ちょっと興味がでちゃいますね。
ブライトフレームを綺麗にするのにトップカバーを外したら、空きスペースが・・1bに露出計を入れるための空間がポッカリ空いてました。
1972発売。距離計連動式プログラム自動露出カメラ。
レンズはミランダ/ソリゴール 38mmF2.8 撮影距離は0.9m〜∞
電子シャッターはセイコーESF(SS4〜1/800)でシャッターをロックするリングを備え、ソフトレリーズも標準。フィルム感度はASA25〜800
セルフタイマー無し、ホットシュー以外に外部フラッシュ用ソケット有り。±1段の露出補正有り。
当時一眼レフ専業だったミランダカメラ唯一の距離計連動コンパクトカメラです。
コニカC35の大ヒットの後を追うように多くのメーカーから同じようなサイズのコンパクトカメラが発売されました。ミランダカメラもカメラの小型カメラブームの流れに乗ったようです。
センソレットのボディはC35より50グラムほど重く420gあり、持った感じもしっかりしています。
電池は現在は生産を終了しているHM-N(NR52)型水銀電池 1.35Vを2個使用しますが、LR44の高さをかさ上げした物を2個入れることで代用できます。
この大きさのカメラには珍しい露出補正ノブを持ち、専用フラッシュを使用することでフラッシュマチックも実現。またテレ/ワイドコンバーターレンズが用意されていました。クロームボディには6色の貼革バリエーション、ブラックボディも存在しました。
ファインダー内表示はC35のような指針は持たず、フラッシュマチックの時にだけ絞り値が表示されます。以上の内容でC35とほぼ同価格はミランダカメラの企業規模ではかなり頑張った方でしょう。
写りは線が細くやや寒色系で、コニカがC35で狙った写りとは路線が違うように感じます(私の個体だけだったらすみません)。
1972年発売の35mm距離計連動・SS優先自動露出カメラ
レンズはキヤノン40mmF1.7(4群6枚)撮影距離0.8m〜∞
シャッターはコパル(B・1/4〜1/500sec) フィルム感度はASA25〜800 セルフタイマーあり
ファインダーはパララクス自動補正あり 絞り値表示あり カウンターは自動リセット・順算式で、表示が1になるまでシャッターは切れません。使用電池はH-D水銀電池1ケ(LR44で代用できます)
1961年に高機能・低価格で発売されて業界を震撼させたキヤノネットの3世代目にして最終機。2世代目のニューキヤノネットとの違いはバッテリーチェックボタンの有無や巻き戻しノブの形状などごく僅かです。
絞りリングをA位置から外せばマニュアル撮影が可能、その場合露出計は切れます。重量は615g。同時代の競合機種コニカC35FDに比べ大きさはさほど変わりないが1.5倍近く重い。
小型レンジファインダーカメラとしては優等生で、安定して良く写ります。欠点らしい欠点も無く、逆にそれがつまらない、と思う事さえあります。
その為か、せっかく綺麗にレストアしたのに何故か持ち出さない1台です。
10年間以上販売され続け、販売台数は100万台以上と言われていて、比較的良く見かけますが状態の良い物は少なくなりました。
私,今は「狸おやじ」の名で中判カメラやシートフィルムの紹介をしておりますが,若い(少年の)頃にこのキャノネットQL17とコニカC35FDを使っておりました。どちらもコンパクトで使いやすいカメラですが,仰るようにQL17はC35FDと比べると少し重い。F16に絞り込んだ時の解像度を四つ切プリントに拡大して比較したことがありますが,C35FDの方がQL17より(特に中心付近で)良い結果でした。当時,F値の小さいレンズ程性能が良いと考えていた私には意外な結果でしたが,これがきっかけとなり,その後欧州でライカMとコンタックスGを購入し,やがて中判テヒニカを入手することになりました。レンジファインダー機の利点は,SLRより小型軽量になるだけでなく,フランジバックの短い広角系の優れたレンズを搭載できる点だと知ったのも,この2つのカメラが最初でした。自分の「レンジファインダー遍歴」の原点を見るようで,とても懐かしく拝見いたしました。
 狸おやじ
狸おやじ  2025/03/28(Fri) 21:44 No.2782
2025/03/28(Fri) 21:44 No.2782
何とキヤノネットやC35FDをお若い頃にお使いになっていてのですね。羨ましいです。
これらのフィルムカメラを手にしたのが還暦近い5〜6年前、新品の頃にお使いになっていた方からのリアクション、とても嬉しいです。
私には大きなフォーマットは(今からでは)難しそうですが、写真機ならどんな物でも大好きな私は大きくてメカニカルなカメラに関する情報も楽しく拝見させて頂いております。
これからも暫くの間コンパクトカメラを中心に投稿をする積りです。偶にクスっと笑っていただけたら幸いです。
小型メカニカルカメラの詳細な解説を興味深く拝読しております。今後とも宜しくお願いいたします。私も機械式のカメラが好きですが,資金と時間が無いので収集は諦め,気に入った機材を少数選び,徹底的に使うスタイルを楽しんでいます。
コニカC35FDは,私が高校生の時に新品で買った「スタートカメラ」でした。
3万5k円程でしたが,自分の小遣いを貯めて買った最初のカメラで,長く愛用しました。ヘキサノン38mmは性能の良いレンズで,F16で撮影したポジ画像を拡大して比較すると,友人のSLR(Pentax)の35mmの画像より高解像でした。広角のレンジファインダー機は当時の(高価で重い)SLRsより高画質だったのです。れんずまにあ様の解説(No. 1721)にあるように,C35FDはフラッシュマチック機構付で,ストロボをシューに取り付けると距離計に連動して絞り値が調節されオート撮影ができる。また,露出計の針を絞り値に(SSを調整して)合わせると背景光量とストロボ光量を一致させる日中シンクロ撮影ができる。全速シンクロ同調(‾1/500秒)のレンズシャッターを駆使して,日中シンクロの基礎(リンホフテヒニカ,No. 2555-56)を学びました。
これに味を占め,次はマニュアルでも撮れるレンジファインダー機として,キャノネットQL17GIIIを購入しました。
このカメラも使い易く,10年近く現役で活躍しました。小型ながらファインダーのパララックス補正があり,総金属製のボディーは多少重いですが,見た目の洗練度はC35FDより上でした。でも若かった当時の私は,より高画質のカメラとレンズに憧れていました。丁度登山や冬山に熱中していた頃で,アルパインカレンダーや山岳写真集を見ながら,いつかリンホフとスーパーアンギュロンを手に入れたいと考えていました。それ以降の話は,このスレッドから外れますので,別の機会に「リンホフテヒニカ」等でご紹介する予定です。
 狸おやじ
狸おやじ  2025/04/01(Tue) 11:07 No.2803
2025/04/01(Tue) 11:07 No.2803
1959年製非連動露出計つき距離計連動35mmカメラ
レンズはCOLOR-HAPONAR45mmF2.8 撮影距離は1m〜∞
シャッターはPRONTOR-SVS(B・1〜1/300)セルフタイマー有り LV値による絞りSSリングの連動有り
重量は実測530g カウンターは底面で手動セット・減算式
巻上げは背面でレリーズは鏡胴脇にあります。背面はヒンジ式ドア。
PORSTはドイツの写真用品商社で数多くのメーカーからOEMで自社ブランドのカメラを調達していました。このHAPONETTE EBも例にもれずRegula-Werk King KG製のカメラと思われますが、このメーカーに関しての情報が少なく確証はありません。BALDAのデザインにも通じる丸みを帯びたデザインはこの時代ドイツでは流行したのでしょうか。レンズの構成や供給元も分かりませんでした。このメーカーは機種によりIsco-Gottingen・Steinheil・Rodenstockから供給を受けていたようです。
GOSSEN製露出計にPRONTORシャッター、鍍金の質も良い方だと思うのですが・・あまり見かけません。
コンパクトで適度な重さ。握り易いですが、アイレットが無いのは残念。写りはとてもシャープで赤みがやや強いです。
1938年発売のレンズ固定式35mmカメラ
レンズはKODAK Anastigmat51mmF4.5(3群3枚)距離は4ft弱〜∞
シャッターは自社製No1 DiomaticでT・B・1/25〜1/150sec セルフコッキング・セルフタイマー付 カウンターは手動セット・順算式 重量は550g(実測)
バルナック型のように丸みを帯びたボディの黒色部分はベークライト製で貼革風の表面仕上げ。折り畳み式ファインダーや突出した鏡胴、左右対称のノブのデザインが微妙にバランスが取れていて可愛らしいです。コダックの35mmフィルムカメラとしては初期のモデルなので、フィルム押さえのローラーユニットは大袈裟です。フィルム装填時には右写真のようにローラーが2つ付いた金具を起こし、下を通します(THREAD UNDER BOTH ROLLERSと彫ってあります)。
裏蓋の圧板は底部のロックレバーと連動し、レバーを閉側に回すとフィルムをガイドレールに押し付けるようにせり出します。
圧板やローラー類はピカピカにメッキされているので、使用時は圧板だけ薄い艶消し黒色のシートを貼っています。こうすることで多少コントラストは改善します。
鏡胴カバーにはスリット状の穴があり、シャッターチャージ時には赤いサインが出ます。レリーズは同じカバー脇、小さなノブを押下します。シャッター音は小さいですが、チャージにはガッチャ!と大きな音がします。カウンター前のボタンで巻止めを解除します。フィルム巻き戻しは巻上ノブを一段引上げて行います。
世界大戦への機運が高まる中、独コダックからのレチナ入手難を恐れて開発された、との資料もありますが、どうなんでしょうか。コダックは米国内のライバル、アーガスに価格で対抗できる物を作りたかったのではないでしょうか。
レチナ同様にアイレットが付いているところもポイント高く、お散歩カメラに最適です。
上位機種のKODAK Anastigmat-Special(3群4枚)付きや、オリーブの軍用モデルも欲しいところです。
1949年発売の35mm距離計連動式カメラ
レンズはANASTIGMAT-WOLLENSAK 44mmF3.2(3群3枚)撮影距離は2ft〜∞
シャッターはWOLLENSAK SYNCHRO-MATIC T・B・1/10〜1/200 絞りは22まで有り
セルフコッキング有り、セルフタイマー無し。重量は430g 枚数カウンターは手動セット・順算式
BOLEX・ALPAの初期設計に関わったジャック・ボルスキー氏がアメリカに渡って創業したのがBOLSEY CAMERAだそうです。
1947年発売のモデルBに二重露光防止機能が付いたのがB2です。モデルBと同じようなアルミ鋳造のボディはかなりガッチリしています。軍用モデル(黒ボディにオリーブ貼革)も存在しましたが、戦場では操作部分が小さ過ぎて使いにくいような・・
距離計は上下合致式でファインダーはレンズの真上、レリーズは鏡胴右手側。巻上解除は巻上ノブを一段(手応えがあるまで)引いてから巻上げます。巻き戻しにはロックは無く、巻き戻しノブを回すだけ。ノブは伸長しないので36枚撮りを巻き戻すと指先が痛くなります。
裏蓋開放には底部のロックレバー操作で、底部ごと外れます。
レリーズは鏡胴右手側のギザギザのついたレバーを倒すのですが、1段目で二重露光防止ピンが出て、2段目でシャッターが切れるという動作をします。これでタイミングがズレるのか、手振れ発生が多いです。カメラをホールドし難いというのもありますが。写りはレンズの状態が悪いのか今ひとつ・・
使いにくいけれど可愛らしい、私の持っている唯一のWOLLENSAKレンズ搭載カメラということでご紹介しました。
1955年発売の距離計連動35mmカメラ
レンズはGRAFLAR50mmF3.5(RODENSTOCK製)撮影距離3ft〜∞ コーティング有り
シャッターはPRONTOR-SVS(B・1〜1/300sec)セルフタイマー有り
重量は695g(実測)フィルムカウンターは手動セット・減算式
セルフコッキングではなく、レリーズはエプロン部の一見セルフタイマーのようなレバーにて行う。
背面の距離計窓は左、ファインダーは右でブライトフレーム無し。巻き止めは無し。巻き戻しは巻上ノブを一段上げて行う。上級機はF2.8レンズ(構成は不明)を搭載しています。
GRAPHLEXは50〜60年代にかけて35mmフィルムカメラも積極的に販売していました。本機はGRAPHLEXが製造販売していた物としては最終機で、これより後は日本のKOWAやドイツのILOCAからOEM供給を受け販売するようになります。
上下合致式距離計はアメリカ製カメラに良くあるもので気になりませんが、フォーカス操作はレンズ左右の黒いシーソー式押しボタン、レリーズ位置はエプロン下部と、まぁ少々変わったカメラです。ケースに入れて首から下げて使う方が良いでしょう。
鏡胴上のカラフルな色分けはストロボ使用時に役に立つよう距離計窓の色分けと合わせて使用するようです。ホットシューも備わります。
裏蓋は底面ごとごっそり外れるタイプで、圧板はピカピカにメッキされているので、使用時には薄い黒色シート(梱包用の薄いテープ)を貼ります。
千代田光学精工1958年発売
距離計連動35mmレンズ固定式カメラ。世界初のSS最速1/2000秒を実現したレンズシャッター機と言われています。
レンズはロッコールPF 45mmF2.0(5群6枚)撮影距離0.8m〜∞
シャッターはシチズン・オプチバーHS(B・1〜1/2000sec)セルフタイマー有り
カウンターは何故か巻戻し側に有り自動セット・順算式。
重量は実測780g・ファインダーはパララクス自動補正有り。露出計は無し。
1/2000秒を実現したOPTIPER-HSシャッターですが、ややカラクリが有り、1/1000では絞りがF4以上(EV値14以上)、1/2000ではF8以上(EV値17以上)の設定時に限られること。
これはシャッター羽のスタート位置をずらして羽が全開になる前に閉じる動作をする為で、余程明るい環境でないと使用出来ないことになります。
このシャッターは更に2年後に発売したミノルタV3で1/3000秒にまで達し、1/1000では制限が無くなり1/2000と1/3000で制限有りとなりました。
ポルストのカメラは、CR-7(Fujica AX-5)を持っており、気になるブランドでした。
ほぼ同時代の一眼レフだけでも多種多様なOEM元で誠に節操がないメーカー(笑)で、特にHaponetteはじめ初級ビューファインダーカメラは謎だらけ。
ボディは簡単にRegulaKingが検索されますが、レンズのHaponarの方はおっしゃる通りほぼ出てきませんね。66のBaldaOEMはEnnaレンズをつけているようで、50mmf2.8のハポナーもエナというページもありましたが確証はありません。
謎ながらしっかりしたカメラのようで、写して楽しいでしょうね。
コダックの初級機はレンズに人気があり一定のファンが居るようです。レチナ1よりさらにプリミティブな操作性で楽しそうです。
ボルシー同様、米国大衆カメラの中で上級の下から中級層を狙うと思いますが、3枚玉で済ませているところが米国らしい。単玉じゃないから上級なのか。でもトリプレットはよく写りますから、日本人の高級志向が変なんですね。
ミノルタV2、しかも動作品をお持ちなのですね。1/2000はそんな制約があったとは。f8ならば、日中ピーカンでASA800なら使える速度。当時のネオパンSSSの限界に思える増感でしょうか。
A2当時の本を読むと、アメリカンデザインと評されています。50年代、目標にするカメラデザインは、ドイツだけでなくアメリカも一角だったのだなと思いました。V2も上に上げられたボルシーにも似ている気がします。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/04/26(Sat) 21:52 No.2839
2025/04/26(Sat) 21:52 No.2839
こちらへ投稿させていただくようになってからカメラの出自や特色をネットで調べるようになり、マニアになった気分です。しかしPORSTに関して、特にHaponette(=King)は情報が少なかったです・・。SearsやSoligorと比べ大衆機が多かったからでしょうか。
ミノルタV2は当時の「Minolta」ロゴをデザインした外部の事務所が担当したということです。ミノルタがカメラのデザインを外部に任せるのが既に50年代から始まっていたことが驚きです。
埋もれている名器、とは言えないけれど当時の熱気が伝わるような機体を求めて彷徨い続けております。
千代田光学精工 1958年発売
距離計無しの35mmレンズ固定式カメラ。世界初(或いは2番目)の露出計連動カメラと言われています。
レンズはロッコール35mmF2.8(4群6枚)撮影距離0.8m〜∞
シャッターはCITIZEN MVL B・1〜1/500 フィルム感度設定ASA10〜400
カウンターは自動セット・順算式、セルフタイマーあり、重量は実測710g、巻上げ・巻き戻しとも底面レバー式。
35mmカメラに広角レンズブームが起きた1950年代後半に発売されました。
ミノルタAシリーズに通じる丸みを帯びたボディとレンズ鏡胴の突出が小さいのが特徴でしょうか。個性的なデザインは外部のデザイン事務所が担当したそうです。
「露出計連動」を謳っていますが、絞り・SSの設定は背面の二重になったダイヤルを操作して露出計の指針と合わせる物です。内側ダイヤルが絞り、外側ダイヤルでSSを設定します。レリーズはセレン電池の上、カメラを構えて真上から鏡胴を見ると、距離指標ではなくP(1m)・G(2.5m)・S(5m)という目測用英文字のみが彫刻されています。距離指標は90度右下に被写界深度と共に彫られています。メーカーとしては「広角は被写界深度が深いから目測で充分」と思ったんでしょうかね。距離計は無いですが、ファインダーはプリズムを使用していて、クリアで見易いです。
それほど人気が無かったのか、販売期間が短かったのか個体数は少ないようです。ただ、写りは確かでモノクロ・カラーネガともに絞ると非常にシャープで驚かされました。逆に距離計が無いのが勿体ないと思ってしまいます。
岡谷光学機械 1954年発売
距離計連動35mmカメラ 露出計無し
レンズはハイコール4cmF3.5(3群4枚)撮影距離2.5ft〜∞
シャッターはセイコーシャMX(B・1〜1/500sec)2回巻上、セルフコッキング
重量は実測610g セルフタイマー有り カウンターは手動セット・減算式
コンパクトで個性的なロード数字シリーズです。ファインダーにはプリズムブロックが使用されていて見易く、丁寧に造られていることが分かります。
珍しいフィルムカッターが内蔵されています。底面のツマミを引いて使いますが、鋭い刃物ではありません。巻き戻しレバーは折り畳んで収納されていますが、やや使いにくい。鏡胴にある小さなレバーはスナップ撮影位置(3m付近?)のクリックストップ有無の切替。
巻き戻しボタンは普通に底面に有りますが、巻き戻し後は背面のボタンを押してリセットする必要あり。
レリーズボタンは2回巻上に連動して2段階にせり上がり、チャージ状態ではボタン根元に赤い帯が出ます。変わった形状のアイレットが付いてます。
ロードのレンズは55年のIVBでF2.8、57年の5DではF2.0へと進化して行きます。
岡谷光学機械は東京光学の疎開工場として40年代初めに設立され、陸軍向け光学製品などを製造していました。戦後も双眼鏡などの製造を続け50年代前半からカメラ製造を開始。カメラ製品名には一貫して「Lord」が頭に付きますが「Lord」は東京光学が戦前に製造していたカメラのブランド名でした。岡谷光学機械は60年頃にはカメラ製造から撤退しました。
オリンパス光学1959年発売
レンズ固定式距離計連動35mmカメラ、露出計非搭載
レンズはGズイコー4.2cmF1.8(5群7枚)
シャッターはセイコーシャSLV(B・1〜1/500sec)セルフタイマー有り、LVリング連動有り
重量は実測670gカウンターは自動リセット・順算式、ブライトフレーム・パララクス自動補正有り
1955年にレンズ固定式距離計連動カメラとしては日本で初めてF2.0を切るF値1.9レンズを搭載して発売された35Sの後継機です。
SⅡ型は1957年に発売され、金色のSマークが付くのは1959年から販売された後期型。初期型ではエプロン部にあったセルフタイマーもシャッター内蔵に変更されています。他にF2.0付き、F2.8付の物もあるようです。
F2.0以下のレンズを持つ他社のカメラはボディも大柄ですが、この機種は割合小型で取り回しは良いです。オリンパスは小型ボディに拘りがあったのかも。
本機は見てくれは汚いですが、レンズは状態が良くとてもシャープに写ります。メッキの錆びた部分を上手く塗装出来ればやりたいところです。
富士写真フイルム 1962年発売
セレン電池式SS優先オート・マニュアル可の連動距離計搭載35mmカメラ。
レンズはフジノンR4.7cmF2.8(3群4枚) 撮影距離0.8m〜∞
シャッターはコパルマジックで B・1/30〜1/500 セルフタイマー無し フィルム感度ASA5〜200
重量は実測720g 露出補正有り パララクス自動補正有り カウンターは底面で自動リセット・順算式 巻き上げも底面。
大きくデザインは少し野暮ったいですが「夢のシャッター」コパルマジックを日本国内で唯一搭載したカメラです。
このシャッターは基本はシャッター速度優先のプログラムですが、5つの速度それぞれにプログラムラインを持ち、指定した速度での露出値がオーバーまたはアンダーになる場合、速度をシフトしてその速度のプログラムラインに自動で設定するという機能を持っています(マニュアル操作も可能)。
しかもその機能は内部に取付られた露出計の針押さえだけでメカニカルに実現しています。写真撮影の失敗を機械的に防いでくれるところが”夢”という訳です。
デメリットとしては速度・絞りの変更が行われても撮影者には変更内容が明示されない、部品点数が多くコストが高い、故障が多い(絞り・SS変更はチャージ後に行うのが必須)、シャッター部品の容積が大きい為レンズの直径を大きく出来ないなど。
結局「夢のシャッター」を積んだカメラはこの機種1台だけで終了となり、その技術は旧ソ連に渡りました。
※ソビエトカメラのスレッドに関連機種を投稿します。
富士写真フィルム1964年発売
距離計・露出計連動35mmレンズ固定式カメラ。SS優先オート・マニュアル露出可
レンズはフジノン45mmF1.8(4群6枚)撮影距離0.9m〜∞
シャッターはシチズンMLT(B・1〜1/1000sec)セルフタイマー有り 感度設定ASA25〜400
カウンターは自動セット・順算式 使用電池はH-D1ケ
重量は実測780g ファインダーはパララクス自動補正有り
比較的仕上げの良い高級感のあるカメラです。ファインダーにはプリズムブロックが使われていて見易く、視野下部にSS、右側に絞り値が表示されます。本体左上のダイヤルはCDSを配したフィルム感度設定用のもの。
フォーカス操作はこの時代のフジ機には幾つか例のある背面のダイヤルで行うもので、カメラを両手で構えたまま右手親指で操作できる。
写りもこのクラスではかなり上位に入るかと。ただし1964年と言えば、カメラはそろそろ小型化・軽量化の波が押し寄せる頃ですね。
理研光学工業 1954年発売
距離計連動35mmレンズ固定式カメラ 露出計は非搭載 巻上は底面トリガーと軍艦部ノブ両用
レンズはリケン・リコマット45mmF3.5(3群3枚)富岡光学製 撮影距離は3ft〜∞
シャッターはリケン(B・1/25〜1/100sec)セルフコッキング有・セルフタイマー無し
重量は実測615g カウンターは手動セット・順算式
リコーの35mmカメラとしては戦前のスーパーオリンピック・戦後のリコレットに次いで3機種目。1953年発売のリコレットにトリガーと距離計を搭載したようなものです。ほぼ同じデザインのリコー35という機種も有り、さらにセイコーシャッター付の機体も存在する為、天板の刻印で見分ける必要があります。
シャッター周りの独特なカバーはシャッターチャージとレリーズのレバーを隠すためのものでした。
トリガー巻上部分のついた裏蓋兼底蓋は後のリコー519デラックスと共用出来ます。ファインダーは分解できませんでしたが、明るくハーフミラーもクリア。SSの設定範囲が少ないのが玉に傷ですが、写りもは良いです。
理研光学工業 1958年発売
距離計連動35mmレンズ固定式カメラ 露出計は非搭載 巻上は底面トリガー式
レンズはリケノン45mmF1.9(4群5枚)富岡光学製 撮影距離は3ft〜∞
シャッターはセイコーシャMXL(B・1〜1/500sec)セルフタイマー無し・LV値によるリング連動有り
重量は実測675g カウンターは自動リセット・順算式
デラックスの名に恥じない各部の仕上げとメッキが煌びやかなカメラです。ただ鏡胴のリングまでピカピカにメッキされていて晴天時はダイヤルの数字が見にくいです。
トリガー巻上げのカメラには巻上げノブと両方付いている機種も有りますが、こちらはトリガーのみです。しっかりとした造りで感触も悪くないです。ファインダーはパララクス補正は無いものの、プリズムを使用していて明るくクリア。シーソー式のフォーカシングも2眼レフでは見かけますが35mmカメラでは希少ですね。無骨なデザインですが写りも良く気に入っています。
※正面左肩の「RICOH」文字の下に円が二つと真ん中に縦棒のマークが有るのですが、これの意味って何でしょうね。当時の複写機リコピーの広告にもこのマークが入ってました。この時代の幾つかのカメラにだけ見られるマークです。
Beier 1959年頃・1970年頃
東ドイツBeier社製35mm目測コンパクトカメラ
レンズはE.Ludwig Meritar45mmF2.9(3群3枚)
シャッターはB・1/30〜1・125 セルフコッキング有 セルフタイマー無
カウンターは手動セット減算式 重量は実測365g・350g(vs)外装は金属で内部はベークライト製
1920年代からカメラ製造を始めたBeier社は大戦前初期には120フィルムやボックスカメラ、1931年には早くも35mmカメラの製造を始めました。
6×9と35mmフォールディングカメラの両方にライツのエルマーを搭載したモデルが存在していたことで知られています。
大戦後は東ドイツ側で数少ないKGとしてカメラを製造していましたが1970年代にはVEBに併合され、1990年近くまでベーシックな小型カメラを製造しました。
写真のBeiretteはBeierの息の長いモデルで、十数年間大きなデザイン変更無く販売されました。Beiretteの名称はその後プラスチック製カメラとなっても1990年頃まで使われたようです。
裏蓋の脱着はユニークで、側面の金具を回転させて外します。フィルムカウンターのリセットは巻き戻しノブを少し引いて回します。
小さく可愛らしいデザインにやられて手に入れてしまいましたが、レリーズの位置か、またはホールドしにくい大きさのせいかブレやすいです。
レンズの描写は悪くないので、ケーブルレリーズか外付けセルフタイマーを接続して愛用しています。
Eastman Kodak
1940年発売の距離計連動レンズ固定式35mmカメラ
レンズはKODAk Anastar50mmF3.5(構成不詳※)撮影距離4ft弱〜∞
シャッターは自社製FLASH KODAMATIC T・B・1/10〜1/200セルフコッキング・セルフタイマー有り
カウンターは手動セット・順算式 重量は実測705g
1938年発売のKODAK35(№2805に投稿済み)は距離計非搭載でした。ライバルArgusとの差を埋めるため、ボディを大幅に変更することなく距離計を載せた物、それがこのKODA35RFです。漸く使用できるまでにレストアしました。
腰下部分はほぼKODAK35のまま、ファインダーと距離計窓を軍艦部に内蔵し、レンズ鏡胴からボディ内へ距離計用アームを付け足してカバーで覆い、フォーカシングには歯車状の突起を取付けました。後付け感が何とも凄いです。この目立つ距離計アームのカバーはプレス物ではなく、ワンピースの鋳造製です。レンズの清掃には距離計アームを外す必要があるので、当然トップカバーもバラすことに。ファインダー等のガラス部品は全てリベット止めです(下の写真は、レンズを清掃するために外す必要がある部品を示しました)。
背面の距離計窓は非常に小さい(2㎜×3mm位)ですが、上下像合致式なので使いにくいというほどではありません。
レリーズ位置も変更なしで、前面歯車の少し上のカバーに覆われた小さなレバーのまま。母体が同じカメラなのに奇妙な外観の重いカメラになってしましました。この機体はレンズの記号から末期の1950年製でした。
※Brian Wallen氏のページによるとAnastarレンズは改良型(Modified)テッサータイプで元のAnastigmat-Specialと同じということです。
そこで思いついたのがこの方式です。
格安のニコンFM2に取り付けられていたNPCプロバックの中のレンズ?(←名称が分かりません)
アパーチュアの寸法より少しだけ大きく(27×39mm)、素通しに裏面が映るので、ジャンクのPEAK製ルーペ(少々レンズが劣化しています)を接着剤で取付けてみました。
結果これ明るくて、蛍光灯の室内でも良く見えます。わざわざ屋外で三脚に乗せてピント調整することが無くなりました。
主にスプリングカメラで、6x9のものが多い。
カットしたすりガラスにピークルーペを張るのですが、落ちそうですし果たしてこれでいいのか自信がありません。
NPC用となると、焦点面を後ろに並行移動させるのですね。
もしかすると、インテンスクリーンを分厚くしたような、光ファイバーを束ねて板にした代物でしょうか。
貴重な機材です。
NPCはジャンクボックスからペンタックス645用を回収していますが、もはやポラロイド100の実用価値はありません。
どうしようか捨てるには忍びないしと思っていたら、面白い用途があるものです。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/07/13(Sun) 20:55 No.2937
2025/07/13(Sun) 20:55 No.2937
EASTMAN-KODAK 1951年発売
可愛らしい距離計連動35mmカメラ
レンズは KODAK EKTAR44mmF3.5(3群4枚)最短撮影距離は2ft コーティング有
シャッターはKODAK SYNCHRO300 B・1/25〜1/300 セルフタイマー無
カウンターは手動セット・減算式 重量は実測500g
コンパクトな外観ですが、アルミ合金ボディはがっしりしています。取外し式の裏蓋も同じ材質。KODAK35に比べレリーズレバーが外付けされて扱い易くなりました。ただセルフコッキングでは無くなりました。
距離計は上下像合わせではなく、ハーフミラーを使った透過式二重像合わせに変わりました。形状は何故か三角形です。
ストラップ取付金具兼用の裏蓋ロックは片側のみが可動します。前面最下部のツマミは多重露出用、背面最下部のツマミは巻き戻し用です。フィルム圧板は相変わらずピカピカの鏡面仕上げ。背面には簡易露出計算板が付属。
写真のボディ色以外に空軍用黒色仕上げと陸軍用の緑色仕上げがありました。
ミノルタカメラ1968年発売
距離計・露出計連動の35mmカメラ
レンズはロッコールQF 40mmF1.8(4群6枚)最短撮影距離0.8m
シャッターはシチズンVEB 1/8〜1/500フィルム感度はASA25〜500 セルフタイマー有
重量は実測540g 使用電池はH-D型(LR44で代用可)1ケ
大ヒットしたハイマチックシリーズよりややスリムかつ小型のミノルチナシリーズでCDS使用による露出計を内蔵したモデル。シャッターは機械式で、露出計連動のSS優先AEとマニュアル露出の両用。軍幹部に設置の小さな露出計メーターはマニュアル使用時にも動作します。ファインダー内には表示は出ません。
前面の丸いダイヤルはシャッターロック(L)・通常使用時・セルフタイマー(V)の切替です。ロックにしても露出計の電源は切れません。使用しない時に電池の消耗を抑えるにはレンズキャップが必要です。
135フィルムパトローネを使うフォールディングカメラのカテゴリを提案します。
このジャンルは広大で、こちらには第一人者のナースマン様がおられますので僭越ですが...
そして従来から、レチナ同盟様や、Jewels of Nostalgia様のような素晴らしいウェブサイトがありますので、詳細はそちらを参照すれば足りるのでしょう。
ただ皆様の目から見てのご感想やアドバイスを伺えれば、情報が豊かになることでしょう
その意味で、同じ機種を重複して投稿頂くのがよいかなと思いました。
折りたたみ方法は、スプリング形式以外にも、ハンドカメラのようなレールを引き出すもの(例を知りませんが)、ストラット(ベベやリリプトなど,35mmは知らない)、Xトラス(カラートなど)、沈胴(コンドールIIやコニカ初期)など様々です。
距離計連動の高級機もあれば、単独距離計内蔵、目測機があります。
「追記:日浦様のご指摘とご提言を考慮し、曖昧だったカテゴリを整理します。
1,135フィルムを使うカメラ。(フォーマットサイズは問わない。)
2,レンズ交換はできない。(例外的に前玉交換のレチナIIc,IIIcは認める。)
3,電動ではなく手動(スプリングは含める)で撮影状態と収納状態を切り替える。(Contax TVSシリーズは手動だが4.に抵触する。どうします?)
4,オートフォーカスカメラ(電動焦点合わせ。戦前に言われたオートフォーカス(距離計連動)はOK)は含めない。
今後ご指摘によってはカテゴリは変更するかもしれません。」
さて、スプリングカメラ形式をとるものは、1934年のドイツコダック レチナ117を元祖とします。(例えばPeggyは1930年ですがパトローネ規格ではない)
精密35mmフィルムカメラはライカが先鞭を付けましたが、普及のためにはレチナのような比較的求めやすい撮影機材と、コダックの簡便なパトローネが必要でした。
Kodak Retina I (model#118) 1935年
レチナ二番目のモデル。きわめてシンプルな構造と操作性、高性能レンズ故に、最初期モデルでも十分以上に現在でも実用的です。
初期ライカは小型軽量ですが、このレチナと並べると、なんとも大きく感じてしまいます。
ましてコンタックスとは全く比較にならない小型軽量さに驚きます。
作りは精密で、畳むと手のひらサイズになり、携帯性抜群です。
最もありふれたクセナーですが、素晴らしい描写力だと思います。
レンズ:シュナイダー Xenar 5cmf3,5
シャッター:コンパー 1/300-1秒,B, T
1937年モデル#141からボディシャッターになりますが、117,118,119,126までは直接コンパーのレリーズを押します。
焦点合わせ:ヘリコイド,最短1m、距離目測
巻き上げはノブ,自動巻止め。巻き止め解除はファインダー背面小レバー。丁度グラフレックスロールホルダーのような要領で解除する.二重露出防止機構は入っていない、大半の古典的中判スプリングカメラと同様の操作性。
イコンタ35と同様の横型スプリングカメラ。
レンズのスペックは良く、シャッターは落ちる、東独によくあるパターン。
このモデルはアクセサリーシューを持たないが、後に折りたたみファインダーから固定ファインダーに変更され、その頂上にアクセサリーシューがついた。
1stクオリティマークつき明るいテッサー5cmf2,8が最大の売り。
シャッターは1/200までの普及型。
焦点合わせはレチナ同様ヘリコイドで、前玉回転ではない。
ツェルトシックスを比例縮小したようなモデル。
目測レチナやイコンタ35と比較して少しゆったりしたサイズのボディ。
裏蓋は取り外し式でうっかりすると取り落としそうになる。
スプロケットを持たず、細かいギザつきのロッドでフィルム走行を感知し自動巻止めされる。
操作性は特に困ったところはないが、ボディシャッターのリンクが曲がりやすく、作動不良の温床。
そこかしこに東独製の節約ムードが感じられる造り。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/16(Wed) 23:47 No.1233
2018/05/16(Wed) 23:47 No.1233
135スプリング。34年レチナ117が元祖ですが、ツアイスにもある。
スプリングの元祖ツアイス。おなじ34年スーパーネッテル536/24。
RFコンタックスの普及品。と言っても、レンズ交換できないだけの高級品。テッサーレンズ、フォーカルシャッター、ドレイカイル距離計付。36年クロームメッキの後期型537/24、38年迄。
戦後は49年単独ファインダーのイコンタ35、522/24。52年単独距離計のコンチナ523/24。50年コンテッサ533/24ドレイカイル距離計、セレン露出計付。55年迄。以降、固定鏡胴へ。
スプリングカメラの老舗。他にホクトレンダー、ウエルタ、バルダ等がある。
ウエルタはウエルチニの項に記載。35年単独ファインダーのウエルチ。37年1眼RFのウエルチニ。38年流線形の後期型。41年迄。
エルマー付きウエルチニ後期型。現在OH中。
同時代レチナ119〜148にエクター付きが有るが(これはシュナイダー製造品と言われている)これに対抗した物?
戦後、ウエルタは東独へ。ウエルチの再生産品が中心。ウエルチニは再生産されていない。スーパーネッテルと共に、戦前の最高級品。
バルダ。35年バルデナ。単独ファインダー縦開き。36年バルデネッテ。単独ファインダー横開き、アクセサリーシュー付き。
37年スーパーバルデナ、RF付。バルダ社は本体がメイン。レンズ、シャッターの組み合わせは、様々。F2,8テッサー付きは、此れも戦前の高級品。
戦後バルダ社は東西に分割。西独バルダ。50年バルデネッテ。ファインダーが軍艦部一体に。スーパーバルデナ。此方も軍艦部一体に。
東独ペルカ社。ペルデカ、バルデナの再生産品。れんずまにあ様の個体は、これの後期品。
フォクトレンダー。案外少ない。39年ビトーⅠ。F3,5スコパー、コンパーラビット付。戦前は此れのみ。
戦後は、50年ビトーⅡ。51年ビトーⅡa。コート付カラースコパーへ。
51年ビトーⅢ。レンズ交換品のプロミネント普及品。F2ウルトロン付き、縦開き。
50年ビテッサ此方もF2ウルトロン付。お馴染み、ビテッサの煙突。プランジャーによる巻き上げ、シャッターチャージ。54年固定鏡胴に。
レバー巻き上げのレチナⅡaの対抗品?
私のコレクション。レチナ148、、エクターアナスチグマット付。
レチナⅡa。F2クセノン付。コンテッサ533/24、F2,8、Tコートオプトンテッサー付。ウエルチウエルチニ後期型F3,5エルマー付き。
これ等、長野様の所で、OHしているので、最後まで使うスプリングカメラだと思っています。
 ナースマン
ナースマン  2018/05/17(Thu) 10:24 No.1234
2018/05/17(Thu) 10:24 No.1234
そうか、スーパーネッテルもこの仲間なんだ。
普及スペックなのはレンズだけで、ボディはコンタックスIIだから全く節約になっていない。ツァイスイコン商売下手。でも使ってみたい憧れの機種。ContaxIIを持っていたら要らないといえばそうなんだけど。
当時ツァイスイコンは35mmフィルムを一般ユーザーが使うには懐疑的だったと思えます。35mmは撮影枚数が多すぎるし、パトローネ出現前は自分で長巻からマガジンに切り出す必要がある。(1ロール分銀紙に巻いて小売りはしていたらしいが)一般には127フィルムベスト半裁16枚も撮れれば事足りるし、ベビーイコンタ赤窓ならカウンター不要で安く上がる。
その後もテナックスなどに回り道してイコンタ35を1948年ようやく出す。
二眼レフに対する対応と似たものを感じます。
ようやく出したと申し上げましたが、イコンタ35は素晴らしいカメラです。
イコンタのスレッドでも出しましたが、再掲します。
私の個体は1950年から供給されたイコンタ35IIとよばれているもので、基本ボディはコンテッサと共通で、操作性も一貫性があります。
底部の大径ノブ巻き上げは軽く、保持した手をほとんど持ち替えずに巻き上げできるのは底面レバーよりもよい操作性です。
シャッターチャージは手動で行う必要がありますが、二重露出防止機構が的確で、レバーによるレリーズは軽く、リズム良く撮影ができます。
造りは高級機コンテッサに通じ、この手のカメラとしては最高級で安っぽいところが全くありません。
レンズは3枚玉Novar2,8/45が主体ながら、人気でNovarの供給が追いつかなかったため同スペックのXenarも併売され、Tessarつきもあります。
Xenarつきはそれほど珍しいわけではないようです。
スプリング形式の35mmカメラには珍しく、45mmと準広角が付いていて差別化されています。
この焦点距離は好き好きですが明るく貴重なスペックです。
私は望遠的にも使える5cmが好きです。(Retinaは5cm表記でも実焦点距離47mm程度とも聞きましたが)
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/17(Thu) 20:45 No.1235
2018/05/17(Thu) 20:45 No.1235
あまり集めるつもりはなかったのですが、良く写るのに滅法安いのでつい手元に。
最初に手にしたレチナは、エクターつきの戦後直後モデル010でした。
まだシャッターチャージは手動ですが、二重露光防止のボディレリーズは便利で、巻き止め解除操作がいらない分、大変スムーズに撮影をすすめることができます。
ストラップアイレットがないため持ち運びにはストラップつきケースが必需品ですが、畳んだサイズは117から戦後010まで変わらず、ケースを使い回しできます。
エクターにはkodak anastigmat ektar表記の、実際にはXenarといわれるものと、本国Kodakが製造したいわゆるUSエクターがあります。
USにはコダック特有のCAMEROSITY製造番号が入っていて、私の010にはEOすなわち1946年製造が、015にはES:47年製造がついています。
私の節穴ではエクター特有の良さがわかりませんが、素晴らしく良く写ることは保証します。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/17(Thu) 21:39 No.1236
2018/05/17(Thu) 21:39 No.1236
同機能の010が重複してもしかたないのですが、ローデンシュトック・イザール5cmf3.5付きを友人が手放すので引き取りました。
イザールもUSエクターも、同じテッサー型です。イザールは戦前在庫だったのかは知りませんがノンコート。
ベルビア100でテスト撮影した結果では、イザールとUSエクターの写りの差は私には認識できませんでした。どちらもf3.5の開放から大変シャープで端正な優秀レンズです。
010の中でも主流のシュナイダークセナーと、名称違いのコダックアナスチグマートエクターは50mmf2.8でした。
日中屋外や明るい室内で使用する分には、ISO400ネガを入れておけばf3.5で十分撮影はできます。
それでもf2.8が必要なかたもおられるでしょうから、選択肢が多いのはよいことです。
レチナ含めヘリコイド焦点調節のスプリングカメラは、ベッドを折りたたむ時ヘリコイドを無限に戻しておく必要があります。
ベッドを開いて即座に撮影すると無限遠なので、スナップにはもう一手間近距離への焦点調整が必要です。
それがイコンタ35のような前玉回転機なら、焦点位置を常焦点にしておけば開いて直ぐにスナップ可能なので、一概にヘリコイドが優れているとは言えません。
私は普段シャッターチャージは撮影直前に行うので、そんなに即応性に拘ってはいないのですが。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/17(Thu) 21:54 No.1237
2018/05/17(Thu) 21:54 No.1237
ボディサイズは117-010と同じで、極めて小型ですが機能追加に応じ、少しだけ重く、010よりもベッドの厚みが増していて、大きなレンズにも対応できるようになっています。
この個体はUSエクター50mmf3.5なので、薄くてもよかったのにと思いますが。
Iaは前述した操作性の改良で、速写性はすばらしく増しました。
その後、Ibから巻き上げレバーが軍艦部上面から下部に移動し、少し操作性が低下したかと個人的に思います。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/17(Thu) 22:02 No.1238
2018/05/17(Thu) 22:02 No.1238
私も自分のHPにもいくつかお気に入りを載せてますが,やはり中ではレチナIIa #016 が好きです.ありふれていて通好みではないですが,やっぱり使いやすいし,なにかと過不足ありません.また他の同等のものより比較的小さくて頑丈.蛇腹も丈夫で指などで触れにくく,なんというか文句がありません.強いて言うなら視度でしょうか.レチナは他にもIIIc #021/1のなぜか黒い奴と,IIIC#028大窓,IIC#029大窓も持っています.このCのついたシリーズでは(個人的にこの手の内蔵露出計はほとんど使わないので)IICが好きかも.タスキ構造じゃなくなりましたが頑丈ですので,人に勧めるならIIIC系列もいいなあと思います。他にUS Ektar のついた #010 も持ってます.他にもあったかも・・レチナIIaは前玉回転式ではないので,オートアップと相性が良いのもいいところです.
ヴィテッサやアルコ35オートマットDもHPで紹介していますが,これらもよく写りました.レンズがいいカメラという印象です.アルコは特に近接ができるのが印象的.フォクトレンダーでは VITO II も持っていますが,作りの良さに感心します.
これらの1950年代のカメラとはちょっと違いますが,実は35mmフォールディングカメラの仲間に入れてもいいのかなと思うものが,初代CONTAX Tです.ちょっと小さすぎて操作性はよくないですが,小さいだけでなく,圧倒的に軽い(レチナの半分ぐらい)なのがよい.海外出張時にできるだけ荷物を減らしたいが,海外の風景をフィルムにおさめたい・・というときには,レチナIIaかCONTAX Tに食指が伸びるときが多かったです.そういいながらも,もうちょっと頑張って中判を持っていっていますが・・他に MINOX 35シリーズやRICOH FF-1もありますね.沈胴を入れるとローライ35も入ってきますが、一応「蓋がある」という縛りで考えてみました.
距離計連動にほぼ限定されていますが,以下に個人的な好みも交えていろいろ書いております.
http://nikomat.org/priv/camera/35mm/index.html
 日浦
日浦  2018/05/18(Fri) 00:04 No.1239
2018/05/18(Fri) 00:04 No.1239
イコンタ系はどれも最高ですね。特に戦前、36〜38年(戦前のドイツがの栄えていた頃)良質なモロッコ革、ミンクオイルで磨けば、今でも艶が出ます。メッキも厚い。ネッター系は、革質が、少し劣る。戦後の物は、戦前イコンタとネッターの中間ですね。
ホクトレンダー。此れも革、メッキ共素晴らしい。錆びたもの見たことない。ウエルタ。此方も素晴らしい。御三家である。
バルダ。此方は劣る。明らかに普及品。但し、スプリングの老舗。作り慣れている。革の劣化、錆が有るが、光漏れ、作動不良はない。
レチナ。バルダよりまし。但し、イコンタには劣る。本体から痘痕。
148、戦前最後の物。痘痕は有るが、張革、メッキの擦れはない。
010、戦後直ぐの物(ほぼ148の再生産品)此方はやはり質が?
国産品だと、小西六。結構質が良い。ネッター並み。ミノルタは小西六に劣る。戦前のオートセミミノルタ。ほぼウエルタウエルトアのコピー。内部のギアを含め、張革、蛇腹、メッキ共に、本家に劣る。
使い勝手。ドイツの製品、右利き用、左利き用がある。イコンタだと、スーパー69は左利き用。スーパー6だと右利き用。コンテッサ系は右利き用です。
ウエルチニは、完全に左利き用。ファインダー、フォーカス、シャッター、全てコンテッサとは逆。右利きの私。コンテッサの方が使いやすい(先日の試写。コンテッサと併用、ウエルチニに手振れが)
レチナは右利き用。レチナⅡa。RF、レバー巻き上げ、セルフコッキング、サイズを考えても、最も使いやすいスプリングカメラだと思う。
F2のクセノンも素晴らし。底面巻き上げのⅡcは使い勝手が劣る。
セレン露出計付のⅢ(コンテッサを含め)今と成っては、セレンが生きているものが少ない。
ツアイススーパーネッテル。以前F3,5トリオター付。手を伸ばしかけたことが。塗りの黒。艶のあるすばらしさ。張革と共に、ライカ以上。ファインダーはライカ型の2眼RF。但し、ドレイカイル、プリズムなので、見え、使いやすさ、共にライカ以上。
シャッター。コンタックスと同じ鎧型ホーカル。音も同じ。
当時、テッサー付きで12万、トリオター付でも8万程。
私、基本的に、コンタックスのシャッター、信頼が?加えて価格。手を出さなかった。
 ナースマン
ナースマン  2018/05/18(Fri) 06:02 No.1240
2018/05/18(Fri) 06:02 No.1240
戦前#150を戦後小変更し継続。
軍艦部巻き上げノブ、マニュアルシャッターセット、ボディレリーズ、巻き止めはレリーズで自動解除。1眼式連動距離計。
レンズは距離計連動に相応しいf2クラスのXenon5cm、Heligon5cm, USエクター47mmがあります。
エクターはカードンに供給されたものと同じエレメントと言われています。
エクターは他の2種とずいぶん異なる描写で、開放ハロが大きく非常に柔らかいが解像力は高く、2段絞るとハロが晴れて繊細な画質になります。
現代レンズと比較するとXenonであっても開放ハロ、コマは残っていますが、エクターほど絞りによる描写の差はありません。
大変優れた操作性のカメラですが、距離計ファインダーの倍率が小さく0.6倍くらいなので、有効基線長が短くなってしまいます。
その分開放では慎重に距離計を合わせるように心がけています。
このモデルもボディにストラップアイレットが装備されていないので、ストラップつきの専用革製速写ケースがあったほうがよいですが、畳むと蓋されるレチナに速写ケースは屋上屋を重ねる感があり、底三脚穴にハンドストラップをネジ込むほうが使い勝手がよいこともあります。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/18(Fri) 18:46 No.1241
2018/05/18(Fri) 18:46 No.1241
意識しておりませんでしたが、Contax TやMinox 35の仲間達もそういえばフォールディングカメラですね。すると末裔TVS3までありますね。
凄くチープ(パカパカのプラ製、固定焦点38mmf4、プログラム)なので紹介を躊躇しますが、京セラのヤシカパートナーというのもあります。(
画像)
自動的に蓋がされる縛りにすると、アグファカラート36が抜けてしまうので少し悩みます。
ナースマン様、今後各論でコレクションをご紹介頂ければこんなに有り難いことはございません。ナースマン様のご評価は、まさに生きた情報ですから。
レチナIIaは露出計なしのレチナとして完成型、究極の操作性でしょう。個人的には底部レバーより軍艦部レバーのほうが持ち手に無理が掛からず望ましいと思っています。勿論底部もそれなりに便利で、使えないと非難するわけではありませんが。
装備の戦後クセノン5cmf2は、恐らく同クラスの5cmの中では最高にシャープな一本かと思います。開放近くではL39のズミクロンやニッコールより上かもしれません。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/18(Fri) 23:09 No.1242
2018/05/18(Fri) 23:09 No.1242
個人的には、AFは除きたい気がします。歴史的には、中判のフォールディングカメラを引き継ぐ形で35mmでも折り畳みや沈胴があたりまえだったところ、キヤノネットやハイマチックの時代にはレンズの大口径化・AE化とコストダウンの要請によって、いったん変形しないカメラが当たり前になりました。その後AFコンパクトカメラの時代になってまた、沈胴が復活してコンパクトデジカメへ繋がっている気がします。
もう1つは、レンズを沈めたり畳んだりする操作が手動か、電動か、という分け方もあるかもしれません。それですとTVS3は仲間に入ることになりますね。
そう考えると蓋の有無はあんまり本質でない気がします。さきほどは蓋の有無の縛りと書きましたが、内心は、手動か自動かで考えていたような気がします。
 日浦
日浦  2018/05/18(Fri) 23:35 No.1243
2018/05/18(Fri) 23:35 No.1243
私は、016、Ⅱa最高のスプリングカメラだと思います。
F2クラスのレンズ、コンパクトなサイズ、使い勝手、全て良い。
然し、セルフコッキングを可能にするため、1つ構造上の欠点がある。レチナ同盟でも、この点の質問が多かった。
1つ前の011、Ⅱ。ノブ巻き上げで、背面に巻き替え装置が付く。
これをレバーにするに当たり、連動部分に、のこぎり型のギアを使っている。この部分に負担が掛かる。経年劣化で、摩耗。連動不調に。
巻き上げは、力を加えず焦らない。フイルム表示、構造上、残数表示。忘れて、0に合わせると、いきなり停止。その場合、シャッターボタンの手前にあるフイルムレリーズボタンを使う。
この欠点を、分割作動にすることで、負担を減らすため、底面巻き上げに?これが020、Ⅱc。但し、上部レバーが有った所、初めから露出計内蔵を考え、1回り大きくなっている。
Ⅱcはレンズ交換可能。レンズはクセノンとヘリゴンがある。其々、前玉のみ交換、これで、35mm、80mmとなる。なので、交換レンズも専用。ヘリゴンとクセノン混用はできない。
ⅠB,ⅢCこの辺りも、人気のレチナ。但し、経年変化でセレンが死んでいるものが多い。
011、Ⅱ。れんずまにあ様が記載している、カードン用47mmエクター付きが有る。見つけるとお勧め。
47mmエクター付。Ⅱで使用するときは、RFで。鏡胴側の距離目織は、他の50mm用と共用している。目測だとずれる?
エクター人気で、010も人気が有る。然し、先にも述べて様に、戦後直ぐの製品。戦前の残り部品で組み立てている。
レ千ネッテと部品共用している物も有る(ツアイスでも戦後直ぐのイコンタ。ネッターの襷使っている物も有る)
アクセサリーシューも付いている物、付いてない物、どちらも有る。
レンズも手に入る物を使っている。その意味でも、レチナでローデンシュトック、イザール付は、010のみ。
本家エクター付と言い、イザール付と言い、れんずまにあ様も中々の珍品コレクター?
レンズに拘らなけれは、戦前最後の148の方が遥かに質は良い。
アクセサリーシュー。私の148には付いていない。
ps)分類に関して。私的には、電池仕様か否かで、分類を2つに分けてはと思います。手動時代はスプリングがメイン、精々ロライ35等の沈胴迄。光学ガラスレンズ、機械式シャッター使用。露光、ピントが人間側の物。
電池時代の物は、露光、ピント共カメラサイドの設定がメインとなる。レンズ其の物も、コンピューター設計、光学プラスチック使用等、手動時代とは全く別の物だと思います。
 ナースマン
ナースマン  2018/05/19(Sat) 06:04 No.1244
2018/05/19(Sat) 06:04 No.1244
スレッドタイトルも、「35mmスプリングカメラ」「35mmビューファインダーカメラ」など、どの機種を含むかで随分変わってきます。
ローライ35を加えるかどうかも思考しましたが、単独スレッドに相応しい独自性と人気を備えたシリーズですので、心配せずとも自動的に除外されるかなと。
意識の外でしたが、確かにAFコンパクトには多くの自動沈胴機が含まれていますね。私もAFコンパクトはこのスレッドの対象には考えていませんでした。
日浦様がご考察の通り、沈胴折りたたみ操作を手動で行うか、電動で自動的に行うかは、一つの解かと思いました。foldingには、自らの意志で折りたたみ操作を行う能動的な意味合いも包含されているということで。
ナースマン様
IIaは友人のをしばらく借用したのみの経験で、そのような弱点があるとは存じませんでした。よい調子の個体を確認する注意が必要ですね。
私のIaも、注意して使おうと思いました。
011のエクター47mmの距離目盛りが他の5cm機と同じ件、まったく存じませんでした。
ただし、他のXenonやHeligon5cmをライカマウントに転用した友人の話では、実焦点距離は少なくともライカの51.6よりも短く、47mmなのではないかと聞いたことがあります。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/19(Sat) 20:38 No.1245
2018/05/19(Sat) 20:38 No.1245
Retina IIIc(スモールC)
底面レバー巻き上げになった。
それまでの8角形から、角を落としたデザインに変更。
前玉交換で、標準5cmf2から、35mmf5.6,またはf4、80mmf4に交換できる。ただし距離計は交換レンズには連動していないため、測距した距離指標を交換レンズのヘリコイドに移し換える必要がある。
ファインダーは50mm標準専用で、交換レンズには外付け専用ファインダー(35,50,80切替)が必要。
セレン単独露出計つき、カバーを跳ね上げると低照度用。
この次のモデル、IIIC(ラージC)がフォールディングレチナの最終機となり、その後は固定鏡胴機に移行する。
IIICは交換レンズに合わせて大きなファインダーに広角・標準・望遠のフレームが全表示される。
友人のIIICアウトフィットを借用した時、メカとしての魅力は大きいのですが、
交換レンズがさすがに使いにくい、一々距離を移し換えていたら間違う。
ファインダー倍率は高く見やすいが、フレームが全部出ていると煩く感じられる。
と思いました。
標準しか使わないと割切れば、随分価格差がありますし、IIIcでよいのです。
ところで私のIIIcはボディ完動でしたが前玉クモリジャンクで随分安価でした。気楽に考えていたものの、結局前玉はどうしようもなく、お蔵入り。
年月が経ち、偶然クリアな前玉だけを見付け、取り付けて見ると、隅々まで全く画質が乱れていません。
普通は前後のレンズは個々に調整されていて本来の組でないと性能が出ないものだと思っていましたが、前玉交換レチナは恐るべき品質管理で、どこからレンズを引っ張ってきても合う精度が確保されているのだなあと驚愕しました。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/19(Sat) 20:59 No.1246
2018/05/19(Sat) 20:59 No.1246
私、戦前バージョンの148を記載します。
先に述べたように、010は、戦前の148の残り部品を使って組み上げた物です。その為、一部レ千ネッテの部品、張革など使っています。
148は39〜40年の製品。メッキ、張革共に戦後のⅡa以上です。
シャッターはコンパー、コンパーラビット(私の個体は300sのコンパー)レンズはF3,5アナスチグマットエクター付き。
このエクターは、クセナーだと言われている。然し、148には、クセナー表示の物も有る。販売地域によって使い分けた?
又は、シュナイダーが自社で組んだエクター?
同時期発売のレチナ、149が存在。こちらはボデーのトリムが、メッキでなく、黒塗り、コンパーシャッター、クセナーレンズのみ。
149が普及品とするなら、シュナイダー製のエクターが存在する?
因みに、39年のレ千ネッテ160には、F3,5コダックアナスチグマット、コンパーの組み合わせである。
使い勝手は、初期のレチナと同じ。但し、シャッターはボデーレリース。目測ですが、距離目盛がFeet。戸惑う。
ファインダーは、枠無し0,5倍(初代117〜010まで同じ)
Ⅱaは0,7倍。比べると、やはり小さい。
私の個体、アクセサリーシューは付いてない。その部分、ねじ止めに成っている。ついている個体も有る。基本的にオプションかも?
画像は、コンテッサとの比較。JR加茂駅展示のC57。
一応、二重露出防止装置が付いているが、簡単な構造。レンズ側使えば、こんな画像も簡単。
 ナースマン
ナースマン  2018/05/21(Mon) 08:23 No.1247
2018/05/21(Mon) 08:23 No.1247
先ず、49年の522/24イコンタ35。れんずまにあ様が、記載。
52年、523/24コンチナ。ドレイカイルでない単独距離計付。
45mm、F3,5ノバー、300sプロンター付と、F2,8テッサー、500sシンクロコンパー付。
イコンタ35と同様、後期型524/24コンチナⅡがある。
50年、533/24コンテッサ。ドレイカイル距離計付RF、F2,8テッサー、500sコンパーラビット付。53年から後期型に当たる、シンクロコンパー付、55年に固定鏡胴となる。尚、55年時点でイコンタ35、コンチナは生産終了している。
コンテッサ3姉妹と言うが、イコンタ35が長女、コンテッサが次女、コンチナが3女。コンチナはメスイコンタの小型版。
私の個体。Tコート付オプトンテッサー、シンクロコンパー付(53年私の生まれ年製)
3姉妹共、巻き上げ、巻き戻しが、底面ノブ。巻き上げは、2つのギアで、パーフォレーション部を動かす(このギアを動かさないと、空シャッターは切れない)ノブが底面にあるため、開いた状態で展示するには、裏蓋にある、ベロを出す。
向かって右がファインダー、ドレイカイルがレンズの上、左にセレン受光部の、左右対称形。左手ピント、右手シャッター。右利き用。
ファインダーは0,7倍。ドレイカイルは流石に分離も良い。
イコンタシリーズの集大成であるが、同年代のレチナⅡaに比べれば劣る。ブローニー版のイコンタ(スーパー6)を小型にして、巻き取り可能にした感じ。
単独セレン露出計はレチナⅡaを超えているが、現代と成っては、私の個体を含め、セレンが死んでいる。
私の個体。手に入れた時、ピントが出なかった。長野様の所でOH。
前の人が弄った様子で、中玉が固定されていなかった。
先日手に入れたウエルチニもほぼワシャー1枚分ピントがずれていた。
最近のジャンク(自身の技術を過信、変に弄って、手に負えなくなった物)がある、困ったことである。
 ナースマン
ナースマン  2018/05/21(Mon) 09:53 No.1248
2018/05/21(Mon) 09:53 No.1248
手元010のイザールはノンコートなので,あるいは戦前モデルなのかとも考えましたが、148にはローデンシュトック付きはないようで、やはり010なのでしょう。戦前在庫のレンズなのか、まだローデンシュトックはコーティングができなかったのか、興味深い所です。
勿論写りではコーティングの差はわかりません。多分テッサー型の反射面数程度では私には認識できないと思います。
その後015は便利になったものの前蓋の突出が大きく、微妙な差ではありますがオリジナルから010以前の畳んだとき平坦に近くなる外観は大変好ましく思います。
コンテッサ3姉妹は、イコンタが長女でコンティナが末娘なのですね。単にグレード順にコンテッサが長女かと思っていました。
恥を承知で知った風なことを書きますがツァイスイコンは大口径フォールディング、コンパクトに消極的で、最上位機種のコンテッサでも2,8のテッサーです。(ビオター付のコリブリも存在しますが)
畳み込み時の平坦さには寄与しますが、コンテッサは前蓋結構突出してるんで意味あるのかな(笑
なので商品の押しの強さは、特に高感度フィルムの性能が期待できなかった当時ではf2のレチナに負けてしまうのだろうなと思います。
でも確かにコンテッサの写りは、「ガウス大口径なんて要るの?」と言うほどの尖鋭さで納得させられてしまいます。そのへんは購入してみないとわからない所が気の毒。
イコンタ35もコンテッサも、固定鏡胴になるまでセルフコッキングは実現しませんでしたが、そのかわりシャッターレリーズの感触がダイレクトで軽く切れが良い。ちょっとストロークは長目ながら、落ちるタイミングはとりやすく私は好みです。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/22(Tue) 22:35 No.1249
2018/05/22(Tue) 22:35 No.1249
148の頃。ドイツが豊かな時代。ドイツコダックも部品供給に問題が無い。自社製の本体に、基本シュナイダーのレンズ使っていた。
149は、黒塗り。レ千ネッテは、黒塗り、トリプレットの普及品。
レチナの黒塗り、イコンタほど艶が無い。張革もネッターに劣る。
戦後、ドイツコダックは困窮。010。戦前の残り部品を組み立て。
本体側。149、レ千ネッテの黒塗りを使った物も。メッキも148に劣る。
自社でレンズ作ってない。取り合えず、手に入る物を組み込む。
本家ロチェスターのエクターを輸入。クセナー、イザールも戦前の物を使ったと思う。
スプリングカメラ。ツアイスが生み出したイコンタが最初。
普及品がネッター。トリプレットのネッター、ノバーレンズ。
高級品。テッサーレンズ、ドレイカイル距離計付。
ツアイスはテッサーレンズに絶対の自信を持っていた。
スプリングカメラをRFにするため考えたのがドレイカイル距離計。
テッサーレンズ、前玉回転でも、問題ないと考えていた。
例えばF2ゾナー。此方は全群移動が前提。基本レンズ交換用。
これをスプリングに組み込むと、一般の距離計が必要。レンズボードもでかくなる。69イコンタ並みに成ると思う。
コンテッサ3姉妹。戦後の製品。イコンタを凝縮した集大成。
普及品ネッターに当たるのがイコンタ35。高級品がコンテッサ。
単独距離計のコンチナ。此方は戦後のメスイコンタ。別系統。
イコンタ35を含め、本体、メッキ、張革は3姉妹とも同じ。
戦後でも、テッサーレンズ、ドレイカイル距離計、絶対の自信が。
ツアイス、F2クラスは、レンズ交換のコンタックス用と考えていた。
F2クラスを組み込んだ、レチナⅡa。連動ピンを使い、良く出来ている。よくこのサイズに出来たものだと感心。
戦前にF2クラスを使ったウエルチナ。戦後のビトーⅢ。どちらも大きく重い。
追伸)ウエルチニOH上がりました。此方でも良いのですが、別項目挙げているので、其方へ掲載します。
 ナースマン
ナースマン  2018/05/23(Wed) 06:04 No.1250
2018/05/23(Wed) 06:04 No.1250
Vitessa Lは元祖Vitessaのシンプルで滑らかな外観に、時代の欲求なのか固定アクセサリーシュー、正面セレン受光窓、軍艦部上面にメーター部を増設しちょっぴり醜くなってしまった後継機です。
といっても当時の他社製品と較べると随分洗練された外観ではありますが。
ところでボディのどこにもLって書いてないので、ちょっと迷いました。ネットで画像を確認し納得。
これはVersion 4または5の50mmf2.8付きです。Lは1954-57の生産ですがバーション毎の生産年はよくわかりません。いずれにせよ結構生産期間は短いのですね。57年からレンズ交換固定鏡胴モデルのVitessa T、1958年からはVitoを距離計連動化したコンサーバティブな機構をもつVitomaticシリーズに交代してしまいます。
レンズはテッサー型のカラースコパー50mmf2.8で、伝説的なウルトロン50mmf2.0にくらべて一段廉価版になっています。この後のレンズ交換機ではウルトロンを選択出来ないのでこのカラスコが表看板になり、それに相応しい開放からシャープなレンズです。
持ってみると密度が高いカメラです。
日浦様も触れておられますが、カメラの材質としては非常に珍しい鉄が外郭に使われており、特にフィルム装填交換時に外郭を外した際、その硬質な感触と造りの薄さが普段触るカメラたちとあまりにも異質なので驚いてしまいます。
5cm固定装着のリーフシャッターカメラとしてはかなり横長で、持つときに引っかかるところがないので革ケースに入れています。
ファインダー窓が右手側(プロミネントもそう)、右手親指フォーカシング、左手巻き上げプランジャーと独特の操作系で最初は戸惑います。数枚撮ると慣れてきてテンポ良く撮影できますけれど、しばらく使わないとまた戸惑います(笑
さてCLPO様のモデルは無限遠だとプランジャーが飛び出してこないそうですが、このLは無限遠でもお構いなしにレンズカバーが開くと同時に飛び出してきます。元来勢いよく飛び出しても大丈夫な強度は確保されているはずですが、まあ長持ちさせたいなら軟着陸する方がいいという意見が多いですね。
ポジをメインにしていた昔はセレン平均測光など全く当てにならないので付いているだけ無駄のように思っていましたが、最近ネガが主体なので、セレンメーターが結構好きになってます。勿論暗い所では役に立たないんですが。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/05/31(Thu) 18:59 No.1254
2018/05/31(Thu) 18:59 No.1254
あがりをみたとたんに目を見張りました。
開放遠景では隅々まで均一に解像しており、今のSkoparを名乗る製品とは雲泥の差です。
なによりコントラストが高く尖鋭度が凄い。目に刺さるよう。
諸事情あるでしょうが、ウルトロンやめちゃってもこれなら十分と思わせるだけのものはあります。(勿論明るさでは代わるものではありませんが)
試写画像は私的なものが多くて上げにくいのが残念。Vitessa L, Skopar 50/2.8, 開放、1/30、TMY
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/06/07(Thu) 07:37 No.1257
2018/06/07(Thu) 07:37 No.1257
大きい方、ヘリア、アポランサーと同系列。尖鋭なのに柔らかい。
私の好きな画像。こんなの見たら、ビトー当たり欲しくなりますね。
私の知っているのは、90年代の、Lマウント国産ホクトレンダー。
模倣のうまい日本人が、新種ガラスでコンピューター設計。ホクトレンダー風に作った?
本家の物は、50年代に完成していた?これ以上必要ない。素晴らしい。
 ナースマン
ナースマン  2018/06/08(Fri) 05:39 No.1258
2018/06/08(Fri) 05:39 No.1258
テッサー型は暗い方が良く写る、f2.8は欲張りすぎで開放は今ひとつ、と、ずっと思っていました。
VitessaLのColor-Skoparは完全にそれが誤解だと思い知らせてくれました。
ナースマン様ご指摘のように、Vitoのほうが軽く小さく使いやすいのは間違いありません。
Vitessaボディは、5cmf2.8にはあまりに重厚すぎるのです。Vitomaticを思わず探し始めたくらいですので...
ただ、蛇腹折りたたみVitoは、確かf3.5だけだったかしら?
現代のカラースコパー含めV....製品は、今の設計、今の材料を使っていますので、昔とは比べものにならないほど凄い性能を期待してしまいます。
また、写りは素晴らしい、現代の性能、写りすぎて面白くない、などという評価もよく伺います。
しかし、私は当たり所が悪いのか、全然そうは思えないのです。
周辺画質が落ちすぎます。1機種だけならまだしも、私が試させて頂いたほとんどの機種がそうなのです。
そういう設計方針なのかもしれませんが、1950年代より周辺が悪いレンズを私は期待しておりません。
今回のColor-Skoparの高性能を見て、つい愚痴ってしまいました。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/06/09(Sat) 23:04 No.1259
2018/06/09(Sat) 23:04 No.1259
1950年 バルダカメラヴェルク製フォールディングカメラ
この個体はプロンターSシャッター:1/300-1,スタインハイル カッサー50mmf2.8(トリプレット)つき.他にラジオナー50/2.9や同スペックのバルダナー、ハポナー、または50/3.5ラジオナー、バルダナーつきがあるが大概3枚玉で廉価版に徹している。
3枚玉f2.9は如何にも欲張りすぎに感じられ、全く期待していなかったが流石はスタインハイル、後ボケを除けばなかなかすばらしい写りで、特に色彩の鮮明さに驚かされました。
操作性は大きな巻き上げノブが特長で、特に変わったことはありません。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/07/05(Thu) 02:18 No.1265
2018/07/05(Thu) 02:18 No.1265
戦前のヴィトーを戦後に再生産したモデル。
戦前のノンコート スコパー(テッサー型),コンパーラピードから、コートつきカラースコパー5cmf3.5,シンクロコンパーに進化した。
角形のレチナと対比し、曲面で構成され優美な外観。
巻き上げ、巻き戻しノブは左右対象に配置され操作性はよい。
機能的にはセルフコッキングがつかないレチナIと同様だが、前玉回転。
レンズの高性能には定評がある。
ベッド部分にシャッターが配置されているのはベッサIIと似ている。
バルディネッテと同じく、今は転売してしまい手元にない機種で恐縮です。
画像も、ベスト判のVirtusと並んだものしかありませんでした。
(ちなみにこのVirtus, レンズの焦点が全く来ない、何か組み間違いが想像される品物)
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/08/16(Thu) 23:13 No.1324
2018/08/16(Thu) 23:13 No.1324
チャートや定点テストで成功したと思っても実写では惨憺たるもので、試行錯誤中ですが、粒状性と解像度だけはすばらしいものです。
その高解像力についてこれるカメラは限られます。
USエクター50mmf3.5はf8付近で申し分ない高解像力を発揮します。
ただ、近距離での目測ミス、手ぶれがたいへん多く、落ち込んでいます。
Retina 1a, Kodak Ektar 50mmf3.5, f8, 1/60, Fuji minicopy HRII, Rodinal R9 x500, 25度30分
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/08/26(Sun) 09:52 No.1349
2018/08/26(Sun) 09:52 No.1349
スプリングカメラのように前蓋を起こすと沈胴レンズが立ち上がる。内部の遮光には布を使っていて蛇腹カメラといえなくもない。
サイズ100x61x34mm,190g(前蓋が丸く盛り上がって2mmだけ前モデルより厚みが増した)
電源:CR1/3x2個(SR44またはLR44x4でも作動します)
露出:絞り優先AE, CdS(f2.8〜f16、Iso100/EV0-17、無段階電子シャッター1/500-8秒、フラッシュをホットシューにマウントすると1/125固定)、x2露出補正つき、電子セルフタイマー
感度設定:ISO25〜1600 (x2補正併用するとISO12可能)
レンズ:Color-Minotar35/2.8(3群4枚テッサー型+スカイライトフィルター固定、マルチコート)
最短撮影距離:前玉回転式 0.7m、目測
フィルム巻き上げ:レバー2作動、分割可能。
ファインダー表示:倍率0.5倍程度、アルバダ式ブライトフレーム、シャッター速度指針表示1/500、1/125、1/30。指針が表示外を指す時は高速範囲外、手ぶれ警告になる。
当時の販売価格:93,000円(エルモ扱い)レモン社の並行輸入では半額くらいという話も。
ローライ35が先鞭を付けた超小型35mmカメラ、ミノックスの回答が、プラスチック外装で非常に軽量で薄型のMinox35EL。そのシリーズの発展型。最初のモデルから外観や基本スペックはほとんど変わらないが、地道な改良が行われている。
最短撮影距離0.7m 前モデルの最短距離0.9mと較べ20cm短縮された。
使用電池が5.6VのPX27から一般的なCR1/3N 2個に変更
スカイライトフィルター別売だったものが、固定になった(そのためか前蓋が2mm突出した)
感度設定高感度側が800から1600へ拡張。
フィルム装填時に先端に食い付くクイックローディングのようなプラスチック構造がスプールに増設された。
他に、デートバック、小型化された専用オートストロボ
使い勝手:薄型で非常に軽量なので携帯がもっとも苦にならないカメラのひとつ。
巻き上げは重い。2回巻かないといけないが,固いので巻き不足になりやすい。しっかり巻く必要がある。
シャッターレリーズは軽すぎるくらいに軽い。誤って指を乗せただけで切れる。手ぶれ防止に有効。
距離リングはレンズ先端にあり軽く回る。誤操作するほどではない。
絞り変更は少しやりにくく指が太いと回しにくい。
近接は35mm広角といえど目測で測定するのはかなり厳しい。しかし私は左手を伸ばした先端が70cmなので、0.9mよりもむしろ精度良く近接出来ると思った。目測カメラは体や歩幅など補助スケールを沢山持っていると有利である。ただ前玉回転で近接すると画質は低下するはずだが楽しさ優先と割切るべき。
ストラップアイレットはないので両吊りストラップつき専用ケースに入れるか、底部三脚穴にハンドストラップをネジ込むしかない。後者が一般的だったと思う。昔旧型のGTをストラップ無し(ベルトクリップをアルミで自作して)で使っていたら何度も落として傷ヒビだらけになったので、ストラップはお勧め。ところで裏蓋は下に引き抜くのですが三脚穴にネジ込まれてると外れない。
レンズ性能はかなり良いのだが、アサヒカメラの解像力テストでローライ35より少し低い値で、リコーFF-1より高値。
最近低感度フィルムをよく使うため、ISO25設定はありがたい。さらにx2補正でISO12まで落とせるのはコンパクトカメラとして希有な利点。高級SLRでも最低感度と最高感度では露出補正が効かない機種もあるため、このx2補正は本物だ。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/09/20(Thu) 21:54 No.1398
2018/09/20(Thu) 21:54 No.1398
ご参照:ttp://www.submin.com/35mm/collection/minox/35mm_variations.htm
MLはファインダー上部にシャッター速度表示がありLED点灯します.
その他の機種は視野右端1/500,1/125,1/30表示の間を指針が動き,その外を指すとオーバーと低速警告を意味します。大雑把ですがこの規模のカメラとしては非常に明快で安心出来ます。
シャッターボタン 軍艦部ボタン 電池 巻き上げ 備考
Minox 35EL (1974) 赤,中央にレリーズネジ バッテリーチェック(BC) ValtaPX27 レバー2回* Color-Minotar35/2.8,
絞り優先,感度25-800,最短0.9m
Minox 35GL (1979) オレンジ,中央ネジ BC, x2補正 同上 レバー2回 同上
Minox 35GT (1981) 黄,ボタン横ボディにネジ BC, x2補正,セルフ 同上 同上 同上
Minox 35ML (1985) 黄,同上 同上 同上 同上 絞り優先+プログラム,
軍艦部平坦,速度表示LED,感度25-1600
Minox 35AL (1987) オレンジ,同上 BC, セルフ 同上 同上 Color-Minor 35/4固定焦点
プログラム露出のみ,感度設定なし
Minox 35GT-E(1988) 赤,同上 BC, x2補正,セルフ CR1/3x2個 同上 Color-Minoxar35/2.8
マルチコート+SLフィルター固定,
感度25-1600,イージーロード,最短0.7m
*ELがギア巻き上げという引用元の記載ですが、現物を確認(1台のみ)したところ、GL以降より指掛かりが非常に小さいながらレバーといってよい突起が備わっています。使い勝手はGL以降と同じ二回巻き上げ(小刻み可能)で、決してオリンパスXAのようなギアではありません。これをギアと言うなら最終機種GT-Eまでずべてギアでしょう。或いは極初期ギアのみだった可能性はあります。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/09/20(Thu) 22:01 No.1399
2018/09/20(Thu) 22:01 No.1399
持ってはいないのですが、観音開きのレンズカバーが印象的でした。全体がプラスチッキーなのですが、今となっては個性的なカメラでした。
 efunon
efunon  2018/09/20(Thu) 22:26 No.1401
2018/09/20(Thu) 22:26 No.1401
ミノックス35は厳密には前カバーと連動した沈胴ですが、同系のコンタックスT、ヤシカパートナーと共に、
レンズを起立させるのが電動ではないということでフォールディングとしてお許し頂けるかと。
所でagfa compactとRolleimaticはいつか使ってみたいです。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/09/20(Thu) 23:24 No.1402
2018/09/20(Thu) 23:24 No.1402
手元にミニコピーHRIIが豊富にあるので目下もっとも使っています。コダックテクニカルパンもあります(他の用途に使いたいので高解像力には控えています)
最近はATP1.1, Adox CMSなどが登場、軟調現像液の種類も1980-2000年代に較べてむしろ選択肢は豊富になっています。
撮影側は、おそらく一眼レフのレンズを絞って使えばかなりのところかと思いますが、常時携帯できるコンパクトカメラで凄い画質が得られたら痛快です。
Contax Tは日浦様のご解説がありますので重複は避けますが、T2以後自動焦点の後継機と比較し大変小型です。
同一サイズまたはそれ以下のカメラは既に存在していました。しかし、レンズに掛けた比重が空前のものでした。
コピーフィルムでは、何処まで拡大しても果てしなく解像しています。
低倍率で全体像
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/11/01(Thu) 23:04 No.1419
2018/11/01(Thu) 23:04 No.1419
ゾナー38mmf2.8は、一眼レフ用ディスタゴン35/2.8と較べて開放では四隅の画質がすこし甘いのですが、圧倒的に小型で、f8に絞ると四隅の画質も均一で文句ありません。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/11/01(Thu) 23:07 No.1420
2018/11/01(Thu) 23:07 No.1420
フィルムはトライXで、試しにロジナール100倍希釈で現像してみたので全く粒状性が違い比較はできませんが、高速シャッターの分手持ちでのシャープネスはいい線いっているように見えます。
ContaxTは何か支持具を使って再検してみたいです。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/11/08(Thu) 00:22 No.1424
2018/11/08(Thu) 00:22 No.1424
他機種ではあまりみられない、少し広角で明るいレンズ。
今までトライXやカラーネガなどISO400フィルムで撮っていたところ、開放から十分に尖鋭で、絞り込むとさらに良くなる、出来がよいモダンクラシックのテッサー型に共通する性能と思っていました。
ミニコピーのような超高解像度フィルムでは、開放からf4くらいまでハロが目立ち、周辺画質がトロンと溶けたような少し甘い印象でした。
f8から締まりが改善し、f11でかなりよく見えますが、コンタックスTのゾナーやローライ35Bのトリオターよりも少し尖鋭度が劣るようです。
絞りを開けると画面上1/3の解像力が特に甘くなるので、フロントスタンダードの平行が少しずれているのかと思いました。
このカメラは厳密に言えばミニコピーには合わない、敢えて言えばもっと高感度で絞り込み気楽にスナップするのに適しているかなと思いました。
作品:「立ち呑み所」イコンタ35,クセナー45mmf2.8、Y2フィルター、f5.6、1/30、ミニコピーHRII(EI50)Photographer's formulary modified POTA, 20dig、15min
 れんずまにあ
れんずまにあ  2018/12/13(Thu) 22:14 No.1472
2018/12/13(Thu) 22:14 No.1472
先に紹介した35GT-Eの基礎となったモデル。
レンズはカラーミノター35mmf2.8、3群4枚テッサー型。フィルターネジはないが別売かぶせフードはスカイライトフィルターと一体になっている。
その他スペックは変わらないが、この個体はISO感度が25-1600となっており、先に記載した一覧表800までと違う。製作年代によって1600になったものがあったのか?
1984年頃使っていた個体が2年で故障友人にあげてしまったが、最近タダみたいなので買い直しました。
その当時から開放画質は芳しくなく思っていました。今度の個体も開放はぼってりした描写で鋭さがなく、開放からかなり尖鋭なGT-Eとは歴然と違う画質です。個体差なのか、無限が合っていないのか、また私が焦点合わせをミスしたのか、もう少しテストしてみます。
絞るとこのミニカメラで撮影したとは思えない尖鋭な画質になります。
追記:電源は、手元のPX27が全滅していて頭抱えましたが、LR44x4個をパーマセルで直列連結したら立派に作動しています。電圧が標準より高めなので心持ちアンダー露光のような気もしますが、ネガならほぼ誤差です。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2019/01/30(Wed) 21:47 No.1494
2019/01/30(Wed) 21:47 No.1494
レチナは主にヨーロッパ向けにローデンシュトックのレンズがついたモデルを当てていたと聞きますが、距離表示はメトリックとフィートが両方混在し、綺麗に分かれるわけではないようです。
標準ヘリゴン50mmf2.0(IIcには50mmf2.8もあります),同じく広角35mmf5.6、望遠80mmf4を、後群を残してバヨネットで前群交換します。
ラージCは大きなファインダー窓に、3種のブライトフレームが浮かぶため、そのまま使えます(そのかわり3種フレーム出っ放し)が、スモールcはボディのフレームは50mmしかありませんので、専用外付けファインダーをクリップオンします。
前玉交換レンズをテストしてみると意外に結構解像力が高く、なかなか悪くありません。
ただし、皆様よくご存知の通り、蛇腹レチナの交換レンズは、ファインダー距離計を単独距離計として使い、標準レンズ用の距離指標を読んで、望遠広角用の距離指標に移し替える大変煩雑な距離合わせになり、じっくり合わせれば精度はちゃんと出ていますが、実際出先でそんなことやってられるかと。
80は無限遠に限定し、35はf値が暗いので、距離計を使わず指標で目測すると実用的に感じます。
ただし、標準以外ではベッドを畳めないので、なんとも微妙な出で立ちになりますね。
この前玉交換レンズは、レチナレフレックスCに装着すると、直接ファインダー内で焦点合わせできるので、大変使いやすくなります。
(もちろん、クセノン交換レンズはクセノン付きボディ、ヘリゴンも対応ボディでないと、バヨネットが違うので相互に装着できません。)
50mmレンズの先鋭度は、シュナイダークセノンのほうが若干鋭く感じますが、ヘリゴンも大変ハイレベルで、実用的には差はないと思います。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2024/12/12(Thu) 15:59 No.2667
2024/12/12(Thu) 15:59 No.2667
これも仲間に入れてもらってよろしいのかな・・既に平成の年号となってからのカメラなので、「趣旨に合わない」とご指摘がございましたら引っ込めます。
無塗装と思われるチープなカメラですが、跳ね上げ式の前扉を開くとフラッシュが現れ、レンズ鏡胴がせり出します。
隣のOLYMPUSμは本体の大きさが分かりやすい様にと置きました。
1990年代前半?に発売されたKODAKのコンパクトカメラです。重量は140g。
フォーカスフリーのレンズは34mmF5.6で機械式シャッターは1/125単速です。背面のノブで巻上げ、巻き戻しレバーは小さく2段階に折り畳まれています。
レンズ脇のフィルム感度切替レバーによって絞りがF8・F11位に変化します。フラッシュ使用時に絞り開放となります。
単4型電池2ケを使用しますが、これはフラッシュ使用に必要なだけで電池無しでの撮影が可能です。重さはたったの140g。
このCAMEOにはフォーカスフリーでモーター巻上の機種とAF機能が追加された機種も存在しました。
フラッシュを跳ね上げて(レンズから距離を取って)作動させるデザインは1980年代からKODAK製カメラに幾つか見られます。フラッシュの調光機能が一般化する以前には有効な手段だったのでしょうか。
オリンパスXA1でフォーカスフリーカメラの(時と場合により)素晴らしいのを知ってからは、ちょくちょく本機のようなお手軽カメラにも目を向け手に入れるようになりました。明るい日中であればパッと見には良い結果が得られることが多いです。
レンズが手動で沈胴位置から撮影状態に組み上がる、手動巻き上げカメラというのがこちらのカテゴリですので、立派に合致していると私は思います。
確かに固定焦点を彼方はフォーカスフリーと言いますね。なんとなくカッコよくなった気がいたします。
400や800のフィルムが微粒子化して常用されるようになった時期のカメラでしょうから、34mmf5.6なら、拡大しなければ1mから無限まで問題ないでしょうね。
でもライカだって広角は絞り込んで3mくらいにセットしパンフォーカスで使うことが多いし、暗ければフラッシュ常備で準備万端ですね。
34mmというのがいかにも彼方様らしい。1mmでも売れるスペック差をつけようと。
XA1は私も愛用しています。電池がいらないのでいつでも即応。スナップではライカ以上の写りだと思います。
他の私の固定焦点カメラはヤシカパートナーを楽しんでいますが、XA1の写りは頭ひとつ以上抜けています。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/01/24(Fri) 23:04 No.2697
2025/01/24(Fri) 23:04 No.2697
元々ケースレスカメラなのでわざわざ一緒に持って行くのも面倒ですが、畳めるのでポケットの隙間に入れても邪魔になりません。
フィルターが固定されているのが特徴で、UV, スカイライト、ND(4?)があります。
GT-EからはUVフィルターが内蔵されたためか、フィルター無しフードのみになりました。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/01/26(Sun) 13:32 No.2701
2025/01/26(Sun) 13:32 No.2701
私もれんずまにあ様と同仕様のレチナIa #015を持っていて疑問に思っていることがあります。
レチナIaのコンパーラピッド搭載機は1951年の発売初期のみと何処かで読んだ気がします。それなのにレンズがESで始まる1947年のレンズが付いていて、本体と年式が合いません。私はてっきりニコイチなどの改造品と思い、使うのを躊躇っておりました。
こうしたレンズとカメラ本体の年式が合わないことって良くあることなのでしょうか。
私はレチナに関してはファンであっても門外漢なので、直接のご返答は到底できかねますが、想像をお許しください。
おそらく貴兄もそう考えておられると思いますが、レンズや部品の在庫を使用して処分することはよくあったのではないかと。
戦後すぐの010は戦前のストックを使っていますし、どう見てもローデンのYsarはノンコートでチグハグです。
Iaはだいぶ後の製品なので同一視はできませんが、前蓋がもっと大きなレンズ用にしか見えず、Ektarf3.5にはもっと薄くできたんじゃないか、ひいてはEktarって在庫処分じゃないかと思ってしまいます。
そのあたりは立派な資料があるのかもしれませんが、素人の邪推でお許しください。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/01/29(Wed) 22:17 No.2708
2025/01/29(Wed) 22:17 No.2708
ご返答ありがとうございます。なるほど、コダックにも色々と事情があったのでしょう。
販売当時はドイツ製レンズの方が人気が高かったのかも知れませんね。他の個体は良く見ていませんでしたが、ESのレンズを載せた個体が沢山出てきたりして・・
ピントを調べても1m、無限遠とも問題無いようなので、このまま撮ってみます。疑問が解けてスッキリしました。
前蓋の件はずっと気にしていませんでしたが、確かに大きいですね。日浦様もコンテンツ内で書かれていたように、畳む時にシャッターチャージ部分辺りから金属棒が現れて来ますので、これを避ける必要があったのかと思います。わたしの1b(小文字)の方はこの金属棒は出て来ませんでした。よって前蓋をスムーズな形状に変更出来たと想像します。
1980年発売の35mmフォールディングカメラ
レンズはカラーチノネクス35mmF2.8(3群4枚)距離は目測で 1m〜∞
シャッターは電子式プログラムシャッター 1/8〜1/1000sec
定価は外付けストロボ付きで¥32,800
重量は225g(本体のみ・実測) 電源はLR(SR)44ボタン電池を2ケ使用
非常に軽量かつコンパクトにまとめられたカメラですが、要所には金属が使われていて安っぽさや弱さは感じられません。
観音開きの前蓋開閉は巻上レバーを一段起こす・戻すの動作にて行われ、これも弱さはありません。ただし、前蓋左右の装飾パネルが接着剤の劣化で失われている個体が多いです。沈胴する鏡胴後ろには小さな蛇腹があります。
絞りとシャッターについてはプログラム任せですが、1/250までは絞り開放のプログラムだと言われています。
写りはビビッドな色合いで高コントラスト、そこそこシャープに見えます。
小さいながらも蛇腹が写りに貢献しているのかも知れません。機体の写真にも写っていますがこれ、電池蓋が失わわれたジャンク品です。無様にもプラバンと金属板で電池を留め、メンディングテープで隠しています(笑)
1978年発売の35mmフォールディングカメラ。
レンズはカラーリケノン35mmF2.8(3群4枚)距離は目測
シャッターはCDSによる自動露出電子式のコパルで2〜1/500sec セルフタイマーは無し フィルム感度はASA25〜400
電池はLR44またはSR44を2ヶ使用 アイレットは片耳
MINOX35シリーズに触発された?かどうかは定かではありませんがサイズも近いものがあります。MINOX35ELの幅100mm×高さ61mm×奥行31mm重量182gに対しFF-1は107mm×64.6mm×30.4mmで218gと外装には金属部分が多いにも関わらずかなり頑張って小型化しているのが分かります。並べて見ると・・やっぱりよく似ていますね。
前蓋裏蓋ともMINOXと比べガッチリしているので、さほど扱いに気を遣う必要がありません。裏蓋はヒンジ式、巻き上げも通常通りの1回巻上げ。前蓋の開閉にて電源が入るのは同じで、低輝度時にはファインダー内に赤LEDが点灯します。距離環にはリコーのカメラでお馴染みのグリーンの二重丸(スナップショット位置)がプリントされています。
フォーカス以外は全自動なのでMINOX35のように絵作りする用途には向きませんが、割合小気味よく使えて写りも価格差を考えればまあまあシャープと言えます。
この機種の多くは経年でファインダーが曇っています。清掃するには細かい場所での半田付けにスキルが要求されます。
この機体色とは別にトップカバーをシルバー塗装にしたモデルが存在しますが私は見たことがありません。1980年には改良型のFF-1sが発売されました。
ベラミは使う友人がいませんでしたが、FFー1は学生時代、恩師がクラブの旅行引率にご持参で、重量級機材を持ち込む学生を横目に飄々とご撮影されていました。
プログラム露出専用ですが、のちに拝見した画像では、暗めの条件でもかなりシャープな画質でしたので、開放近くでも優秀なレンズなのでしょう。
当時はミノックスGTユーザーでしたのでFF-1に手を出さず、最近気になってもオークションでは結構な価格でまた気楽には手が出せません。
ベラミもプログラム専用ですが、FFー1同様にレンズの性能は定評がありますね。
FF-1Sは確かレンズがマルチコートになったのでしたっけ。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/03/21(Fri) 22:34 No.2775
2025/03/21(Fri) 22:34 No.2775
私の中ではなぜかリコーのレンズでは失敗が少ない気がします。相性が良いというのでしょう。写真のリコーオートハーフも真面目に掃除したらとても良く写るようになりました。
リコーのフィルム末期に販売されていた3枚玉の廉価なAF/MFコンパクトカメラ、MF-1、RX-60など(どちらも30mmF3.9の3枚玉)も良く持ち出しています。
さて、FF-1sなんですがレンズもマルチコートに変更されたというのは初耳でした!欲しくなっちゃいますねぇ・・なにしろ販売されていた頃は私はあまりカメラに興味が無かった頃でして、メーカーサイト内の情報(電池消耗時にシャッターが開かずに切れてしまう現象を電子レリーズにすることで改善、セルフタイマーを追加、ファインダー周辺のデザインを変更)くらいしか知りませんでした。れんずまにあ様の情報に感謝いたします。
RetinaのKodak-Anastigmatについて以前から疑問があり投稿します。
Ektarが付かないKodak-Anastigmatは廉価版でトリプレットだという情報があるのですが、手元にあるKodak‐Anastigmat (Type 119)、U.S.A Kodak Ektar (Type 010)、Xenar (Type 118)の後群は同じ2枚張り合わせで3群4枚のテッサータイプに見えます。
Kodak Catalog Projectの1935−38年のUSA Printed カタログを見るとXenarがanastigmat lens と表記され、Kodak-Anastigmat Ektarはそのまま表記されています。
1935−38年の複数のカタログでType 119 (黒塗り)は掲載されず、117 anastigmat lens (写真はXenar) と126 Kodak-Anastigmat Ektar以外のレンズの記載はありません。
いずれも$57.50 1種です。
私はKodak-Anastigmat Ektarを持っていないのですが、Xenar、Kodak‐Anastigmat、Kodak-Anastigmat Ektar、U.S.A Kodak Ektarは3群4枚のテッサータイプなのでしょうか?
U.S.A Kodak Ektar付きの Type 016 IIaがあるのですが、Compur-Rapidが付いているのにシャッターチャージギアカバーにSynchro Compur用のM、X表記があるので、さすがにこれはType 015 Iaのレンズを移植したものだと思うのですが、あってもおかしくはないような気もしています。
 Nya
Nya  2025/03/29(Sat) 03:49 No.2784
2025/03/29(Sat) 03:49 No.2784
US Ektar 50/3.5つきのIIaは貴重ですね。私は初めて拝見しました。
私もKodak Anastigmat Ektarを持っておりませんので反射光など調べることはできません。
今直ちに証拠資料を提示できませんが、今までの知識では、Kodak Anastigmat Ektarは、Schneider XenarのOEMと聞いています。
Xenar、Kodak-Anastigmat Ektarは同一として、3群4枚構成のテッサーです。
U.S.A Kodak Ektar は確かな構成図が出てきませんが、Ektraの50/3.5や、Signetの44/3.5の構成図は3-4の3群目張り合わせ局面の向きがTessarと逆の画像が検索されます。
Retina 010のUSEktarはテッサーかもしれませんが、いずれにせよテッサー系統とみてよさそうです。
Kodak‐Anastigmatはちょっとわかりません。Reomarなどトリプレットもありますね、でも3枚構成はRetinaでなくRetinetteというジュニアブランドに装着されてますから、Retinaに3枚玉が装備されたとは考えにくいのではないでしょうか。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/03/29(Sat) 19:13 No.2786
2025/03/29(Sat) 19:13 No.2786
実は少し前にRetinaのKodak-AnastigmatについてChatGPTが、
「Type119 RetinaのKodak-Anastigmatはトリプレットで廉価版として作られた」と回答しました。
前提となる条件や情報を何度か追加して質問しての回答でした。
ChatGPTはネット上の情報を元にしているのでそういう情報がどこかにあるのか?と思いました。
戦前のKodak-Anastigmat付きはRetinette Type160改のRetina I Type167がありますが、この前玉回転トリプレットの情報から、メッキなし黒塗りのType119 RetinaにKodak-Anastigmatが付いたものが同様の廉価版だという情報があるのかもしれません。
Kodak-Anastigmat付きと記載のあるRetina Type010は戦後すぐに戦前のレンズ在庫を使って作られたようですから、もしかするとType119(1936−38)の後の黒塗りのType 143(1938−39)、Type149(1939−1941)にもKodak-Anastigmat付きがあるのかもしれないと思って色々検索しているのですが、見つかりません。
後群の反射からテッサータイプであるのは間違いないと思うのですが、もやもやしています。
 Nya
Nya  2025/03/30(Sun) 01:14 No.2787
2025/03/30(Sun) 01:14 No.2787
今後とも何卒よろしくお願いします。
こちらも気をつけておきますが、新たな情報を発見されましたら、ぜひご提示ください。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/03/30(Sun) 09:05 No.2788
2025/03/30(Sun) 09:05 No.2788
https://shiura.com/camera/autographic/index.html
に載せているレンズは Ektar と書かれていない(このころはまだ Ektar というブランドがなかったのかも)のですが、レンズ記載の特許情報からわかるように正真正銘の Tessar です。
Retina の Kodak のレンズは、Ektar に関する情報は多いですが、Ektar の記載がないものについては情報が乏しいかもですね。私も、よくわかりません。。
なお一般論として、ChatGPT 等の回答は誤りを含むことが非常に多いです。確かに、ネット上の情報をもとに学習していますが、ある特定の情報を勝手に一般化したりします。質問してから調べるわけではないので、人間で言えば「昔、・・・という話を聞いた気がする」みたいなぼんやりした記憶から答えるような感じです。
今回の場合では、例えば、他の米国製の廉価なカメラに搭載されている Kodak Anastigmat が3枚玉だ、というような情報があれば、それを勝手に一般化した可能性もあります。言語運用能力は非常に高いので、こちらからすべての情報を与えて要約させたりすると高性能ですが、事実の記憶という点ではまったく容量が足りず、事実関係の確認(ChatGPTそのものから知識を引き出す)は避けたほうがいい、ということが言われております(当方、情報科学系の研究者です)。
ChatGPT にも Deep Research という機能があり、これは質問に対して ChatGPT が自ら Web検索しながら答えを探していく仕組みになっていて、回答の信頼度が向上しています(もちろん完全ではありません)。その過程で参照したURLも表示されるので、合っているかどうか自分で確認することも出来ます。
 日浦
日浦  2025/03/30(Sun) 12:18 No.2790
2025/03/30(Sun) 12:18 No.2790
https://chatgpt.com/share/67e8bd25-ec28-8008-b756-2780e420c1e7
deep research が出した結論としては、F4.5がトリプレット、F3.5がテッサー型、というものです。情報が少ない分野のため、正しいかどうかはわかりませんが、いろいろな情報源を収集できるだけでも有用なように思えます。当方の画面では思考?(集まる情報に対し、次はこのキーワードで検索して、・・という経緯)が表示され、それもなかなかに面白いものでした。
ps. これだけのことが、質問を投げて10数分待てばできるので、まさに、驚異、脅威・・です。
Type119も含めて戦前RetinaにはEktarなしのKodak Anastigmatがあったのですね。
戦前Retinaの情報はアメリカコダックの情報だけで、ドイツ製造の情報は殆ど見つけることができませんでした。
ChatGPTの検索能力の方が優れていると認めるのはちょっと悔しい気がします。
The Retina I’s lens/shutter options list explicitly includes a “Kodak Anastigmat 1:3.5 f=5cm (French-made lens
フランスレンズが大好きなので、これは魅力的ですね。
 Nya
Nya  2025/03/30(Sun) 15:28 No.2795
2025/03/30(Sun) 15:28 No.2795
ちょっと気になったのですが。
私の所にあるKODAK35はanastigmat4.5ですが、上位機種には4枚構成で3.5のanastigmt-specialが付いている、となっていますがこコレって関係ありますかね?
Retinetteも1939年から製造されているはずですが、アメリカKodakのカタログには載っていません。
Kodak35は米国製造だと思います。
不思議なことに1939年3月のカタログに乗っているKodak35 Kodak Anastigmat Special の写真ではレンズ銘がf:3.5 51mmで、10月号ではf:3.5 50mmとなっています。
同年にはKodak Bantam Specialも発売されいています。
1939年3月号にはType141 Retinaも載っていますが、10月号以降Retinaは載っていません。
ドイツRetinaの製造情報が戦禍で失われて詳細が分からないようなのですが、ドイツ語で検索すると情報があるのかもしれませんね。
 Nya
Nya  2025/03/31(Mon) 00:08 No.2797
2025/03/31(Mon) 00:08 No.2797
もう既にKODAK35に関してもお調べになっていたのですね。大変失礼いたしました。
自分のKODAK35をトピックに投稿しようと以前からあちこち調べておりました。その際に、「戦禍が近づいてRetinaの輸入に頼ることが出来なくなる」ことからKODAK35が開発された、とする記事を読んでいたのでひょっとしてRetinaとKODAK35の部品にある程度共通する部分があったのではないかと考えた次第です。フランジバックも近いように見えます。
※ウチのKODAK35(初期型)のANASTIGMAT4.5レンズも51mmでした。
51mmのKODAK35が実際にあるのですね。
調べている途中でKODAK35のKodak Anastigmatが51mmという記述はあったのですが、写真は50mmばかりでした。
添付画像は1938年10月のUSコダックのカタログで11月に発売予定となっています。
このf3.5 51mmレンズのシリアルNO.は87AT、左側のf.5.6 50mmは136M2と読めます。
1939年3月の発売後のカタログでも同じ画像が使われています。
しかし添付画像右側の1939年10月のカタログでは、f3.5 50mm NO.978、f5.6 50mmはNOなしになっています。
51mmレンズは販売前の量産試作機かなにかでカタログには載っているけれども実際に市販はされなったんじゃないかと思っていました。
取り敢えず撮ってから様のレンズのシリアルNOはいかがですか?
市販されていたとすると、実際に焦点距離が51mmと50mmで異なっている可能性もありますね。
f3.5 Kodak Anastigmat Special 51mm、f4.5 Kodak Anastigmat 51mm、f5.6 Kodak Anastigmat 50mmって、どうしてそうなったんでしょう?
 Nya
Nya  2025/03/31(Mon) 14:56 No.2800
2025/03/31(Mon) 14:56 No.2800
Agfa Super Solinette
デザインは好きなのですが、きれいな円形絞りなのにレンズがSolinar f3.5だったりノブ巻き上げシャッターチャージ非連動とか中途半端な感じです。
フォールディングカメラとしてはとても薄くフラットなのですが、なかなか撮影に持ち出す機会がないです。
Rollei Rolleimatic
これもデザインはとても好きなのですがEEが凡庸でf2.8のレンズを活かせない感じです。
EEもデザイン並みに攻めてPetri Computer 35とかのように絞り開ける設定にしてほしかった。
 Nya
Nya  2025/03/31(Mon) 15:03 No.2801
2025/03/31(Mon) 15:03 No.2801
ペトリカメラ1968年発売
これも35mmフォールディングカメラという認識で宜しいでしょうか。
レンズが沈胴する連動露出計つき35mmコンパクトカメラ。距離計は無し。
レンズはCCペトリ40mmF2.8(3群4枚)撮影距離は1m〜∞沈胴量は約11mm
シャッターはペトリMS機械式(B・1/15〜1/250)セルフタイマー無しフィルム感度ASA25〜800
重量は実測395g 電池は1.35V水銀電池1ケ(LR/SR44電池で代用可)カウンターは自動リセット・順算式
シャッター速度と絞りを軍艦部のダイヤルで、フォーカシングを背面のダイヤルで行う独創的な操作体系。カメラを左手で保持したまま、巻上レバーを含め全て右手人差し指と親指だけで操作できます。ファインダー内に露出計の針合わせとフォーカス距m表示・アイコン有り。レンズを繰り出すと露出計の電源ON、沈胴するとOFF、またシャッターチャージでON、レリーズ後にOFFとなります。沈胴状態から撮影可能な所(∞位置)まで繰り出すのに3回転半くらい回す必要があります。これは少々面倒かと。最短距離までは更に3/4回転くらい。鏡胴まわりのダイヤルはフィルム感度設定用です。
レリーズボタンはシャッターダイヤルの中心にあり、ストロークも短くキレる感覚も軽いので重量の割にはブレ難いです。電池が無くとも運用できるところも好ましいです。
レンズは四隅はシャープではないものの、コントラストが良く見栄えのする写真が撮れます。
EASTMAN KODAK
1950年発売の沈胴するレンズ固定式35mmカメラ
レンズはKODAK Anaston51mmF4.5(3群3枚)距離は2.5ft〜∞
シャッターは自社製FLASH200でB・1/25〜1/200sec セルフコッキング無 セルフタイマー無
カウンターは手動セット・減算式 重量は450g(実測)
828フィルムを使用するPONY828の翌年に発売されました。販売期間は828モデルの方が長かったようです。軍艦部も含めベークライト製ボディに貼革風の表面仕上げですが、シャーシ内部は金属製です。鏡胴はローライ35のような動きで、約12mm沈胴した状態はグラグラですが、展張した時の手応えはしっかりしています。
レリーズボタンは軍艦部上にあり、巻止め解除は背面。巻き戻しスイッチも背面です。裏蓋は取外し式で、フィルム圧板はピカピカのメッキ仕様です。
子供や初心者向けのカメラと思われますが、そこそこ鮮明に撮れます。このレンズはKODAK35の物と同じなのかなぁ・・名称は違えど51mmF4.5は同スペック。
コダックのレンズに詳しいBrianWallen氏のサイトを見ても良く分かりませんでした。
小西六写真工業1957年発売
専用パトローネ(12枚撮り)を使用する35mmフォールディングカメラ
距離計・露出計無し(59年発売のコニレットIIMは露出計つき)
レンズはコニター50mmF4.5(3群3枚)撮影距離は1m弱〜∞
シャッターはコパル(B・1/25〜1/200)セルフタイマー無し
重量は実測300g 大きさはパールの2/3くらい。 カウンターは手動リセット・順算式 アパーチュアサイズは30×36mm。
フジペットのように子供向けに売られたそうですが、どっこい造りは良いです。前蓋やタスキにもしっかりとした剛性があり、蛇腹も粗末なものではありません。ですが、本体はベークライト製なのでストラップ用の穴や裏蓋留め具付近が破損している個体も見受けられます。
巻止め解除は右手背面のノッチをスライド、これは巻き戻し時も使います。カウンターは巻上パトローネの回転角で進むので巻き太りで間隔が開いていきます
本来は幅は35mmながら12枚撮り無孔フィルムを使用するカメラですが、パトローネに詰め替えしてマスクを入れることで通常の35mmフィルムも使えるように考慮されていたようです。現在はパトローネもマスクもまず見つかりません。
撮りっきりコニカの一部に入っている小型パトローネの大きさがオリジナルの物に近く、カメラ内部を少し削ることで使用が可能になります。が、巻き戻しは出来ません。
1985年にウクライナのアーセナルが発売したMINOX35ELのコピーカメラ。
ボディ色は写真の緑(と言われてます)以外に黒も有り。絞り優先オート、フィルム感度設定はISO25〜800。レンズはKIEV-KORSAR 35mmF2.8でコーティングされている様です。
MINOX35ELとの外観の相違は
・外寸の幅、高さ、奥行とも1〜2.5mmずつ大きい。重量は同じ(実測182g・電池別)
・巻上げレバーが大きい(MINOX GTと同じ位の大きさ)
・バッテリーチェックボタンが無い
・ホットシューの造形がシンプル
位のもので、使用する電池、2回巻上げ、鏡胴内部の構造、ビスの種類や位置などもコピー度は非常に高いです。
前オーナーから「まともには動きませんし、まともに写りません」とのコメントがあり、初撮りも散々な結果でした。ネットの情報を見ても作動/結果に関して厳しい指摘の多い機種のようです。
何とか状況を克服するために分解。シャッター羽接触部分のグリス汚れ?と錆を清掃・研磨。露出感度の大幅なズレ(4〜5段分アンダー)をちょっと人には言えない方法で修正。さらにこの色のボディは裏蓋厚みの薄さから来る光漏れ発生が多いようなので、ジャンクで購入したMINOX35EL用の速写ケースを装着(キツイです)して使用することで一応解決。逆光では試していませんが、絞り・シャッターもまともに動き、MINOXと同程度のシャープな写りを楽しめるようになりました。ケース付きジャンクだったMINOX EL
(こちらは液漏れによる腐食)も同時に修理して、そっくりさんが揃いました。
PROUD CHROME SIX
隅田光機製作所 1951年頃
レンズはK・YAMASAKI BIO-CONGO75mmF3.5
シャッターはSYNCHRONT(自社製?)B・1〜1/200 セルフタイマー有
6x6・6x4.5切替マスク内蔵 裏窓式
2,000円とは言え、普段はスルーしている当たり前の50年代の国産フォールディングカメラだと思ったのですが、レンズ銘板を見るとCONGOの文字が。スマホで検索すると、戦前から21世紀まで大判用レンズを製作していた山崎光学研究所製のレンズと分かりました(2013年廃業)。
俄然興味が湧き、持ち帰ってカビと錆びにまみれた機体をレストア中です。
外装とレンズ、シャッターは何とかなりそうですが、問題は蛇腹。これは時間が掛かりそう。
ほぼ大判用レンズ専業だった山崎光学が何故50年代の一時期にだけ中判カメラのレンズを製造していたのかは分かりませんが、何とか写る様に直したいものです。
山崎光学から分かれた山崎光学写真レンズ研究所は現在も小規模ながらライカレンズの修理と研磨・再コーティングでかなり有名です。一族で100年間にわたって写真レンズに関わっているのも日本の企業として興味深いです。
掘り下げると色々と面白い状況が見えてくるかもしれません。
2次資料以下の噂話ですが「山郫光学はこのレンズの販売代金の債権を回収できなかった。」
http://blog.livedoor.jp/toshioimawaka/archives/5097299.html
拙宅には廃業後駆け込みで在庫をお譲りいただいたテレ構成300mmf8と400mmf8、製版または写真館用のバレルレンズ、伸ばし用レンズ、借用中の中判木製暗箱に付属した105mmf4.5があります。
いずれも大変高画質で、廉価版と侮って食わず嫌いだったのを反省しています。
東南アジアの写真館でトップシェアは伊達ではないですね。
 れんずまにあ
れんずまにあ  2025/08/21(Thu) 22:13 No.2978
2025/08/21(Thu) 22:13 No.2978
カメラメーカーが生まれては消えたという時代に振り回されたのでしょうね。
私はこれが唯一のコンゴーレンズ。本体をもう少し調整して撮影しようと思います。
ついでに私が見つけた山崎光学研究所の記事はちょっと古いですが
https://chiiden.net/?p=3751
山崎光学写真レンズ研究所については
https://camerafan.jp/cc.php?i=152
を読んで興味を持ちました。どちらも職人技の世界、なんと素晴らしいものでしょうか!

 ナースマン
ナースマン